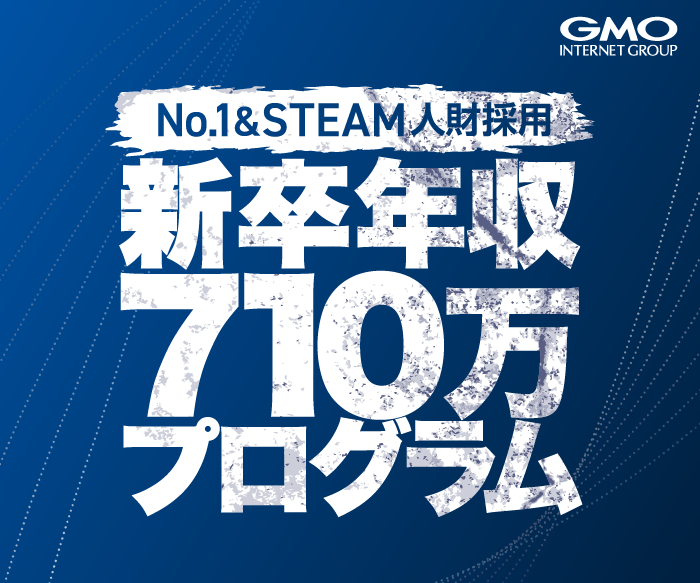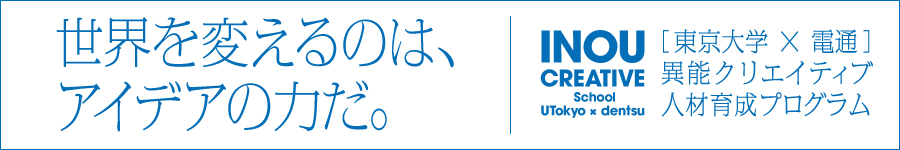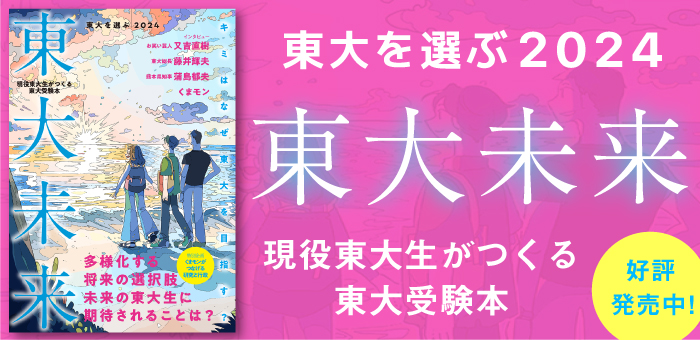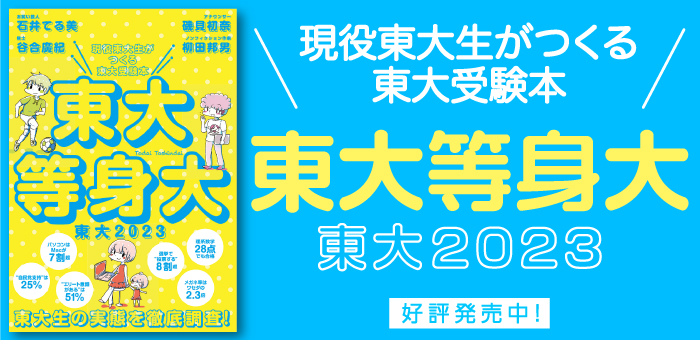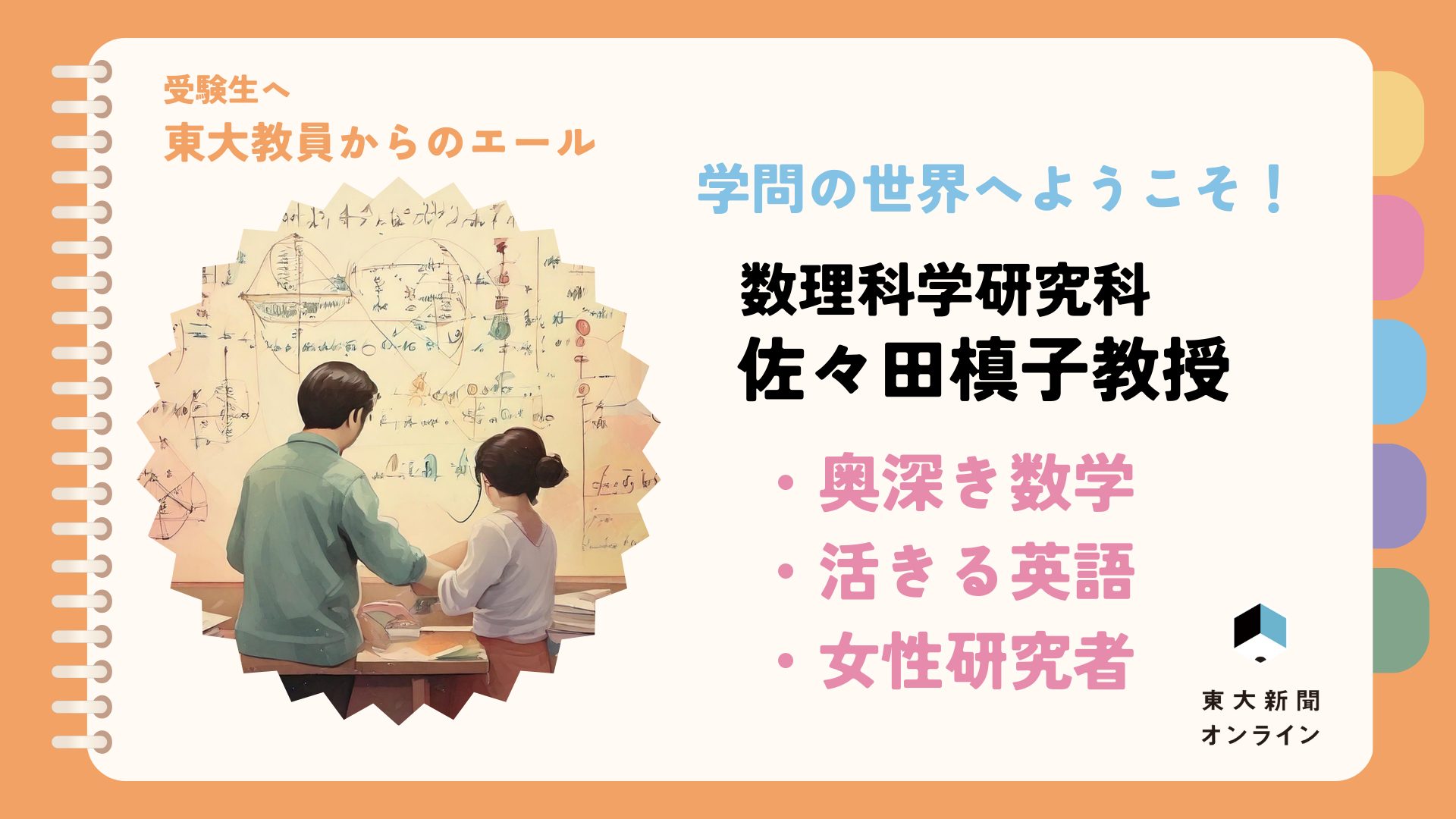
ついに入試本番。東大大学院数理科学研究科で確率論・統計力学を研究する佐々田槙子教授に、学生時代の話や研究について聞いた。この先に広がる学問の世界に思いをはせつつ、頑張れ受験生!!(取材・溝口慶)
━━入試当日の思い出はありますか
数学は得意だと思っていたのですが、大学入試や大学院の入試では数学が全然できなくて落ち込んだのを覚えています。受験生は、試験当日はネガティブなことは考えずに「自分ができなかったら周りもできていないはず」と、いつも通りリラックスして頑張ってください。
━━研究内容について教えてください
専門は確率論、統計力学です。高校までの物理で全てのものは原子、分子から出来ていると習いますよね。原子・分子のレベルで観察すると物理法則があるわけですが、このミクロな世界と、私たちが普段目にしているマクロな世界は、当然つながっていますが働いている物理法則の見た目は全然違うんです。例えば、氷が0℃になると水になるとはいうものの、1個の水分子に注目するとマイナス1℃でも、0℃でも、プラス1℃でも振る舞いはほとんど一緒なんです。ただそれが大量に集まってマクロ現象となると、ある温度から急に違う振る舞いをしだして、マクロの世界で変化が見えるようになります。ある意味、大量の構成要素があってはじめて起こる振る舞いなんですね。人間でも、一人一人は背の高さや成績が違うとしても、たくさん集めればだいたい正規分布が見えてきます。正規分布のような法則は大量にデータがあるからこそ生じる法則で、一人一人のデータを見ても分かりません。そういうことがマクロの世界では起きている。ミクロ現象とマクロ現象がどうつながっているのか、まだ解明されていない部分がたくさんあるので、確率論や微分方程式などを使って数学的に説明したいと思っています。
特に興味があるのは、熱の拡散や物の拡散です。透明な水の入ったコップに、赤いインクを落とすと丸く広がりますね。ミクロで見ると、その赤いインクの中に分子の動きがあって、一個単位で見てみるとそれぞれ違う方向に好き勝手動いているんです。みんな勝手に動くけど結果的に丸くなる。物の拡散とか熱の拡散は、基本的には分子それぞれがランダムに動いているのに、マクロレベルで見ると非常にきれいに丸く広がる法則性が出てくる、それが面白いなと思っています。
━━専門を確率論に絞ったきっかけは何ですか
学部3年時の確率論の授業です。それまでの確率論はサイコロを投げるとか、場合の数の話とほぼ一緒みたいな感じでしたが、現代的な確率論を使うと、持っている情報に応じて確率、つまりどういう結果が起こるのかという期待度合いが変わる、ということをきちんと表現できることが、とても面白いと思いました。
人間の世界においても、1年先の株価を予想しようとしてもぼんやりとしか分からないですよね。でも、日が経ってその1年後の日に近付いていくにつれて予想は確実になっていきます。例えばサイコロの1・3・5の面に青いシールを貼って2・4・6の面に赤いシールを貼ったと仮定すると、それを振った時の情報は青か赤かですが、その背後にある情報は六つの数字です。だから、青赤という情報しか見えなかったときの期待値と、六つの数字の精度で情報が見えたときの期待値といったように確率を情報に応じてスライスして見られる(※)。同様に、どれだけ情報があれば来年の株価の期待値はこうなる、というように表現できる。そこでは時間の変化は情報の増大と考えられて、物理の問題や株価予測、天気予報や感染症の拡大でも情報が増えるとだんだん予測の精度が上がってくる。現代数学では、情報の増大によりランダムに見える事象の確度が上がっていくという状況を定式化できているんです。それがすごく面白いと思いました。
※:(佐々田先生より)サイコロにシールを貼る例は、舟木直久「確率論」に書かれている内容に基づく。
━━どうして研究者になったのですか
小さい頃から算数が得意で、数学に関わる仕事がしたいなと思っていましたが、中高時代は周りに数学の話ができる友達がいなくて、寂しいとも思っていました。一方で他の人とは違う強みだと前向きに捉えてもいました。
東大では、理Ⅰに入ったのもあって、数学好きの友達がたくさんできました。数学を一緒に勉強して、教え合えるのが楽しかったです。
3年時に数学科に進学すると、女子は自分だけでしたが、授業ごとに新しい考え方に触れられるのが面白くて、勉強を続けたい、研究したいと思い大学院へ進むことにしました。修士課程では他大学から入学した友達もできてさらに面白くなり、また就活もしてみましたが自分が働いているイメージがあまり湧かなくて、やっぱり研究者を目指そうと思いました。大学院生の頃、東大に研究会のために来ていたフランスの先生に研究しに来るように誘われて、頻繁にパリへも行きました。フランスでは研究環境が全然違って、数学科にも女性の先生や学生が多かったです。他にもピアノの腕前がプロ級の研究者がいたり、休みの日にはみんなで山へ登っていたりと、人生を全て研究に注がなくてはいけないということは全くないのだと学びました。研究者の仕事って、研究会などで頻繁に海外へ行けて、それも楽しいと思って、研究を続けたいなという思いが強まりました。
━━学部時代の授業はどういったものでしたか
数学の議論をする機会が多かったです。3年時の演習の時間は、たくさん問題を渡されて解けた人が前で発表して、そこは何でそうなるのか、こうやって解いてもいいんじゃないか、などと議論する形式でした。自分だったらこう解くけど、全然違う人もいるんだと数学について多様な考えを知ることができました。4年生になると、先生とのセミナーで毎週専門書の内容を学生が発表するというのがメインの授業でした。
━━逆に教える側になって、授業はどうですか
楽しいです。特にセミナーは一番いいですね。授業では、できるだけ学生からフィードバックをもらって、授業についてどう感じているか、どういうことに興味があるか、など、学生の考えを聞けるようにと思っています。前期教養課程の1年生の授業でも、宿題1問と授業の質問や感想を毎週提出してもらっています。この質問や感想がとても面白く、100人分ぐらい集まると、授業のどこが難しかったかが見えてきます。「こういう風にやってもいいんですか?」というアイデアが出てくることもあります。学生の目線でどう説明すると分かりやすいか考え、なるべく一方方向にならないように工夫しているので、学生からの感想を読むと励みになります。そういう双方向のコミュニケーションの機会が無いと、同じビデオを全員が見るのと変わらなくなってしまいます。
━━文系からでも進振りで数学科に進むことは可能ですか
文系から数学科に来る学生は結構いますよ。私の研究室に来た学生にもいました。実は数学には哲学に近いところがあると思います。研究のスタイルも人文系に近く、大きな器具も買わないし、他の人との議論が研究の大部分を占めているんです。数学は1人での研究が主というイメージは間違っていて、他の研究者との対話からアイデアが出てくるものです。論文の著者の数が少なく、全員がその研究の全体を理解しているようなやり方も人文系と似ていると思います。だから文系の学生さんが来ても問題ないと思います。
━━研究において語学はどれほど大事ですか
すごく大事です。あえて言うと英語は本当にやった方がいいです。博士課程の時にチューリッヒに行ったのですが、海外生活も、一人暮らしも初めてだったんですね。そこで1カ月、何も分からないサバイバルの世界に放り込まれて、そこで何もかも英語で聞くしかないわけです。やっぱり最低限の英語っていうのは絶対に必須だと思いました。私が通っていた中高が、話す・聞く、ということの教育をかなりやってくれた学校だと思うんですね。受験勉強ではどうしても読み書きに偏りがちですが、実際の生きたコミュニケーションの中では、話す・聞く能力が大切だと思います。
読み書きは今、機械でかなりできるようになったので、日本語のメールを書けばAIがきれいに翻訳してくれるし、日本語で論理的な文章が書ければ、そう遠くないうちに論文さえも英語に全て翻訳できるようになると思います。それに、コミュニケーションをとるにあたって、話すのは練習で何とかなるけれど、聞くのは早くから耳をきちんと育てていく必要があります。リスニングさえできれば、とりあえず会話の流れはなんとなく分かるし、イエスかノーかぐらいは答えられます。でも、聞き取れなかったら本当にどうしていいか分からないですよね。道を聞くにしても、ホテルで何か壊れて困った時でも、たとえ準備をしてから話しかけることはできても、相手に早口で返された時に理解できなければ目的を達成できないので、リスニングはしっかりやっておきましょう。
私も、正直学部生の頃までは、英語を使わなくても生きていけると思っていたけれど、研究で海外へ頻繁に行くようになり、各地で日常生活するために必ず使うし、研究者になると、論文も全て英語で読むようになるし、海外では講演も議論ももちろん英語でするので、この日のための中高の授業だったんだと強く思います。それから、駒場で1年生か2年生の時に、英語のドラマを見る授業を選んだんです。本格的な、ネイティブの人が見るようなドラマを1時間程度観て、その後に隣の学生とどんな話だったとか、どこが印象に残ったとか英語で話し合う授業だったと思います。今思うと毎週1時間ぐらい、速い英語を聞き続ける機会があるのは良かったと思います。
━━「数理女子」というサイトで、女子学生に向けて数学の話を発信されています
慶応義塾大学に所属していた時に、数学科には女性研究者が少ないという話をしていて、環境によって入ってくる情報量が全然違うのかなということで情報発信をしようとなったのがきっかけです。私自身中高は女子校でしたが、数学科について何も想像がつかないというか、行った人が身近にいなかったです。周りの女性からは、数学科への進学について親から特に心配されたといった話も聞いたんです。数学科へ進みたかったけれど、親に反対されて違う学部に行ったという話も聞きました。実態を知らないとイメージだけで、女性もやっていけるところなのか、友達はできるか、ということや、就職先や結婚への不安などを持たれることが多いです。もちろん、女性数学者はたくさんいますし、研究者以外にも多方面で数学出身の女性が活躍していますし、家庭を持っている人もたくさんいます。就職についても、AIや量子コンピュータ等の関連で業種の幅もとても広がっているんですよ。こういうことが、中高生やその親御さんに見える形になっていない、ということに問題があると思ったんです。
あとは「数学って何の役に立つの」と聞かれることがありますね。本当は身近なものにもたくさん使われていますし、数学を使うといろいろな分野で独創的なこともできます。例えばウェディングドレスのデザイナーさんが線を決めるのに数学的な関数を使っていたり、パティシエさんが幾何を意識していたり、いろいろな所で数学を使っている話をサイトに書いてもらっています。まとめると、自分たちが必要だと思った「世界は数学であふれている」「数学を生かす将来」「数学は楽しい!!」「リアルライフ」の4つのテーマで原稿を依頼して、記事を掲載しています。
━━女性ゆえに研究の上で困ったことはありましたか
やっぱり進学して最初は友達ができませんでしたし、最初の子供を出産した時も、身近に経験を聞ける研究者はいませんでした。妊娠中は仕事がどう難しくなるのか、産休・育休中は授業や研究発表の予定をどうすれば良いのか。また、子供が生まれてからは、いつ頃から出張できるものなのか、全く研究時間がとれなくなってしまったけれど大丈夫なのか……。相談できる女性研究者が周りにとても少なく、何も分かりませんでした。ただ同世代で同じ時期に出産した数学の研究者友達がいて、彼女の存在はとても大きかったです。一緒に手探りで頑張って、さらに日本数学会の会場で「女性誰でも懇談会」という会を始めました。後輩、次の世代に、私たちの経験を少しでも共有したいと思い「こういう事例ややり方があるよ」ということを伝えたり、他にも研究会で託児室を作ってもらえるよう働きかけたりもしてきました。やっぱり研究会で女性が1人の時は、明らかには困らずとも、居心地のいいものではないことも多いんです。年齢・研究実績とともに、あまり女性という属性ではなく、一人の研究者として見られるようになってきましたが、特に若い人に対して日本だと性別や所属する大学、研究室など属性で認識しようとする傾向があると感じます。海外では違うと感じることが多く、パリへ行った時も、所属ではなく興味や研究の話から聞いてくれることが多く、いいなと思いました。「背の高い人が理系に進学するのはどう思いますか?」みたいな質問はおかしいと思うじゃないですか。女子学生の理系進学や数学科進学についても質問されること自体が違和感になるのが理想です。
━━新入生へ向けて一言お願いします
これからの東大の勉強をぜひ楽しみに来てください。大学では、面白くて深くて多様な「学問」と「人」がたくさん待っていますよ。
佐々田 槙子教授(東京大学大学院数理科学研究科)
11年東大大学院数理科学研究科博士課程修了。博士(数理科学)。慶応義塾大学助教・専任講師、東大大学院数理科学研究科准教授を経て、23年より現職。