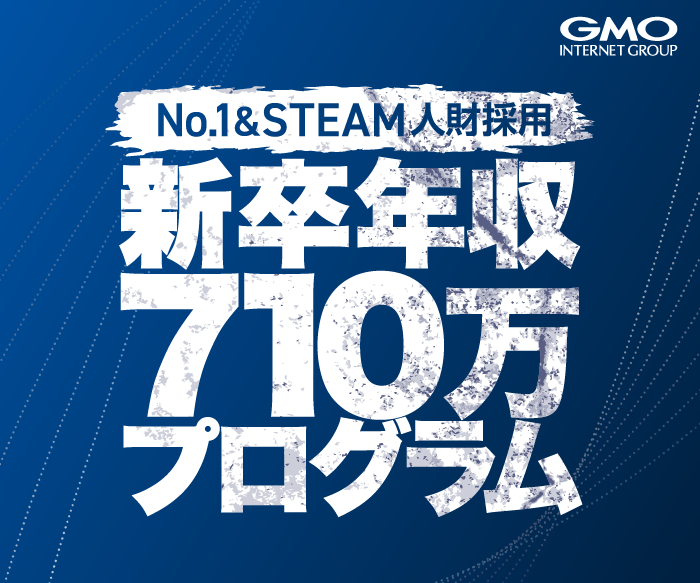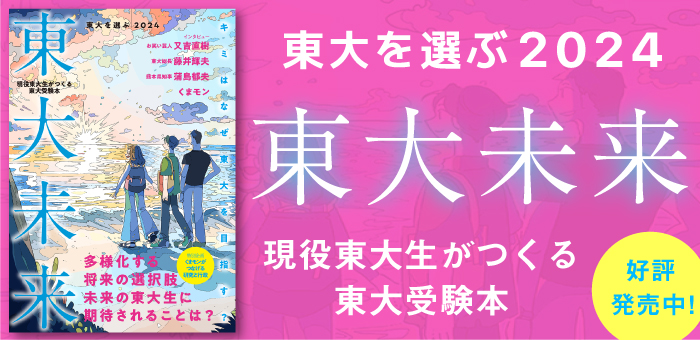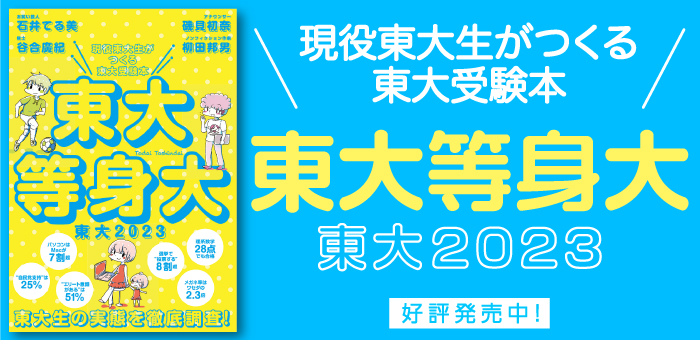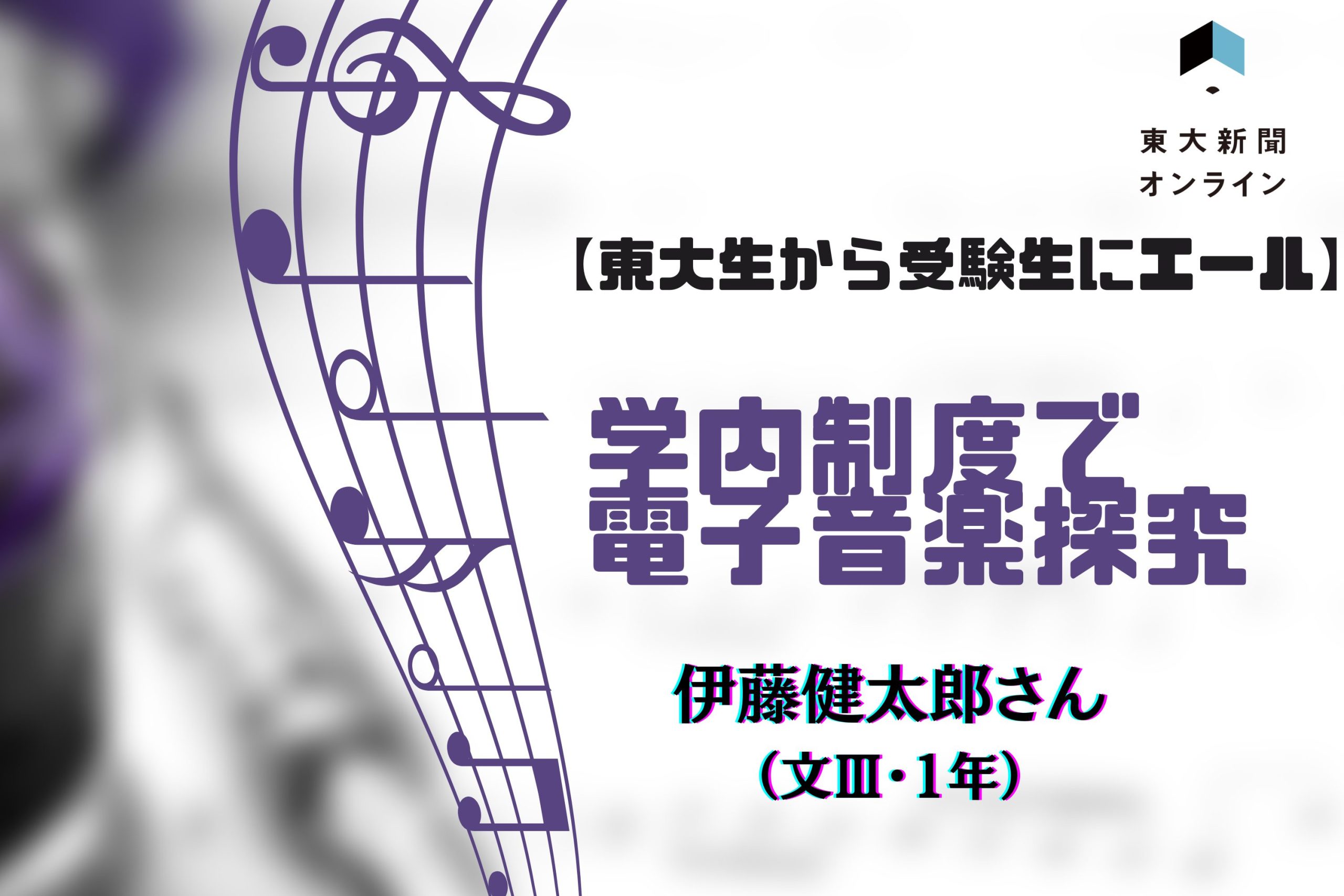
東大では学生の知的活動を支援するべく様々な制度が整備されている。しかし、学生側からの主体的なアプローチが無ければ、そうした制度が活用されることはほとんどない。今回はその一つといえる「自主ゼミ」制度を利用し、「電子音楽概論」を開講した伊藤健太郎さん(文Ⅲ・1年)に話を聞いた。積極的に活動に取り組む姿からは、大学生活について重要な示唆が得られる。(取材・管原秀太)
──自主ゼミについて教えてください
自主ゼミは東京大学教養学部学生自治会が運営する制度です。講義内容に特別な縛りはなく、学生が自身の興味関心に沿った講義内容を計画します。自治会から講師料の支払いを受けて、外部講師の方をお招きします。開講数には限りがあり、応募された講義計画案に対して選考が行われることがありますが、そこでは今までに開講経験がない講義案が有利になるような制度設計がされていますから、新入生の方々にはお勧めできるでしょう。講義を行う教室も自治会が確保してくれます。
──伊藤さんはこの制度を利用し「電子音楽概論」を開講しました。どのようなきっかけがあったのでしょうか
高2の頃から電子音楽に対する関心を持っており、かねがね電子音楽を体系的に学ぶ機会を得たいと思っていました。入学時に自治会からの案内で自主ゼミの存在を知り、せっかくならばと思い応募申請を行いました。大学に入った以上は何か特別なことをやってみたいという漠然とした気持ちもありましたね。
──「電子音楽概論」の具体的な授業内容を教えてください
アナログシンセサイザーの仕組みや電子音楽の技術発展について学んでいます。回によっては実際の機材に触れるほか、電子音楽の作曲を行うこともありますね。電子楽器を扱う音楽家の技能と地位の向上を目指す団体である日本シンセサイザープロフェッショナルアーツに依頼し、毎回の講義内容に合わせて講師の方が来てくださいます。毎回の講義内容は話し合いで決定するため、柔軟な変更も可能です。今後は作曲ソフトの操作実習も行う予定です。友人なども誘い、現在はおよそ20人が電子音楽概論を受講しています。
──東京大学を志望されたきっかけを教えてください。音楽趣味が多少なりとも影響しているのでしょうか
成り行きで決めた側面が強いです。高校時代に人文系の学問を修める決意を固めましたが、研究に本腰を入れるのは大学院以降になるとも考えていました。ですから学部生時代を過ごす大学に特にこだわりはありませんでしたね。ただ、東大の充実した施設と人材はやはり魅力的です。高校時代の研究活動が評価されうる推薦入試での受験を高3の夏に決意しました。
──伊藤さんは関心分野が非常に幅広い印象を受けます
そうですね。東大の強みは「引き出しの多さ」だと思います。サークルも多様ですし、学生も実に様々な人がいます。私としても自由な時間が多い前期教養課程の間は面白いことをし続けていたいという気持ちが強いです。 引かれるものがあったら必ず逃さないようにしています。
──今後の展望を教えてください
当面は地に足を付けることが目標です。私は変化のない生活を送ることが苦手で、現在も音楽系のサークルに三つ所属し、委員会活動にも参加しています。たしかに様々な活動を並行して行うことができるのは1、2年生ならではですが、同時にこの期間で人生における基本像のようなものを固めたいと思っています。
──受験生にメッセージをお願いします
まずは、自分を追い込みすぎないようにしてください。必死に物事へ取り組むことは重要ですが、きつい思いをすれば良いわけではありません。より楽な方法を追い求めつつ頑張ることもできると思います。そして、睡眠時間は適度に確保してください。
東大入学後、皆さんはサークルやバイト、勉学などで多くの選択をします。いろいろなことをやりたくなるでしょう。私としては、そこで選択肢を絞るのではなく、可能な範囲で全て試してみることも大事だと思います。一回きりの大学生活ですから、自分を苦しめない範囲でやれることは全てやってみましょう。