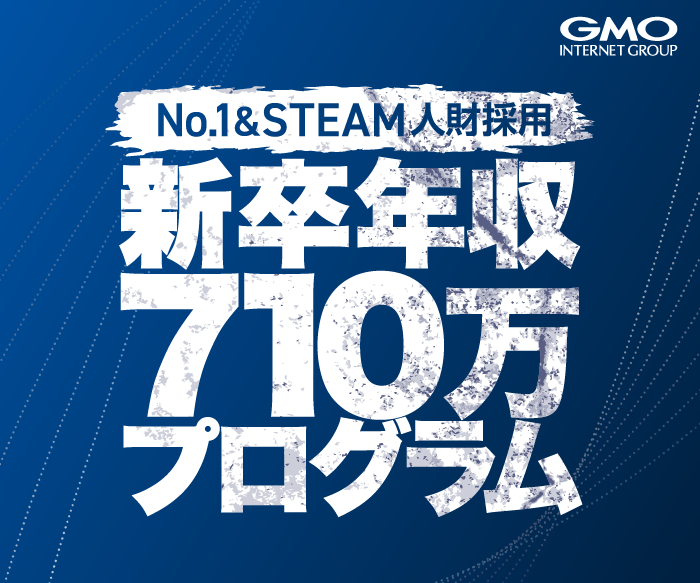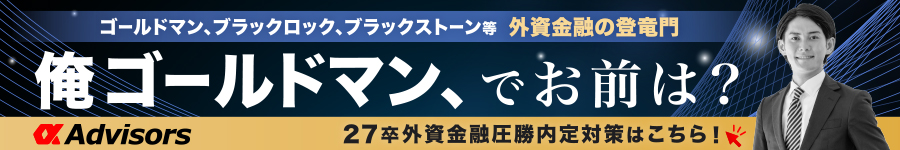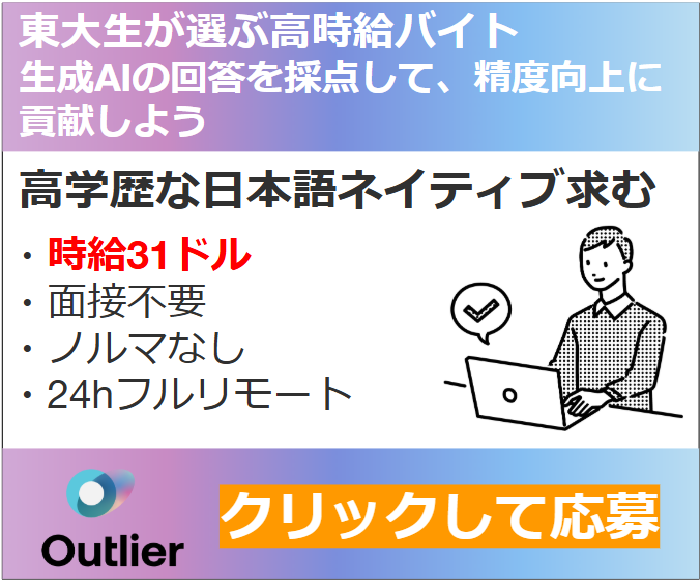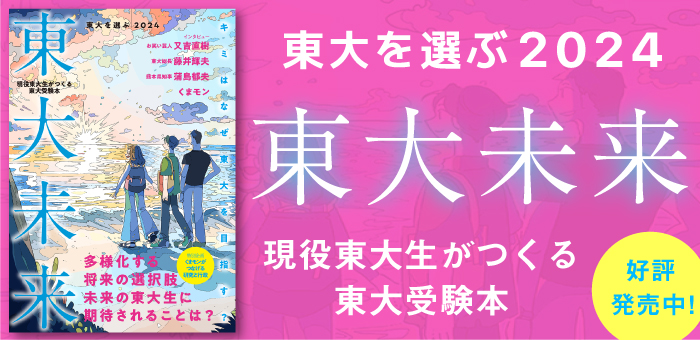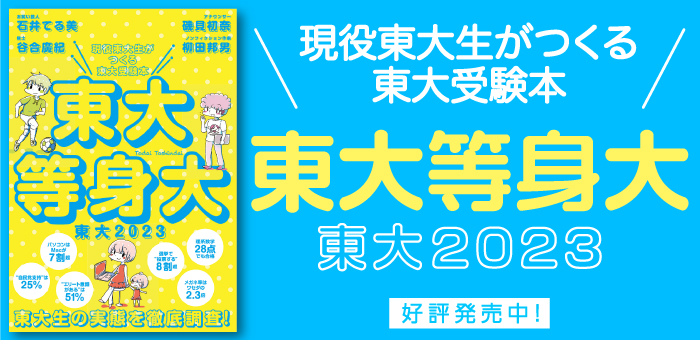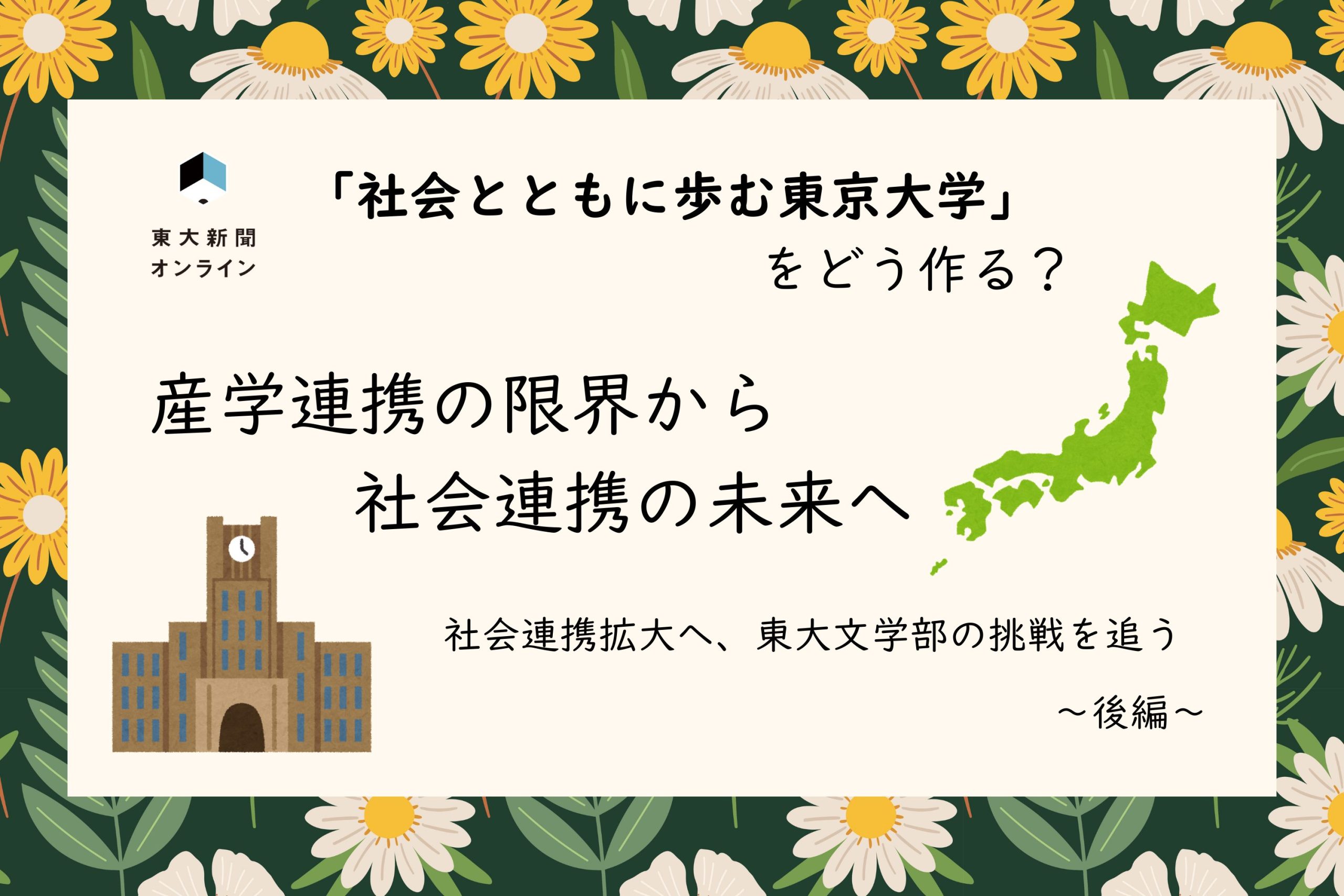
2021年、東大大学院人文社会系研究科・文学部は、和歌山県新宮市と連携協定を締結するなど、社会連携の一環として地方自治体で人文知を生かす動きが始まっている。理系分野での産学連携が進む中で、人文系分野での社会連携はどのような可能性を秘めているのだろうか。今回は社会連携本部副本部長を務める秋山聰教授(東大大学院人文社会系研究科)に、東大の社会連携の現状と展望について話を聞いた。(取材・岡嶋美杜、岡拓杜 撮影・岡拓杜)
──産学連携と社会連携にはどのような違いがありますか
産学連携と聞いて思い浮かぶのは企業との連携で、中でも企業と大学の双方に研究成果の応用活用による相互利益を生み出すものだと思います。それは革新的な製品を作り出すような物理的な利益でもあって、多くの場合、工学系の分野で連携が進みます。一方で社会連携は、地方自治体や地域の市民団体など幅広いステークホルダーとの連携を意味します。例えば私が所属する文学部では、北海道北見市や和歌山県新宮市と連携してきました。他の自治体の方にも興味を持っていただいており、これからの展開が期待されるところです。社会連携と産学連携の関係性については、前者の一つとして後者が含まれると言っても良いかもしれません。
──東大文学部での社会連携が始まった経緯について教えてください
北見市との連携は60年以上続く一番歴史がある連携です。当時の言語学の服部四郎教授が樺太アイヌ語の調査のために常呂町(現・北見市)を訪れた際、非常に熱心な市民の方から、常呂町の遺跡の発掘をしてほしいという要望を受け、考古学の駒井和愛教授にそれを打診したのがきっかけでした。常呂町には、後期旧石器時代からの数多くの遺跡が残されていて、1957年以来、文学部による発掘調査が続いています。現地には実習施設が建てられていて、学生たちが考古学の実習を行っています。
──新宮市との連携はどのようなものですか
北見市との連携が文学部の中でも考古学という専門分野に特化したものになっているのに対し、新宮市とは文学部の全分野が関わってくるような社会連携を行っています。連携協定を結んだのは2021年です。具体的には、熊野学(熊野の歴史・文化を人文・社会・自然科学などの各分野から研究し、その独自性と普遍性を解明、その個性や魅力を検証する取り組み)とそれによる地域振興、国際交流イベント、体験活動プログラム(東大の学生が今までの生活と異なる文化・価値観に触れることができる体験型教育プログラム)などを実施しています。実は新宮市との連携は、私が熊野古道を友人たちと歩きに出掛けて、その際に新宮市の市民団体の方と親しくなったのが始まりです。地元の居酒屋で市民の方から、高齢化や少子化が進む新宮市を何か面白く盛り立てることができないかというお話をいただいて。そこから私が何度か講演に行ったり、知り合いの教授や外国人の友人を連れて行ったりしていたところ、新宮市の教育委員会や市長が私の活動に興味を持ってくださりました。
──個人的な人脈や経験が社会連携につながっているのですね
北見市・新宮市との社会連携は共に、人と人とのつながりがきっかけです。その背景には地元の価値を知りたい、広めたいという、市民の方々の熱意もあります。一方で、人間同士の個人的なつながりには年限があるので、何らかの制度化が必要だと感じています。例えば担当教員の定年が近づくと、引き継ぎの前に後継となる担当教員と一緒に地域に出向いて、人間関係を作るところから始めなければなりません。理論的には制度化すれば自然と進んでいくような気もしますが、実際にはお互いの相性もあるでしょうし、必ずしもうまくいくとも限らないわけです。
連携の始まりの部分に関しても、文学部の中に私が室長となって人文学応用連携推進室を開いていますが、自治体や企業との連携の窓口になるという理想にはまだ届いていません。現状では、教員有志が自主的に行っていて、今後どのような支援体制を整えていくか考えることが、これから定年までの3年間で私が取り組むべき課題だと認識しています。
──財源はどのように確保していますか
産学連携と異なり、社会連携は直接金銭的利益を生み出すわけではありません。そのため、活動を継続するための財源確保が大事になってきます。現在は主に東大基金から支援を受けているのですが、寄付金ですので継続性が問題になってきます。当初、大学側が自前で資金を用意して地域に持っていくという形で行っていたのですが、最近は北見市も新宮市もふるさと納税に「東大との連携」という項目を作ってくださいましたのでその資金も使えるようになりました。また、文学部が設立した独自の基金から、社会連携のための割り当てをもらっています。社会連携を今後も安定して継続し拡大していくためにも、財源多様化を進めていかなければなりません。
──ただ、特に人文系の学問と資金調達は結び付きにくいイメージが強いです
室町時代から江戸時代にかけて「熊野比丘尼(くまのびくに)」と呼ばれる尼僧が、「熊野観心十界曼茶羅(まんだら)」や「那智参詣曼荼羅」の解説(絵解き)をしながら、熊野への参詣や寄進を呼び掛けていました。こうした広報活動は勧進とも言い表せて、これを英語にするといわゆる「ファンドレイジング(寄付集め)」です。神社仏閣が当時行っていた勧進のノウハウの研究は、まさに私たちの領域ですよね。だから現代版の勧進というイメージを持てば、両者はそうかけ離れた存在でもないかもしれません。実際に絵解きの再現をしている方がいて、その方とニューヨークやフィレンツェでパフォーマンスを行ったこともあります。かつて絵解きによって熊野への参詣が人々に広報されたのと同じように熊野の魅力が世界へ発信されているのは面白いですよね。
──新宮市との社会連携では、どのようなことに力を入れているのでしょうか
一つは国際的な広報活動です。私は西洋美術史を研究対象としているのですが、熊野の文化を知り合いのヨーロッパの研究者に紹介すると非常に面白がってくれます。彼らが興味を持ってくれたことを発端に、熊野の魅力がじわじわとヨーロッパの国々に広がってくれたら良いですよね。海外の大学教授を熊野に招待したり、東大の留学生の熊野研修を実施したりしています。去年のフランス、リヨンでの国際美術史学会では、熊野のお札と西洋の巡礼地の巡礼記念品の比較もしました。
もう一つ力を入れているのは、新宮市の中学生を東京に招く3泊4日の研修です。東大構内の見学に加え、東京国立博物館や国立西洋美術館などを周ります。東京から遠く離れた場所で暮らす彼らに、東大で学ぶことに意欲を持ってもらうと同時に、東京と地元を比較することで、地元の価値に目覚めてもらうのです。
──社会連携の大学側へのメリットとは
東大に研修で来てくれた中学生の感想文が素晴らしくて、私自身とても勉強になるのですよ。彼らの潜在的な可能性を実感します。博物館で熊野関連の展示物をじっと見ている子や、考古学の専門家の話を聞いたことで地元を掘ってみたいと話す子がいましたね。それから「東大教授というといかめしいと思っていたが意外とそんなこともなかった」という感想も聞きます(笑)。ただ、よく考えてみると、日本学術会議の会員任命拒否問題について世間で無関心な人が多かったのも、東大の教員に対するそうしたイメージが関係しているのではないでしょうか。社会連携を通して研究者がこれまで社会と関わりを持ってこなさすぎたと個人的に意識するようになりました。
これまで研究者が自分たちのやっていることやその面白さを社会に分かりやすい言葉で語ることを怠ってきたのではないかと思っています。中学生に学術的なことを説明するのは、慣れないことで難しいですが、どのように話せば彼らを感動させられるか考えたり、感想文を通して彼らから鋭い指摘をもらったりすることは、研究者にとって大変刺激的なのですよ。そうやって、中学生と研究者が相互に影響を与えながら学べるのがこの研修の良さだと思います。
──今後、産学連携や社会連携が拡大することで、就職ではなく大学院進学を選んだ場合でも社会とのつながりを意識することが増えてくるのではないでしょうか
私が学生だった頃は、学部生にしても大学院生にしても、社会から隔絶した場所で勉強していましたね。私は美術史を学んでいたので美術館には行っていましたが、それ以外は大学のキャンパスに閉じこもって研究していました。今でもある程度そういう面はあるでしょうから、在学中にこういう社会連携活動に参加してみるのは悪くない体験です。社会のこと、特に地方の現状を知る上で、学外活動は重要だと考えています。研究者を目指す人も、なるべく早く社会とつながっておく方が良いですよ。学者同士だけでなく、一般の人たちに自分の研究の楽しさを語れるようになるべきだと思います。学問の存続のためにはやっぱり社会からのシンパシーが必要なので。
──工学系の研究に比べて人文系の研究は、社会にどう役立つのか尋ねられることが多い印象があります
そうですね。私も若い頃、自分の研究が何の役に立つのか考えてしまうことがありました。でも「役に立つかどうか」はかなり危険な考えでもあると思います。「役に立つかどうか」というのは、その時すぐに役に立つかということですよね。でも研究は時間をおいて役に立つようになることもあります。役に立つものが何かは時代や地域によって変わるので、絶対的な基準ではありません。理系でも何十年も経ってからその研究の重要性が認識されることがあります。だから「役に立つかどうか」ではなくて、もっと緩やかに物事を捉えるほうが良いと思います。一方で、研究を役に立てる努力も必要です。人文系の学問も「知ることの喜び」という点では社会に貢献できるのではないかと感じています。それから、既成概念をひっくり返すとか、常識と非常識の境界線を揺らがせることは、人文系の学問だからこそできると思っています。
──社会連携の今後の展望は
大学が自治体と連携するというのは、欧米にはあまりない取り組みだそうです。新宮市に海外の研究者を呼んで講演してもらうと、市民の方が大勢集まり質問もたくさん出るのですが、そのことに海外の研究者はみんな驚きつつも質疑応答の時間を楽しんでいます。だから、こういう社会連携自体を日本型の連携の一つの形として国際発信できそうですよね。
社会連携は連携先の地域の広報や学術活動の振興になるだけではなく、大学や研究者が社会と対話し、自らの研究分野の「面白さ」を語ることができるという貴重なきっかけでもある。現在、東大で人文学系の学問を専攻している学生にとって、社会連携はそれほど身近な存在ではないだろうが、せっかくなら東大だからこそ得られる学外との交流の機会をもっと活用していっても良いかもしれない。物理的な利益を直接生まない人文系の社会連携では財源の確保がより深刻な課題となっているが、ここでも大学と地方の間での対話によって、より多くの人を巻き込みながら財源多様化を図っていくことが求められている。
秋山 聰 副学長 (東京大学大学院人文社会系研究科教授)あきやま・あきら/ 97 年独フライブルク大学哲学部 Ph.D。博士(哲学)。東大大学院人文社会系研究科助教授などを経て、11 年より人文社会系研究科教授。21 年〜 23年人文社会系研究科長・文学部長、23年より東大副学長(地域連携推進、渉外活動推進)。