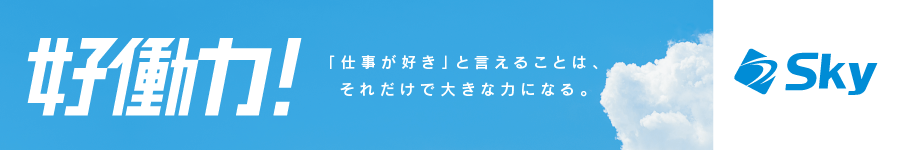その①はこちらから
私は、社会福祉法人・ゆうゆうの職員さんに案内され、生活介護事業所「にょきにょき」を見学した。これからの半年間、主にここで働く予定だ。
ここでは、食事や排泄に介助を必要とするなど重度の障害を持つ18歳以上の利用者さん20名程が、平日の10時から16時までの時間を過ごしている。廃校になった中学校の校舎を利用しており、中に入ると「音楽室」「1年1組」といった部屋のプレートや廊下の雰囲気に懐かしさを感じた。
担当の職員さんは、私と一緒に各部屋をまわりながら、利用者さんに私のことを紹介してくださった。「○○さん、山本斐海(あやみ)さんです。」「○○さん、あやみさんです。」同じ苗字の方が何人もいらっしゃるため、私は「あやみさん」と呼んでいただくことにした。私も続いて、利用者さんに声をかける。「こんにちは。山本斐海です」
私は勤務先を決める際、「重度の知的障害や自閉症の方と、長い時間を過ごしたい」とゆうゆうにお願いをしていた。それは、休学の一つの目的として、昔の私が障害のある方々と過ごしてきた記憶をなぞり、今の私として丁寧に捉え直すような、そんな経験をしたかったからだ。
私には、4歳か5歳の頃のある記憶が、映像のように鮮明に頭に残っている。
それは、父親に連れられ、両親が以前働いていた東京都の生活介護事業所を訪れた日の記憶だ。その事業所は、庭のようなスペースを用いて夏祭りを開いており、利用者さんや職員、地域の方が集っていた。
父親が、昔関わっていた利用者さんと会った時のこと。父親はとても嬉しそうな笑顔で「〇〇さん、久しぶり」と話しかける。
しかしここで、利用者さんからの返答はない。ゆらゆらと体を動かす利用者さんに、父親は、やはり笑顔で「また会いましょうね」と言った。
幼稚園児だった私にとって、この光景は非常に不思議に映った。「利用者さんは、父親の言っていることの意味をわかっているのだろうか」「父親は、どのような気持ちで利用者さんに話しかけているのだろう」と、素朴な疑問を抱き、傍観していた。
私は、他者とのコミュニケーションを取る際、主に言語を用いたり表情を読み取ったりする。しかし昔出会ったこの利用者さんは、父親に言語を用いて何かを伝えたわけではなかったし、笑顔などの表情で父親の言葉に応えたわけでもなかった。少なくとも当時の私にはそう映った。
前回の記事 で、私が昔から障害に関心があり、大学でも障害をテーマにしたゼミに所属していることを述べたが、ここ数年、重度の知的障害や自閉症の方と長時間過ごす機会は設けられていなかった。他の障害をテーマにしたり、比較的軽度の知的障害をもつさまざまな方と出会ったりする中でも、この光景が頭のどこかに引っかかっていた。
私と同じ方法で言語を用いてコミュニケーションを取っているわけではない彼らは、日々、何をどのように考え、どのようにコミュニケーションをとっているのか。長い時間をかけて知りたい、感じたいと思った。
にょきにょきの利用者さんと初めて挨拶をした時、人生の中で幾度となく経験してきた「緊張する私」「安全な殻の中に隠れる私」が立ち現れた。「こんにちは。山本斐海です」と挨拶する私の声は、彼らに向かっているようでありながら、彼らからの言語での返答があるとは限らないことを予想して、私の内側に向かっていたような気もする。私を覆う「緊張」や「殻」は、これからの半年間を彼らの「支援者」として過ごすという事実を前に、一層厚いものに感じられた。
利用者さん一人ひとりが何をどのように考えているのか、出会ったばかりの私にはよくわからない。今までに出会ってきた重度の知的障害を持つ方についても同じだ。しかし、今まで大きく異なるのは、平日の日中ほぼ全ての時間を、しかも「支援者」として、利用者さんと過ごすということだ。毎日を「殻」の中で過ごしてはいられず、彼らの感情や訴えを、ほんの少しでもわかってみたいと強く思うようになった。

ある日、「音楽室」で過ごしていた一人の利用者さんが、私の手を引き、ドアノブを開けて外へ出ようとした。私は「体育館で走りたい」というメッセージだと思った。彼はしばしば体育館に行って走っているからだ。
私は、「体育館行きますか」と声をかけ、一緒に「音楽室」を出る。しかし、彼が向かったのは水道だった。手洗いが嫌いなはずの彼が、蛇口をひねって冷たい水で手を洗う。私は、彼がなぜ手を洗っているのかよくわからず、そのまま手洗いを見届けた。そして、彼は「職員室」へと向かう。「職員室」に用事はないはずだ。私は、彼が何をしたいのかわからないまま、「音楽室に帰りましょうか。」と声をかけて彼と音楽室へ戻った。
他の職員さんにこのことを話す。職員さんは、「もうお腹が空いているのかな」と言った。「職員室」は、机や椅子を取り替えて昼食をとる場所として使われているからだ。手洗いをしたことにも納得ができる。一見不可解に思える行動も、確実に彼の「言葉」だった。
お昼ご飯ができるまではもう少し。「私もお腹空いたなあ」と呟いた。
食事介助を行うことも、私にとっては初めての経験だ。
例えば、友人同士で定食屋に集い同じメニューを食べたとする。そこでどのおかずから食べるのかは、10人いれば10通りだろう。私は好きなものを後に残しておくタイプだ。
私は利用者さんの隣に座り、箸とスプーンを持つ。私が彼のお皿に一口分の食事を乗せ、彼はそれをスプーンで食べている。彼がどの食べ物から順に食べるのかを最終的に決めるのは私だ。彼の視線から彼の食べたいものを察する。彼は好きなものから食べたいタイプで、好物に熱い視線を送る。しかしそこで彼の好きなものから渡していくと、最後には「そこまで好きではないもの」が残り、彼の食事へのモチベーションがなくなってしまうこともある。

食べる順番によって、完食できるか否かや食事の後半のストレスが変わってくるため、彼の希望を全て叶えることが良いとは限らない。好きなものを食べたいという彼の意志と、栄養バランスやストレスを考えて、どの食べ物から食べてもらうかを決める。私にとって容易とはいえないことだ。
利用者さんは、私が想像していたよりもずっと、私とのコミュニケーションを試みてくださっている。彼らは確実に私に何かを伝えている。しかし、私にはそれが何かわからないことがほとんどだ。また、彼らはにょきにょきで過ごす1日の流れをわかっていて、私が次にするべき支援もわかっているのだろうが、私にはわからない。
なんだか、日々、自分が利用者さんから教わっているような感覚である。
(寄稿=法学部3年 山本斐海(休学中))
【連載 国内福祉留学記】