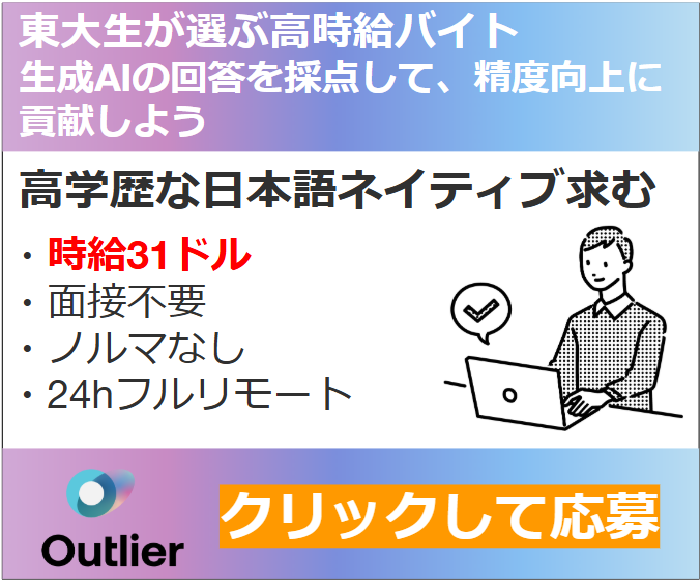東京大学新聞の前身、「帝国大学新聞(帝大新聞)」が創刊したのは1920年12月にさかのぼる。その頃学生が主体となって活動した「新人会」という組織をご存知だろうか。
今回は1920年代「帝大新聞」の学生に大きな影響があった「新人会」について研究を行ってきたヘンリー・スミスコロンビア大学名誉教授に取材した。スミス教授は1960年代に東京に来て、学生運動が真っ盛りの時代に「新人会」OBら関係者に会い、『新人会の研究 日本学生運動の源流』(東京大学出版会、1978年)を書き上げている。そのような時代背景と、スミス氏の東大への留学などの個人史を含めて、「東大新聞の歴史」を考える際に二重に興味深い話を聞くことができた。
(取材・東京大学新聞社OB 清水篤)

工学から歴史学へ
──ご著書『新人会の研究』を執筆されるに至った、1960年代に初めて日本に来られるまでの経緯についてお話しください
皆さんは「東大新聞」の関係者ですが、私も高校生時代には新聞制作に意欲を燃やしていました。私の出発点はニューハンプシャーのプレップスクールにあります。有名なエリート校でした。2年生の時に課外のクラブ活動として新聞部に入りました。週2回の発行で、4年生の時に編集長をやりました。
そしてエール大学に入学しました。曾々祖父から5代続いてのエール大学です。ここでも新聞部を覗(のぞ)いたのですが、熱気に溢(あふ)れた雰囲気におされて入部はしませんでした。
私は、父は鉱山技師、母方の祖父は電気工学技師という環境で、1940年にアリゾナ州で生まれました。それで大学は工学部に入ろうと思ったのですが、1年生の時にいきなり取った上級原子物理学の授業に苦しみ、やはり前から好きだった歴史学を専攻するようになり、その後の生涯が決まりました。
中学校からフランス語を勉強していましたので主にヨーロッパの歴史を学びました。特に「戦間期」とよばれる、1918年から1939年のフランスの歴史に興味を持ち、ジャック・ドリオ(Jacques Doriot)という異色的な人物のことを知りました。フランス共産党の創設に参加したことで有名になり、サン=ドニという労働者の地区の代議士になりましたが、扇動的な宣伝が上手なカリスマ的な人でした。社会党との共同戦線を支持し、共産党から除名され、だんだん右翼に近づき、いわば「転向」して、右翼の大物になった人です。イタリアの独裁者・ムッソリーニとも深交を結び、第2次大戦にドイツ軍に入り、1945年2月そこで最期を遂げました。
今「左翼」とか「右翼」といいますが、始まりはフランス革命議会で、議会内で左側に座ったのが革命進歩派の「左翼」、右に座ったのが保守派の「右翼」というわけです。私自身の現在の位置は、センターレフト、つまり「穏健的なリベラル」の立場と思っています。余談ですが(笑)。
このジャック・ドリオの人生の軌跡が、日本でいえばまさに「転向」です。日本の左翼から右翼への「転向者」、その中に多くの東京帝国大学エリートの「新人会員」がいたのですが、そこにジャック・ドリオの姿が重なり、「新人会」への興味になったのかも知れません。
大学3年の春学期の終わりにドリオの研究のレポートを出し、1962年の秋に大学に戻ったら、1年のフランス留学から帰ってきたばかりのルームメイトがパリで取った中国の歴史の講義がとても面白かったという話を聞き、それでは自分もアジアの歴史を勉強してみようと決心しました。4年生の秋学期に中国史と日本史の授業を取りました。日本史の方はちょうどミシガン大学からエールに移ったばかりのジョン・ホールが先生で、すでにアメリカでの日本研究の第一人者でした。絶えずヨーロッパと日本の歴史を比較しているとますます興味が湧いてきて、日本で日本語を勉強する決心をしました。
──スミス先生の、日本留学時代の研究生活や暮らしの思い出を
私が初めて来日したのは、大学を卒業して間もない1962年9月のことで、 スタンフォード大学日本語研究センターに1年間通い、一所懸命日本語の勉強をしました。センターは目白台の「椿山荘」の隣にいまだにある「和敬塾」という、細川家が作った熊本県出身の学生寮に置かれていました。その時、私は寮ではなく、新宿若松町の新築の木造アパートで1人暮らししました。
大都会生活はその時が初めてで、都市に対する興味が湧きあがってきました。ただし未だ都市とは何かなどと真面目に考えることはなく、ただ都市の環境を観察することだけで精一杯でした。やがてこの経験が江戸東京の歴史を研究することに繋(つな)がり、「新宿」という都市論の論文を書くことになりました(ピーター・グラック共著「A+U」、1973年)。それから江戸の都市空間、錦絵に描かれた江戸名所など、いろいろなことを調べましたが、やはり出発点は60年代に実際に東京に住んだ経験でした。
スタンフォード・センターでの日本語の勉強は大変好きだったので、大学院では学部でのフランス近代史の研究の延長線上として大学院で日本近代史をやってみようと思い、ハーバード大学に申請しました。家族のほとんどがボストン近辺に住んでいたからです。
ハーバードの大学院では、指導教授のアルバート・クレイグと相談して、日本にもフランスのドリオのように左翼から右翼に転向した例があるかと尋ねましたら、まあ、あるとすれば東大の新人会という学生運動あたりを探せばいいだろうという答えでした。つまり、フランスと同じように、今でいう「戦間期」、つまり我々の視点から見れば二つの世界大戦の間の時代で、日本にも激しい「右」と「左」のイデオロギーの対立のあった時代でした。その頃、新人会の歴史について書かれたものは少なかったですが、 思想の科学研究会の『共同研究:転向』という3巻の本が平凡社から出ていて、その中に半沢弘・佐貫惣悦の「前期新人会──赤松克麿・麻生久」、鶴見俊輔の「後期新人会──林房雄・大宅壮一」という重要な論文が載っていました。これが私の研究の出発点となり、最初から「転向」の問題が頭のなかに根強くすりこまれました。
一応の研究テーマが決まっても、いまだ2年半の準備時間の後、やっと1966年の1月に日本に戻ってきました。それまでは、いつも飛行機でしたが、その時は旅客船で行こうと思いました。その当時未だアメリカ・プレジデント・ラインのサンフランシスコから横浜までの定期船があって、プレジデント・ウイルソン号に乗りました。ハワイに寄ったのが面白かったのですが、それでも10日くらいかかり、あまりにも退屈だったので太平洋を船で渡ったのはこの1回 だけ(笑)。
1967年の2月に日本について、プレジデント・ウイルソンで知り合った、アメリカの留学から帰ってきていた日本人の夫婦と一緒に調布市の新築の木造アパートに住むことになりました。最寄りの駅は小田急線の成城学園前駅でしたが、アパートは駅からは遠く、調布市の三船プロダクションの近くにありました。駅から徒歩で約20分でしたが、周りは田んぼだらけでとても静かな所でした。

当事者を地道に取材
──いよいよ、元新人会員たちのインタビューに取り組まれることになります
このあたりのことは『新人会の研究』の後書きにも載せましたが、1967年2月から2年間ほど日本に滞在して、本格的に新人会関係者へのインタビューに取り組みました。当時存命だった新人会員のインタビューで、一番早かったのは、1964年の夏、嘉治隆一と林要でした。そこから間が空いて、1967年から1969年まで35人にのぼる元新人会員に会うことができました。
このインタビューについては、準備が一番大切でした。事前に入念に当人に関して調べて、「この資料によると○月○日、あなたはこのような事件に参加したとか、またはこのような発言をしたとか……」と尋ねると、本人は頭をかきながら苦笑いして、「そんなこと覚えていないなあ」などということもありました。皆さん当時60代から70代という社会的にも地位がある方も多かったのですが、証言については極めて率直で、何でも聞いてくれ、という協力を得ました。記憶になくなったことはあったでしょうが、覚えている限り、また自らの記憶にあることは本当によく話してくれたと今でも思っています。
新人会メンバーには、当時のことなので往復はがきで「お会いできませんでしょうか?」と往信面に書き、都合の良い日程や場所については来信面でお返事をもらい、ご自宅などへ訪ねて行きました。その三十数人のを訪問するために東京中を歩き回りましたが、東京という大都会の多様性、つまり当時はまだまだ郊外には畑や田があったり、都心でも大きな緑地帯があったりという、不可思議な魅力に魅せられていった記憶があります。
中野重治の小説『むらぎも』に登場する人たち、また作者の中野自身に会えたこと、そしてキリスト教徒として社会運動にも取り組んだ住谷悦司・同志社学大総長ら、記憶に残る人々がいます。
──当時は大学内でも学生運動が盛んで、大学紛争へ突入という時代でした
当時日本の大学は、学生運動が真っ盛り。しかし私は残念ながら、アメリカでも日本でも現実の学生運動とは、ほとんど接触しませんでした。インタビューを受けた皆さんたちにも、多かれ少なかれ目の前で起こっていた学生運動について、自分たちのかつての運動に重ね合わせて色々な思いがあったでしょうが、特にそれが、彼らの証言に影響を与えたというようなことはないと思います。
この『新人会の研究』の翻訳書でも触れたように、新人会創立50周年記念集会が、奇しくも1969年1月19日安田講堂攻防戦の当日に、当時赤門近くにあった学士会館分館で開催されました。催涙ガスの匂いが漂う会議室で、「新人会」を振り返る集会に多くのOBが出席し、私も招待を受けて参加していました。本当に「歴史的な集い」となりました。
学生運動が、ゲバ棒と警察機動隊との衝突、と運動の過激化が急速に社会問題になっていたころで、新人会OBたちもこれについては否定的な見解を述べることが多かったように思います。当時の暴力的な学生運動に好意的な見解を述べたのは、田中清玄ぐらいだったように覚えています。新人会の本にも書きましたが、清玄さんは確かに「転向者」に違いはありませんが、それとともにフランス語でles extrémes se touchesというように、右と左が接点する微妙な位置に存在していたと思われますね。私がずっと以前に研究したジャック・ドリオと相通ずるところがあるように思います。

──インタビューした中で、印象的だった方はいらっしゃいますか
こうやって喋(しゃべ)っていると、当時お会いした色々な方の顔が思い浮かび、思い出が尽きませんが、現実社会や政治への考え方、世の中の捉え方には、多様なものがありました。
また私も、1920年代当時の彼らの活動や出来事、学生時代の彼らの考え方と同時にその後の人生や経歴、そして新人会活動がその人生に与えた影響など、注意深く彼らの言葉を聞きました。中にはその後の人生について触れたがらない人もいましたが、逆に積極的に問わず語りに非常に多くを語る人もいました。学生時代の思いが如何にその後の人生で変化していったか、「転向」したか、ずっと自分はそれを意識して生きてきたなどを彼らは語ってくれました。
「帝大新聞」をはじめ新人会関係の史料の収集はこの頃社研の図書室のスタッフだった小黒義雄さん、有山照雄さん、今井典子さんらに大変お世話になりました。史料はどこで探すかとか、コピーはどういうふうにつ作ればいいかとか、いろいろと相談に乗ってもらいました。皆さん献身的に私のインタビュー活動を支えてくれました。
「帝大新聞」のOBである菊川忠雄氏の著作『学生社会運動史』(中央公論社、1931年。伏字を復元して1947年に海口書店刊)には、大正・昭和初期の出来事が網羅されていて、たいへん参考になりました。菊川氏は1954年に亡くなられていて、お会いすることはかないませんでしたが、新人会の「幹部派」と言われ、服部之総らに対抗した「非幹部派」の中心人物で、新人会の活動を穏健な大衆運動につなげていこうという思想の持ち主でした。その著作を見ても素晴らしい方だったと思います。
さて私は1968年にハーバード大学に戻り、学位論文を書き、その論文が元になった『Japan’s First Student Radicals』(ハーバード大学出版会、1972年)という最初の本を出しました。この日本語版が「新人会の研究」であります。同じ年に ハーバード燕京(エンチン)研究所のフェローで在米中だった京都大学の松尾尊兌先生が手伝ってくれました。松尾さんは日本での出版に際しては、翻訳者であり、私のミスや誤解を訂正してくださり、原書よりも翻訳書の方がしっかりしたものになりました。また詳細な脚注や、親切な「訳者あとがき」を書いてくれています。今でも大きな感謝の念を懐いております。先生が3年前に亡くなったことは悲しい限りです。
──今振り返り「新人会」とは何だったのでしょうか。またこの「新人会」研究の意味は
今の日本の状況を見ても、また世界的に見ても、旧「共産主義」の消滅から始まった左翼リベラリズムの衰退は明らかです。私はあくまで「センターレフト」の温和な自由主義者で、これら左翼に積極的に加担する気はありませんが、歴史と精神史の中で、改めて「新人会とは何だったか?」考える必要があると思います。
労働組合や労働運動に根差さない、それも国家権力の牙城としての東京帝国大学の「新人会」という運動は、あくまで学生時代の一過性のもの、また学術的理論的で、「大衆を啓蒙する」という知的な傲慢さがあった等と批判されたりもしましたが、果たして労働組合による政治運動や社会運動だけが評価されるものなのでしょうか。その後、日本の知的な風土に根付いた、「新人会」の業績は、戦後憲法や保守主義、立憲主義や経済成長にも大きな影響を与えたのではないでしょうか。
私が、新人会員OBのインタビューで、当時の思想や行動だけでなく、現在の自分自身に至った軌跡を詳しく聞いたのもそのためです。「新人会」ははしかのような学生時代の一過性の思想活動でなく、「転向」のように形を変え、仮に逆の政治的立場になっても各個人の中でその体験は生き続けたのではないでしょうか。
━━今後も「新人会研究」は重要ということでしょうか
20世紀に入って「自我に悩み、社会を心配する若者」という社会青年のイメージは、初期新人会のレトリックにも当てはまります。「新人会」は皆さんもご存じのように、1920年代の学生運動として歴史に大きな影響を与えたわけではありませんでした。たった10年しか続かなかったうえ、学生という「過渡的な身分」であって、社会に出て活躍する前の思想的な体験と位置づけられています。それは日本の旧制高校の素晴らしい青春体験と同様に、懐かしく回顧されても、それ以上社会的に価値のあるものものとは思われませんでした。
私の本の後、慶応大学の中村勝範教授の研究室でも、十数年にわたり、大学生大学院生らによる「新人会研究」が続き、元・新人会員への聞き取りや資料収集がありました。しかしそれらが、社会で十分に注目されたり、論じられたりした気配はありません。1980年代以降、学生運動や大学改革の動きが過去のものとして忘れ去られ、また大学が社会に取り込まれる中で、新人会だけでなく「学生運動」全体が「エリート大学生の優雅な、社会的悩み」という形で、社会からその価値が貶(おとし)められるようになってきたのではないでしょうか。
あらためて「新人会とは何だったか」、決してひるむことなく今後も歴史的な意味を見つめ直してみる価値があると思います。
◇
ヘンリー・スミス名誉教授 (コロンビア大学)
1941年生まれ。1962年イエール大学卒業、1970年ハーバード大学博士号取得。現在、コロンビア大学名誉教授。編著書に『浮世絵に見る江戸名所』(岩波書店、1993年)など。浮世絵、江戸から東京への都市景観・文化、赤穂浪士など日本の文化を多彩に論ずる。またアメリカ人学生の日本留学を助ける「京都アメリカ大学コンソーシアム(KCJS)」の事業にも長年貢献している。
【参考】『新人会の研究』より本文の引用