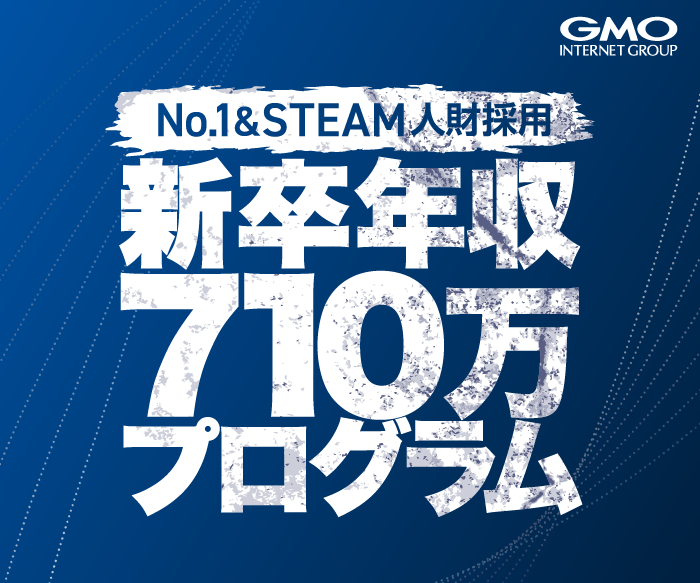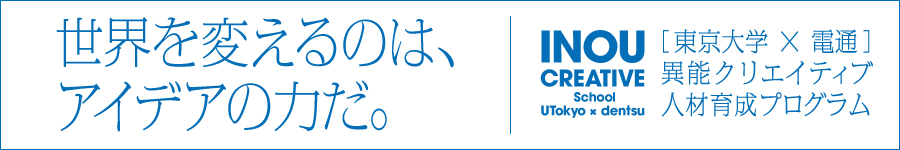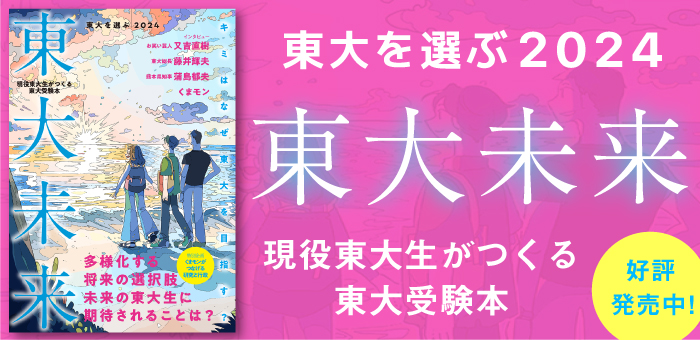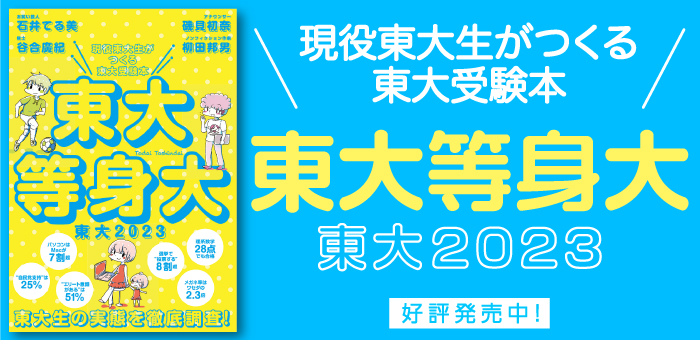西欧に対する後進性へのコンプレックスを抱え、「西欧とは異なるもの」としての独自性を打ち出そうとしてきたロシア。そこで育まれてきた思想とは何だったのか、そしてロシア社会において思想はどのような役割を担ってきたのか。また、今年2月でロシアによるウクライナ侵攻開始から3年を迎える。今回の戦争が自身の研究や考え方に与えた影響も含めて、20世紀初頭のロシア思想、特にフロレンスキイを中心に研究を行う細川瑠璃講師に話を聞いた。(取材・石井誠子)
フロレンスキイの言葉を紡ぐ
学生時代は研究者を目指していたわけではなかったという細川講師。ただ、第二外国語で選択したロシア語は、せっかく選んだからにはしっかりと身に付けて卒業したいと考えていたという。2年生の時に20世紀ロシアの有名な詩人たちの作品をロシア語で読むゼミに参加したことがきっかけで本格的にロシアを勉強したいと思うようになり、その後は教養学部地域文化研究分科ロシア東欧研究コースに進学した。当初はロシアの美術に興味があり、卒業論文では画家のヴルーベリを扱ったが、美術を研究することの難しさを感じていたという。画家が制作時の意図などを手記や手紙に残していない場合、絵画だけから全てを読み取るのは難しい。また、距離の遠さや手続きの複雑さゆえに気軽に現地に行けず、美術研究はしづらかった。
そんな中、20世紀初頭のロシアの思想家、フロレンスキイとの偶然の出会いが転換点となった。卒業論文の口頭試問で、美術を専門にしたいのであれば美術に関して書いた思想家を読んではみてはどうかと助言を受け、フロレンスキイを読み始めた。そこからフロレンスキイの思想に興味を持ち、美術から思想の研究に移ったと経緯を語る。「卒業論文の執筆時には、ロシア思想をやろうとも、博士課程まで行くかも決めていませんでした。ただ、フロレンスキイの言葉を読むにつれて、彼についてもっと知りたいと思ったのです。その出会いがあったからこそ、今この道に進んでいるのだと思います」
もちろん、ロシア思想の研究においても困難はある。特に、2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻を境に状況が大きく変わったという。開戦前はロシアとの学術交流は活発だった。科研費(科学研究費助成事業)を使ってロシアに渡航することも、ロシアにいる研究者と共同で学会を開き、ロシアで学会発表をしに行くこともできた。しかし開戦後、ロシアへ自由に渡航することができなくなってしまった。ロシアに経済制裁が科されているためロシアから資料を入手できず、さらにロシア人研究者との交流も減ってしまったと話す。昨年3月にはリトアニアで学会が開かれたが、リトアニアとロシアの関係悪化に伴いロシア人の入国が制限されているため、ロシア人研究者の参加はかなわなかった。ロシアの隣国であるリトアニアにとってウクライナで起きていることは他人事ではなく、次の戦場になる危機感が背景にある。
「ただ、ロシアという国と向き合う上で、これくらいの困難は仕方がないと思う部分もあります」と続ける。ロシアとは言論の自由に対する困難を抱え続けてきた国だった。誰もが自由に言葉を発信できたわけではなく、たとえ発信してもそれが自分の意にそぐわない形で出版されてしまうことがあった。帝政時代やソ連時代には検閲が行われ、政府の方針にそぐわないと見なされれば出版を差し止められた。そのため、詩人や小説家、思想家は、亡命者に原稿を委ねて外国で出版したり、地下出版をして仲間内だけで読み回したりすることで、何とか自分たちの言葉を紡いでいった。「その歴史を踏まえると、現在の戦争に伴って起きていることはある意味でロシアらしくもあります」
スターリン政権下の1937年、フロレンスキイは知識人であるという理由で粛清される。書きためていた原稿も多く、思想に関しても大きい著作を書いている最中だったが、それを納得の行く形で完成させられないまま絶たれた人生だった。「彼の言葉がそのまま歴史の塵(ちり)の中に埋もれてしまうのを、その時間の流れからすくい出し、他の人たちに届けたいのです」と細川講師は思いを
語る。かつての人の言葉を受け取り、次の世代へと紡ぎ続ける行為は「人文学の営みや使命そのもの」であり、「たまたまフロレンスキイの思想に出会ったからには、それをちゃんと受け取って次の世代に渡したい。そう思うと、先ほどの困難も仕方のないものとして受け入れられます」と強い意志を見せた。
近代化するロシアの葛藤
20世紀を代表する思想家であり、「ロシアのレオナルド・ダ・ビンチ」と呼ばれることもあるフロレンスキイ。モスクワ大学で数学を修めた彼は科学者として活躍した一方で、ロシア正教会の神父も務めており、宗教とのつながりも深かった。彼の思想は、宗教と科学がいかに融合しうるのか、分かり合えない部分はどこかなど、両者の関係性を考察する手掛かりにもなるという。また、当時のモスクワはロシアの文化の中心地であり、そこにつどう芸術家との交流も深かった。フロレンスキイを研究すると、必然的に20世紀初頭のロシア文化史を俯瞰(ふかん)していくことになる。
20世紀初頭のロシアは日本と同様に西欧から遅れて近代化した国だった。19世紀には近代化が始まり、地理的に近いドイツなど西欧の文明を吸収する中で、「西欧の進んだ文明に対して遅れたロシア」という自意識が形成されていく。一通り西欧の思想を吸収した19世紀半ばに、西欧にどこまで迎合し、どこまで独自性を出すべきかという迷いが生じるようになる。その結果、ロシア思想は大別してスラヴ派(ロシアやスラヴ人の独自性に立脚した哲学を追求するべきとする立場)と西欧派(西欧に学ぶべきとする立場)に分裂する。
スラヴ派の運動の一環として、ロシアの芸術を西欧とは異なるものとして発信する動きが見られた。20世紀初頭に起きた、バレエ団「バレエ・リュス」による、ロシアのバレエを国外へ輸出する動きはその一例と言えなくもない。輸出先のパリでは、ピカソやココ・シャネルなど、当時のさまざまな分野の芸術家たちがそれを面白がり、あるいは共鳴し、共同で作曲したり舞台芸術を描いたりした。ロシアを西欧とは異なる「野蛮」な面白さを秘めたものと見なして、その独自性を打ち出していく試みであった。このような運動はナショナリズムの台頭に結び付きかねない点で問題もあるという。「例えば哲学においては、単にロシアの面白い独自性を発掘するだけであれば良いかもしれませんが、『西欧とは違うロシアの世界』を押し出すことで、政治的な動きにつながることもありえます。その点で、現在の戦争に結び付く部分もないとは言えません」。当時のロシアは「ロシア性」と「外国との協調」との折り合いをどう付けるべきか模索していた時代だ。自分たちに向けられているオリエンタリズムを内面化している部分もあるが、ロシアという国の宿命的なところもそこにあるという。ロシアは西欧に地理的に近いため、自分たちの後進性を強く意識させられた。独自性の出し方が常に懸案事項であり、それがロシアの運命を形作ってきたのだった。

科学か宗教か フロレンスキイの宇宙観
スラヴ派において、ロシアの独自性は宗教に見出されることもあった。同じキリスト教でも、西欧はカトリックやプロテスタント、ロシアは正教と、宗派の違いが見られる。19世紀後半には、正教の教義や宗教思想に自分たちのアイデンティティーを見出し、それを哲学に取り入れる動きが起こった。
フロレンスキイもその一派であり、宗教的、神秘的な物を追求しようとする宗教哲学の潮流の中にいた。とはいえ、彼は西欧に対して反発的であったわけではない。実際、フランスの数学者ポワンカレやアインシュタインの理論を自身の思想に取り入れ、また幼少期にはドイツの文学者ゲーテの作品に親しんでもいた。西欧の学問や知を尊重しつつ、一方で西欧に迎合しない何かを作り出し、ロシアの独自性を打ち出していこうとする立場を取っていた。彼の思想の中心にあったのは、西欧の哲学が提示してきた近代的・合理的な世界観への抵抗であり、それまで取りこぼされてきた神秘的なものや論理で語りえないものをあえて哲学の言葉で語る試みであった。
神秘思想とは神との融合を目指す思想を指す言葉だが、フロレンスキイの中では筋道だった論理を経てそこに到達している。一例として、天動説という宗教的な宇宙観を科学的知識によって示そうとしたことが挙げられる。そこでフロレンスキイは、例えば「運動は相対的な物である」という相対性理論の部分的かつ不完全な引用から、「宇宙において地球が動いている」という主張と、「地球が止まっていて周りが動いている」という主張はどちらも成り立つと言えるのではないか、などと論じていく。西欧の科学に通じているために科学的に見える後付けがいくらでもできてしまうのだ。提示したい世界観のために科学をこじつける目的論的な方向性や宗教的な拠り所のために科学とは言えないが、宗教と科学を混ぜ合わせ、両者の境界をあいまいにしている点が面白く、人を引き付ける。迷信や陰謀論も目的論的な世界観で作られている点で似た部分があるという。「フロレンスキイの神秘主義的な主張を信じるのは違いますが、その頭の使い方や理路をたどっていくと、人間の思考がどのような過程を経て作られていくのか見えて面白いです」と魅力を語った。
ロシア社会と思想 危険性と可能性
ロシア社会において、思想は現在でも重要な位置を占める。「ロシアは自分たちの思想に対して誇りやアイデンティティーをもっているという印象を受けました」とサンクトペテルブルグ大学の哲学研究科に留学していた頃を回想する。「ロシアで哲学と言えば第一義的にロシア思想を指し、研究者もロシア思想を扱う人が多かった印象です」
ソ連という国家自体、共産主義というイデオロギーを体現してできた国家だった。「ロシアには思想が単なる本の上の言葉ではなく強い影響力を持ち、社会にそのまま体現されるという文化的特徴があります。言葉の持つ力が強く信じられている社会だと感じます」。「言葉の持つ力」とは良い影響だけに限らず、思想家の言葉が一部の政治家に悪用される場合もある。例えば、プーチン大統領はロシアの思想家、特にフロレンスキイと同時代のイリインなどの思想を読み込んでいる。ウクライナ侵攻開始後、自身の演説の中で 20 世紀初頭のロシアの思想家を引用するなど、意識的に取り入れている様子が見られるという。「ロシアは後進性に対するコンプレックスが大きく、それを解消するために自分たちの思想家が書いたものを読むべきだとの意識があります。だからこそ、ロシアの後進性の問題に向き合っていた 20 世紀初頭の思想家をプーチンも読むのでしょう」
ロシア思想が現在のウクライナ侵攻に直接的に影響しているかについては議論の余地がある。しかし、方向性としては「西欧とは異なる自分たち」を意識する部分が根底にあるという。その自意識にはロシアに加えてウクライナなどの周辺国も含まれ、これらの国が合わさり広い意味で「ロシア世界」を構成しているはずだと考えられている。今回の戦争でも、西欧とロシアの境界がウクライナとロシアの間ではなく、ウクライナと西欧の間にあるはずだという、西欧とロシア世界を対立させる考え方が背景にある。そのため大局的に見て、西欧との違いを強調し、ロシアの独自性を打ち出そうとしたフロレンスキイを含むスラヴ派の思想とつながりがないとは言えない。
ここで問題なのは、西欧との違いがロシアの保守的な方向性と結び付けられてしまっていることだという。ロシアは後進性を伝統的価値観の保持という肯定的な言葉へすり替えることで、コンプレックスを解消しようと試みている。その過程で、もともとロシアの保守的な人々が持っていた考えを西欧との違いとして打ち出してしまったのだ。開戦後、ロシア国内でLGBTへの弾圧が一層激しくなっているが、これもLGBTをごく普通のものとして受け入れている西欧との違いを打ち出したいがために、弾圧する方向性へ向かってしまっている部分があるという。「私はそれに憤りをおぼえています」と細川講師は続ける。「ロシアを研究していると言うと、ロシアに対して親和的だと誤解されることがありますが、実際は必ずしもそうではありません。ロシアの研究者として、ロシアの行いの全側面に同意しているわけではないと強く言う必要があると感じました。その立場を発信していく意味で、例えば東京でプライドパレードが行われる時は必ず参加するようにしています」とロシアによるウクライナ侵攻後の意識の変化を語った。

「開戦前、ロシア研究はニッチでマイナーな世界であり、その面白さを伝えることに重点が置かれていたという認識がありました。ロシアの独自性も単に面白いものとして発信していましたが、そうとも言っていられない事態になってしまったわけです」。ロシア思想とは、西欧に対する他者として自分たちがどう振る舞っていくか、他者同士がどう向き合うべきか、あるいは他者が集まってできている共同体をどう考えていくべきか、といった問題に光を当てようとしている思想でもある。本来は他者について考える想像力を養い、西欧主導の文明「ではないもの」の可能性を提供しうるものだったロシアの独自性だが、今回の戦争で、それがナショナリズムにつながりうることも浮き彫りになった。「これからもロシアやスラヴ地域に関わるに当たって、単に面白いものとして紹介するのではなく、自分の言葉の重みを常に意識しなければいけないと思います」
さらに、ウクライナ侵攻を受け、ロシア中心の見方に懐疑的になったと研究に対する姿勢を振り返る。「学生の頃所属していた地域文化研究分科ロシア東欧研究コースも、つい『ロシア科』という名称で呼んでしまっていました。ロシア東欧という枠組みの中で、ロシアの存在感が強く、どことなく東欧を無視しがちだった部分があります。私もスラヴ地域を考えるときに、まずロシアを軸に考えてしまう癖がどうしてもありました」。今回の戦争を受け、ロシアに加えてもう一つ軸足を持っていた方が良いと感じ、これを機に20世紀に論理学者を多く輩出したポーランドなどの東欧にも目を向けたいと話す。同じスラヴ圏といっても、ポーランドの宗派はカトリックで、正教会が中心的なロシアとは異なる社会でもある。「ロシアという枠組みを越えた、スラヴの専門家を目指しています」と抱負を語った。