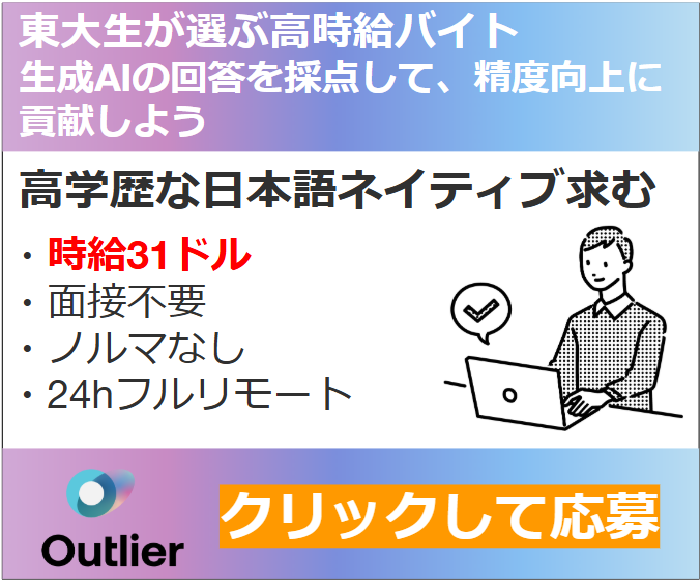キリスト教と聞いて思い浮かべるものは何だろうか。多くの人はヨーロッパ文化圏と結び付けて考えるかもしれない。確かに、高校までの歴史で習うカトリック、プロテスタント、ギリシア正教(※1)などの耳になじみのある宗派は、ヨーロッパを中心舞台として語られることが多い。しかし、キリスト教の実態はヨーロッパの枠に収まりきらないほど多様だ。地中海とカスピ海の間に広がるコーカサスやその周辺地域にもキリスト教の信仰は存在する。さらに、コーカサス諸国の中でも、ジョージアではギリシア正教会の系統に属するジョージア正教会、アルメニアでは非カルケドン派(※2)のアルメニア教会が主流であり、信仰される宗派には違いが見られる。
浜田華練准教授は、アルメニアをはじめとするコーカサスのキリスト教を中心に研究を行っている。アルメニア教会は周辺の諸教会や身近な他宗教であるイスラームとどのように関わってきたのか、浜田准教授の研究半生も含めて話を聞いた。(取材・石井誠子)
※1:いずれの宗派も5世紀にローマ帝国によって招集されたカルケドン公会議を承認している。カルケドン公会議では、受肉した神であるキリストにおいて神的本性と人的本性が共存するという教義(二本性説)が採用された。
※2:カルケドン公会議を承認していない宗派。アルメニア教会のほか、シリア正教会やエジプトのコプト正教会が属する。カルケドン公会議の二本性説を退け、キリストにおいて神的本性と人的本性は合一するという教義(合性説)を採用。

研究の原点は「東方間違い」
「その時面白いと思ったことに食いついて、場当たり的に生きてきました」と語る浜田准教授は、宗教にはもともと関心があったそう。「伊勢神宮で有名な三重県伊勢市の出身で、宗教を『宗教』として意識する機会が多かったことが理由の一つかもしれません」。中学高校ともにカトリック系の学校に通っていたため、キリスト教も身近な存在であった。大学受験が終わった後に読んだドストエフスキーに引かれてロシア正教に興味をもち、第二外国語はロシア語を選ぶ。一方で、中央アジアのイスラームにも関心があり、研究対象を何にしようか迷っていた。
「アルメニアに行き着いたのは、事故のようなものです」と学部時代を振り返る。当時駒場に着任したばかりだった高橋英海助教授(当時)の授業を受けたことがきっかけだった。授業のテーマは東方キリスト教。「東方」と聞き思い浮かべていたのは、西欧に対する東方のロシア正教やギリシア正教だった。いざ授業に出てみたら、「東方間違い」であったことに気付く。実際はシリアやコーカサスという意味の東方を指していた。しかしその授業の中で、ロシア語を学んでいるのであればアルメニアについて調べてみてはどうかと高橋助教授に言われ、アルメニア教会について調べることに。ふたを開けてみると、自分が今までやりたかったことが詰まっていることに気付いた。
キリスト教は中東に起源を持つが、中学や高校で学ぶ世界史では、ある時期からヨーロッパのキリスト教についてしか語られなくなる。しかし実際は、シリアやアルメニアなどの東方キリスト教が、現在ではイスラームが中心となっている中東地域でキリスト教の伝統を保持してきたのだ。また、アルメニアは19世紀にイラン領からロシア帝国領に併合された歴史がある。浜田准教授はロシア正教が主流であったロシア帝国内における、正教ではないアルメニア教会の処遇に関する議論にも興味をもった。「中央アジアや中東とロシア、イスラームとキリスト教のどちらを研究対象にしようか迷っていた時に躍り出てきたのが、地理的にも中間の位置にあるコーカサスのキリスト教でした。両者のいいとこ取りができるのではないかと思い、安易に飛びついたというわけです」
地域文化研究は「毎日が異種格闘技戦」。同じゼミに古代のスキタイ人をテーマとする人がいたかと思えば、ユーゴスラビア紛争やチェチェン紛争など現代のテーマを扱う人もいる。「なぜそのテーマを研究するのか」とわざわざ問うてくる人はいない。何をやってもよく、自分のやっていることに価値があるという前提を共有している世界は居心地が良かった。初めはアルメニアから始まったが、隣国のジョージア、さらにはシリアのキリスト教にも関心が広がっていき、今に至っている。一方で、研究内容について問われた時、答えに困ることがあると言う。コーカサスとは何か、なぜその地域にキリスト教の信仰があるのか、などの背景から説明する必要があり難しい。それでも、「一言で説明できないところに面白さがあるのではないでしょうか」と笑顔を見せる。
「冷蔵庫ではない」生きた伝統 多様な姿
アルメニアをはじめとするコーカサス地域は、ヨーロッパとアジア、キリスト教とイスラームという、文化圏や宗教圏の狭間にあたる地域だ。ここでは普段当たり前のものとして捉える境界が絶対的なものではないことに気付くことができる。例えば、キリスト教とイスラームは対立関係の構図の中で語られがちだが、史料からはそのようなステレオタイプとは異なる実態が見えてくる。
「13、14世紀になると、教会が公的なものとして残した教義書や歴史書の他に、物語的な性格をもった文書が写本に書き残されるようになります」。日本でいう『今昔物語集』のような説話文学に近いもので、一般人を登場人物とし、宗教的な教訓を含む。その中には、キリスト教徒と異教徒の友情や恋愛も描かれている。アルメニア人は、14世紀に最後のアルメニア王朝であるキリキア・アルメニア王国が滅びた後、イランやオスマン帝国などのムスリムが多数派であり支配者である地域に少数派のキリスト教徒として暮らしていた。「彼らにとって、ムスリムは当たり前のように隣にいる存在であり、日常的に接する隣人でした」

現代は多様化、グローバル化の時代と言われるが、多様化やグローバル化は現代になって初めて現れた現象ではない。人間社会本来の姿は多様だ。一方で、時代ごとに多様性を画一化しようとする覇権的な力も働いている。そのような権力を持つ勢力の言説は広く出回りやすいため、歴史を紐解いていく上で、画一化しようとする言説の方がどうしても目に付いてしまう。「ところが、地域と地域、あるいは文化と文化の狭間に生きる人々の中には、一国の歴史や文化などの画一化された叙述の中には出てこない、人間社会本来の多様な姿が目に見える形で残っています。彼らの歴史、あるいは彼らが残した文学作品を研究することは、現代でも十分に意味のあることです」
さらに「古い時代を扱う時の姿勢として、その地域独自の文脈の中で培われ変容してきた伝統の中に、今生きている人がいるという視点も大切です」と話す。この考えに至った背景には、あるアルメニア人修道士の言葉があった。
大学院生の時にベネツィアでアルメニア・カトリックの修道院が主催するアルメニア語サマースクールに参加した時のことだった。同じくサマースクールに参加していたヨーロッパ系の研究者が、アルメニア語文献の中には古代ギリシア思想や古い聖書の翻訳など、ラテン語やギリシア語文献では失われてしまった古い文献が残っており、研究対象として興味深いと話していた。それに対して修道士が冗談めいた口調で言った言葉が「私たちはあなたたちの冷蔵庫ではない」だった。この言葉が非常に印象に残っていると言う。
「冷蔵庫というのは、非常に秀逸な例えです」。ヨーロッパの人々からしてみれば、自分たちの文化的なルーツとして捉えているキリスト教や古代ギリシア思想をアルメニアが残していると見ているのだろう。確かに、冷蔵庫に古い食材が保存されているように、アルメニアのような辺境とも言える地域には古い状態で保存された史料がある。中心地域は新しい物との入れ替わりが激しいため、辺境にこそ古い文化が残りやすいというのはしばしば言われることだ。しかし、中心に位置する人間が、自分たちの作りたい「料理」のために必要な「食材」を「冷蔵庫」から適当に取り出すこと、自分たちの文化にとって重要な古い文化を都合よく残しているものとしてだけ辺境を捉えることは、非常に自己中心的な物の見方ではないか。自分自身も日本人としてキリスト教や古代ギリシア思想とはやや距離がありながら、アルメニアやコーカサスを冷蔵庫のように扱ってきはしなかったか。そんなことを突き付けられたと回想する。
「古いものは誰かが残していかなければ失われてしまうため、古い時代を扱う研究者としては、それらをどうにかして掘り起こしたいという願望はあります。一方で、アルメニアという地域の歴史的・文化的背景の中で育まれ変容してきた文化があり、その中で今も生きている人間がいます。古いものが変わらずに残っているというよりは、生きた伝統がそこにあることを忘れないようにしなければいけません。その意味で、『冷蔵庫ではない』という言葉は深く心に刺さりました」
権力勾配の中で ロシア帝国におけるアルメニア教会
狭間に生きるアルメニア教会の歴史は、不均衡な権力関係に翻弄(ほんろう)される歴史でもあった。19世紀にロシア帝国に併合されてからの出来事を見てみよう。ロシア帝国では正教を最も優越する宗教として国の根幹に据えており、ロシア皇帝は正教の守護者であると規定されていた。その中で、正教以外の宗教や宗派のうち認められたものに関しては「外国宗教」として法的な地位を与えられていた。
1840年代には、それまで外国宗教として位置付けられていたアルメニア教会を正教会の一部にしようとする教会合同の動きが出てくる。主な推進派はロシア正教会の聖職者および一部の内務省の役人。アルメニア人側はおおむね反対していた。教会合同に際して、カルケドン公会議で決定された事項を認めるか否かという教義のすり合わせの他、暦の違い、聖餐祭(せいさんさい)で使うパンを発酵させるか否かなどの細かい風習に関して妥協点を探る必要があった。ただし、アルメニア教会と正教会は対等な立場にあったわけではない。帝国内で多数派であるロシア正教の聖職者が提唱した教会合同の実態は、少数派のアルメニア教会が段階的に正教化するというものだった。1960年代以降、キリスト教の諸宗派の違いを乗り越え、多様性の中で一致を目指すエキュメニズムという運動が世界的なキリスト教の潮流として見られるようになるが、当時の教会合同はそのような動きとは前提がかけ離れていた。
「宗教とは自分たちにとっての正統を作り出す営みです。その過程で、どうしても正統の枠組みから漏れ出てしまうものも出てきます」。それを異端として排斥することには問題があると言う。しかし、正統派を自認する人々が、正統の枠組みからはみ出た人々を主流派の中に包摂しようとすることは果たして良いことなのか。「正統の枠組みからはみ出た人々にも、築いてきた伝統が存在します。また、正統教義という枠組み自体も所与のものではなく、長い時間をかけてなされたさまざまな議論の上に成り立っているものです。お互いの正統を尊重しつつ、自分たちの正統に含まれないような人や集団を1個の主体として尊重する在り方が重要になります」

アルメニア教会の権力との不均衡な関係はこれだけに留まらない。もう一つの例として、ロシア帝国の対オスマン政策が挙げられる。アルメニア教会には他の外国宗教とは異なる特殊な事情があった。ロシア帝国領である東アルメニア地域の中に、アルメニア教会総本山のエチミアジンが含まれていたのだ。これは、ロシア国外にあるアルメニア教会もロシア帝国内にあるエチミアジンのアルメニア教会の管轄下に置かれることを意味する。このねじれをどう利用するかがロシア帝国によるアルメニア教会政策の根本に据えられることとなった。
当時のロシア帝国はオスマン帝国と何度も戦争を繰り返していたが、オスマン帝国内にはアルメニア人が相当数存在していた。その中には現地の社会で経済的・政治的に高い地位に就いている人もいた。ロシア帝国としては、ロシア国外のアルメニア人を味方につける上で、できる限り支配下にあるエチミアジンの権威を有利な駒として使おうと目論んでいた。その一環として、アルメニア教会の総主教に当たるカトリコスの地位を高めようと、正教会の高位聖職者と同等あるいはそれ以上に特権的な地位を与えることもあった。しかし、19世紀末にアルメニア人のナショナリズムの気運が高まってくると、帝国側は教会が運動の中心となることを警戒し、アルメニア教会の財産を没収するという抑圧的な政策に一転する。一連の流れから、アルメニア教会がロシア帝国の対外・対内政策に都合よく振り回されていた状況が見えてくる。
多数派と少数派の権力勾配はいつの時代・地域においても見られる現象だ。「例えば、私は数少ないロシア語選択者の1人として、学内である意味マイノリティーの立場にありました」と学生時代を引き合いに出す。「サークルなどで自分がロシア語選択者であることを話すと、必ず『なぜ?』と聞かれます。不思議なことに、フランス語やスペイン語選択者に対してそのような質問は向けられません。マイノリティーは、なぜか存在するだけで理由を問われるんですよね」

マイノリティーの属性を持った人々は、存在理由を問われる他に、困難を乗り越え今に至るストーリーをマジョリティー側から常に求められると浜田准教授は語る。「確かに、そのストーリーが同じ少数派の属性を持った人々のエンパワメントにつながることもあります。しかし、そのようなストーリーが多数派から少数派に求められること自体が権力勾配の現れであることを意識することが必要です。私も日本にいる以上、日本人であるという意味でマジョリティーの立場にあり、また研究者として、物事の背景や今に至る経緯を考えることが多々あります。少数派に対して存在理由や明確な動機を求め、ジャッジする視点に陥っていないか、常に自分としても意識しなければいけないと思っています」
最後に、学生に対しては「私が学生だった頃よりも将来について考えていたり、目標に向けて努力したりしていて感心します」。一方で、もう少し目の前の楽しいことに集中しても良いのではないか、と投げかける。「そうできない環境を作ってしまっている責任はあるので無責任には言えませんが」と断りつつ「大学時代は、面白いことが身近にごろごろ転がっている、人生の中でも稀有な時間です。面白いと思った人には積極的に絡んでいってほしい。教員は特に、絡まれて嬉しくない人はいないと思うので」と続ける。「偶然の出会いや出来事に自分の人生を変えるものがあるかもしれません。予想外のことを楽しむ余裕をもって生きてほしいです」と締めくくった。