毎年恒例の退職教員インタビュー企画。今回は、哲学の一分野である現象学を専門とする哲学研究室の榊原哲也教授を訪ねた。現象学の始祖であるフッサールの思考の変遷を精緻なテクスト解析によって明らかにするとともに、近年は看護や医療ケアの現場に入り、新たな現象学を模索している。フッサール哲学の魅力、そして看護の現場から見えてきた新たな視点について聞いた。
(取材・山口岳大、撮影・円光門)

━━卒業論文から一貫して、20世紀ドイツの哲学者フッサールを研究してこられました。フッサール哲学のどのような点に魅力を感じたのでしょうか
駒場の学生時代、「自分」が何者なのか分からなくなって。僕の世代の10年上には団塊の世代がいて、1969年の東大全共闘による安田講堂占拠の時に安田講堂の上にいた、下にいたという話をしていた。僕が学生だった頃も、社会的活動に積極的な学生がいた。僕もそれは大事だと思っていたけれども、世界に関わる手前で、世界に関わる「自分」がどう生きるべきか、どう世界に関わるべきか、分からないところがあったんですよね。「自分」を見つめないと一歩踏み出せないと思った。ただ一方で、社会をかっこに入れて自分だけ見つめていればよいとも、決して思わなかった。
そう考えていた時、渡邊二郎先生(東大名誉教授。ドイツ哲学が専門)の言葉が自分の求めていたものとピタッと一致したんです。フッサールの現象学には「現象学的還元」という根本的な方法があります。これは、世界をかっこに入れて自分の純粋な意識に立ち戻るということ。この方法を、自分の意識に閉じこもることだと受け取る人が少なからずいます。だけれども、渡邊先生はこうおっしゃった。「それは誤解であって、世界をかっこに入れても世界はなくならない。世界を見つめることは自分を見つめることであり、自分を見つめることは世界を見つめることである。これが、現象学的還元の根本精神である」と。言い換えると、世界を見るためには自分を見なければならないし、自分を見ることで世界も見えてくるということです。世界をかっこに入れても、自分の意識のうちに世界は自分に見えているままに残っている。フッサールの魅力は、ここにあるのかな。
それから、フッサールは距離がうまく取れて付き合いやすい。フッサールの記述は、見えているものに忠実で非常にナイーブなんですよね。だから、彼のテクストを読み進めながら、このまま議論を進めると袋小路に入りそうだなと思うと、本当に入って行ってしまう。それに対して、メルロ=ポンティやハイデガーの場合は、先々まで見通されている、完成された記述です。だから彼らを研究しようとすると、その完成された議論をなぞるあまり批判的に読めず、研究者自身がメルロ=ポンティやハイデガーになってしまう。そうすると、研究対象と距離が取れず論文にならない。その点、フッサールは距離が取れるんです。
━━フッサール研究での最大の成果は、何だと思われますか
フッサールの書物に『イデーンⅡ』というものがあります。これは1913年に公刊された『イデーンⅠ』の執筆直後から書かれたもので、続刊として出るはずだったんだけれども、まとまらずに遺稿として遺されたんです。弟子たちの手も借りて生前から編集が続けられたテクストは、没後、全集第4巻『イデーンⅡ』として出版されました。この書物の原草稿を掘り起こして、これまで知られていなかった思索の歩みを明らかにしたのが、僕の最大の研究成果だと思います。
フッサールの思索は、静態的現象学から発生的現象学へと変わっていきました。意識とそれが認識する対象の間の相関関係の構造を明らかにするのが静態的現象学ですが、発生的現象学は、この意識が時間の経過の中で生成変化するものだと考える点に特徴があります。思索が変化したことそれ自体や、それぞれの現象学の内実はすでに知られていたんだけれども、どんなふうに変化したかは分かっていなかった。どうして分からなかったかというと、思索のターニングポイントとなった時期の草稿を年代順に読めなかったから。『イデーンⅡ』の草稿執筆はちょうどこの時期だったんだけれど、編集の過程で異なる年代の草稿がごちゃごちゃに混ぜられてしまった。だから原草稿を掘り起こせば思索の歩みが分かるんじゃないかと思ったんです。ベルギーのルーヴァン大学とドイツのケルン大学にある、フッサールの遺稿やその写し、蔵書などを保管している「フッサール文庫」で草稿を解読した結果、発生的現象学へと展開する第一歩が分かったんです。これをまとめた僕のドイツ語の論文が、今でもよく引用されています。
現在、『イデーンⅡ』とそれに続く『イデーンⅢ』の原草稿が全集の一環として出版されることになり、準備が進んでいます。これは僕の論文がきっかけです。研究を始めた時は「編集された『イデーンⅡ』がすでに出版されているのに、今更なぜ原草稿なんか読みたがるんだ」と言われたんですけど、頼み込んで文書を探してもらっているうちに、フッサール文庫の研究者の方々も関心を示してくれ、出版する意味があると考えたようです。
東大の文学部は、テクストを丁寧に読み、そこから書き手の意図を丹念にくみ取る営みを非常に大事にします。そういう方法を採って、今まで誰も気が付かなかったことを見つけられたことは、大きいですよ。日本ではあまり注目してもらえないけれど、フッサール研究をしている海外の研究者は注目してくれますね。
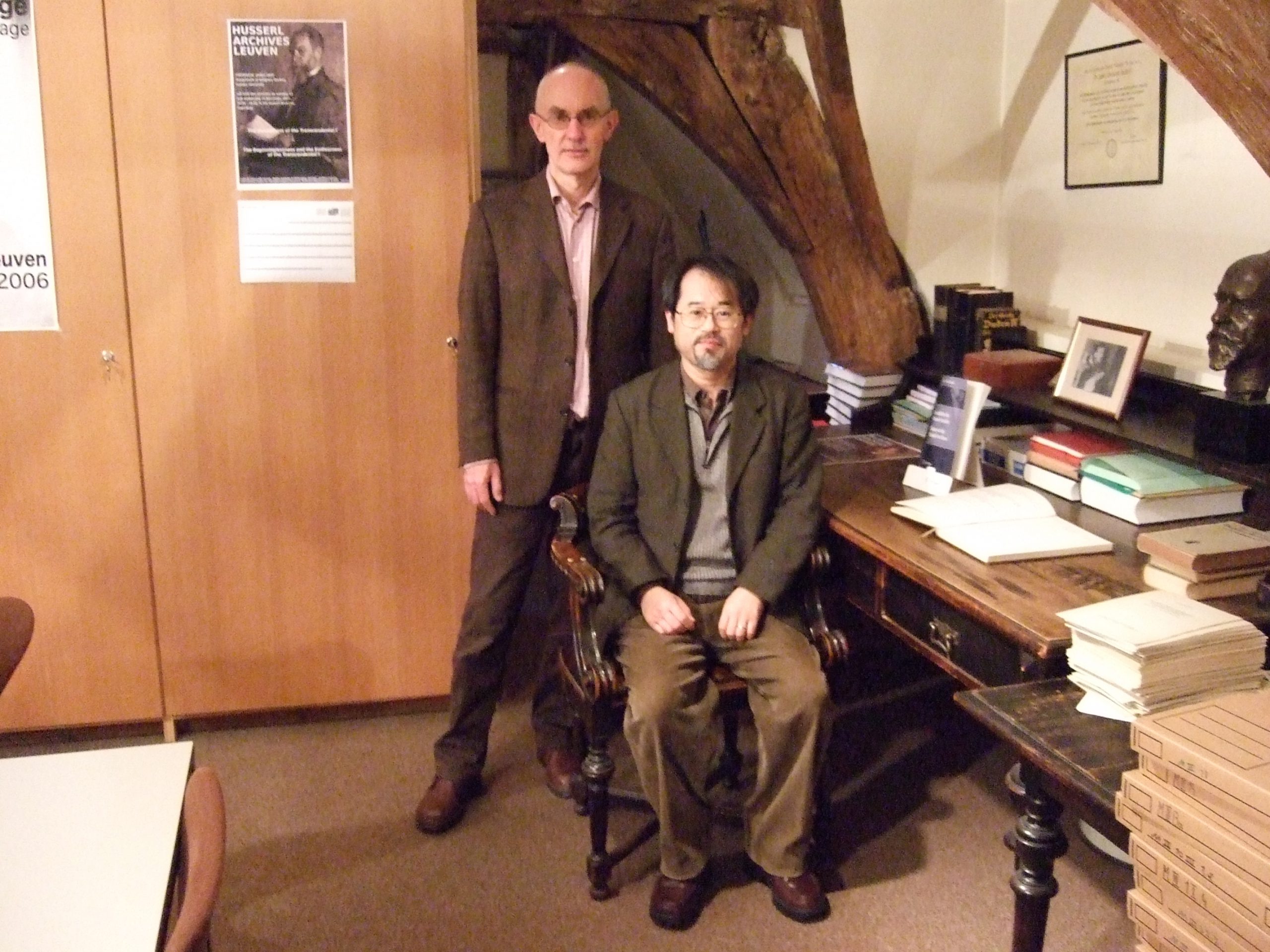
━━この10年ほど、看護や医療ケアの視点から現象学に取り組まれています。こうした研究を始められた背景には、どのような経緯があったのでしょうか
僕は東大に来る2003年までは立命館大学の教員をしていたのですが、01年に学部の上に乘らない独立大学院がいくつかできたんです。そのうちの一つが、心理臨床、家族関係、教育などを学ぶ応用人間科学研究科というもので、下に学部がないために各学部から何人かずつ出向いて授業をすることになりました。そこで、哲学専攻で一番若かった僕が行くように命じられたんです。
一体どうしようと思って。しかも、現場の人たちがいっぱいいる。京大附属病院のベテランの看護師長さんとか、30年学校の先生をしていた人とか。怖いですよね。本だけ相手にしていれば何も言われないですが、現場にいる人に「それって何でもないですよね」と言われてしまえばそれでおしまいなので。そんな時に、大阪大学の臨床哲学研究室の友人から「今、看護の方面で現象学が注目されているらしいですよ」と言われ、今でも僕の愛読書であるパトリシア・ベナー(米国の看護理論家)の本を紹介されたんです。これを基に授業をすることに決めた当初は、半期だけやって逃げ帰ろうと思っていました。でも、やってみたら面白かった。こちらは現場のことを何も知らない一方、向こうは現象学を知らないので、お互いに勉強できることが分かったんです。東大に移った後も立命館大学で授業を続け、結局それは12年間にわたりました。
━━看護の現場に入ることで、どんな発見がありましたか
初め看護の世界で現象学が注目されていると聞いた時は「そうか、現象学が看護に応用されるんだ」と思い、応用現象学ということになるのだろうと見当を付けました。しかし、研究を始めると、これは単なる応用じゃないなと。
僕の博士論文(『フッサール現象学の生成――方法の成立と展開――』)の一番大きな主張は、フッサールの哲学は「事象そのものの方から(von den Sachen selbst her)」記述も方法も立ち上がってきたものだ、ということでした。ハイデガーが定式化して有名になったモットー「事象そのものへ!(Zu den Sachen selbst!)」ではないんです。先ほど、静態的現象学から発生的現象学へと変わっていったという話をしましたが、フッサールは、探究される「事象」である意識が時とともに変化するものだと気付くと、その「事象」の性質に合わせて現象学のスタンスも、発生的現象学へと移行させざるを得なかったんですよね。
ケアの現象学も同じで、ケアの営みという「事象」から立ち上がらないといけないわけです。これは新しい現象学であって、応用ではありません。フッサール、ハイデガー、メルロ=ポンティなど現象学と呼ばれるものはさまざまありますが、これらを応用しようとすると、当てはまらない事象がいくらでも出てくるんです。それを一つ一つ丁寧に見ていくことが必要です。
━━既存の現象学ではくみ尽くせない事象には、例えばどんなものがありますか
ハイデガーに、自分の死を先取りすることで初めて本来の自分に目覚めるという考えがありますが、そうとばかりは言えない。僕は研究の一環で現場の看護師にインタビュー調査をしてきましたが、看護師の語りに、自分の死を先取りしながら本来の自分になろうとしているケースはほとんどありません。看護師のケアの原点は多くの場合、未来の自分の死ではなく昔出会った患者さんの死です。若い頃に自分が十分ケアできずに亡くなっていった患者さんのことが忘れられないわけです。今も残り続けている忘れられない患者さんの死、つまり患者さんの死の「既在」こそが、本来の自分であろうという在り方を動機づけているんです。だから、ハイデガーの言っていることは全然違う。
ハイデガーには他にも、「他者に対する気遣い(Fürsorge)」には極端な二つの型があり、その間で行ったり来たりするという考えがあります。二つの型というのは、「他者に代わって跳び込む(einspringen)」気遣いと、その反対の「他者の前で跳ぶ(vorausspringen / vorspringen)」 気遣いです。しかし、看護師の話をつぶさに聞いていくと、こうした二つの型にどうも当てはまらない。「他者の前で跳ぶ」ということの意味については解釈が分かれますが、自分の死を先取りして本来的になった人間が、その在り方を他者に示し、その他者も自分の死を先取りして本来の在り方に目覚めるよう促す、というのが僕の読みです。しかし、これはどこか押し付けがましい感じがする。看護や教育の世界には、「寄り添う」という考え方があります。寄り添うというのは、ためらっている人の肩を少し後ろから優しく押すような感じであって、決して「前で跳ぶ」ということではない。ハイデガーの記述には、この微妙な感じが出てきません。
現場で看護師たちは、寄り添うことをごく自然に実践してるんですね。それを抽象的な言葉にして語ることはあまりない。しかし言葉にしなければ誰にも伝わらないですよね。そうした営みの言語化に、まさに人文系の人間は関わることができると思います。。こういうことって、一つ一つの事例を検討していくことだから体系にはならないけれども、とても面白いんです。
━━理論化・体系化できないと、哲学としての普遍性を持ち得ないようにも思います
透析を専門とする看護師さんの経験の成り立ちをまとめた論文を『哲学雑誌』(東大の哲学会が発行している機関誌)に載せてもらったことがあります。哲学の人は誰も何も反応してくれなかったんだけど(笑)、看護関係の人たちは読んですごく良かったと言ってくれて。これは看護師さんの個別の体験のはずなんだけれども、それを読んだ看護学校の先生が「この論文に出会えて良かった。私がなぜ看護教員を続けているのか分かった気がした」と言ってくれたんですよね。つまり、個別的、具体的な体験がある種の普遍性を持つわけです。抽象的な理論を頭で理解させるのとは違い、魂を揺さぶるようなものがある。こういう仕方で人に訴えかけて普遍的な事柄を伝えることもできるんだなと思いました。
抽象的なものは、個別のものが持っている文脈を全てはぎ取るでしょう。そうするといろんな事例に当てはまりはするけれども、頭で理解してそれだけなんです。個別の文脈が入っていると一般化はされていなくても、そこに入り込むことができますよね。小説と似ています。このような意味での普遍性って、哲学では明らかになっていないですよね。でも、あるんです。絶対。
━━現在、社会には人文学を軽視する風潮もありますが、先生は人文学をいかに擁護できると考えますか
医療の世界では、必ずエビデンスを取ります。このエビデンスは数値であり、数値に表れないものは取るに足りないものとされます。看護においても、看護全体の質を高めようと「科学的根拠に基づいた看護(Evidence Based Nursing)」が提唱されたことがありました。でも、数値にならないものはここから抜け落ちます。ところが看護師さんは、数値化されないけれど、実感としての手応えを持っています。これは、現象学的に言えば「意味を帯びた経験」です。
医学的に捉えられた「疾患」と、意味を帯びたものとして経験された「病い」があるとすると、後者はエビデンスに基づくだけでは捉えられないんです。このような「病い」を捉えるときに、人文知はすごく大事。少しでも良い看護をしたいと思っている看護師さんは、このことに気付いています。ケアの現象学が注目される理由は、こういうところにあります。私自身は現場の人間ではないですが、現場の人にこういう話をすると、「うんうん」とうなずいてくれるんですね。こういう言語化ができるのって、人文学なんですよね。
昔は僕の研究は社会の役に立たないし、現象学は自分が面白いからやってるだけなんだなあと感じていたけど、ケアの関係の仕事をするようになって、生きてて良かったなあと思いました。本当に。現象学を選んで良かったと。だから、現象学、哲学が必要というのは実感としてあります。
━━学生に対してメッセージをお願いします
特に院生には、国内だけでなく海外の学会にも出て行ってほしいと思うかな。
哲学研究室では、BESETO哲学会議を駒場の村田純一先生と共に立ち上げ、これまで11回やってきました。北京大学、ソウル国立大学、東大の哲学系の院生と教員を中心とする国際学会です。院生が英語で自分の成果を発表し、それについて三つの大学の院生と教員が議論をします。
面白いと思うのは、院生同士のコンタクトが会議が終わった後も続くこと。初めの頃に参加した学生たちは、研究者になった今も交流を続けているそうです。同じ世代で互いに切磋琢磨(せっさたくま)しながらキャリアを積んでいける人とのつながりは、大きいと思います。BESETO立ち上げた教員も、みんな若い頃にドイツに留学していてつながりがあったからこそ、やろうという話になった。若い頃のつながりが、お互い教授になってから質の違うつながりを生んでいるわけです。海外の学会に参加し、いろんな大学の同年代の学生とつながることが、5年たち、10年たち、15年たったときに、実り豊かなものになるかなと思います。













