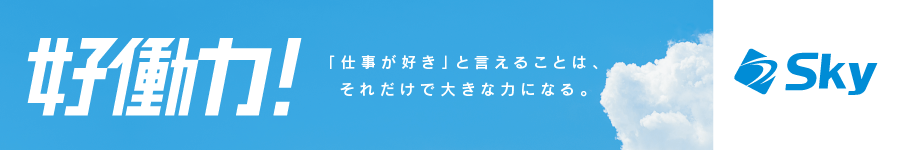昨今ジェンダー、経済格差などを描く韓国現代文学が注目されている。中には書店だけでなく映画館でも人気を博する作品まである。隣国の社会が生み出す、どこか目新しい感覚が人気の源泉なのだろう。その一方で、近代朝鮮文学に対する注目度は高くない。確かに75年以上も前に書かれた文学作品に新鮮な感覚を求めることは難しい。しかし、韓国現代文学を評価するモノサシで近代の作品を評価する見方は再考する必要がある。植民地として帝国日本の支配を受けた朝鮮の文学は、朝鮮のみならず日本の近代を問うためにも無視できない存在なのだ。朝鮮文学が日本の支配の影響をどのように受けたのか、あるいは受けなかったのか——この論評は、単なる文学史の通覧にとどまらず、日本の近代を問い直す手掛かりとなるだろう。
(寄稿)
近代化と植民地化の荒波の中で
19世紀後半の朝鮮では、西洋および日本の衝撃と圧迫の中で近代化の遅れを挽回しようとする努力が本格化する。近代教育を受けた新しい知識人層が輩出し、新聞と雑誌を通じて文明と国家に関する議論がせきを切ったように湧き出た。その中の一つとして小説改革論が提唱され、新小説と名付けられた作品が1900年代に次々登場した。新小説は、勧善懲悪の話の伝統から抜け出せはしなかったが、開港以後の現実を背景に文明開化の当為性を強調した。李光洙も生涯を通じて文学の社会的役割を深く信頼した。彼が早稲田大学在学中に書いた『無情』(1917年)は、民族という想像の共同体に目を付けた青年たちの話だ。李光洙は、近代文明を信奉し、朝鮮の将来を楽観視した。
1919年を境に李光洙を批判する新感覚の作家が現れた。その中でも、日本の自然主義文学の影響を受けた金東仁と廉想渉の活躍が目立った。金東仁は、『無情』の啓蒙主義を攻撃した。芸術は真理や倫理と完全に分離されなければならなかった。三・一運動直後の獄中体験を反映した「笞刑」(1922年)で彼は、「独立とか民族自決とかいう大義より、一眠り、一杯の水が大切だった」と豪語した。ロシア小説の沈鬱(ちんうつ)さが色濃く影響している廉想渉の初期の小説は、三・一運動の挫折を糧にした。彼の「万歳前」(1924年)は、東京から帰ってくる留学生の旅程を描いたものだが、封建遺制と癒着した植民地近代の断面を鋭く捉えている。作中の主人公は「朝鮮は墓」だと落胆する。
「日帝」への抵抗
文学を武器に植民地統治に抵抗した者もいた。流れ者の労働者として北間島(豆満江北側の地域)を転々とした崔曙海は、自身の体験を書いた「飢餓と殺戮」(1925年)で文壇に衝撃を与えた。社会主義で武装した青年たちがその後に続く。1925年には朝鮮プロレタリア芸術家同盟(KAPF)が結成された。論争が繰り広げられたが、創作の成果は芳しくなかった。彼らの文学的に成熟するためには時間が必要だった。現在でも傑作とされている李箕永の『故郷』と姜敬愛の『人間問題』が発表されたのは、KAPF解散前年の1934年になってからだった。
土地を失った農民たちは都市に流入し、労働者や産業予備軍として都市の虚栄を支えた。「運の良い日」(1924年)や「都市と幽霊」(1928年)は、都市の成長を不安げな視線で見守る。玄鎭健は妻が重い病気にかかった人力車夫の悲劇的な一日を追い、李孝石は京城の所々に隠れている貧民達を発見して驚く。2人の小説家が描写した京城は貧困と病で呻き、取り残された者は、自動車や電車を恨む。
KAPFの解散と同時期に文壇はモダニズム的傾向を帯びるようになった。モダニストたちは、言語と技巧に敏感で、市井の日常と個人の内面に注目した。朴泰遠の「小説家仇甫氏の一日」(1934年)、李箱の「翼」(1936年)では、欲望と倦怠(けんたい)感が絡み合った迷宮として京城が再現されている。不遇な小説家は創作用のノートを脇に抱え、「剥製になった天才」は「アダリン(睡眠薬の一種)」に酔って、京城市内をさまよう。しかし、ボードレールや横光利一の影響を受けたという点だけを挙げて彼らの憂鬱(ゆううつ)と夢想を説明し切るのは難しい。彼らは、日本人街と朝鮮人街が対照をなしている植民地都市を歩いていたのだった。
もう一人のモダニスト李泰俊は、京城の周縁部に注目した。彼は「月夜」(1933年)、「孫巨富」(1935年)、「夜道」(1940年)で、必死に近代を追いかける人々を愛情に満ちた視線で見守った。作中の登場人物たちは、一貫してどこか欠けていてやぼったいが、純情を保ち続けている。これらの作品は、世界体制の周縁部に後から組み込まれた朝鮮のカリカチュア(風刺画)でもあった。李泰俊の小説を読んでみると、まさに「朝鮮的」だと言いたくなるような、独特なペーソス(悲哀)が胸を打つ。
日中戦争を起点として文壇の自由は深刻な危険に晒された。1940年代に入り朝鮮語での創作を巡る状況が急速に悪化した。発表する誌面を確保するのも難しく、日本語創作が公然と求められた。いわゆる近代文学の暗黒期だ。しかし文学の全てが中断されたわけではない。たくさんの文学者たちが内鮮一体と戦争協力に応じた。信念を持って先頭に立った者もいれば、筆を折ることができずに屈辱に耐えた者もいた。忘れたい過去が、暗黒期という比喩で誤魔化された。その恥辱の歴史と正面から向き合ったのが、林鐘國の『親日文学論』(1966年)である。
朝鮮戦争を経る中で文学者たちは北と南に分かれた。社会主義系の者だけでなく、李泰俊や朴泰遠なども北に行くことを選んだ。その結果、朝鮮文学史に欠落が生じた。韓国では1988年になるまで120余名の越北作家の作品は刊行できなかった。民族問題や左右対立は、近代文学研究が長らく抱えた問題である。1990年代後半からは社会主義の崩壊やポストモダニズムの影響で、近代と文学そのものを考え直し始めた。最近では、植民地期の日本語小説やジェンダー問題などが注目されている。
もう一つの文学——詩
金素月と尹東柱は若くして亡くなったが、2人とも韓国で最も愛される詩人として残った。韓国語の世界では、金素月の詩はどこかなじみのあるものだ。金素月は民謡などの伝統的なリズムと日常の言語を好んで書いたが、推敲を重ねとてもよく研ぎ澄まされた詩語を完成させた。「つつじの花」(1922年)は南北問わず絶唱だと評価される。愛する人との別れに自責の念を感じ、また諦めながらも打ち勝とうとする意志が、読者の心を震わせる。詩人の言葉は、遠回しでなく一度に胸に迫るが、読めば読むほど深みが増していく魅力がある。そのため、彼の詩を翻訳しようとする者は、しばしば絶望感に陥る。
尹東柱はおそらく日本でもよく知られている人物だろう。中国延辺の朝鮮人街で生まれた彼は、延禧專門学校(現在の延世大学校)で学ぶ。その後立教大学、同志社大学に留学中、治安維持法違反容疑で逮捕され、1945年福岡刑務所で獄死した。野蛮な暴力の末に力尽きた彼は、わずか27歳だった。尹東柱の原稿を大切に保管していた友人のおかげで、解放後彼のデビュー作にして遺作の詩集『空と風と星と詩』(1948年)が刊行された。彼の詩は叙情的だが、時代の暗さに負けまいとする青年特有の精神が星のように光っている。彼の詩が年を取らないゆえんである。

(東京大学教養学部附属教養教育高度化機構)
96年韓国・ソウル大学卒、10年ソウル大学大学院博士課程修了。博士(文学)。東京外国語大学特定外国語主任教員を経て、18年より現職。