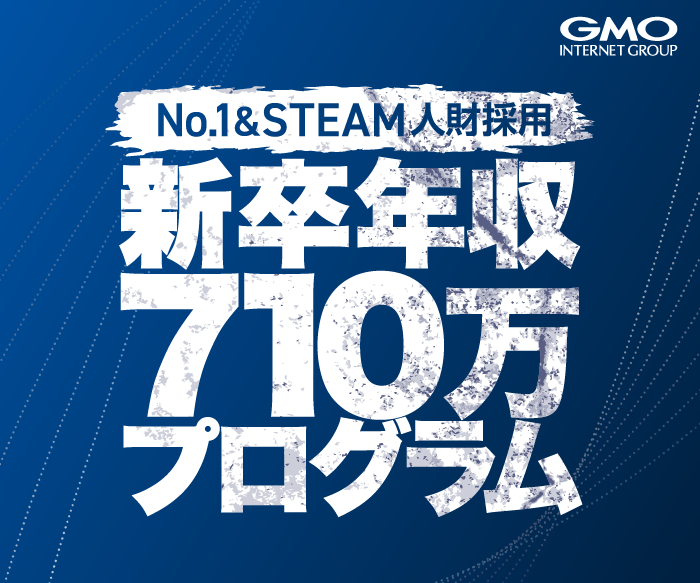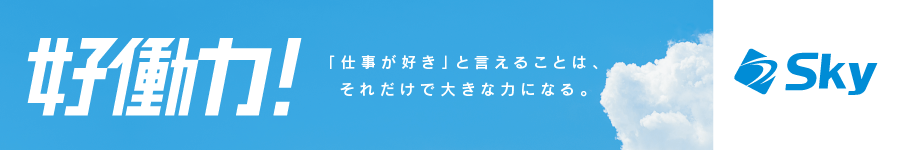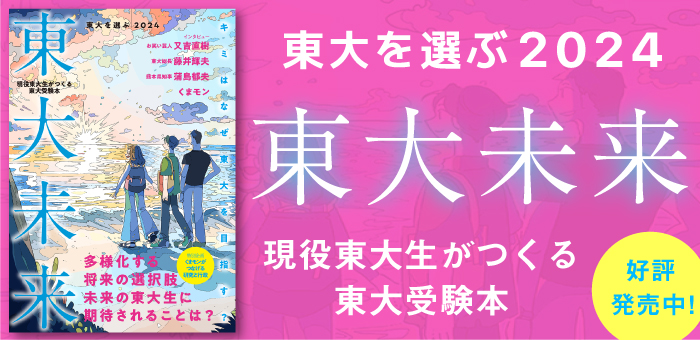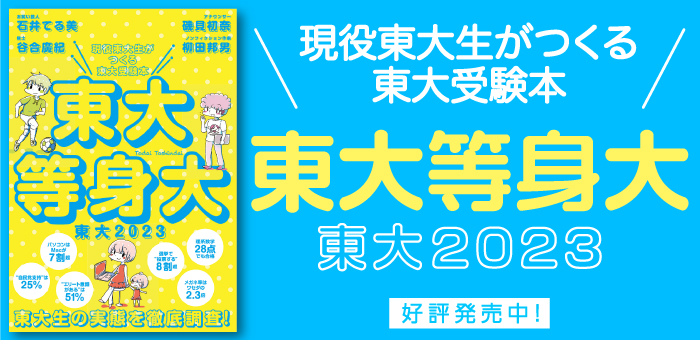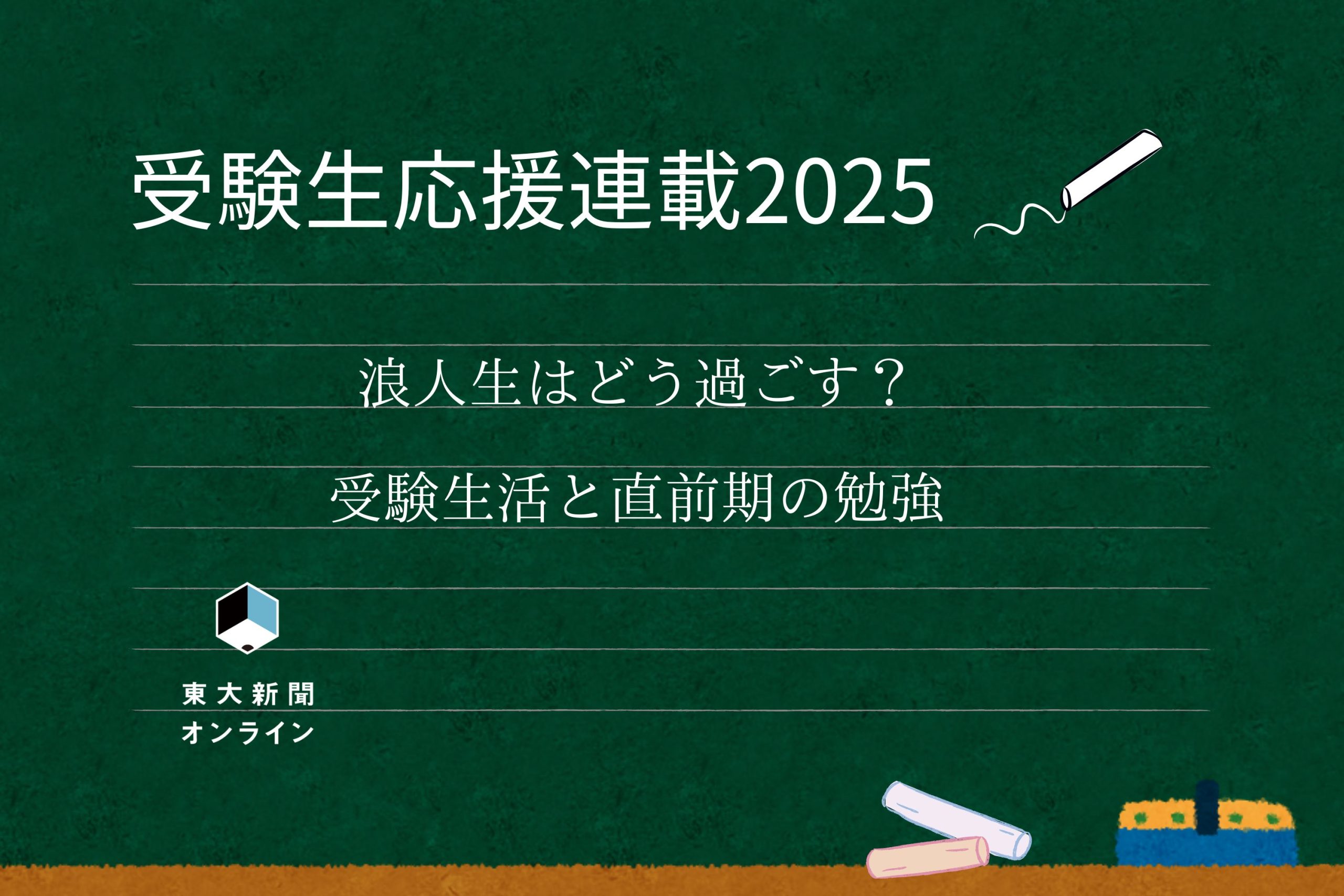
進学選択では工学部建築学科に内定し、歴史ある建物が並ぶ本郷キャンパスで学んでいるAさん(理II・2年)。四国の中高一貫校を卒業し、河合塾広島校で1浪を経て入学。浪人時の受験勉強について、現役時との違いに焦点を当てて語ってもらった。(取材・田中莉紗子)
──2次試験直前の過ごし方を教えてください
2日で1回分のペースで東大オープンや東大実戦の過去問を解きました。一方、現役時はとにかく東大の過去問を消費しました。
──浪人時はどう過ごしていましたか。現役時に過去問を解いたため、解く問題に困ったのではないでしょうか
浪人時は、現役時に済ませた東大の過去問はあまり解かずに、予備校の教材と東大模試の過去問に取り組みました。直しを含めて問題を完璧に消化するようにしました。他方で、現役の時は過去問を消費しなきゃという気持ちが強すぎて、間違えた問題をきちんと吸収する余裕はなかったです。
──現役時との違いや、現役時の反省点として浪人時に意識した点はありますか
経験の多さのおかげで分かったことですが、浪人時は現役時よりも、確実に押さえるべき問題と解けなくても構わない問題の区別がきちんとできていたため、時間を有効に使えました。
一番の違いは、浪人して時間にゆとりができたため、理系科目は意地でも自力で問題を解こうと心掛けたことです。現役時は、解法に関する知識量の不足のせいにして解答をすぐに見てしまいがちでした。しかし、浪人時は確実に必要な知識はある状態なので、それを活用して自力で解こうとするのを意識しました。
結局自分の頭で考えることが何よりも重要で、問題の量よりも優先すべきことです。下手な解き方でも自分の力で解き、模範解答と比較すると、それぞれの解法の向き不向きや特性が分かるし、問題の本質も見えてきます。
予備校の授業でも問題を解く上での基本を抽出し教えてくれていましたし、講師に自分の解き方について意見をもらうことで、解法の特徴や問題の本質が見えるようになりました。問題の本質を言語化してまとめる時も、浪人時の方が本質までしっかり掘り下げられていたと思います。これらのおかげか、浪人時は特に数学の成績が上がりました。
──逆に、現役の時から続けたことはありますか
英単語帳の『鉄緑会東大英単語熟語 鉄壁』を1日1章のペースで例文も含めて音読しました。記憶が定着するし、耳も英語に慣れてくるのでリスニング対策にも多少はなると思います。
──併願する大学はどうしましたか。これ以上は浪人できないという葛藤はなかったのですか
私大は東京理科大学の共通テスト利用のみで、後期試験は九州大学に出願していました。建築学科に行きたい気持ちが強く、私大は学費が高いので、東大が駄目なら九州大学に行こうと決めていました。併願校は模試の判定や過去問の手応えでは大丈夫そうだったので、これでも駄目なら2浪もやむなしと思っていました。
──予備校はどのように使いましたか
実家への帰りやすさを重視し、地元に一番近い広島の予備校を選びました。東大志望は理系10人くらいと少なめでしたが、東大コースがあり学習環境としては整っていたため、東京や大阪の予備校にこだわらなくても大丈夫だと思います。
普段は大阪や神戸で授業をしている講師も週1で授業に来てくれて、広島拠点の講師以外の授業も受けられたので、講師の質も問題ありませんでした。
授業の選択については、得意教科は取らないという選択も良いと思いますが、私は全部受けました。予備校が作ってくれるペースに乗っかって力を付けられたため、個人的には全部取って良かったです。
自習室もよく使っていました。私は、勉強は予備校で終わらせ、浪人中に住んでいた河合塾の寮では自分の自由時間を過ごすようにしていました。場所で区別することでメリハリがつきました。
また、講師とコミュニケーションを取りたい気持ちもあり、積極的に質問しました。質問を通して自分の思考の整理もできました。
──浪人時は精神的に苦しかったり不安になったりしたこともあったと思いますが、それはどのように乗り越えましたか
講師に相談しました。浪人時は順調に数学の成績が伸びていたのですが、2次試験直前に受けた東大本番プレテスト(河合塾)の数学で大失敗し不安になりました。そこで講師に自身の気持ちを伝えると、「試験の時は問題が配られたら今までのこと、周りのことは気にせずに問題と自分の一対一の関係だけに集中するように。目の前の問題にだけ真摯(しんし)に向き合って」というアドバイスを講師自身の実体験も交えて面白おかしく伝えてくれました。それが精神安定剤になったと思います。
他には、講師に書いてもらった応援メッセージがお守り代わりになりました。また、予備校の友達とのご飯やおしゃべりは良い息抜きになったし、一緒に励まし合って頑張れました。家族も支えになりました。