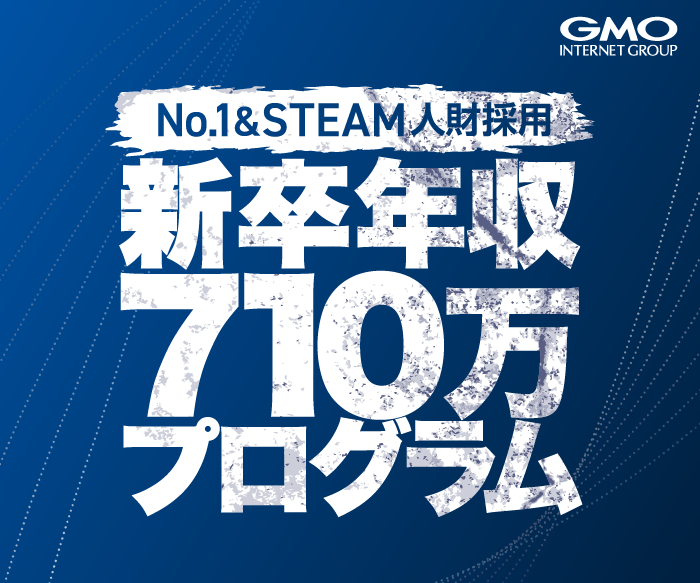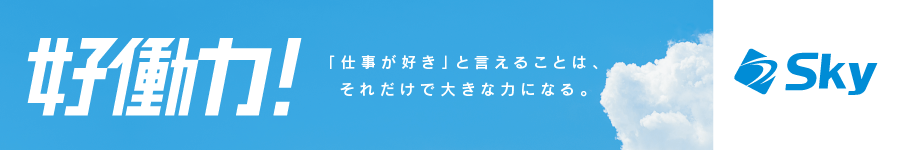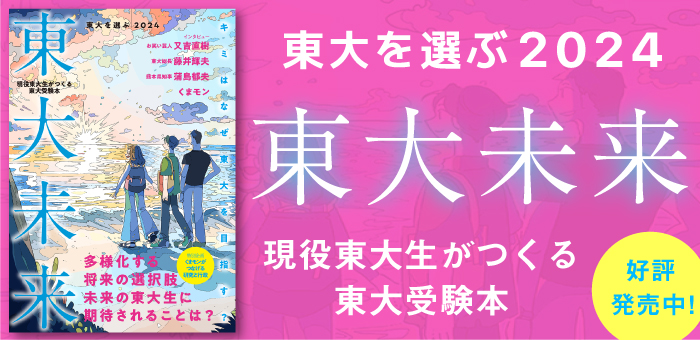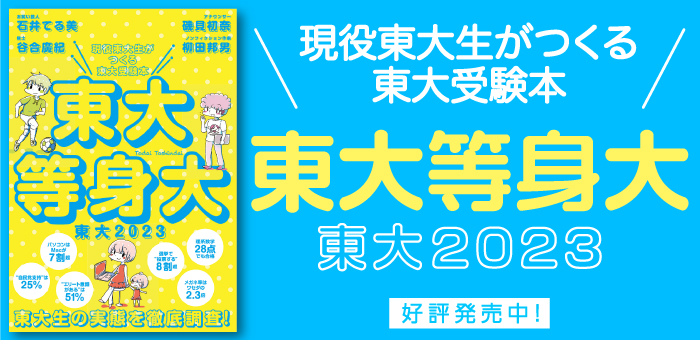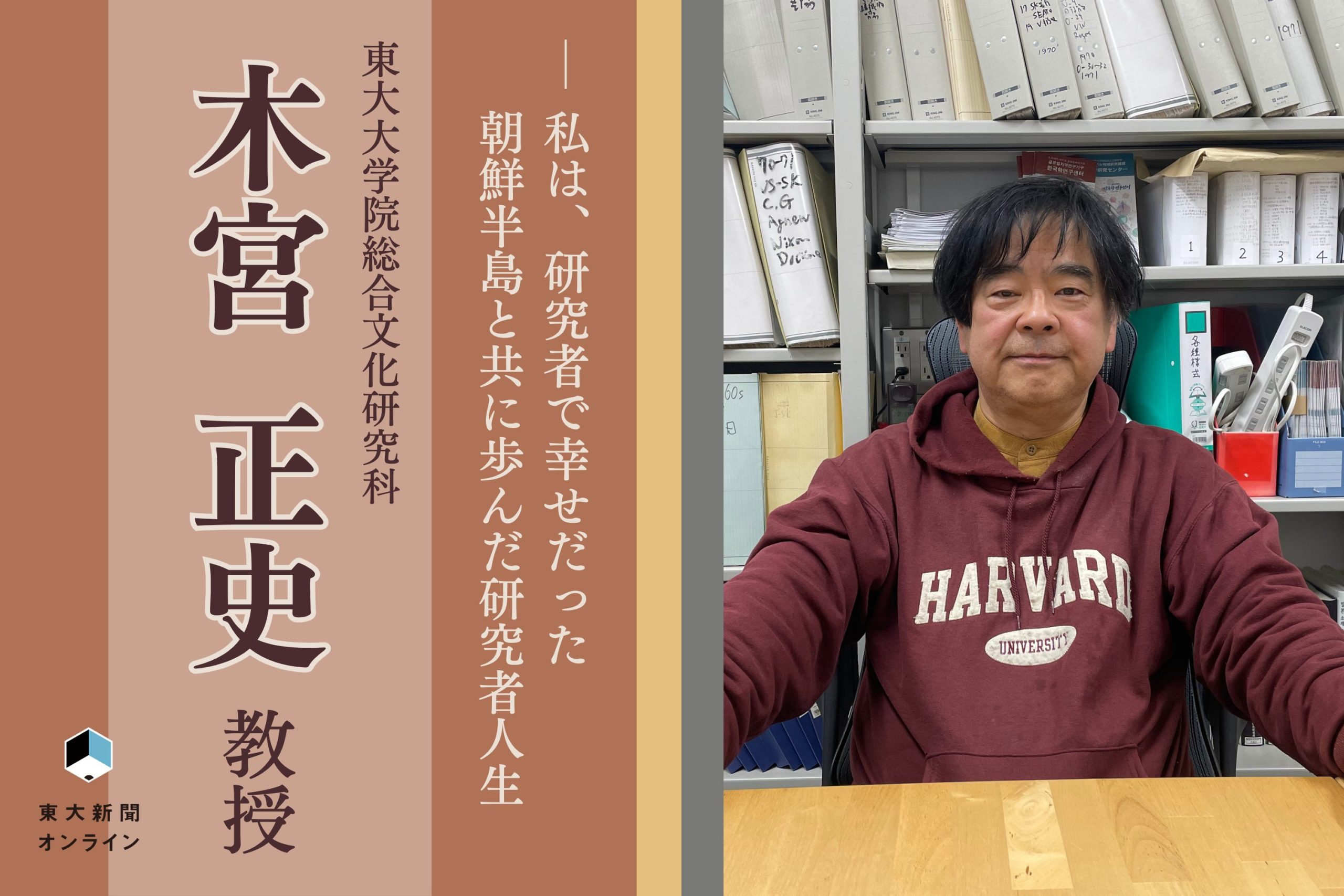
日韓関係はまさに日本の外交においては切っても切り離せないものだ。自分たちの世代の日韓関係は子供や孫の世代にまで受け継がれていく、と語るのは木宮正史教授(東大大学院総合文化研究科・2024年度当時)だ。長年韓国や朝鮮半島の政治を中心とした国際政治を研究し、昨年度をもって東大を退職した木宮教授にこれまでの研究生活の歩みや東大生へのメッセージを聞いた。(取材・丹羽美貴)
政治学に魅せられた学生時代 恩師との出会い
─東大では法学部に進学しました。法学や政治学との出会いを教えてください
高校生の時に漠然と弁護士という職業には憧れがあり、文Iに入学しました。入学後は後期課程でも教養学部で国際政治を学ぶことも視野に入れていましたが、2Sセメスターに国際政治学が専門の坂本義和先生が当時開講していた『政治における未来構想』という全学自由研究ゼミナールを受講したことが転機となりました。
─まさにこの瞬間が後の恩師との出会いだったのですね
一言で表すとこの先生の下で学びたい、と直感的に思ったことがきっかけでした。その後法学部に進学し、政治学を専攻し坂本先生のゼミで学び、国際政治学者の道を志すようになったわけです。
ただ研究者人生はそう順風満帆に進みませんでした。学部を出てすぐに助手になろうと、先生に相談をしたときのことでした。助手になるには学部生の時点で他の学生の博士論文程度の論文を書き上げなくてはならず、先生には助手にはならず大学院に進学することを勧められました。自分の将来に思い悩んだものの、最終的には大学院への進学を決めました。
─そこにはどういった思いがあったのでしょう
当時は学部生と大学院生が同じ授業を受けており、大学院生を目の当たりにしてそのレベルの高さに圧倒されました。自分の中でもさらに学問を深めたいという思いがあり、両親にも頼み込んで院進を決意し、研究者の道を志すようになりました。
坂本先生にアドバイスをもらった当初は自分の中でも迷いがあったのですが、今振り返ってみればあの時に院進を勧めてもらって良かったと思っています。
─現在は韓国や朝鮮半島を専門的に研究していますが、興味を抱いたのはいつ頃だったのでしょうか
学部時代から「南北問題」には関心を抱いていました。特に関心があったのは第三世界、と呼ばれる国々です。当時、韓国は独裁体制のもとで経済発展を追求する開発独裁の典型でした。
韓国にとりわけ関心を抱くようになったのは大学院に進学してからのことです。進学後に韓国語を学び始めました。
いわゆるそうした周縁部に位置付けられる地域からグローバル社会を「逆照射」してみたいということを考えるようになったのです。当時は日本と韓国の関係、という2国間の関係よりは、朝鮮半島を通してグローバル社会の構造をどのように解釈することができるのかを考えていました。
─「逆照射」というのはかなり特徴的な言葉ですね
はい。当時の国際関係というのは今よりも大国間の関係が国際関係の重要な要素になっていました。大国から見た国際関係の歴史ではなく、周辺部や第三世界から見た世界はどのように見えるのか関心がありました。坂本先生のゼミや授業からそうしたヒントを得ることもありましたね。
坂本先生のゼミでは当時「軍事化(militarization)」を鍵概念にして、グローバル社会の構造をどのように理解するのかを探究していました。なぜ、経済発展を成し遂げるために軍事化、換言すれば権威主義体制になってしまうのか、あるいはなぜ民主化と経済発展とが調和的に進まないのか、といった疑問もグローバル社会への課題意識を抱くきっかけになったのだと思います。
─博士課程では韓国の高麗大学に留学しました。当時は軍事独裁体制下だったと思いますが、在学中に印象的だったことはありますか
当時は、テレビなどを通して韓国にまつわるニュースは入ってきてはいましたが、韓国の人々が日々どんな暮らしをしているのかは分からず、情報を仕入れることも難しい時代でした。
坂本先生の弟子のお一人が高麗大学の教授をされていた縁もあり、留学をしました。最初は言葉が聞き取れず、授業もさっぱりで苦労しましたね。ただ2学期目に入ると授業も次第に理解できるようになっていきました。
大学では学生が軍部独裁打倒を掲げたデモを毎日のように行っていました。学外に出ようとすると現地の機動隊が催涙ガス弾を打ってくるような状況でした。朝登校すると催涙ガスの残りで目が痛くなったことや、授業中に催涙ガスが打ち込まれて授業どころではなくなってしまったこともありました。
─韓国の民主化運動を肌で感じたのですね
まさに、激動の時代でした。私は当初第三世界を通してグローバル社会の政治構造を把握しようとしていました。構造を把握、というと何かあらかじめ決まっていて不変のものを理解すると考えがちです。ですが実際に韓国で生活をしていると、その価値観にも変化が現れました。
周りの韓国の学生に「何のために政治学を勉強しているの?」と聞くと「自分たち国の政治や社会を変えるために勉強しているんだ」と言うのです。自分の政治学を学ぶ目的とは少し異なっているように思いました。当時の日本は55年体制下で政治が変わる、というイメージを抱くことができませんでした。
最初は同級生の言葉を聞いても「そう簡単にはいかないだろう」と思っていました。ですが、1987年に入ると次第に韓国の政治体制が軍事独裁体制から民主主義体制へと変わり始めたのです。上からの民主化、というよりは一人一人の行動が政治を変える力になっていました。韓国に留学して最も印象的だったことは人間の力によって政治や社会が変わり得ることを実感できたことです。この経験は人生にとって重要だったと思います。日本人だから、といって個人的に嫌な思いをしたことがなかったのも幸運なことでした。
一方で日本の侵略と支配の歴史を実感する場面もあり、韓国の人が日本についてどのように思っているのか推しはかることもありました。日本人として私が日本に抱くイメージと、韓国の方が日本に抱くイメージが異なることを実感させられた機会でした。
知的に誠実に、研究者として歩んだ人生
─東大に着任してから29年が経ちました。これまでの問題意識の変遷を教えてください
最初の問題関心は「経済発展と政治体制の関係」にありました。博士論文も1961年の軍事クーデターによって就任した朴正煕政権の経済政策について書き、経済政策とその結果としての経済成長と政治体制にどのような関係があるのかを1945年以降の韓国現代史を通して考察しました。政治経済学的な関心が強くあったと思います。
ただ、韓国が次第に開発途上国から先進国に、開発独裁で権威主義国家から民主主義国家へと変化していき、私が東大に着任した頃は先進民主主義国へと移行していました。そこで着目したのが米国の外交史料です。大国である米国と韓国の関係は切っても切離せないものです。そこで米国の外交史料を読み解いて韓国の外交政策や歩みを考えるようになりました。
そして、1995年から韓国の外交史料が公開されるようになったのです。例えば、日韓国交正常化やベトナム戦争へ軍隊を送ったことなど、韓国の外交について考える際に、韓国の外交史料だけではなく日本や米国の外交史料とつき合わせて外交の在り方を明らかにしたいと考えるようになったのです。韓国の視点から朝鮮半島の冷戦を見ることもできるのではないか、と考え、先に述べたような「逆照射」を外交史の視点から分析できるのではと考えるようになりました。年代ごとに公開される外交文書を国ごとに見比べながら韓国の外交の姿を明らかにしていきました。
─外交史料が公開された、ということは大きな出来事だったのですね
この取り組みで興味深かったのは韓国外交の採り得る選択肢の幅についてでした。これまでは当時の大国であった日本や米国に挟まれ、外交政策の選択肢の幅が限られていたのではと考えていました。もちろんそれは否定できない側面もあるかもしれません。しかし、韓国なりの世界の見方やどのように外交を進めていけば良いのか、選択の幅を広く持って考えていたのではないか、ということを発見したのです。このようにして韓国の視点から朝鮮の現代史を再解釈していくことを試みてきたわけです。
─日本との関係についての研究はどうですか
最終的には日本との関係についても考えるようになりました。私は自分自身を非政治的な人間であると解釈していたので、政治に関わることは積極的にはしてきませんでした。
ただ、韓国の研究者の友人に誘われるような形で、2005年から日韓有識者間政策対話を始めることにしました。日韓それぞれ5人ずつ参加する形で私は日本側の座長を務めました。議題に応じてさまざまな人と議論を交わし、年に2回ほど開催しました。今では30回を数える会になりました。最初は乗り気ではなかった部分もあったのですが、この時期はちょうど日韓関係があまり良くありませんでした。そうした状況下で今の日韓関係をどのように分析し、いかなる関係を構築していくのかを考えなければならないと感じるようになりました。
私も年を重ねるうちに考えるようになったのは「自分の子供や孫の世代にどのような日韓関係を残せるのか」ということです。私の世代は明治の人から受け継がれた、朝鮮を侵略していた時代からの日韓関係を受け継いでいます。その関係が残っている部分も大いにあります。日韓関係について外交史料を分析する作業と、そうした知的な作業に基づいて、現実の日韓関係をどのように分析して維持、変更していくのか政策指向的な部分にも取り組もうとしたわけなのです。
韓国の経済政策から、外交史料の読み解きを通して得た朝鮮現代史の再解釈、そして実際に目の前にある日韓関係についての思考へと移り変わってきたのです。もちろん並行していた部分もありつつ、次第に進化していった過程があるように思いますね。
─研究者として心掛けてきたことを教えて下さい
知的に誠実でありたい、という思いでしょうか。例えば、私は1980年代半ばに韓国に留学し、韓国の人々から人間の力で政治は変わる、という一見当たり前のようでこれまで全く気が付かなかったことを実感させられました。そこで得た実感を何らかの形で「恩返し」していきたいという思いがあるのです。
─「恩返し」というのはどういった意味合いでしょう
今の日韓関係はこれからも変わることのない仕方がないものだと諦めるのではなくて、私が韓国の人に教えてもらった、人の力が政治を動かす、ということを信じてみても良いと思います。少しでも現実に対して働き掛けてお互いにとって望ましい方向へと変えるということはしていかなければならないし、できることなのではないかと思います。私は研究者として論文などを発表して社会に対して働き掛けることができます。それが私にとって知的に誠実である、ということだと思います。恩師である坂本先生が背中で示してくれたことでもあります。
─これからの研究の展望を教えてください
もう少しタイムスパンを広げるような形の研究をしていきたいと思いますね。19世紀末から20世紀初め、日本と韓国(大韓帝国)は西欧という列強に対してどのように立ち向かうのか、という側面では立場と同じくしていました。ただその後、日本は韓国を侵略して日韓関係は大きく変わってしまった。いわゆる非対称的な関係にあったのです。しかし、現代となってはある意味で対称に戻ったと言っても良いでしょう。韓国は1人あたりの名目GDPでは日本を追い越すほどに成長し、米国と中国という大国に挟まれている、という共通の状況下に置かれています。私は今こそ知恵を出し合って対応することが必要なのではないかと思います。19世紀の後半から20世紀前半、20世紀後半、21世紀前半のそれぞれで日本外交と韓国もしくは北朝鮮の外交の比較をしながらも関係を見つめ直すことを行いたいですね。
学生との交わり 社会を底から支えるインフラを築く
─研究者でもあり、教員でもありました。学生と交流する中で印象的な場面はありますか
私の大学院の学生の半数近くは留学生でした。中でも、韓国出身の学生が多く、彼らの多くは日本と朝鮮半島の関係についての研究をしていました。韓国は厳格な学歴社会で、なんとか彼らに博士号をとらせて帰ってもらいたい、と思っていました。学生に学問を教える、というのが教員としての責務だと認識している一方で、それだけでは割り切れない人と人とのつながりを感じています。ある意味ではそういった関係が日韓関係を底から支えているようにも思うのです。学生に日本と韓国の関係がいかにそれぞれの国にとって重要なのかをしっかりわかってもらうといった、自分がやっていること自体が今後の社会を底から支えるインフラのような役割を担えているのならばうれしいですね。卒業生の中には今でも交流のある人もいます。
─東大の前期教養課程では自分の専攻にかかわらず幅広い学問分野に触れる機会があります。今後さまざまな道に進む学生が「政治学」を学ぶ意義をどのように考えていますか
韓国は国民の政治に関する意識は非常に高いものです。日本はそれに比べるとそこまで政治に関心がなくても生きていける社会です。ただ政治的な営みというのは「非政治的」な人間が少しだけでも政治に関わることで初めて成立するものだと思うのです。政治を支える知恵というものを学生が持ってもらえれば良いのかなと思います。数多くの非政治的な人が政治を支えなければ政治は成立しない、ということを学生に伝えたいのです。
─最後に学生へメッセージをお願いします
私は研究者になって幸せだったと思っています。振り返ってみれば、研究者として自分のやりたい研究を思う存分でき、ストレスの少ない職業だったと思います。自分で自分の仕事をある程度決められる、というのは大変なことである一方で、非常にぜいたくなことだと思うのです。全員が全員、社会に出たら自分の仕事を決められるわけでもないので、そういったぜいたくさを求めるのであれば研究者は悪くないなと思います。
社会に出ると、全てが自分の思い通りにいくわけではありません。ただ、与えられた制約にがんじがらめになるのではなく、その制約をいかに自分にとって個人的な学びを発展させるための機会へと変化させることができるのかを意識すると、人生って悪くないのかな、と感じられると思います。

(東京大学大学院総合文化研究科)
93年東大大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学。92年韓国高麗大学大学院政治外交学科博士課程修了。政治学博士。東大大学院総合文化研究科助教授(当時)などを経て、10年より現職。