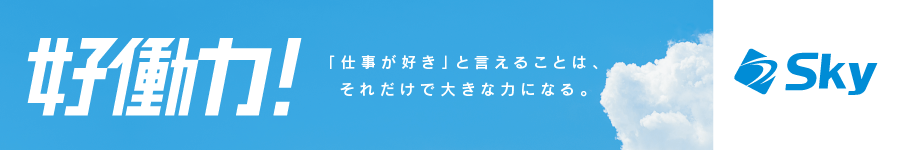奇妙な忠告
「十字架を身につけているなら服の下に隠しなさい」
クリスマスも間近の頃、大学の試験も終わり友人と観光でイスラエル側にあるナザレという町に向かった。イスラエル側に入る際の検問所で色々とトラブルがあり、予定よりも行程が遅れたため、ナザレの南数キロにある町のジャンクションから二人でヒッチハイクをした。我々を乗せてくれたのはカトリックのアラブ人の年配女性二人組だった。
この「忠告」のあとも、「ムスリムがいるところはヨーロッパでもパレスチナでもどこでも問題が尽きない」と、声高にムスリムへの不信と嫌悪を口にし続ける二人組は、車に乗せてくれたことには感謝しつつも、一種の被害妄想にとり憑かれているのではないかと感じるほどだった。友人が「ユダヤ人(イスラエル人)とは問題がないのか」と尋ねると、「彼らは親切で優しいわよ、ヨーロッパ人みたいなものだもの」と答えていた。
ナザレはイエスが幼少期から公生涯に入るまでを過ごした町でもあることから、イスラエル側に位置しながら現在も多くのアラブ人キリスト教徒が住んでいる。旧市街周辺はアラブ系住民がほとんどで、イスラエル国籍を持ちながらもパレスチナ人としてのアイデンティティを強く持つ人たちも多くいる。実際、ナザレで入ったレストランで友人たちとウェイトレスにアラビア語を使っていたところ、ウェイトレスがパレスチナ国旗のカラーで色づけされ、イスラエル建国前のパレスチナをかたどったネックレスを誇らしげに見せてきたくらいだ。
そうした中で同じアラブ人であるムスリムよりも、同胞であるはずのパレスチナ・アラブ人を抑圧している国家の国民であるイスラエル・ユダヤ人の方が好ましいと答える彼女らには驚かされたたものだった。

パレスチナ・アラブ社会のキリスト教徒
現在パレスチナでムスリム住民とキリスト教徒住民との間で、両者間の軋轢や対立が実際に顕在化しているわけではない。また多くのキリスト教徒がパレスチナ人としての文化的・政治的アイデンティティを持っていることも事実だ。その一方で、ムスリムが大多数を占めるパレスチナ・アラブ社会の中で、少数派であるキリスト教徒の住民が一切不満を感じていないわけでもないようだ。
既述のナザレでのエピソードも然りだが、西岸地区のナブルスのアラブ人カトリックの家庭でホームステイをしている留学生の友人曰く、彼のホストファミリーも時たまムスリムに対する不信感や自分たちの肩身の狭さを口にするようだ。もちろん、こうした限られた証言だけを参考に、彼らが抱く不満や肩身の狭さをキリスト教徒全体に一般化して論じることは決して出来ない。しかしながら、それを裏付けるような社会的・政治的要因がないわけではない。

例えば、以下のことはパレスチナに限らず他のアラブ世界でも当てはまることだが、一般にキリスト教徒の家庭の方が裕福で、教育水準も高く、一世帯あたりの子供の数も少ないというイメージがある。これは事実無根のイメージではなくある程度正しいのだが、こうしたイメージがムスリム系住民との間での軋轢にも繋がることもある。ムスリムからは裕福で、教育水準の高いキリスト教徒の家庭は妬みの対象となり、他方でキリスト教徒からすれば一世帯あたりの子供の数が比較的多いムスリムの家庭は、ただでさえ少数派である自分たちのコミュニティを脅かすものとも映る。
キリスト教徒は海外へ移民するものも多く、欧米諸国にいる親類などとのコネクションを利用して、ビジネスに成功するパターンがよくある。エジプトのサウィーリス家はコプト・キリスト教徒の家系で、中東屈指の実業家として知られているし、日産自動車のカルロス・ゴーン氏は、レバノンのマロン派キリスト教徒の移民2世だ。アラブ系キリスト教徒の知識人も多く、パレスチナで言えばエドワード・サイードや作家のエミール・ハビービーなどが挙げられよう。
また政治的側面に関して言えば、2006年のパレスチナ議会選挙でのハマース系政党の勝利に見られたように、パレスチナでもイスラーム主義政党の支持は根強く、こうした政治事情もムスリム多数派の社会での肩身の狭さを感じる要因になり得るだろう。歴史に鑑みても、例えば19世紀末の世俗的なアラブ・ナショナリズムの黎明期においてアラブ系キリスト教徒が果たした役割は大きく、その背景にはイスラーム的社会秩序における市民権の不平等があった。(後編に続く)
(文・田中雅人)
聖夜の空に揺れるパレスチナ国旗(前編)【パレスチナ留学記4】