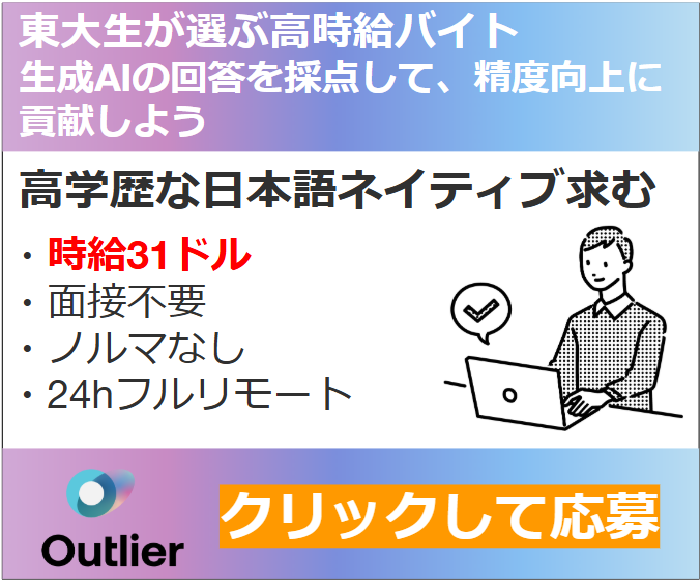折り紙や切り絵にどのようなイメージを持っているだろうか。前者は小さな子供が遊びで作るもの、後者はきれいな飾りや絵画の一種、といった認識の人も多いだろう。ここに、そのような予想を覆す多彩な題材の採り方・表現技法で創作活動に取り組む、2人の東大ゆかりの「紙アーティスト」たちがいる。1人目は、仏教美術をはじめとするさまざまなモチーフを取り入れた折り紙作品を制作している益子遼祐さん(工・3年)。そして2人目は、時にデジタル技術も駆使しながら、切り絵を通して「物語」を伝えることをテーマとする清重影織さん(2015年東大教養学部卒)だ。今回は2人に、自身の創作と東大での経験との関わりや紙を用いた創作と他分野の融合の妙味などについて聞いた。こちらの想像をはるかにしのぐ奥深さを持つ「紙アート」の世界をとくとご覧あれ。(取材・鈴木茉衣)
「折り紙」×「宗教」=?

19年に仏教芸術をテーマとした折り紙作品『胎内仏』で、学生の美術振興を目的としたアートコンペ「学展」の外務大臣賞を受賞した益子さん。題材よりも技巧的な精密さが優先されがちだという折り紙に、仏像という古典的な題材を持ち込み、新たな表現を作り出した。
益子さんが折り紙を始めたのは幼稚園にいた頃だった。「他の人とそれほど変わらなくて、教室にあった折り紙スペースのようなところで遊んでいました」。幼少期は折り紙が好きだったものの成長するにつれて気付けば縁遠いものになってしまっていた、という人は少なくないだろう。しかし、益子さんにとってそれは現在に至るまでずっと夢中になり続ける対象になった。なぜ折り紙という趣味を手放さなかったのかについて、益子さんは「ずっと続けられる環境があったということが大きいと思います」と語る。例えば通っていた中学・高校には折り紙部があり、迷いなく入部を決めた。現在も東大の折り紙サークルOristに所属している。「例えばドラゴンを作ることにこだわる人もいますし、小さな作品をたくさん作る人から表裏で色の違う紙でカラフルな作品を作る人まで、作風に人となりが出ていて面白いです」。キャンバスに描く絵はあらかじめ枠の大きさが決まっているのに対し、枠を含めて全てを自分で選ぶことができるのが折り紙の魅力の一つだという。
以前の弊紙の取材では「折り紙には『理系的な面白さと文系的な面白さ』がある」と語っていた(20年12月8日号掲載)。最初の構造を作る段階は論理的で答えがはっきりしているが、仕上げに当たる造形は、決まった正解のない芸術だ。芸術的な感性には「思想」が必要だという。学問的な関心を抱く分野も多岐にわたる。工学部計数工学科に所属しているが、進学選択では文学部や経済学部とも迷い、哲学や宗教にも関心を持つ。

幅広い関心は作品作りへも生かされている。『胎内仏』は仏教美術に題材を採っているが、これは宗教の中でも特に仏教へ興味を持ったからだ。「小さい頃から仏像が好きで、なぜか引かれるものがあったんです」。魅力を感じたのは造形という側面にだけではない。例えばニーチェのニヒリズムやハイデガーの「『存在』は世界との関わりの中で理解され、また『存在』という言葉も世界との関わりの中で使用される」という思想に、仏教の「空」との親和性を感じるという。ドイツ哲学と比較することで「哲学としての仏教」を見いだした。ヒンドゥー教の神々も取り入れられているなど、さまざまな宗教を包摂した上での「悟り」があるのが仏教の面白さだという。「自分の直感的に美しいと思ったものと思想として説得力があると思ったものが重なった題材だから仏教を選んだ、という感じです」
工学部計数工学科では、神経科学を定式化し、機械学習へ応用することに主に関心を持っている。学習内容の芸術への応用についてはまだはっきりとした展望があるわけではないというが、機械学習のモデルの一つである生成モデルを利用した作曲などに挑戦している。折り紙をアルゴリズムで設計することもできるが「一アーティストとしてAIに芸術を取られたら嫌だ、という気持ちもあります」。思い入れが深いからこその、折り紙はあくまでも「自分でやる領域」として確保したいという思いだ。「芸術と機械との関係性の在り方については多くの芸術家が悩んでいるところだと思います。芸術は人間が人間らしく在る代表的な分野なので、AIが人間をどう超えるかということを考えるのにはいい題材なのかもしれないですね」。今後は芸術と工学の高度な融合を模索することが一つの目標だ。


緻密な世界を彩るアート
自身のことを、芸術や勉強などいろいろなことをやって初めてバランスを取れるタイプだと語る益子さん。芸術はいわば、人に邪魔されず、気の赴くままに取り組みたい「ユートピア」のような領域だという。「半年ぐらい芸術にあまり触れず数式ばかり追う生活をしていた時、なんだか『生活に色がないな』と感じました」。学問、特に科学の世界で求められるのは第一に正確さだ。そのような「細い道」を通ることが楽しくもあるし、窮屈でもあるという。「モノクロを極めた世界と、芸術に触れることがもたらすカラフルな世界の両方が自分にとって必要なんです」。しかし、必要だということは必ずしも簡単だということを意味しないようで「描いた絵をアーティストの方に見ていただいた時に、勉強に影響を受けてきちんと型にはまり過ぎた作品になっていると指摘されてしまったことがあります……。抽象芸術にも挑戦してみたいですが真面目に作ろうとすると難しいんですよね。芸術家には命を懸けてでも対象に向き合うような人も多いですが、そんなふうに芸術の根源にある狂気のような感覚と理性を自分の中に同居させて作品を作るには、まだまだ修行不足だと感じます」と苦笑い。「型」と「自由さ」の両立は折り紙におけるテーマでもある。緻密に構造を作るところは論理的で答えが決まっている一方、造形は連続的な営みで、芸術としての側面があるからだ。
折りながら「紙の表情それ自体が作品になりそうな、自分の中のイデアが形になったような感覚になる瞬間がある」のだと語る。自分が心の底から美しいと感じる形を迎えに行くことが、紙を折るという営みだ。「派手な言い方をすれば、神のようなものが降りてくるのを受容して作品を作っている感覚でしょうか。神との一体化は伝統芸能や東洋宗教にも共通する態度ですね」。一つ一つの作品に魂を注ぎ込み、懸命に芸術を探る。紙を折ることを通し、自身の感性をも世界へ織り出してゆく姿にアートの豊かさを見た。

資料の魅力を伝えたい!
清重さんは「切絵童話」と称する自身の作品で、一点の絵画としての切り絵表現にとどまらず、時に動画、ARなどのデジタル技術を組み合わせることもしながら「物語」を届けている。

「切り絵には小さい頃から興味がありましたが、最初から自分でも作ってみようと思っていたわけではありません」。戦時中にインドネシアで従軍していた祖父がたくさん持っていたワヤン・クリ(インドネシアの伝統的な影絵芝居で使われる人形)に興味を持っていたことも原体験の一つだ。自身での制作についても、始まりは既成の図案に沿って切ってみるところからだったという。とはいえ、当時は切り絵に関する書籍なども多くなかったため、独学でのスタートだった。転機となったのは大学卒業後の出来事。ハンガリーへ留学することになった大学時代の友人へ贈るカードとして、初めて図案からの本格的な創作にチャレンジしたのだ。「他の友人たちが凝ったものを作っていたので、私も描いてみようかなと思ってやってみたら、意外と描けるじゃん! と思って(笑)」
入学時の科類は文IIIで、教養学部教養学科超域文化科学分科学際日本文化論コースへ進学。幕末に来日した外国人についてなど、日本における文化の勉強をしていた。第二外国語としてロシア語を選択していたこともあり、卒論では日本でのロシア正教の受容のされ方について書いたという。日本文化には古典籍が関係してくるなど「東大での勉強ではいろいろな資料に触れる機会がありました。図書館が大きくて、こんなにたくさんの資料があるのだということに感動しました」。卒業後は、東大の図書館職員として働き始めた。「図書館は資料がたくさんあってせっかく面白いのに、その存在をあまり知られていなくて、ただ本を借りるだけの場所になっているのがすごくもったいないと思いました」。情報の宝庫である図書館で、利用者がその人にとって大切な情報にリーチできるような環境を整えることによって「人と情報をつなぐ」ことに関心を抱いたという。
資料の面白さのとりこになった経験は、二つある創作の軸のうちの一つである「知的好奇心を満たすこと」につながっている。創作の題材として選ぶものにも、古典をはじめとする「図書館にある、面白そうなもの」が多いという。例えばイタリアで開催した作品展ではガリレオ・ガリレイの一生をテーマにした。昨年に発表したアプリ『AR切り絵百鬼夜行絵巻』は東大総合図書館蔵の『百鬼夜行図』を基にしている。「今イタリアに住んでいるのですが、生活していて日本人としての自分の異質さを感じることがあります。では日本人としてどんな作品が作れるのか、ということを考えているんです」。学際日本文化論コースで日本について学んだことは、現在の創作にも色濃く反映されているのだ。「日本文化、日本美術の面白さにもっとチャレンジしたいです」

「切り絵」×「物語」=?
「知的好奇心を満たすこと」と並ぶ、もう一つの創作の軸は「お話を書くこと」だ。創作に本格的に取り組み始めたのは社会人になってから、余暇を充実させるためだったが、自分で楽しむために話を作ること自体は小学生の頃からしていたという。
テーマにすることが多いのは「心」だ。「創作をしていたのは、自分の中のマイナスを埋め、生きづらさを解消するためでした」。感情を登場人物に託し昇華する、そんな営みを通じて自分自身を癒すことが最初のモチベーションだったという。しかし創作を継続するうちに自分自身の感情はだんだんと満たされていき、自分以外の人々に対して同じようにプラスをもたらす方向へとかじを切りたいと感じるようになった。「物語を届けることで世界を明るくする」ことを掲げている現在の軸となっているのは「人生がつらい人や生きづらい人に、物語を伝えることを通じて、少しでも楽になってもらいたい」という思いだ。「図書館もそうですが、人と情報をつなぐこと、とにかく伝えることが好きなんだと思います」。ストーリーには昔自分が悲しかった経験や、それをどう捉えるべきか考えたことが反映されている。
あくまで鑑賞用の絵画としてのイメージが一般的な「切り絵」という表現技法を通じて、連続した「物語」を届ける、という試み。珍しい手法は「小説を書くなど物語を表現することを単独でやっている人と、切り絵を単独でやっている人ならそれぞれたくさんいますが、それらを組み合わせるという事例はあまりないのでは」という発想が基になった。
「切り絵」と「物語」の融合にとどまらず、さらに多様な手法を使ってそれらを表現することにも注力している。例えばアプリ『AR切り絵百鬼夜行絵巻』は、起動して切り絵作品にスマートフォンをかざすとARのアニメーションが見られるようになる仕掛けだ。図書館職員を経てソフトウエアエンジニアとなり、プログラミングを習得したことが大いに生かされている。


動画やARなどのデジタル技術を用いることで目指すのは「物語を現実へ拡張すること」。ARを利用すれば紙という縛りのない自由な表現ができるのではないか、と考えた。「『ハリー・ポッター』の映画で新聞に載った写真が動く描写がありますが、あんな風にアートが動き出したら魔法のようで面白いな、と思いました。デジタル技術を使えばいろいろなことができて、まるで魔法みたいだなと思うんです」。小さい頃に好きだった飛び出す仕掛け絵本のように、鑑賞者が一方的に受け取るのではなく物語があたかも現実に働き掛けてくるかのような鑑賞体験を追究している。「ただ動くというだけでは、すぐに飽きられてしまう」という難しさもあるからこそ、いかに感動を作り続けるか、ということが鍵だ。「切り絵や創作はずっと続けると思いますが、物語を届けるのに必要だと思ったら新しい技術や表現方法に挑戦することもあると思います」。創作への意欲はとどまるところを知らない。