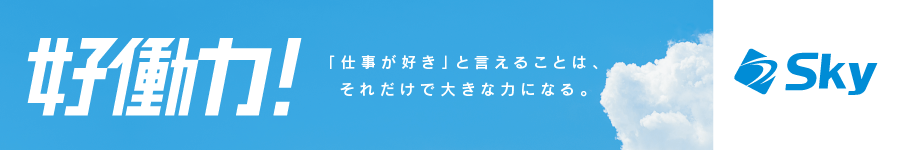東大教育学部を卒業後、日本経済新聞社で記者になった中野准教授。結婚・妊娠を機に周囲の扱いが変化したことに疑問を持ち、ジェンダーを学び直そうと第1子の育休中に修士号を取得。2015年にフリージャーナリストに転じ、ジェンダーや子育てなどの問題を報じてきた。現在は東大の教員として、学内のジェンダー平等推進を担当する中野准教授に、自身のキャリアや既存の在り方を疑う問題意識、話題となった「#言葉の逆風」キャンペーンについて聞いた。(取材・松崎文香、撮影・五十嵐崇人)

盛り上がる大学祭を求めて 「駒場グランプリ」を創設
──東大を目指したきっかけは
私は東京出身で、幼稚園の時から国立の教育機関に通っていました。そのまま付属校に進学し小・中学校と過ごす中で、国立の学校の制服を着ているだけで「勉強したのね」と近所の人に褒められる経験をしたんです。記憶もないような幼い時にたまたま入った学校によって評価される。学歴って何だろう、と思うようになりました。「学歴」への疑問の延長線上で大学受験の際も、日本で一番と言われる東大に一体何があるのか、東大を見てみたい気持ちがありました。学歴ピラミッドを批判するなら、その頂点である東大に行って、批判する方が説得力があるという思いもありましたね。
──なぜ文Ⅲを選んだのですか
日本の学校システムへの疑問から、日本と海外の学校を比較したいと思い、高校生の時アメリカに1年間留学しました。いざ留学すると、アメリカには日本の文化祭のように、生徒が中心となって準備する学校行事がないと気付きました。卒業前のダンスパーティー「プロム」では、お金をかけてドレスを買って当日楽しむだけで、生徒は自分では何もしない。日本の教育にも良さがあるなと再認識しました。大学では、教育を社会の中に位置付けたり比較したりする学問がやりたいと考え、教育学部を視野に文Ⅲを選択しました。
──実際に東大の前期教養課程に入学して、どのように感じましたか
もともと学歴社会を批判したいという気持ちで入ったのでうがった見方をしていたかもしれませんが……。
駒場の大きな900番教室では、前の方で豆粒みたいな大きさの先生が講義をし、学生は私語がすごい。男性たちが「昨日かわいい子いた?」とか、サークル勧誘の飲み会の話で盛り上がっていました。一方、文Ⅰや文Ⅱの学生の多くは、入学と同時に司法試験や公認会計士試験に向けたダブルスクールを始めていました。飲み会路線か資格試験対策ばかりで、誰も大学の授業を聞いてないことに驚きました。
東大には、新入生に「上クラ」といわれる2年生が、授業や大学生活について教えるオリエンテーション合宿がありますよね。その中で、駒場では楽な授業でできるだけ良い成績を取って、2年次の進学選択で行きたいところに行くんだと教えられました。授業に関する情報も、学生が単位や成績の取りやすさを「鬼」や「仏」などで評価した『逆評定』という冊子しか、当時は出回っていませんでした。行きたい学部に進学するのは良いけど、皆が苦労して入る東大で授業は中身は聞かずに単位と点数だけ取れれば良いという態度には「何のために東大に入ったの?」と、疑問でした。入学当初は大学がつまらなくて、自分が楽しむにはどうすれば良いのかと考えて、いろいろな活動を始めました。
──どのような課外活動をしていたのですか
1年生の時は、会社やNPOを立ち上げたり政策立案コンテストに挑戦したりと、活発に活動している学生を紹介する本を制作することにしました。私自身はゼミのフィールドワークや大学生コミュニティーで広いつながりを持つ兄の知り合い経由で、NPO法人「カタリバ」を立ち上げた今村久美さんなど、面白い活動をしている学生と知り合う機会が多かったのですが、多くの学生はそのような存在を知らないよなと思ったのがきっかけです。多様な活動をしている大学生がいると伝えるために、学生団体など様々な活動を取材して本にまとめ、仲間と自費出版しました。出来上がった本を生協に置かせてもらったり、売り歩いたりするうちに、私たち自身も知られるようになっていきました。
そうこうするうちに東大内にもいろいろな人がいることが分かり、次は『逆評定』へのアンチテーゼとして、面白い授業の紹介冊子を作ろうと動き始めました。上級生から偏った情報しか与えられず、授業に関する情報も『逆評定』だけという状況がおかしいと思っていたからです。興味関心の軸を持って聞いてみれば後期課程に進学してから生かしたり、面白く感じることができたりするのですが、そういった授業のとり方を誰も教えてくれないのはもったいないですよね。教養学部の副学部長にこのプロジェクトの話をしたら、大学側もちょうど初年次教育を設計し直そうと動いており、大学から予算をもらって次の新入生全員に配ることになりました。
他には、オープンキャンパスなどでのガイダンス改革にも取り組みました。その後大学側も上級生からの情報に触れる前に学部主催のガイダンスをやろうということになったんです。合格直後の入学前のタイミングで、新入生を集めた新歓イベント「FRESHSTART」を始めました。あとは、駒場祭委員会にも入っていましたね。

──駒場祭委員会に入ったきっかけは
入学直後の五月祭にクラスで出店して、当時まだ日本では流行ってなかったタピオカを売ったんです。美術が得意なクラスメートが装飾を頑張ったこともあって、当日は即完売でした。一方周りのクラスをみると、テントをただ立てただけで「なんか売ってればいいでしょ」という雰囲気でした。高校の時は文化祭といえば、クリエイティブなタイプの生徒が自ら手を挙げて盛り上げる、すごく楽しいイメージだったので、当時の五月祭の全体的なレベルの低さに驚きました。そこで秋に駒場祭があるからと、テントの装飾をした美術が得意な子、高校の時に文化祭実行委員長をやっていた子と私の同じクラスの3人で駒場祭委員会に入りました。
──駒場祭委員としてはどんな活動をしたのですか
駒場祭委員会は五月祭やオリエンテーション委員と兼任している人が多く、大変な業務を担っていることもあり、とても官僚的な組織です。それも重要な役割なのですが、クリエイティブというより祭りをそつなく終わらせることに重きを置いた団体だと感じました。そこで、私たち3人は入会1年目でしたがやりたいことをいろいろ提案していました。
実現したものの一つが、来場者に良かった企画を投票してもらう「駒場グランプリ」です。出展する学生のモチベーションになって、企画のクオリティーが上がればと思い、提案しました。もう一つは、イベントステージでのオープニングセレモニーとフィナーレです。当時は始まりと終わりのイベントが何もなく、その日になったらなんとなく祭りが始まり、気が付くと終わっている状態でした。朝にオープニングセレモニーをやり、フィナーレで駒場グランプリの結果発表をやれば、祭りとして一体感がでると考えました。ただ、初年度はその時間帯に人がおらず、がらんとして切ない空気のまま終わったので、全てうまくいったわけではありませんが。
結婚、妊娠で変わる扱い ジェンダーを学びに大学院へ
──後期課程では教育学部に進み、卒業後は日本経済新聞社に記者として入社しています
教育学部では教育社会学を専攻し、高校から大学、大学から社会へといった移行過程や、社会における教育機関の役割について考えていました。新卒一括採用についても、学生が周囲の流れに巻き取られるように就職し、長時間労働などを含む会社のカルチャーに染められることへの問題意識がありました。教育社会学では「学校は洗脳装置」と言ったりもしますが、会社も洗脳装置だと感じていました。
学部1年次から、新入生向けの冊子作りなど、情報発信によって「“普通”を疑う」ようなことを続けてきたので、社会人になってもそれをやれる仕事が良いと考えていました。皆が進む道と違う選択肢もあると示し、皆が同じ方向を向くことで見落とされる大事な事実を発信することで、社会をましにしたいと思い新聞社を選びました。新卒で入った人が企業で洗脳されるという問題意識から、企業取材ができる日本経済新聞社を志望し、ダメだったら大学院に進学するつもりで、受けたのはほぼ1社だけでした。
──入社後はどんな記事を担当したのですか
入って1年は、とにかく言われたことをやる日々でしたね。数字が苦手だったので最初に学んでおいた方がいいと思って証券部を希望して配属され、企業の財務取材が担当でした。でも1年目でも担当できる週末の紙面で、関心があるテーマの取材ができることもありましたし、証券部の先輩達と、ESG投資(環境、社会、ガバナンスの三つの観点から企業を評価して行う投資)関連のまとめ記事や企画記事を書くなどもしていました。普段は担当業界の記事を書くのですが、その企画では、社会的な責任に目を向けている企業や、取締役会のガバナンスがしっかりしている企業を業界問わず取り上げました。
入社して数年経ち、自分がしたい取材ができるようになってきた時に、ライフイベントがありました。25歳と比較的早くに結婚したんです。
──その後、第1子の育休中に大学院に入学しています。なぜ再び大学で学ぼうと思ったのですか
結婚した途端、扱いを変えてくる上司がいたんですよね。取材相手との会食に、結婚したんだからお前は連れていかない、と言われたんです。真意は不明ですが「食事の場に独身女性を」的な意味合いで今まで連れていっていたのかな、とか「はあ?」と思うことが結婚して増えたんです。妊娠して、周囲の扱いの変化はさらに加速しました。大学時代から私がいろいろな活動をしてきたと知っている仲間にすら「円佳もそうやって女の幸せを選ぶんだね」とか「バリバリキャリアを積んで、記者やるんだと思っていたけど降りたんだ」と言われたり……。結婚や妊娠によって記者として第一線で活躍するのをやめた、と解釈されることが本当によくありました。それまではセクハラなどをあまり気にしてこなかったのですが、過去を振り返るとこれまでも結構あったなということにも気付き始めたのがこの頃です。
自分の状況が変わって、それまで気が付かなかった問題が見えてきました。うまく言葉にできないネガティブなことがたくさんあって、ジェンダーを学び直さなきゃと思いました。女性がライフイベントと仕事を両立する上で単に育児が大変という以上に、周りからの扱いがなぜこうも変わるのかという疑問を論文にしたいと、大学院に入りました。学部卒で新聞社にたまたま入りましたが、大学院に行きたい気持ちは当時からあったし、いつか大学に戻るかもしれないともずっと思っていました。立命館大学の先端総合学術研究科を選んだのは、上野千鶴子さんが客員教授として教えるという情報を聞いたからです。
──育児と大学院を両立するのは、想像するだけで大変そうですが
妊娠中から怒りを感じる出来事がたくさんあって、とにかく怒ってアドレナリンが出てたのかな……。出産の2カ月前に、住んでいた東京から京都に行って、大学院入試を受けました。子どもが生まれて入学した後も、産後うつならぬ「産後ハイ」で勢い付いていたのかもしれません。
大学院の入学同期に、現在れいわ新選組で参議院議員をしている天畠大輔さんが居ました。重度障がい者で、東京で車いす生活をしていました。Zoomができる前ですが、天畠さんが参加される授業はSkypeで遠隔参加できるようになっていたので、東京で子育て中の私も便乗して遠隔で受けさせてもらいました。ゼミも授業も自分の発表回は同じ週の木曜・金曜にまとめるなど工夫して、月1回程度、子連れで大学のある京都に行き乗り切りました。初めは母も一緒に行ってもらって、そのときに京都で一時保育の場所を見つけて、次からはそこに子どもを預けていました。結果的には1年半くらいで、あとは書いた論文を出すだけの状態になりました。もう一度やれと言われても絶対やりたくないというか、できないと思いますが。
──修士課程修了後、一度は日本経済新聞に復帰しますが、その後フリーのジャーナリストになっています。会社に所属していた時と、違うことはありますか
そもそも育休中に辞めるつもりだったのが慰留され、育休から復帰して1年半働きました。その間に修士論文を『「育休世代」のジレンマ』(光文社)という本にまとめたこともあり、女性活躍推進法の議論の場などに呼ばれることが増えました。新聞社の記者ではなく、本の著者の中野円佳として発信したい場面が増えたのが、フリーになったきっかけの一つです。新聞社では、金融や政治など自分の得意分野が明確になって、一つの専門的なテーマを追いかけ始めるのが、40代後半とかなんですよね。私は女性活躍や働き方改革といったテーマに集中したい気持ちがあったのですが、当時まだ29歳だったので、会社はまだいろいろ経験させたいというスタンスでした。また、社内婚だったこともあり子育てをしていく上で、いずれどちらかに転勤があったらもう片方は辞めるしかないと感じていたことも、退職を後押ししました。
一方フリーでの活動は、収入が不安定だったり、取材費を原稿料から捻出しなきゃいけなかったり大変です。批判的な記事を書いて訴訟リスクを抱えても、自分で弁護士などを頼る必要があります。法的にも金銭的にも、フリージャーナリストはなかなかつらい立場です。
自分がいる場所にたどり着けない人への想像力を持って
──15年に東大大学院教育学研究科の博士課程に入学された後、東大の男女共同参画室(当時)で働き始めています。現在も後継組織の多様性包摂共創センター(IncluDE)に所属していますが、なぜ東大に戻ったのですか
17年に夫がシンガポールに転勤になったのを機に、東大の博士課程に籍は残したまま帯同しました。シンガポールでもジェンダー系の取材は続けていましたが、フリーのまま例えば60代まで発信していけるのか、と考えたときにどこかで行き詰まると感じていました。毎回書きたいテーマが出てくるわけではないので、発生したニュースに反応して素早く書くより、長期的に追えるテーマを考えたいと思い始めました。そのために博士課程にもいましたしね。そろそろ帰国してもいいかなと思っていたころに、東大の男女共同参画室(当時)の求人を目にして、夫をシンガポールに残して子どもと帰国する前提で、応募しました。
──中野准教授が関わった、多様性包摂共創センターの「#言葉の逆風」キャンペーンは学外のメディアにも取り上げられ、話題になっていました。どのようなプロジェクトだったのですか
もともと、男女共同参画参画室(当時)では、学生8:2・教授9:1のジェンダーバランスはおかしい状態だと構成員の意識を改革するために、総長や理事・副学長の旗振りの下で#WeChangeという女性教員を増やす活動していました。教職員向け研修などを実施してきたのですが、もっとインパクトある形で問題を可視化できないかという議論になりました。女性がなぜ少ないのかの理由の一つに、専門用語で「マイクロアグレッション」と呼ばれる、日常に潜む小さな差別があります。東大内や東大にたどり着くまでの過程で女性に投げかけられている言葉が、東大の偏った男女比につながっていると伝えるために、策を練りました。
私の専門の教育社会学でも関連する研究はなされていて、例えば女性は理系に向いていないというバイアスを親や教員が持っていると、女子生徒が理系を選択しにくいという報告もあります。ただ、研修などでこうした論文を紹介しても、聞き手にあまりインパクトがない。実際に「何年前の話?」と言いたくなるような言葉が女性に投げかけられているので、実際の声を拾って「今もあるんだ」と伝える方向で固まっていきました。
そこで、最初に「なぜ東京大学に女性が少ないのか?」という問いのポスターだけを、食堂のトレーなど構内に掲示しました。その時の反応は、学内外から「女性に能力がないから一択でしょ」という回答がとても多く聞かれましたね。「女性の志望者が少ないから」というのは正解ではあるのですが、じゃあなぜ志望者が少ないのかを考えてもらいたかった。問いの掲示から1週間後にその要因の一つである、女性に投げかけられてきた差別的な言葉をまとめたポスターを掲示しました。ポスターに使われている言葉は、東大の女子学生や女性の教員にアンケートを取って集めた実際の言葉です。
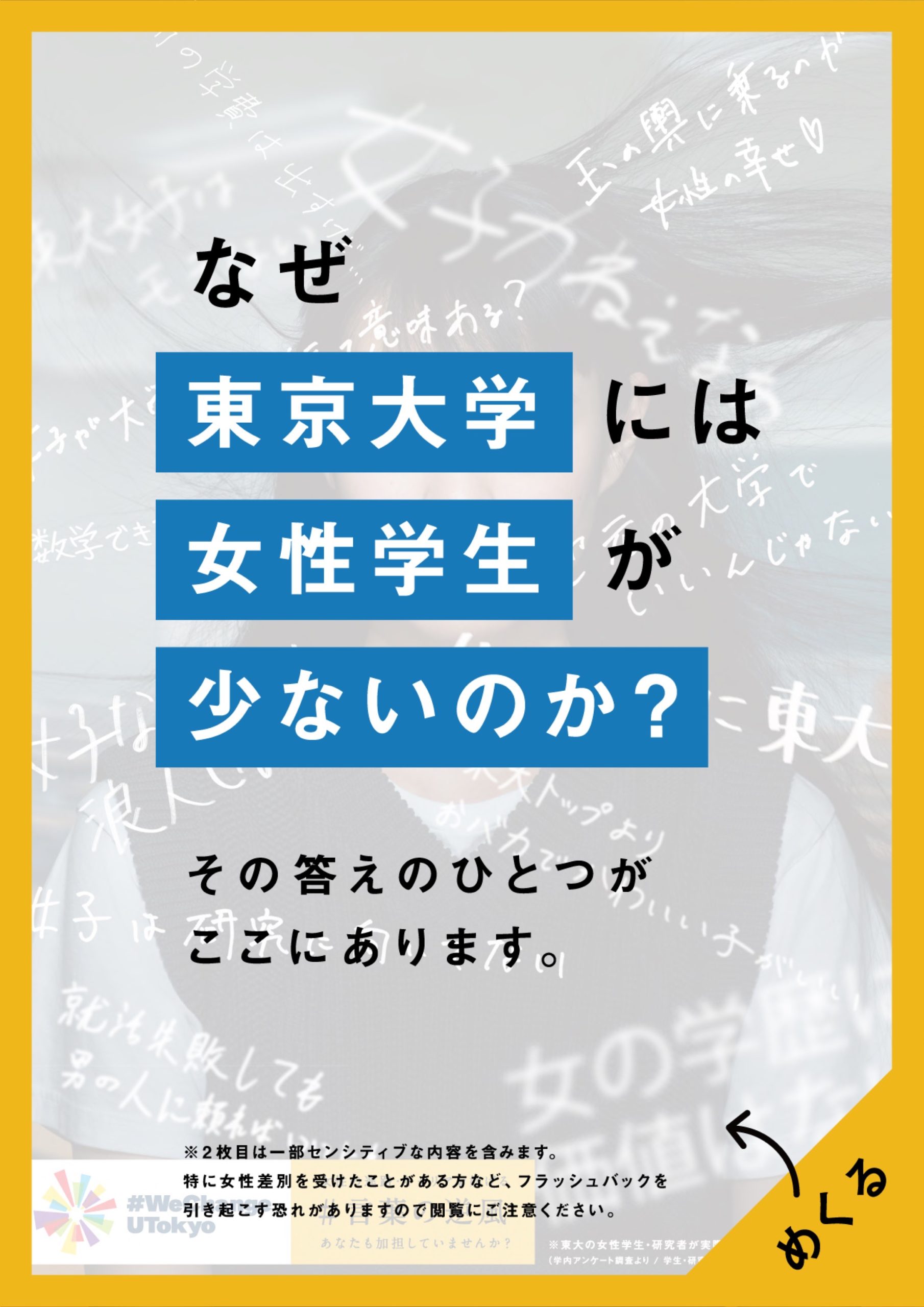
言葉が載ったポスターをそのまま掲示する案もあったのですが、学内にこのポスターがあふれると、逆に女性が落ち込んだりパフォーマンスが下がったりする現象が起きると懸念されました。アンケートの際に、思い出すのもつらかったという声も聞かれ、ポスターを見るまでに「めくる」という工程を挟むことで、すぐに言葉が目に入らないよう配慮しました。
──駒場祭を訪れる東大を目指す受験生や、東大の構成員にメッセージをお願いします
私のキャリアはジグザグに見えるかもしれませんが、学部時代に冊子を作った頃から軸はぶれていません。既存の当たり前に対して、疑問を感じたときに流さず、どう変えられるかをいつも考えてきたと思っています。現状を変えるアプローチは人によって違い、法律を変えたいと思う人もいれば、学校の先生になって教育で変えたいと思う人もいる。私の場合はその方法が情報発信や研究で、研究であっても論文にするだけでなく、広く読まれるように工夫したいという思いがあります。
東大には既存の競争システムに適応できる人が入学しがちだと思うのですが、そもそもその競争の仕方で良いのかと既存の社会や東大の在り方を疑ってほしい。不利な要因で自分がいる場所にたどり着けない人たちへの想像力を持って、社会をもっと良くするために頭を使ってほしいです。
【関連記事】