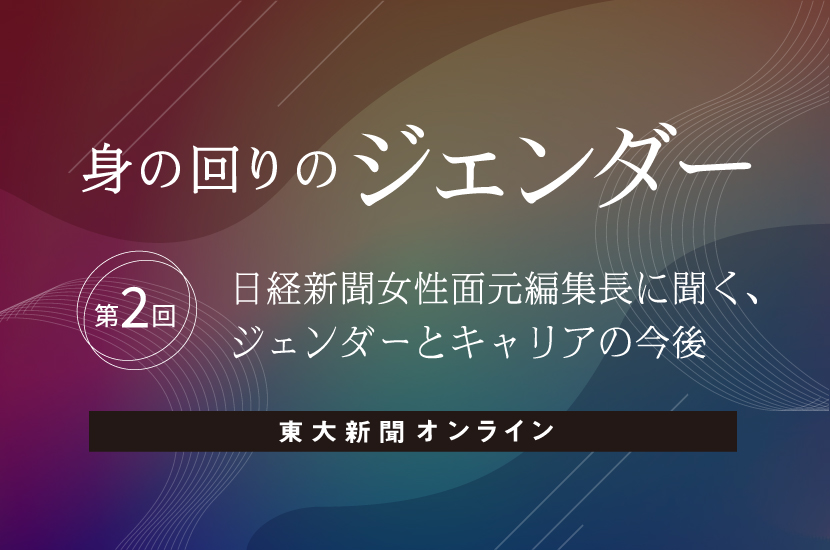
「二十一世紀の日本は本格的な少子・高齢化の時代を迎えますが、結婚しない女性の増加や晩婚化、そして長寿化と、その先導役はいうまでもなく女性です。労働力としても、また消費や投資、社会の担い手としても女性の比重は必然的に高まってきます。国の財政も、企業の経営、家庭や地域の問題も女性の動きを理解できないままでは新時代の糸口はつかめなくなっているのは間違いありません」。これは、1998年に出版された書籍『女たちの静かな革命』(日本経済新聞社)の前書きにある言葉だ。出版から20年以上を経た現在でもなお、この指摘の重要さは変わらないように見受けられる。日本経済新聞元女性面編集長の中村奈都子さんに、キャリアとジェンダーに関する20年間の変化や今後の展望、東大生が意識すべきことについて聞いた。(取材・鈴木茉衣)
日本の女性は「家事をし過ぎ」?
一般に女性のキャリアについて考える時には、出産などのライフイベントの存在が大きく関わってくるとされる。中村さんはまず、このことについて「出産や育児のために休暇を取りやすくする流れは生まれてきているが、育児休暇を長く取れるようにすることや時短勤務をできるようにすることだけではなく、希望する女性が早期に復帰しやすくなるようなシステムももっと必要なのでは」と語る。
さらに、性別役割分業意識がまだ根強く残っていることもあり、日本では男性と女性の家事労働時間の差が目立つ。OECD(経済協力開発機構)が2020年にまとめたデータを基に内閣府男女共同参画局が公表した情報によると、日本の無償労働時間の男女比(男性を1とした時の女性の倍率)は5.5倍と、OECD諸国の中でその値が特に大きい。またこのデータは、国際的に見て日本は、男女ともに有償・無償合わせた総労働時間自体が長いことも示している。
家事から身だしなみに至るまで、女性たち自身にも「なんでも完璧にやろうとし過ぎる生真面目さがあるのではないでしょうか」。家事や育児などは「当たり前にできなくてはいけないこと」だ、という発想の人も少なくない。「当たり前にできる簡単なこと」なのに人には頼みづらいという意識は一見矛盾しているようにも思えるが、このことには女性たちへの外部からの圧力が関わっている可能性もある。しかし、年代や地域によっても価値観の違いがある上「真面目さはルールによって変えられるものでもありません」。サービス自体は少しずつ普及してきているというが、ただ単に他国の真似をするだけではなかなか現実に即したものにはならない。その分、意識を変えていくことが重要だと語る。「24時間でできることは限られているので、優先順位を考えると良いのではないでしょうか」。特に育児については「やればやるほど限りがなくなる」ので、日常的なケアの部分は他の人に頼ることも一つの手だ。その分性別にかかわらず、子の心や悩みなどの親にしかサポートできない部分にはしっかりと向き合うようにする、という在り方を提案する。「毎日ちゃんとしなくても大丈夫ですし、たまには楽をしてもいいんだ、という割り切った意識がもっと広まれば良いと思います」
20年間の「静かな革命」
冒頭で紹介した『女たちの静かな革命』は、日本経済新聞が1998年1月から7月にかけて朝刊1面などで連載した記事を再構成したものだ。中村さんはその半年以上にわたる連載の取材班の一員だった。「当時はまだ現在ほど『女性』や『個人』が意識されてはいなかった」と回想する。
それでも、連載への反響は大きかった。「経済状況の悪化という閉塞した状況を打ち破るために女性の社会での活躍が鍵になることは分かっていたものの、なかなか動けない時代だったと思います」。非正規雇用に関する問題など、現在でも注目されている内容も数多く含まれているが、これは「20年間ずっと言い続けてきたことが、現在に至るまでの間に少しずつ社会の問題として意識されるようになってきた」ことを表しているという。
しかし、何も解決されなかった訳ではない。「問題として発信している内容自体は大きくは変わりませんが、働く女性は増えましたし、いわゆるM字カーブもなくなってきていますよね」。自身の出産時と比較しても「今の方が保育園や保育施設に入りやすくなっているように思えるし、ベビーシッターのサービスも増えてきている」という。育児と仕事を両立させる女性の存在ももはや驚かれるものではなくなった。世界の変化が日本の変化以上に早いので遅れているように見えるが、確実に前には進んでいると語る。「日本経済新聞社の新卒の記者も4割は女性ですし、一般社会では例えば選択的夫婦別姓導入を求める署名活動があったように、特にここ1、2年は若い人の力を感じます」
女性面編集長を務めた2年間では、記事への反響がかつてよりもさらに大きくなっているのを感じた。例えば「選択的夫婦別姓も賛否が分かれるテーマですが、それぞれの立場の人から意見をもらうことが多くあり、新聞からの一方通行ではなくなってきています」。さまざまなシンポジウムやイベントについて「登壇者の3割は女性がいる方が良いのではないか」と提案した記事と同じ紙面に登壇者全員が男性であるイベントの告知が入っていた時には、そのことへの指摘も受けたという。「自分の主張と現実が必ずしもかみ合うとは限らない」という例ではあるが、そのような指摘があること自体、読者からのジェンダーに関するトピックへの関心の高さを表しているとも言えるのだろう。
反対意見にも耳を傾けよ
「20年前と現在の差は、グローバル化が圧倒的に進んだことです。海外からの視点、世界基準というものがより強く意識されるようになりました」。もはや「日本はこうだ」だけでは済まされない。例えば東京オリンピックも、世界的な基準から見たら「おかしい」自分たちの意識や行動に気付き、多様な視点を受け入れるチャンスとなるのではないか、と中村さんは語る。
性別に限らず国籍や年代などのあらゆる属性について、誰もが無意識のうちに偏見を持っている。だからこそ、その存在を認識した上で「それを超えようとしていくことが大切なのではないでしょうか」。男女共同参画やダイバーシティーについて報道する立場としては、企業の経営や政策決定の場で女性が活躍することが総合的に見るとプラスになるということを、データに基づいて伝えることを意識しているという。記事の視点がある特定の立場に寄りすぎてはいないかを常に考え、記者同士で話し合うこともしている。
いろいろな人の意見を取り入れようとするのは「反対の意見にも耳を傾けないと、対立が生まれるだけで解決にはならない」からだ。価値観は生まれ育った環境や受けてきた教育に強い影響を受けて形成される。例えば違う年代の人と意見が合わなかったとしても、そこには生きてきた時代や経験の違いが関係しているかもしれないという。「東大生も恵まれた環境で育った人が多いですが、正反対の環境を生きてきた人と交流することで見えてくるものがあると思います」
中村さんは東大の変化にも期待を寄せる。執行部の過半数が女性となることや2021年度入試での合格者の女性の割合が過去最高だったこと、さらにいわゆる「東大女子お断りサークル」を認めない旨を教養学部オリエンテーション委員会が発表したという学生が主体となった動きにまで触れ「日本の大学のリーダーとして、大学や構成員に大きく変わってほしいし、世界の中のリーダーになってほしい」と語った。「上野千鶴子さんの祝辞も話題になりましたが、一生懸命努力してそれが報われ、希望を持って入学した人が多いからこそ、その能力を周りの人の幸せのためにも使ってほしいです」

【連載「身の回りのジェンダー」】
【連載・身の回りのジェンダー】①「メディア表現におけるジェンダー平等は普段の情報発信から始まる」林香里教授に聞くAI研究の最前線
【関連記事】











