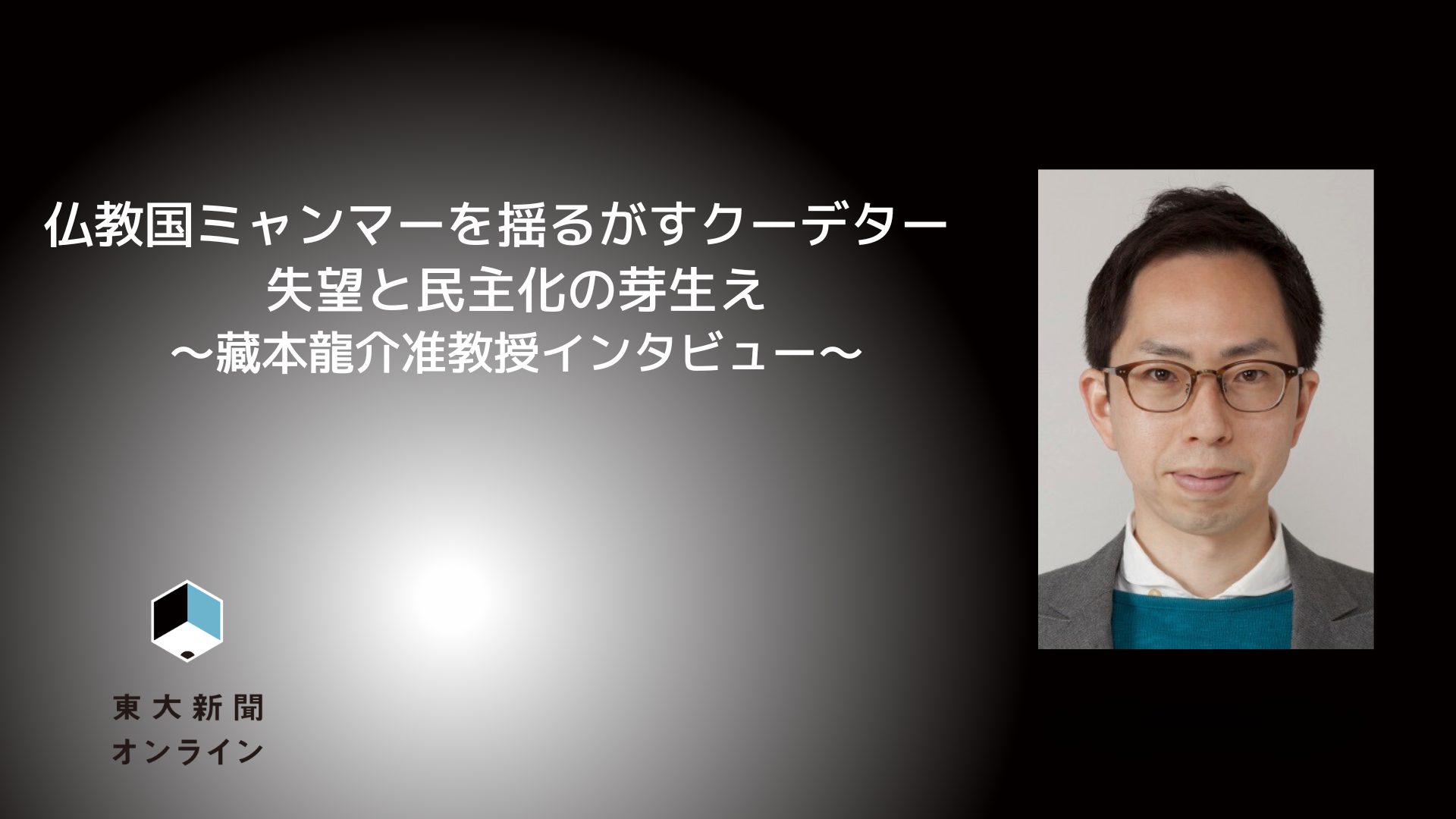
ミャンマーと聞いて最初に思い浮かぶのは何だろうか。アウンサンスーチー氏、クーデター、そしてロヒンギャ問題。2021年2月1日のクーデター以降国軍が政権を握るミャンマーは仏教国としても知られる。ミャンマーにおいて仏教とは何か、仏教と政治・民主化運動は現在、そして歴史的にどのような関係にあるのか。ミャンマー仏教を専門とする藏本龍介准教授(東大東洋文化研究所)に話を聞いた。(取材・峯﨑皓大)
仏教国「ミャンマー」と宗教対立の原因
──ミャンマー国内における仏教はどのような位置付けなのでしょうか
まず量的な観点として、ミャンマーの人口の約90%が仏教徒で、その大部分は上座部仏教徒です。出家僧は約50万人で人口の約1%に当たります。寺の数は約6万寺で、人口がミャンマーの約2.5倍の日本で寺の数が約7万7000寺ほどであることを踏まえればかなり多いと言えるでしょう。
次に歴史的な観点として、ミャンマーの始まりは11世紀ごろにビルマ族が中心となって建てた統一王朝・パガン朝とされています。最初に統一王朝を作る過程で仏教を国教としたため、国の仕組みも仏教を前提としたものになっていました。19世紀のイギリスによる植民地支配の影響で仏教的な国の仕組みは崩壊しましたが、植民地支配後もミャンマーの多くの人が描く国家像は仏教を前提とした国家像で、人々の意識にも仏教は大きく関わっています。
──なぜ上座部仏教が多数を占めるのでしょうか
統一王朝成立前にインド発祥の仏教がミャンマーに流入しましたが、同じ仏教でも上座部仏教、大乗仏教などの宗派に分かれており、多様な宗教世界が広がっていました。世俗権力は、宗派ごとに民衆の世論や動きが形成されて統治の上で不都合が生じることを懸念していました。統一王朝を建てるに当たり、上座部仏教を正統、それ以外を異端とすることで国を統一し、その仏教を守る存在として王を位置付けました。王朝を建てた後は、上座部仏教の聖典であるパーリ仏典を確立したスリランカから僧を招き、上座部仏教に基づく国家づくりを進めていきました。

──イスラム教やキリスト教などの他宗教とは歴史的にどのように共存してきたのでしょうか
王朝時代から異教徒はミャンマー国内に存在していました。異教徒であっても宮廷で重用されることもあり、共存していました。現在のように宗教間対立が大きくなったのは植民地支配がきっかけです。イギリスによる植民地支配の特徴でもある分断支配、つまり少数民族を重要な地位に登用したり、金融業をムスリムのインド人が営み生活が豊かになっていったり、ということにより多数派のビルマ人たちの異教徒への反感は高まっていきます。また、当時のビルマ人はブッダの教え「サーサナ」を信じているという認識で、現在のように他の宗教に対置される「仏教」を信じているという認識はありませんでした。しかし植民地支配下でビルマ人が植民地政府から粗末に扱われたり、キリスト教の宣教師が大量に流入してきたりすることを目の当たりにして「われわれは他とは違う仏教なるものを信じている」という意識が芽生えます。「われわれは多数派で、この国は仏教の国であるはずなのに政治的・経済的にも自分たち以外が優遇されている」と思い始めてビルマ人には不満がくすぶっていました。これらが現在にまで続く宗教間対立につながっていると言えます。
広がる出家者への失望 民衆が民主化の先頭に
──2021年2月1日に起こったクーデターをどのように受け止めたか教えてください
私がミャンマー現地で長期調査していたのは06年から08年で、その時は完全な軍事政権下でした。その時から出家僧が中心となり民主化運動が活発化していきました。16年にNLD(国民民主連盟)政権が誕生し、現地の私の友人たちの生活を見て「一気に経済的に豊かになって希望に満ちあふれているな」と思っていました。11年の民政移管からは10年間もその流れが続いていたので、このままの政体が維持されるのではないかと思っており、全く予想外の出来事でした。
──知り合いなどにクーデターの影響を受けた人はいますか
どれほど影響を受けたかは人によります。国軍側の人たちの生活水準は変わらず、裕福な暮らしを維持しています。一方で市民不服従運動が展開され、特に公務員は今の軍部が政権を握る国に仕えるか否かが踏み絵のようになっており、知り合いのヤンゴン大学の人類学の教授にも、自主的に辞職をした人が何人もいます。生活のために職は必要だけれども軍事政権に仕えたくないという思いで公務員を辞めた人が多くいて、その人たちの生活水準への影響は大きいです。またコロナ禍とも重なり、市民不服従運動の一環として行われた医師らのストライキや、軍による酸素ボンベの買い占めなども影響して多くの知り合いが亡くなりました。
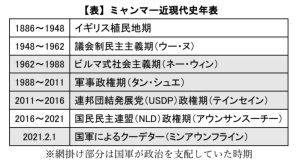
──最近は報道も減ってきています
最近はウクライナ戦争やイスラエル・パレスチナの紛争などもあり、国際ニュースとして報じられなくなっています。しかし現状は何か事態が好転しているわけでもなく、ずっとジリ貧が続いている状態です。
──クーデター前、国際社会から注目を集めていたロヒンギャ問題ですがクーデター前後でこの問題についての国民の意識の変化はありましたか
ロヒンギャ問題が注目された17年当時と現在では国民の意識は全く違います。スーチー氏率いるNLD政権下では多数派の仏教徒たちは完全に反ロヒンギャでした。17年には軍が主導したとされるロヒンギャの掃討作戦について国際社会から多くの批判を集めたもののスーチー氏は黙認しました。スーチー氏自身が反ロヒンギャであったからなのかは定かではありませんが、少なくともあの時点でロヒンギャ問題に対して国際社会が要求するようなアクションを起こしていたら、20年の選挙では多数派の仏教徒から支持は得られないだろう、という考えはあったと思います。クーデター以降、多くの一般市民たちは軍による虐殺、収監を目の当たりにし、また、ロヒンギャがかつて経験した社会からの疎外を経験し、「ロヒンギャも同じようなことを軍からされていたのか」という想像力が働きました。出家者と在家者の間で隔たりはあるものの、少なくとも在家者の間では、反ロヒンギャ感情は小さくなっています。現在行われている反軍事政権デモは宗教を超えて広がりを見せています。
──ミャンマーでは仏教は政治にどのような影響力を持つのでしょうか
先に述べたように国家形成に当たり仏教が大きく関わっているため、国家運営である政治と仏教は無関係ではあり得ません。一方で、ミャンマーでは社会から離れた存在である出家者が社会に深く関わることは矛盾が生じるため、政治にはコミットするべきではないという規範があります。しかし、植民地支配以来、出家者による反植民地支配闘争やサフラン革命、保守派仏教徒団体「マバタ」や仏教僧ウィラトゥの先導する反ムスリム運動など表立った政治活動は行われてきました。活動の中身にかかわらず「出家者である」ということが作用し民衆の支持を広く集めるため、大きな影響力を持ちます。
──国軍と仏教、国軍と出家者の関係は
国軍は、自らが正統な指導者であると主張するために仏教を利用してきました。1960年代にネー・ウィン将軍による軍事政権ができた当初は政教分離を図りましたがうまくいかず、方向転換して仏教と深く関わるようになりました。軍事政権はいかに自らが仏教を支援する素晴らしい政府なのか、ということをアピールすることに執心するようになりました。顕著な例として、90年代以降のパゴダと呼ばれる仏塔の建設、有名な出家僧への称号授与、出家僧へのお布施などがあります。これらの活動を通して、軍は仏教を熱心に支援する、かつての王に匹敵する存在であることをアピールし、それゆえに自らが正統なミャンマーの指導者であると主張しています。現在のクーデター後においても国軍の最高司令官であるミンアウンフラインらは新たに多くのパゴダを作るように動いています。
国軍と出家者の関係は少々異なります。最近の例では2007年に発生したサフラン革命が挙げられます。当時の軍事政権が生活必需品の価格を高騰させ、国民の生活が困窮しました。しかし、一般の国民が軍事政権に抗議をしても軍に鎮圧されることが目に見えていたので、立ち上がることのできない国民に代わって出家者たちが立ち上がり、抗議デモを行ったのがサフラン革命です。大きな特徴としては出家者が国軍関係者からお布施を受け取ることを一切拒否したことです。輪廻(りんね)転生の世界観の仏教徒にとって、お布施とは功徳を積んで良い生まれ変わりをしたり、あるいは最終的に悟ったりするための修行と位置付けられています。そのお布施を国軍関係者から受け取ることを拒否したことを踏まえれば、サフラン革命時点では出家者は反国軍だったと言えます。
しかし、その後仏教徒以外の異教徒や少数民族も取り込んで国を作ろうという理念を掲げる、リベラル色の強いスーチー氏・NLDの勢力が拡大していく中で、出家者はこのままではミャンマーが仏教徒の国でなくなってしまう、という危機感を募らせていきました。これが出家者たちによる仏教ナショナリズムの芽生えにつながり、そして反ムスリム運動につながっていきました。この局面で出家者と国軍の考えが一致し、国軍と出家者の関係が融和的になりました。例えば、反ムスリムを掲げる出家者の仏教ナショナリズム団体は15年の選挙では明確に国軍支持を打ち出し、同様の傾向が20年の選挙でも見られました。もちろん出家者全員が国軍支持であるとは言えませんが、多くの有力な出家者は国軍支持を明言しているという事実があります。
──国軍と融和的になっていった出家者を国民はどのように受け止めているのでしょうか
例えば、22年3月時点でLike!約1800 件、Comment約120件、Share 約550件を獲得しているFacebookの投稿に「クーデター後、ミャンマーの上座部仏教が、信仰に値するものかどうかが疑問視されるようになった」「この大災害を前にして、僧侶たちの指導的役割が発揮されているかどうか、疑問が残る」「今日の上座部仏教僧たちの振る舞いは、自分たちが頼っている社会に対して無責任であるようにみえる」というものがあります。従来はタブーだったこのような発言がミャンマーで出てきたことは非常に驚きです。この背景には、クーデター後、軍事政権により多くの国民が苦しんでいるにもかかわらず、何のアクションも起こさない出家者たちに対する失望感があると思います。07年のサフラン革命の時のように、出家者が国民の側に立って軍事政権に立ち上がるという流れはほとんどないのが現状です。すでに国民が立ち上がっているから出家者が立ち上がる必要がないという考えがあるにしても、明らかに出家者の動きは鈍いです。民主派は、自らが思い描く国のイメージと出家僧の思い描く国のイメージとの隔たりに直面し、以前ほどは出家者に尊敬の念を抱いていないと思います。
──出家者が先頭に立ったサフラン革命と異なり、今回のクーデターでは国民が先頭に立っています
今まで民主派の国民の意識は「国軍は嫌だからスーチー氏に頼りたい」ということに向いていました。しかしクーデター後は、スーチー氏の政治復帰を望むより「自分たちでミャンマーという国を作っていきたい」と考えており、「自分たちで現状をどうにかしなければならない」という気運が若者を中心に高まっているような気がします。このことは今までのように出家者やスーチー氏に頼ってムーブメントを起こすのではなく、自分たちの手でこの国を作ろうという動きにつながっています。今までミャンマーでの民主主義の理解は曖昧で「仏教を支援する指導者が良き指導者である」という意識が広く国民に根付いていましたが、クーデターを機に自分たちがこの国をどうしたいかを国民が考えるようになり、民主主義への理解が深まっているようにも思えます。具体的な展望につながるかは今までのミャンマーの歴史を踏まえると心もとないところがありますが、少なくとも大きな変化ではあると思います。












