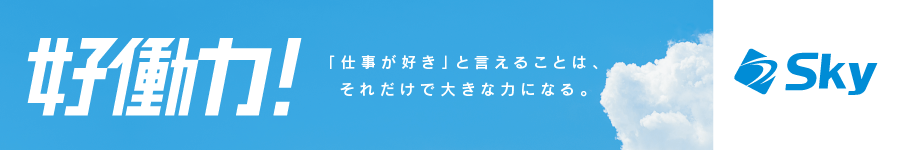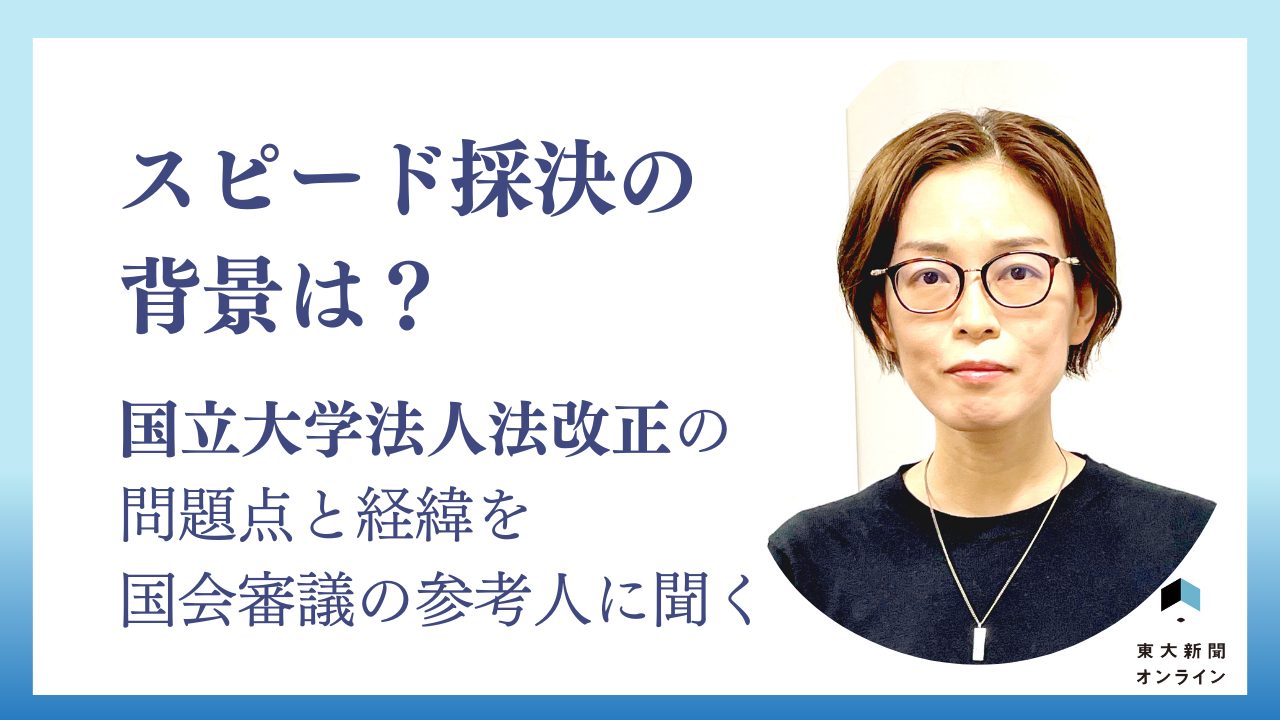
先月13日、国立大学法人法の改定案が臨時国会にて成立した。中期的な経営方針を決定する合議体「運営方針会議」の設置が東大にも義務化される見込み。一部の大学教員や学生から強い反対の声が上がったが、与党は16項目からなる附帯決議を加えることで成立に持ち込んだ。法改正の問題点や経緯について、国会での審議に参考人として出席した隠岐さや香教授(大学院教育学研究科)に寄稿してもらった。(寄稿=隠岐さや香)
昨年の12月13日、大学法人法の一部を「改正」する法律が臨時国会を通過した。これまでにも国立大学法人は何度も改正されてきたのだが、2014年以降はとりわけ、学外関係者(特に経済界)による大学運営参加を増やすこと、各部局(学部)の教授会による自治的なボトムアップの構造を弱めること、一方で学長と執行部によるトップダウン的な意思決定を強めることが実現されてきた。今回の法律はいわばその方向性の終着点として理解可能だが、それだけではない例外的な特徴として、異常なスピード採決がなされたという事実がある。
法案は大半の大学関係者が知らないところで作成された後、10月31日に閣議決定、11月の臨時国会で突然審議入りした。その結果、激しい議論が巻き起こり、四万筆を集めた反対署名や研究者による抗議のスタンディング、国立大学協会による懸念の表明がなされ、最終的には附帯決議が16項もついての法案採決という異例の展開となった。以下では一体何が問題視されていたのかを中心に法律の内容を確認し、背景にある文脈について考察したい。
同法律には、東京大、京都大を含めた五つほどの大規模な国立大学法人を、政令により「特定国立大学法人」として指定し、それらに強い権限を持つ合議体「運営方針会議」の設置を義務づけることが明記されている。運営方針会議は流石に教育・研究の内容には踏み込まないとされるものの、従来なら役員会(学長や理事など)にあった組織の目標や予算に関する決定権が、学長から選ばれた三名程度の同会議委員のものとなる。委員の属性について特に定めはない。だが、考えようによっては誰が委員に選ばれるかにより大学の運営が大きく影響を受けるともいえる。たとえば、短期的な収益を重視する経営マインドの人物がその地位に着任すれば、急激な授業料の値上げが起きたり、特許料収益等の少ない「稼げない」学部が廃止されたりする可能性はある。なお、運営方針会議は上記以外の国立大学も必要に応じて設置できるとされており、五法人以外も無関係ではない。また、公立大学や私立大学の経営にも同様の発想が持ち込まれるのではと影響を懸念する声はある。
改正された国立大学法人法には、大学が土地・財産の運用を柔軟に行えるようにするとの内容も含まれる。そのため、学内の土地が私企業に貸し出されることが増える一方で、保健診療所や寮といった、学生たちの生活には関わるが「カネにならない」施設が軽視される可能性が指摘されている。無論、大学構成員の意見を反映して運用が行われるのならよいが、残念ながら日本の国立大学は学生や一般教職員の意見を民主主義的にくみ上げる制度を充分に備えていない(欧米では学生紛争の激しかった1968年以降、学生や職員も投票で自らの代表を評議会等に送り込める仕組みを備えた大学が多い)。幾つかの大学では既に学生あるいは教職員と執行部のコミュニケーションが難しくなっている。学生寮廃止に対し抗議した結果、大学との裁判に追い込まれた学生もいる。
一方、上記のような解釈とは逆に、今回の法律が大学のガバナンスには大きな変更をもたらさないとの見方も存在する。法律が単に「屋上屋を架す」、すなわち従来の仕組みを複雑かつ非効率にしただけのものに過ぎないとの見方である。確かに過去の法改正により、国立大学には既に運営方針会議の機能と重複する様々な機能が付け加わっている。たとえば、学外者の委員から成る経営協議会という組織があり、学長のガバナンスを「監督」する学長選考・監察会議という学外者を含む組織も存在する。しかし、ならばどうして今回の法律がこのように拙速に作られたのかが問われねばならない。
端的に言うと、同法律は大学経営の効率性を高めることより、政府による大学への介入を容易にするために作られた可能性がある。まず、運営方針会議は学長を単に補佐するのではなく「法人運営を監督」し、その解任に関わる権限すら持つ仕組みである。また、運営方針会議の委員は学長に任命される前に文部科学大臣の承認が必要とされており、ここに政府介入の余地が生まれている。国会審議でも、2020年に起きた日本学術会議の任命拒否事件のように学長が提案した委員を文部科学大臣が承認拒否するのではとの懸念が表明された。こうした批判を受け、通過した法律には「過去に政府の意に沿わない言動があった者等について、言論活動や思想信条を理由に恣意的に承認を拒否することのないよう、大学の自主性・自律性に十分に留意する」ことが附帯決議として記載された。だが、附帯決議には法的拘束力がない。
この法律の目的が明らかにされていないことも、疑惑と憶測を産んでいる。法律を作る場合は根拠となる事実、すなわち立法事実が示されるべきだが、それがないのだ。しかも国会審議の終盤では、法案作成過程を示す公文書が残っていないという驚愕の事実が明らかとなった。かろうじてわかったのは次のようなことである。
運営方針会議という仕組みは元々、先に政府が運用を始めた大学ファンドの運用益を受け取る予定の「国際卓越研究大学」にのみ設置されるはずであった。制度設計をした内閣府総合科学技術・イノベーション会議(CSTI)によると、同ファンドは受益者となる大学に年率三%程度の「事業成長」を求めるため、経営体として機敏なトップダウン型の意思決定が必要ということであった。
だが、2023年5月頃に変化が起きた。法案の内容が、国際卓越研究大学だけではなく「一定規模以上」の国立大学法人も対象にするものとの提案に切り替わったのである。誰がこの提案を行ったのかは依然として不明であり、文部科学省高等局とCSTI、内閣法制局の間の協議に由来することしかわからない。かくして6月には政府関係者を中心に法案の中身が作られ、7月から8月にかけて文部科学省の関係者が東京大、京都大を含む複数の大学学長を個別に訪問し、説明と意見交換を行った。だが、その内容は9月7日にCSTIが関連資料を公開するまで外部には知らされなかった。
意図が説明されないまま秘密裏に用意された出来事といえば、日本学術会議の任命拒否事件が思い出される。同事件は、2018年頃に内閣法制局が学術会議法の解釈変更を行うことで実現可能となった。また、続く自民党およびCSTIによる日本学術会議への「改革」要求には「学術関係者による自治を弱め、外部関係者の関与を拡大させる」という今回の法律と似た発想が見いだせる。
日本学術会議問題はCSTIが経済安全保障の取り組みを進めた時期と重なっている。その中では「特定重要技術分野」として軍民両用研究を振興する仕組みが形作られ、国家安全保障に影響しそうな技術流出を厳しく取り締まる一連の考え方(研究インテグリティ)も登場した。経済安全保障は時にやり過ぎを生む。企業関係者が軍事転用可能な装置を不正に輸出したとの疑惑をかけられて冤罪逮捕者を出した大川原化工機事件は記憶に新しい(2023年12月判決)。遡れば、学術会議問題でも2020年に中国への技術流出に加担したとの疑惑をかけられ、学術会議側が事実無根と否定する一幕があった。
実は、経済安全保障への関心により大学やアカデミーの自治を弱体化させようとする動きは複数の国で進行している。特に右派ポピュリスム政治が支配的な地域では公立、私立を問わず大学自治やそれに伴う「学問の自由」を「学者の特権」として攻撃する傾向が強く、米国やオーストラリアのような国ですら研究者の危機感が高まっている。実に憂慮すべき状況である。事態の悪化を受けて、UNESCO等の国際機関や民主主義多様性研究所(V-Dem)は「学問の自由」が特権などではなく、むしろ国際人権規約に定められ、自由な民主主義体制を支えるものであるとのメッセージを発するようになった。
こう書くと、日本だけではないことに安堵する人もいるかもしれない。だが、V-Demの作成した指標によると、日本の「学問の自由」度は約180カ国のうち下から数えて3割から4割の間に位置する。危機的な水準との自覚は持つべきだろう。果たして日本はここで踏みとどまれるのか。そして、国際的な状況悪化を食い止める側に回れるのだろうか。第二次世界大戦後、焼け跡の中から民主主義を掲げた国の矜恃が試されている。