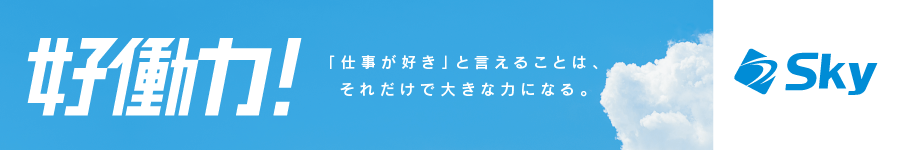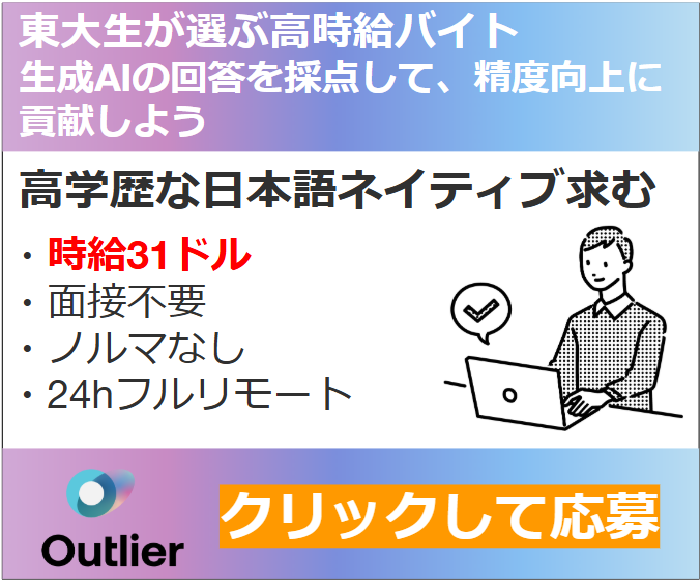「考えるためにフィールドに行く。学んだことを現場にぶつけてみないと、僕は本当の意味で考えてないような気がしてしまう」
そう語るのは、東京大学総合文化研究科で教えながら、途上国での開発援助にも携わり、学術と実務の両面で活躍されてきた木村秀雄教授。すっと背筋の伸びた立ち姿からは想像できないが、今年度で定年退職を迎える。
「本を読んで理論を知っただけでは、わかった気にならない。現場で『練習問題』を解く必要がある」と語る木村先生に、理論と実践を統合することの重要さについて聞いた。

「文化人類学」の青年海外協力隊員としてアマゾンへ
学生運動が激しくなる中、ひたすら哲学書を読む高校生だったという木村教授は、1970年に文科三類へ入学した。自分のフィールド(調査地)を持ちたいと文化人類学の道に進み、南米の熱帯雨林アマゾン地域を研究することに。
現地調査の手段を探していると、国際協力機構(JICA)のボランティアである青年海外協力隊を勧められ、博士課程1年次に選考を受けた。翌年から文化人類学の隊員として南米の国ボリビアに派遣され、アマゾン北部の村で語り継がれる神話の構造分析に取り組んだ。「先住民に聞かせてもらった神話をテープに録音して、書き起してスペイン語訳して…1分の神話で100時間くらい作業したかな」。論文を書きながら、延長期間も含めて3年間現地で暮らした。
アンデスに通う30年 理論と現場の往復
当時は文化人類学教授のポストが全国で増えていて、協力隊の任期を終えた木村教授にも仕事が舞い込み、亜細亜大学で教え始めた。中南米研究者チームのフィールド調査にも参加し、毎年のようにアンデス山脈の高地に滞在。コミュニティの在り方を考える社会組織論の視点から、先住民の暮らす農村を観察してきた。
よそ者への警戒心が強い農村で、論文の材料を集めるのは容易ではなかった。「日常生活で先住民に、なぜこういう行動をしているのか?と尋ねたところで、彼ら自身も説明できない。ケンカとか葬儀とか、何か出来事が起きた時こそ、そのコミュニティの人間関係がはっきり見えてくる」。そう実感してからは、できるだけ多くのハプニングに遭遇しようとアンテナを張って過ごしてきた。
アンデス山脈の村々をめぐる合間には、都市へ降りて本を読み、湧いた疑問をひたすら考える。本で学んだ「理論」と自分が見た「現場」の、一致する部分としない部分。それを確かめる往復の中で、既存の理論に対する自分なりの見解を組み立てることが重要だという。
「30年以上南米に通い続けているのは、好きとか楽しいというよりも…フィールドにいないと僕だめなんだよね、本を読んだだけではわかった気になれない。人類学の理論の勉強はすごく面白いけど、現場に出て“練習問題”を解いてみないと、本当の意味で理解はできない。だから僕は考えるためにフィールドに行っている」。

導かれて開発援助の現場へ
母校である東大の総合文化研究科に移った1990年代から、青年海外協力隊の派遣前訓練など、JICAからの仕事を依頼されるようになった。現在も途上国での開発プロジェクトの評価に携わる木村教授にとって「現場」とは人類学のフィールドだけでなく、開発援助事業の最前線という意味も含む。大学と援助機関をまたいだ活動経歴は、2004年に創設した「人間の安全保障」プログラムの、国際協力の理論と実践を統合するという教育方針に活かされている。
「はじめから国際協力を目指して進んできたというより、仕事を一生懸命やっていたらご縁がつながってここまできた。自由に好きなことをやるには、駒場は生きづらい場所ではなかったね。文化人類学を始めたから今の僕はこうなっているわけで、その恩は大きい」。様々な現場を見てきた木村教授の目には、鋭く衰えない好奇心が覗く。
インタビュー2では、木村教授が委員長を務める「人間の安全保障」プログラムについてお伝えします。
中編:「国際問題の理論と実践をつなぐ人材を育てよ」木村秀雄教授 退職記念インタビュー2
後編:開発援助の新たな指針「持続可能な開発目標」とは? 木村秀雄教授インタビュー3
《木村秀雄》
1950年生まれ。総合文化研究科超域文化科学専攻教授。「人間の安全保障」プログラム委員長。青年海外協力協会理事。著書は『響きあう神話現代アマゾニアの物語世界』(世界思想社1996年)など。