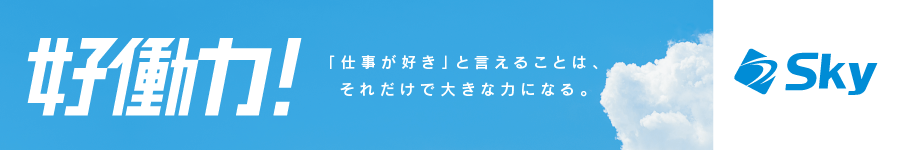本郷の生協書籍部のレジカウンター脇にある「売り上げランキング」のコーナーでは、一時期新書部門の1位の棚にこんな宣伝文句が載った帯の本が置かれていた。
「東大VSアイビーリーグ 6勝4敗で東大の勝ち!?」
『教えてみた「米国トップ校」』というタイトルのこの本は、帯から受ける印象とは裏腹に、東大と米国プリンストン大学の内実を比較することで東大の強みと弱みを再認識し、そこから見えてくる東大が取るべき改善策を提言した一冊である。この本の著者こそ、毎年東大とプリンストン大で半年ずつ教壇に立つというあまり例がない生活を送っている佐藤仁教授(東洋文化研究所)だ。
東大が日本国内の学生をも引き付けられなくなるのではと懸念されている現状をさまざまな学生への取材から描き出してきた特集「蹴られる東大」。6回目となる今回は、日米双方の大学事情に詳しい佐藤教授にインタビュー。「東大には欠点の改善と優位点の強化という両にらみの改革が必要」と語る佐藤教授に、東大がこれから取るべき方策を聞いた。
(取材・高橋祐貴 撮影・安保茂)

全ての問題の根幹にある「教員の時間配分」
──『教えてみた「米国トップ校」』の中で、一つ一つの授業で学べる内容を深め、教員の授業負担を減らすためにも授業のコマ数を減らすべきとしていますが、それが東大では進まないのはなぜなのでしょうか
一つにはおそらく学生の取り合いという事情があると思います。本郷の教員が駒場の1、2年生に授業を行うことで、自分の学科に来てくれる学生を確保している側面があるわけです。もし学生が受ける授業数を減らすと、本郷の学部からすれば人材供給の回路を一つ断たれてしまうことになるので、簡単にはいかないのかもしれません。
後は語学のように、教えるのに一定のまとまった時間を必要とする科目が前期教養課程に多いことも授業のコマ数を減らせない原因の一つであると思います。ただ一般論としては、授業のコマ数を減らせば先生の負担も減るはずで、反対する教員がそう多いとも思えないので、なぜ授業のコマ数が減らないのかという点に関しては僕も疑問に思っているところです。
僕は今プリンストン大で行われているくらいのコマ数、すなわち学生の側からすると週四つの授業、教員は1学期に二つの授業を受け持つくらいが適切だと考えています。もちろん本でも書いたように、授業の数をただ減らすのではなく、一つ一つの授業の密度を濃くして、授業外で多くの学習を学生に積ませるようにしなければなりません。
──現在東大の授業は1コマ105分ですが、これには長すぎるという学生からの不満も度々聞かれます。授業時間を短くすることや、プリンストン大のように授業時間を教員の裁量に任せることはできないのでしょうか

おそらく一番の問題は時間割の調整が難しいことでしょうね。プリンストン大では大教室での講義の授業のほとんどが、講義が50分×2コマにディスカッションの授業が50分×1コマの計3コマで構成されます。50分という授業時間は教員にとっても学生にとっても集中力を保つ上では適切です。この制度を導入するとまず、一つの授業で時間割が多く埋まってしまうので取れる授業が限定されることになりますよね。この意味で授業時間の問題は授業のコマ数削減の問題と不可分です。そして授業の時間割を全学部がそろえなければ、学部をまたいで学生が授業を取ることができなくなります。この点は何とかしなければなりません。
東大でも過去にトップダウンで時間割を柔軟なものに改革しようとした例はあったと思います。でもそれが変わっていないのは、各学部の自治があり、学部ごとの裁量がとても大きいため、それぞれの部局の個別事情に抵抗されたからではないかと想像します。
──著書の中で、講義形式の東大の授業には講義ならではの良さもあるという話をしていますが、より講義の内容が学生に伝わるようにするためにはどのような改善の余地があると考えますか
やはり将来教員になる大学院生を早い段階から教師として訓練することを大学として制度化しなければならないと思います。今の日本の制度だと、ティーチング・アシスタント(TA)の院生は本当に雑用をしているだけで教師としての訓練を受けていません。一方米国だと、博士課程の学位取得の条件として、少人数のゼミ授業を1人で受け持って教えるということが課されます。院生とはいえ学生から授業評価を受けるので文句を言われる場合もあるし、実際に教える前には研修も受けて、例えば討論式の授業の中で発言しない学生にどうやって発言させるか、といったところまで訓練されてから臨む、本格的な実地練習なわけです。こうした練習を院生のうちに何回か積んでいるのと、東大のように「今日からあなたは先生です」と言われていきなり教壇に立たされるのではやはり違うでしょう。
確かに今東大でも東京大学フューチャーファカルティプログラムのような教員育成の講座が開かれており、教育に関心のある院生は受講しますが、こうした人たちは意欲があるから元々自分たちである程度教え方について勉強するんですよ。困るのは「自分はできる」と思い込んでいるけど学生からするとひどい教え方をしている、というような教員で、こういう人たちの教え方を直すには教員になってからでは遅いと思います。

もう一つ米国大の教え方でいいと思うのは、著書でも触れていますが他の教員と一体感を持って行うチームティーチングがあることです。日本でもオムニバス形式の授業がありますが、他の先生が授業を担当する日には授業に行かない教員がほとんどでしょう。他の先生の授業を見てその講義術を学べる点でチームティーチングは優れていますが、いかんせん日本の大学教員は忙しすぎて、自分の担当でない日にも授業に行くのは嫌だと思うほど疲弊しているわけです。
学生に授業が面白いと感じてもらうには、教員が自分の専門分野について楽しそうに語っている姿を見せることが第一だと思います。しかしそれもさまざまな学務に追われてへとへとになっている状態だとできませんよね。まずは教員の忙しさを解消し、心と時間の余裕を持たせることができないと、大学の講義の質の向上は望めないでしょう。
東大が今抱えている問題の根本には先生たちの時間をどのように配分するかという話があって、授業に割くのか、研究に割くのか、入試を含む学務に割くのか、その時間の奪い合いなわけです。だからこそ著書で強調している通り、改革は一体的に進めなければなりません。「入試改革をして多様な学生を取れるようにしろ」と言いますが、それはすなわち授業や研究に割く時間を削れと言っているのに他ならないわけです。教員の仕事全体を鑑みずに一部の問題を取り上げて改革を進めるのは的外れだと僕は思います。
教員の負担を減らすために
──著書の中で教員の時間を確保するために事務職員の戦略的活用を提案していますが、これはどの程度実現可能なのでしょうか

それに関しては実際にかなり改革が進んでいます。東大は数年前からリサーチ・アドミニストレーターと呼ばれる、研究活動の企画やマネジメントを行う高度事務職員をある程度高給で迎え入れる制度を整えてきました。
ただ、根底にある問題として、教員が意思決定をして事務職員はそれに従う、という環境が長く続いたため、そもそも事務職員が大学の意思決定を先導するというカルチャーがないことがあります。この文化的な問題を短期間で解決するためには、思い切った権限委譲をするしかないでしょうね。現在五神(真)総長が主導して、大学の事務を行うのに際して教員が所属する委員会の数を減らしています。事務職員に任せられる仕事からは教員を撤退させる仕分けが進んでおり、この成果がどのように出てくるか、というところだと思います。
──教員の負担を減らすためのもう一つの施策として入試業務の外部委託を挙げていますが、具体的にどのような方策が取れるでしょうか
僕は今のセンター試験にあたる1次試験に関しては完全外注してしまっていいと思います。現在は問題作成や試験監督に大学教員が駆り出されていますが、両方とも完全外注できるのではないでしょうか。
一方2次試験は力を入れなければならない部分なので、何年かに1回汗をかかなければならない教員が出てくるのは仕方がないでしょう。ただここに関しても、入試のノウハウを持っている退職した名誉教授を呼び戻して、さまざまな学務に協力してもらうことで現役教員の負担を減らすシステムがよいと思います。こうした取り組みによって、教員の入試業務の負担を減らす余地はまだまだあるでしょう。五神総長のイニシアチブで退職教員の再雇用は始まりつつあるので、成果を見守りたいところです。
米国大のいわゆる全人評価型の入試制度は、公平性が担保できないので、私立大学はともかく国立大学で全面的に取り入れるには危うさがあります。コストも考えると、現在のペーパーテスト入試は一つの落としどころだと僕は考えています。著書でも触れていますが、試験一本型の入試の方が多様な学生を採れる可能性もあるわけです。これよりいい入試制度がないとは言い切れませんが、大学というのはやはり勉強するところなので、学力一本で選抜している今の東大の入試は、決して悪くはないのではないでしょうか。
合格者の99%が入学する東大は「異常」
──日本国内の財団による奨学金の拡充により、一部の学生は学費の高い米国トップ大に東大よりも安く進学できるようになってきていますが、こうした中で東大が日本の優秀な学生を確保し続けるためにはどうすればいいでしょうか

まず前提として、一つにはそういう恵まれた奨学金を得られる学生はとても限られているということを認識しなければなりません。加えて、奨学金をもらったから進学できるということと、大学に入ってから心地よく生活できるかどうかという点は全くの別問題だということもあります。米国のトップ大というのはある意味階級社会で、学生の半分くらいは4年間で2000万円を超える額の学費を黙って支払えるような家庭から来ています。そうした場所に奨学金のおかげで進学できたとして、例えば「夏休みにどこに遊びに行くか」といった普段の何気ない会話の端々に、育ちの違いを感じざるを得ないような場面が多々出てくるはずです。こうした階級格差が米国の社会だといえばそれも一つの勉強ではありますが、単に奨学金をもらって進学できることになったからといってそれで万歳という話ではないことは覚えておいてほしいです。
その上で、東大が学生を引き付けるにはどうすればいいかという点についてですが、それはいかに東大での教育を魅力的なものにしていけるかというところに尽きると思います。そのために、今まで挙げてきたような改革を着実に進めていくことが大切です。
僕は実は、学生だけでなく教員も含めて東大からごっそり海外に抜けていくというステップが、東大が本気で変わるためには必要だと思っています。今まで東大がなかなか本腰を入れて改革してこられなかったのは、結局殿様商売だからですよね。学生はほとんど入学を辞退しないし、教員も一度東大に来たらほとんど移らない。そんな状態で改革と口では言っても、本気で取り組む理由がないわけです。米国だと、ハーバード大だって2割の学生は入学を辞退して他の大学に流れます。それだけ熾烈(しれつ)に学生の奪い合いをしているわけです。一方東大は99%がそのまま入学する。これは考えてみたら大学としては異常ですよ。合格者の3割が入学を辞退するくらいになり、若手の優秀な教員がどんどん海外に引き抜かれるというような事態になって初めて、本当に切迫感を持った改革が東大でも行われるのではないでしょうか。
──まだ東大の危機感は足りていないと思いますか
東大の全体を見渡している東大の幹部の人たちは、相応の危機意識を持っているはずです。実は、五神総長が『教えてみた「米国トップ校」』を数十冊まとめて購入し、副学長や各部局長の方々に配布してくださるということがありました。一度、各部局の幹部候補である補佐の人たちが集まる総長の補佐会議で、僕の本の提案をどう大学として受け止めるかについて議論したこともあります。そういう意味でこの本の問題意識は安田講堂の本丸に届いています。
加えて、幹部陣だけではなく、人材集めに苦労している一部の大学院の教員なども、ある種の危機感を持っていると思います。しかしながら、こうした一部の教員の危機感は、個人レベルの危機感であって、大学全体の制度をどうしたらいいのか、という意識にはなかなか結集していない印象を受けます。総合的な危機感という意味では、まだ足りていないのではないでしょうか。
東大は世界と勝負しなければならない
──東大の現在の世界での立ち位置は、どのようなものだと認識していますか

これはおそらく分野によって著しく異なりますね。自然科学や工学の人たちは、世界と対等か、勝っているという意識で研究していると思います。逆に文系だと、例えば法学や人文学に携わる人たちは、そもそも世界と比べて自分がどういう立ち位置にいるかを考えるという発想すらないかもしれません。その一方で、ある程度グローバル化した学問分野では、例えば経済学のように、院は米国に行くのが前提になっていて、いわばメジャーリーグに選手を送るためのマイナーリーグとしての地位を自覚している分野もあるわけです。東大の世界での立ち位置というのは一概には言えないと思います。
ただ、そもそも東大の世界における立ち位置というものを本気で考えている人が東大にはどれほどいるのかという点が大事だと僕は思っています。実際の立ち位置が客観的に見てどうか、ということよりも、世界を意識して教育や研究を行っている教員がどれだけいるか、ということの方が重要です。
──東大は日本人のために作られた大学であり、世界と競争することはない、という考え方もありますが、東大が世界の大学を意識しなければならない理由は何なのでしょうか
もちろん東大は東大の道を歩む、という考え方もあるとは思います。ですが、ではこれから先ハングリー精神あふれる人材がどんどん海外に出て行き、そうでない人材だけが東大に残るというような状態になることを容認するかどうか、という観点が一つ。それから、大学ランキングなどの指標にも左右されて動いている留学生のマーケットにおいて、米英の大学に受からなかった人たちだけを呼び寄せる大学に甘んじていていいのかという疑問も出てきますよね。さらには、東大に海外から寄付してくれている人々もいて、彼らは世界から見た視点で東大を評価するわけで、こうした人たちにアピールをしなくていいのかという問題もあります。なのでやはり、今のグローバル化の中で世界を無視して我が道を行くという選択肢は東大にはないのではないかと僕は思います。
──では、東大が国際的に存在感を高めるためにはどうすればいいのでしょうか
これも分野により異なりますが、文系の分野について言えば、好む好まざるに関わらず英語で書くということをしていかなければならないでしょうね。そしてそれをサポートする体制を大学で整えるべきです。英文校閲を依頼する費用を出す、書いたものを海外の出版社に売り込むプロを雇うなど、できることはあると思います。もちろん全ての教員に画一的に「英語でも書け」と言う必要はありませんが、中には英語で書いてみたいと思っている研究者もいるはずなので、そうした人々を後押しする仕組みが必要ではないでしょうか。
海外から来た留学生や研究者に、いかに過ごしやすい環境を提供できるかという視点も大切です。1年程度東大で過ごして、東大が良い場所だと思ってもらえれば、母国に帰ってから「東大はこんなにいい場所だった」と周りの人に話してもらえるわけじゃないですか。国際的な発信力を高めるためには、外への発信に加え、こうした「内なる発信」も不可欠だと思います。

◇
「プリンストンに戻ったら、また白熱教室ならぬ顔面蒼白教室をやらなければ。」取材後、数日のうちに日本から米国に戻り授業をする予定だった佐藤教授から言われた言葉だ。「この年齢になった私だって挑戦を続けているのだから、君たちの世代もぜひどんどん挑戦していってほしい」と話す佐藤教授からは、学生にもっとハングリーになってほしいという願いが伝わってきた。
東大には一体的に改革しなければならない制度上の問題が山積している。今回の取材で東大の上層部がかなり自覚的に問題に対処しようとしているということが見えてきたが、一方でわれわれ学生にもできることがあるだろう。学生の一人一人が現状のシステムの中でできる限りの挑戦をし、「もっと積極的に学びたい。それがしやすい環境にしてほしい」というメッセージを東大の制度を動かしている大人たちに行動で伝える。学生一人一人のこうしたハングリー精神の積み重ねが、東大をより充実した学びの場に変えていくのではないだろうか。
※次回は東大から1年間プリンストン大学に交換留学した経験を持つ東大OGに、後期課程も含めた東大とプリンストン大の比較を行ってもらいます。次回掲載予定は5月25日です。
【関連記事】
【蹴られる東大】
本音で語る、僕らが海外を選んだ理由(上) 海の向こうへの挑戦
本音で語る、僕らが海外を選んだ理由(下) 海の向こうで見たもの
ハーバードで2年間 気づいた「自分、東大、ハーバードの強み」
拝啓 悩める高校生へ 〜東大生とハーバード大生が伝える、2大学の魅力〜
勉強に対する姿勢の差 東大生は勉強していると胸を張って言えるか