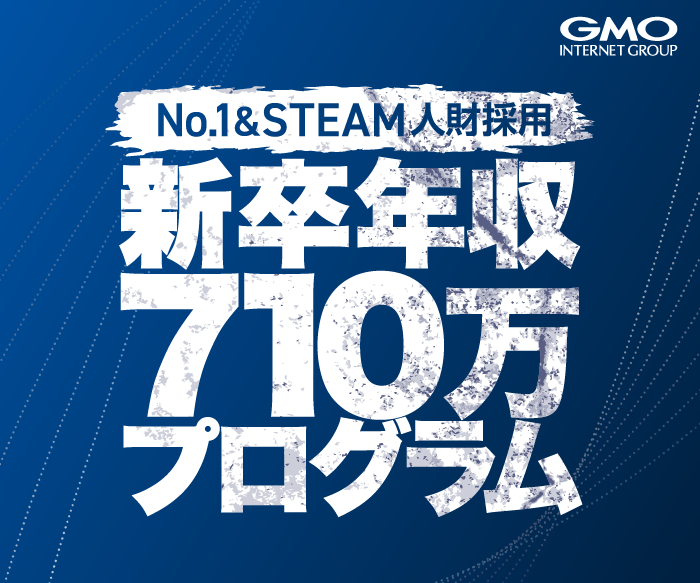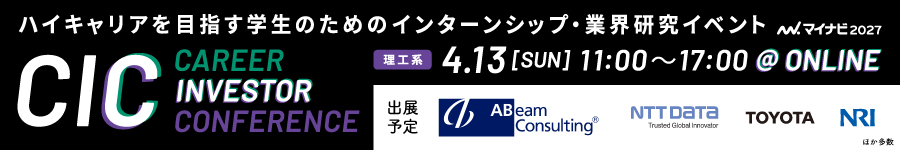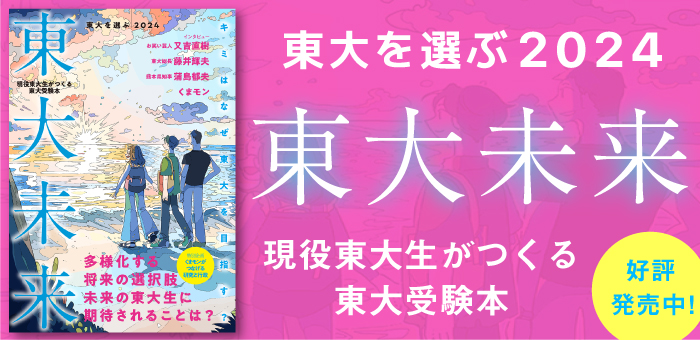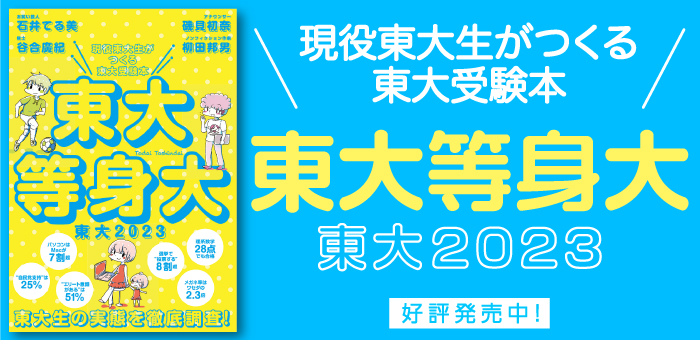東大は日本の国立大学の中で最も多くの額の公金が投入されている大学だ。東大に入学すると、私立大学と比べて安価な学費で授業を受けられ、キャンパスの施設を利用することができる。この恵まれた環境を利用できる「特権」を与えられた東大生は、どのようなことを意識して学生生活を送るべきだろうか。学生時代に東大闘争に関わり、その後弁護士として労働問題などに取り組む傍(かたわ)ら30年以上「法と社会と人権ゼミ」(川人ゼミ)で講師を務める川人博弁護士に、東大での学生生活やゼミを通して考えることなどを聞いた。(取材・平井蒼冴、撮影・赤津郁海)
経済学部から弁護士に 学生時代の友人は大切
━━大学入学以前に印象に残っていることは
私は大阪の泉佐野市という、大阪の中でも少し田舎の地域の出身です。通った小学校と中学校は地元の公立でした。大学入学以前だと中学生時代が一番記憶に残っています。とても荒れていた中学で、今でいう授業崩壊が起きていました。学校を取り巻く環境としても、さまざまな差別や人権侵害が問題になっているような地域だったんですよね。戦後間もない頃の貧しさも残っていて、特に中学校時代は社会問題に直接触れる機会がたびたびありました。私にとって中学生時代はある意味で人権の縮図のようなものだったと思います。このことがのちの人生に大きな影響を与えたと思っていますね。中学を卒業すると堺市の三国丘高校に進学しました。高校時代は柔道部のキャプテンでしたが、体育会系の持つさまざまな問題も体験したりしました。
━━東大を選んだ理由は
私の高校からは京都大学や大阪大学に進学する道が主流でした。ただ、私の場合は首都東京に行きたいっていう意識が強かったんですよね。どうせ行くのなら、大阪や京都の大学より首都東京に出たいと。東京の大学の中でも東大を選んだ理由は、日本一の難関と言われていて、優秀な学生が全国から集まっていたからです。あとは、二つ上の兄も東大に入っていて、それも当然影響しましたね。
━━東大に入って感じたことは
クラスオリエンテーションはやっぱりすごく良かったですね。上級生のメンバーが企画してくれたレクリエーションを通して大学生活のイメージやクラスのまとまりを作る上で重要だったように思います。あと、われわれの頃には文Ⅰ・Ⅱ合同クラスも半分以上は男子だけでした。私のクラスには男子しかおらず、衝撃的でしたね。
━━経済学部から弁護士を目指したきっかけは
一番上の兄が経済学者をやっていたこともあって、文Ⅱを選び経済学部に進むところまでは何の迷いもありませんでした。ただ、学部卒業前、院進のための勉強をしていた時、法学部に進学したかつてのクラスメートたちに彼らの司法試験の勉強会に誘われました。結構悩みましたが、結局司法試験を受験することにしたのです。当時は司法試験予備校もなかったので友人や先輩で先に合格した人たちから勉強会で教えてもらいました。私は1度も法学部の授業を受けたことがなかったので、ゼロから勉強を始めたのです。でも教えてくれた仲間が優秀だったので2年弱で司法試験に合格しました。そういうわけで、選んだ学部は今の仕事に直接関連していないですが、弁護士になって失敗したとは思っていません。ただ、もし経済学の道に進んでいたら「経済と社会と人権ゼミ」を開いたら楽しいかなと考えることもあります(笑)。
━━大学生活全体で印象に残っていることは
今振り返ると学生時代の友人は、先輩後輩含めとても大事だなと思います。大学までの友人は、利害関係のない人間関係だと思うんですよ。でも社会人になると人間関係を築く上で、ビジネス上の利害関係が前提にあって、この人と付き合うと得だという意識が入ってくるのです。
学生時代には、人間関係を築くとき損得を考えることはないと思いますが、これは大事なことなんですよ。社会人になって悩み事があっても、職場のメンバーには相談しづらいことは往々にしてあります。この時、利害関係のない学生時代の友人が大切になってきます。
私は大学紛争という異常な時期に大学時代を迎えたのですが、それでも大学での人間関係が結果的にその後の人生に特に精神的な面で影響を与えていますね。大学のクラスで同窓会を開くと、70 代になっても動ける人のうち約半分は来てくれるんです。やっぱり大学時代の友人との人間関係に良いものがあるから集まるんですよ。読者の皆さんも学生時代の人間関係は大事にしたらいいと思いますね。
闘争の「異常」な1年 大きな財産に
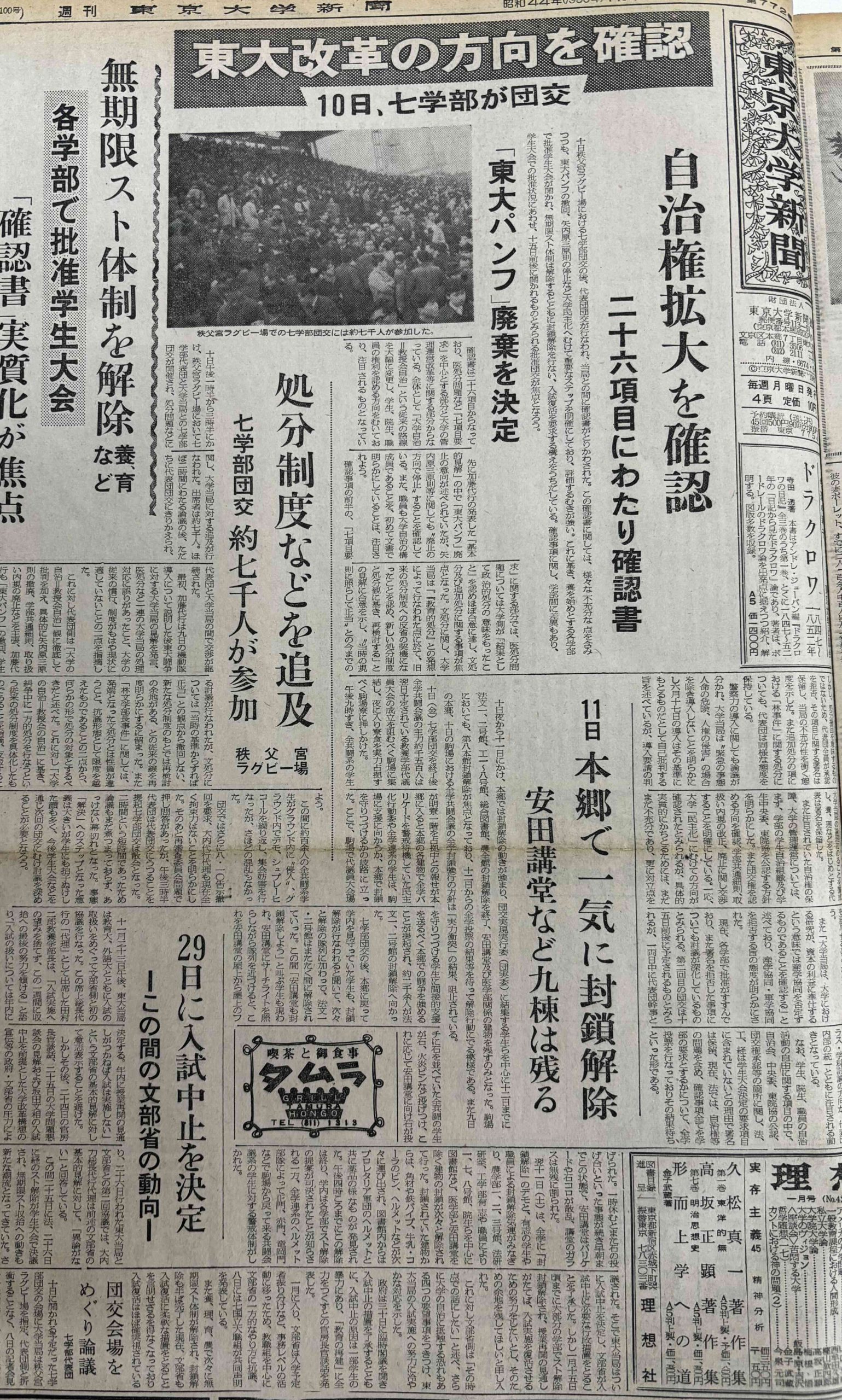
━━大学で学生運動に関わったきっかけは
私は1968 年に入学したのですが、その年の1月から既に東大の医学部の学生は全面的な授業のストライキをしていました。つまり東大闘争、あるいは東大紛争は私が入学する前からから始まっていたんです。東大闘争が東大全体に広がったのは、68 年6月20 日に安田講堂前で集会が開かれてからです。多くの学生がストライキあるいは授業放棄をして、1万人以上が安田講堂前に集まったんです。私のクラスからも、私含め60人中50人くらいが集会に参加しました。
私が入学した時点で、東大は既にマグマが溜まっていて、いつ噴火してもおかしくない状況でした。そういう状況で私や私のクラスメイトを含め、多くの学生が参加したという経緯があります。
━━闘争に関わった中での思い出は
私は第一に東大の中の人権闘争だと思っているんですよ。まず闘争の発端となった医学部学生のストライキは新人医師への人権侵害に対する抗議から始まっているんです。1967 年当時まで、医学部の学生は大学を卒業して1年間無給で働いてからでないと国家試験を受けられないという、ひどい人権侵害の制度でした。そして、このインターン制度に代えて提案された登録医制度案も新人医師の人権を尊重しないものだったので、68 年1月に東大医学部生がストライキに突入しました。このストライキの中で、東大医学部の学生が大量に処分を受けたのです。退学など非常に重い処分もあった上に、処分された人の中には明らかな冤罪(えんざい)だった人もいました。この理不尽な処分も重大な人権問題といえるでしょう。
東大の多くの学生がストライキをしたのは、まずはそういった人権侵害を正すことが大きな目的だと思います。6月20 日に学生が今では考えられないような数集まって、声を上げたということはとても印象に残っています。
━━昨年、東大では学費問題に関し安田講堂の前で何度か集会が持たれましたが、集まった学生の数は1万人に遠く及ばない数でした。当時と今との違いは
昨年の集会に参加した人から話を聞いて、全く時代が違うなと思いました。もちろん、100 人でも200 人でも集まるのは大切なことです。ただ、私たちの頃は、学生の人権があまりに蔑(ないがし)ろにされているという声と、大学を変革しなければいけないという声が大きかった。
東大闘争に多くの学生が参加した背景にはいろいろ要素があると思いますが、当時は今ほど学生の中に富裕層が多くなかったと思うんですよ。地方の学生で、仕送りがない人も相当いましたし、クラスに何人か自分で稼いで実家に仕送りしている人もいました。収入面も含め、学生が育ってきた基盤が、1960 年代と今では大きく異なっていましたね。今では中学受験のために、小学校から塾に通う子どもも多いようですが、当時は浪人生くらいしか塾に通うことはなかったです。経済的な条件の違いは大きいと思います。
ただ、学費問題で集会に参加したのが100 人でも200人でも、それは重要なことだと思うんですよね。少ない数だから、あまり意味がないとも思わないですし。学費がどう使われるべきかについて考え、声を上げるということは、大学にとっても大事なことだと思います。教員や執行部だけではなく学生も議論に加われば、必ず全体にとってプラスになります。ぜひ引き続き関心を持って取り組んでいってもらえればと思います。
━━闘争に参加したことがキャリアに与えた影響は
東大闘争の最終盤に、学生の間で意見が分かれます。私も含め多数は大学側が医学部生への処分の撤回を認めたら、ストライキを解除すべきという意見でした。それで、私が1年生だった1969 年の1月10 日に大学側と学生代表とで、処分の撤回や学生の声を大学に反映できるようにすることを大学に認めさせる「東大確認書」というものを交わしました。私は教養学部の学生代表の1人として確認書に署名しました。
確認書を交わすまでの流れの中で、筋の通る要求をきちんとすれば最終的には正しい解決に至るという信念を持つようになりました。弁護士として活動する上でも、事件があった時、筋が通らないことに対してきちんと申し立てをすれば、たとえ時間はかかっても事件は解決すると思っています。大学1年生の1年間の体験は今でも大きな財産です。
現場で感じ取れ 効率重視は危険

━━ゼミを始めたきっかけは
東大確認書で、大学運営において学生の声を尊重する理念が確認されました。その理念のもとで、教養学部では学生の自主ゼミへの、教室の提供をはじめとする支援が拡充していきます。そんな中、1980 年代後半に学生から弁護士を招いたゼミを開きたいという声が上がります。92 年春、当時は過労死の問題にかなり取り組んでいましたが、自分が大学時代に関わった確認書の理念に基づく自主ゼミを担当することに時間を割く価値があると思い、引き受けました。その頃は2、3年くらいで講師を終えるとイメージしていましたが、もう今年で34年になります(笑)。
━━初期と今のゼミの違いは
ゼミがスタートした1992 年と今とで、実はほとんど同じなのです。人権の問題について現場から学ぶというゼミのモットーはずっと変わっておらず、フィールドワークで現場に行ったり、さまざまな専門家に話を聞いたりということを92 年から今までずっとやっています。もちろん行く現場は変わります。新しく生まれた社会問題もある一方で、ゼミが始まって以来今も取り沙汰される環境問題など、ずっと続く問題もあります。
━━弁護士として、どういうゼミを目指したいのですか
他大学だと、弁護士がゼミを開いて1年生の時から法律の勉強を教えていることが割とありました。ただ、自分が弁護士をしている実感からして、それはどうなのかと思ったのです。
駒場にいる時期に、世の中や社会の状況、現実がどうなっているかを少しでも多く知ること。これが将来法律家になる上でも、他の分野に進む上でも共通の基礎になるのだと私自身弁護士になってから実感しました。弁護士になってから、やっぱり自分は世間知らずだなと思って勉強することも多くあるのです。
それでゼミではフィールドワークを重視しました。その中でも特に印象に残っていることがあります。ゼミの初めの頃に、新聞の印刷工場の労働者が輪転機の前で倒れて亡くなった事件を弁護士としても担当していました。そこで、この印刷工場にお願いして、フィールド
ワークをさせてもらいました。どういう労働環境で、どういうところに無理があったのか見学しました。今でも当時のメンバーは、あのフィールドワークはとても勉強になったと言っています。
他にも1年目から自分や友人が担当している事件などから学生に勉強の機会を与えるということをやってきました。これこそが、大学の研究者ではなく弁護士がゼミをやることの意味だと思います。全体で見れば弁護士会は社会のあらゆる問題をカバーしているんですよね。しかも弁護士会は学生の勉強のためといえば喜んで協力してくれます。そういう意味では、弁護士は大学の教育活動に協力するのに適した職業かもしれません。
━━ゼミを通して学生に伝えたいことは
何か正解を得るために現場に行くわけではないのです。現場に行ったり現場にいる人の話を聞いたりすると、自分が当初考えていなかったもの、想定していなかったものを感じ取ることができるんですよ。自分の頭で自主的に考えることはとても重要だけれど、できる限り現場に足を運んで、現場に接して悩みながら思考を発展させることを大事にしてほしいということを学生に伝えています。
何かを勉強しようと思っても、特に今はスマホで検索すれば瞬時に答えが出てくるじゃないですか。レポートを書くことだって、AI を使えば短時間で効率的にできます。でもそれって私から見ると怖いのです。自分で仮説を立てた上で、そこからは現場で学ぶということ。効率は悪いかもしれないけど、これは効率の問題ではなく、根本的な問題だと思っているので、心掛けてほしいです。
━━ゼミを始めた頃の学生と今の学生の違いは
ゼミが始まった1990 年代の学生と今の学生を比べると、90 年代の学生たちにはまだ時間的にも、精神的にもゆとりがあったと思います。今だと、東大では1限が8時30 分と朝早くから始まって、5限が午後6時35分と遅くに終わりますよね。大学の同級生にこのことを話すと、信じられないと言われます。「そんな遅い時間まで授業に出るやつがいるの」なんて言われました(笑)。多くの人は1日に授業を三つほど取りますし、それぞれの授業に予習と復習も必要なわけで、ゆとりは全然ないですよね。
これは当たり前ではなくて、私たちの時はもちろん、1990 年代と比べても全然違います。よくいえば大学側がカリキュラムを充実させたり、授業時間を伸ばしたりさせて授業を充実させているといえます。ただ、サークル活動や自分で勉強したいことを自主ゼミなどで勉強すること、あるいはアルバイトみたいな授業以外に学生時代に経験しておくべきことをすることが困難になっているように思えるのです。そういう意味では、学生にゆとりがなくなってきたのは今の時間割になった2015 年からのように思えます。
特に新入生はゆとりを持って駒場での2年間を過ごしてほしいと思います。新入生は受験生活の延長として駒場時代を過ごしてしまうことがあり得るのですよ。ただ、私は、受験生活から完全に抜け出た世界で生きてほしいと思います。受験生時代は入試に合格しなければいけないから仕方ないとして、その先をどうするか。国家公務員や法曹になることを将来考えている人に対し、予備校が1年生の時から試験対策をすればいいと宣伝をしています。受験生活の延長で過ごしてしまうと、予備校に通った上で授業もたくさんとって、しかも授業でも多く「優」を取ろうと頑張ってしまうわけです。でもこういった生活を送っていると、人生のどこかでつまずいてしまうのです。進学選択で人気の高い学科に行きたい人もいると思いますが、受験生活の延長にならないように授業を自主的に活用することを意識して勉強してほしいです。
━━ゼミで特に印象に残っていることは
ゲスト講義で社会問題の被害者の方に来ていただくことが多いですが、ここで印象に残っていることは多いです。例えば、広島の被爆者の方に来ていただいた時のことですが、その方は駒場東大前駅についてすぐ具合が悪くなってしまわれました。それで大学の保健室でしばらく横になってもらったのです。でも、授業の時間が近づき、どうするか聞いたところ、起き上がって「話します。学生さんに話したいです」とおっしゃってくださったのです。一次被爆をされた方で、とても苦しかったのでしょうが、自身の被爆体験をお話されたのです。
━━東大生に必要な意識とは
社会問題の被害者の方の中で、将来重要な地位につくであろう東大生に話をしたいと思っている方は多いです。その方たちが、東大生に期待するものは東大生が想像する以上にあるのですよ。東大生には、その期待に応えるという意識を持って欲しいです。
一方で将来、収入の多い富裕層になりたいという思いを抱く東大生もいると思います。もちろんお金を稼ぐのは自由だし、楽しいことかもしれないけれど、東大に大量の税金が投入されていることを考えてほしいなとも思います。授業料が値上げされるとはいえ、地方国立大学に比べ、東大には全国でもダントツの税金が投入されています。そう言ったお金が元手になっていることもあり国民から大きな期待を受けているわけです。この期待にどう応えるかということを、東大生には考えてほしいと思いますし、東京大学新聞社でも頑張ってほしいです(笑)。
最近、言い過ぎかもしれないけど東大生がアイドル化していると感じます。東大というブランドが学問を極める上で、例えば留学しやすくなると言ったふうに有利になるのは結構だと思うのです。ただ、例えばバラエティー番組で東大生がもてはやされるのを見ると、それは関係ないのではと思ってしまいます。このイメージはメディアが作り出したものかもしれませんが、東大生がこのイメージに乗っかっている部分もあると思います。世の中のためとか、科学の発展のために頑張っている東大生がテレビ番組に登場するのは意味があることだとは思いますが、残念ながらそういうことはほとんどないのです。今、世間で東大生が商品化されているのを見ると、東大生にとってよくない環境であると感じます。
━━新入生へのメッセージを
先ほども言いましたが、新入生には駒場での2年間で精神的にも時間的にもゆとりを持った学生生活を送ってほしいです。そして新入生の保護者の方にも、お子さんの自由な選択を尊重してほしいですね。