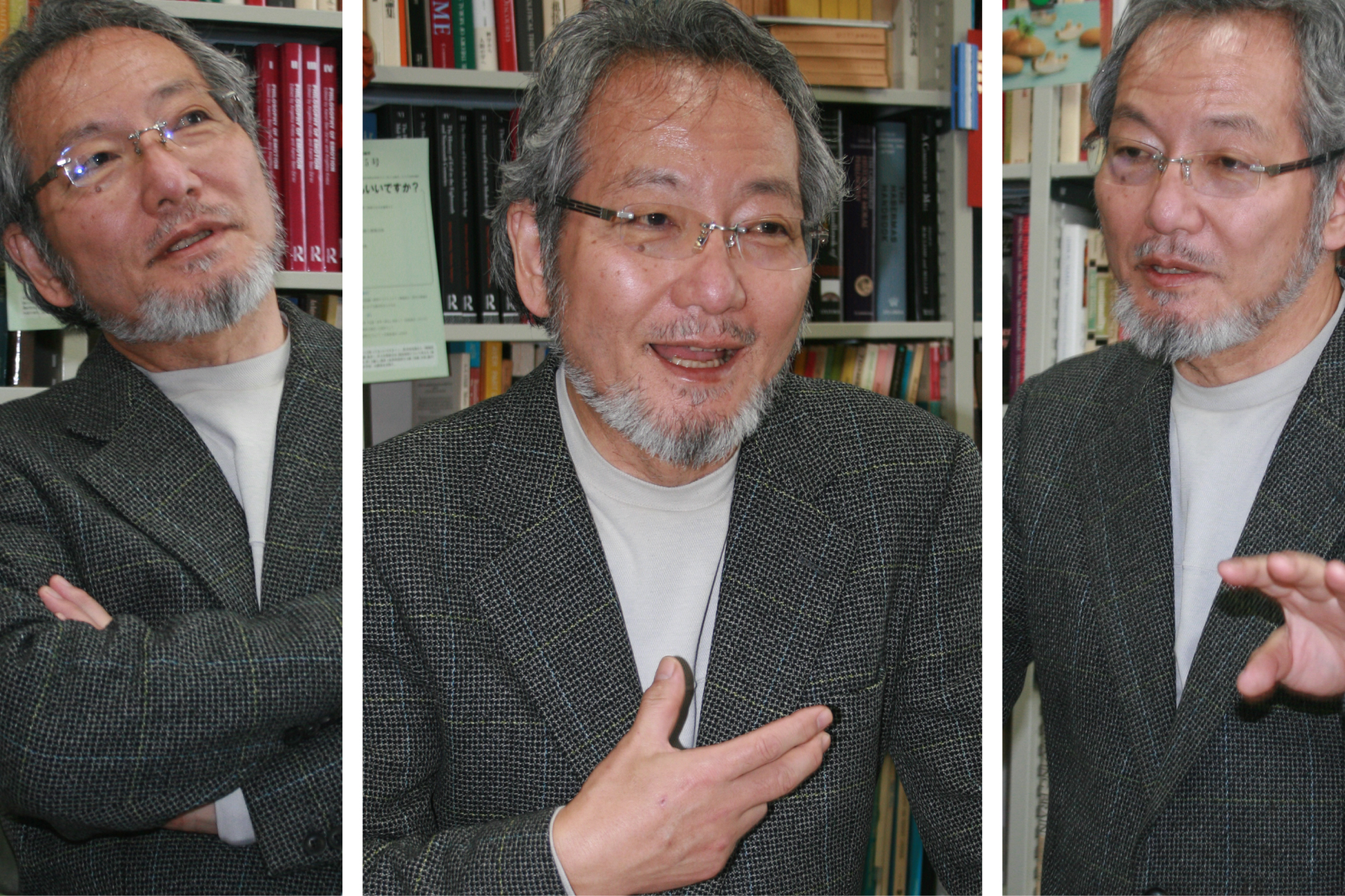東大で30年近く法哲学研究に携わり、正義論から憲法改正論まで幅広く独自の議論を展開してきた井上達夫教授のロングインタビューを2回に分けてお届けする。前編では、今年度で東大を退職される井上教授に、自身の研究理念や哲学観、学生へのメッセージなどについて聞いた。
(取材・円光門、撮影・山口岳大)
後編はこちら

77年法学部卒業。東大助手、千葉大学助教授などを経て91年に東京大学助教授に転任、95年より現職。近著に『立憲主義という企て』(東京大学出版会)、『生ける世界の法と哲学――ある反時代的精神の履歴書』(信山社)など。
――2020年に出版された『生ける世界の法と哲学――ある反時代的精神の履歴書』では小学生時代に自身が体験した貧困や家庭崩壊についての記述があります。この体験は先生の法哲学研究にどのような影響を与えましたか
私が東大に入学した当時はまだ授業料が年間で3万6千円だったが、にもかかわらず親の平均年収は「お坊ちゃま、お嬢ちゃまが行く」と言われた慶應のそれよりも高かった。私の周りにはそういう恵まれた層がいたので、私はある意味でユニークな存在だったと思う。
このことが自分の思想形成にどう影響したかというと、左右を問わず戦後日本の政治家・国民・知識人が惑溺している欺瞞に敏感になったね。特に、昔の「進歩的文化人」とか、今の「自称リベラル派」など、きれい事を言う人たちの欺瞞が鼻もちならなかった。自分たちは安全地帯にいて既得権を享受しておきながら、そのコストを相対的に恵まれない層に転嫁して平然としている。このような欺瞞を私はずっと具体的な事例に即して批判してきた。
――具体的な事例とは
憲法9条問題について言えば、長年私が著作やメディア上の言論活動で指摘してきたように、保守派だけでなく護憲派も憲法を蹂躙している。彼らはこの欺瞞の付けを、米軍基地が集中する沖縄や、危険な任務を負いながら日蔭者扱いされる自衛隊員に押し付けている。
自衛隊員になる人の多くは、決して裕福でない家庭の出身者だ。高卒が多く、防衛大学校生も給与がある。陸上自衛隊高等工科学校では中卒者が給費をもらって高校教育を受けられる。
私は少年時代に貧困と家庭崩壊を経験したが、今では考えられない幸運な事情で東大に入り、研究者にもなれた。しかし、もし大学に行けなかったら、自衛隊員になっていた可能性もある。給料がもらえるし、通信技能や飛行士技能など専門技能を身に付けられるからね。
「原理主義的護憲派」と私が呼ぶ勢力は、自衛隊を違憲だとしながら政治的に受容し、「修正主義的護憲派」と呼ぶ勢力は、自衛隊は戦力でないから合憲と言う詭弁を弄し、いずれも、いざ日本が侵略されたら命を懸けて国民を守れと自衛隊に言う。戦力を否定する憲法を擁護しているふりをしながら、世界有数の武装組織たる自衛隊の防衛力にちゃっかり寄生している。
こういうのを「頭は左、財布は右」と言うんだ。自衛隊を日蔭者扱いしながら、実際には防衛戦力として利用して平然としている彼らは、自分や自分の子が自衛隊員になるのを想像できない恵まれた層の人が大半だ。こういう人たちの欺瞞に対して私が敏感になったのは、何よりも知的誠実性を最重視する私の思想によるが、その背景には私の出自の影響もあると思う。
――今の学生を見て思うことは
入学前も入学後も、私たちの時代ほど、勉強していないようだ。受験産業が高度化した結果、「試験に受かるための効率的な学習」が主流となり、教養の裾野が狭くなった。東大生でも、親が高い教育投資の能力と意欲を持ち、小さい時から、塾等で効率的学習に慣らされてきたため、自立的思考力を磨かないまま受験技能だけで東大に合格した者が増えてきている。それで入った後、授業に付いていけなくなる。高校時代までは天才だ、大秀才だと言われていた者が、東大に入るとただの人、時には劣等生になる。そういう現実と自己イメージとのギャップが受け入れられなくて、メンタルな問題を抱える学生、さらには不幸にも自殺してしまう学生も増えてきた。私の属する法学部でも、学部専用の学習相談室というのが設けられているが、学習相談に加えメンタルな悩みの相談がその重要な役割だ。それは全学レベルの学生サポート施設だけだと対応が追いつかないからだ。
――学生には何を求めますか
今の学生は政治や社会の問題を議論したがらないと聞く。いきなりそんな話をするのは恥ずかしいと思うのであれば、せめて読書会を議論の場として作ってほしい。私が学生だった頃は、知的虚栄心というか、少なくてもこれは読んでいないと恥ずかしいよねという本のリストがあった。そういう意識が今は少なくなってきていて、それでも良いと私は思うが、自分の身の丈に完全に合わせてしまうと成長はなくなる。分かりやすいものばかりに目を向けるのではなく、難しいけど忍耐強く論理を追えば分かるというレベルの本を、自分一人だとくじけそうになるかもしれないから仲間と一緒に読んでいくというのが良いんじゃないかな。一冊の本を1、2カ月かけてじっくり読むことは、見えざる著者と持続的な対話をすることでもある。その過程でいろいろなことを考える力が身に付くんだよね。
――先生が最も影響を受けた思想は
私は傲慢な人間で、誰か特定の哲学者や思想家を権威として崇めることはしない。ただ、法哲学を専攻すると決めた大学4年生のときに、恩師、碧海純一先生の勧めでカール・ポパーの『開かれた社会とその敵』(Open Society and Its Enemies)を原書で読んで、プラトン、アリストテレス、ヘーゲルなど、それまで哲学史の中で権威とされてきた哲学者の言説を徹底的に批判する彼の議論に、目を開かれた思いがした。私の基本的な立場は今でもポパーの可謬主義に由来する。すなわち、いかなる主体も自身の信念の不可謬性を主張できず、当たっていたとしてもせいぜい真理の一面にすぎないとする立場だ。
この立場を取るためには、自らの信念を超えたある客観的な真理の想定が必要だ。それに照らしてこそ、おのおのの信念が誤っているとか部分的にすぎないとか言えるのだから。客観的真理を否定する相対主義者は、他者の信念が誤っているという主張を放棄するのと同じ理由で、自己の信念が誤っているとする他者の批判を無意味とみなす。この点で、独断的絶対主義者と同じ穴のムジナだ。こう言うと、相対主義は独断的絶対主義を否定するものだと反発する人も多いだろう。
そういう人たちに私が言っているのは、「自己の信念を相対化すること」と「自己の信念に相対化すること」を区別せよ、ということだ。「を」と「に」という助詞の違いだけだが、哲学的に決定な相違がここにはある。可謬主義は「自己の信念を相対化すること」を求め、そのためにこそ自己の信念を超えた、誰もそれを確知したと標榜できない客観的真理の理念を、相互批判的討議の規制理念として想定するのに対し、相対主義は客観的真理を否定し、真理を「自己の信念に相対化すること」により、自己の信念を真理の最終審級として絶対化してしまうのである。
「客観的な真理」というと、ポストモダンの脱構築派は「支配的通念を上から押し付けている」と条件反射的に反発してきたが、それは客観主義と絶対主義を混同している結果だ。特定の信念を絶対化するという絶対主義を排除するためにこそ、いかなる主体の信念も超えたという意味での客観的な真理や正義が想定されねばならない。そうすることで初めて我々の信念の可謬性、有限性が自覚され、だからこそ自分と違った立場の人との間の相互批判的な討議を引き受け続けようという発想が生まれる。もっとも、ポストモダンの指導者のデリダは「法は脱構築可能だが正義は脱構築不能だ」と認め、実定法を相対化するためにこそ、それに対する批判的討議の規制理念として正義理念が不可欠性であることを承認した。この発想は権威的信念に対する批判的討議の規制理念としての客観的真理の想定につながる可能性はある。
――東大生へのメッセージをお願いします
他者の言説を評論家的に批判して済まして「賢がる」のは止めなさいと言いたい。どんな主張だって可謬的だし、弱点はある。その粗探しをして鬼の首を取った気になるなと。真の批判は単なる否定ではなく積極的な営為だ。批判者は、より良き代替的な説だと自ら信じる立場を提示し、反論に応え、擁護できなければ自説を修正する責任を引き受けないといけない。
そのためには、他人のふんどしで相撲を取るのではなく、自分の頭で考えることが必要不可欠だ。「カントにおける自由の概念」だとか「ヘーゲルにおける歴史の概念」だとか、私はそういった類いのいわゆる「哲学学」をあまり評価していない。特定の哲学者・思想家の作品を権威的テクストに祭り上げ、「虎の威を借りる」ごとく、そのテクストの解釈と称して自分の主張をこっそり忍ばせる者がままいるが、これは感心しない。
もしカントを持ち出すとするなら、「汝自身の悟性を使用する勇気を持て」という彼の啓蒙観を実践することだろう。自分の名前で自分の主張を展開する勇気を持て。もちろんその過程で考えが独り善がりにならないために、直接会えない他者の議論を読書を通じて学んだり、友人数人で相互批判的な討議をしたりすることはとても重要だ。
自分を匿名化して他人を叩く欲望が炎上するネット社会だからこそ、叩かれるのを恐れず自分の意見をはっきり言い、正々堂々とフェアな議論ができる人間になってほしい。
――自身の最大の研究成果は何だと考えますか
自分としては、「全部」と答えたいところだね。私の法哲学研究全体の基礎をなし、最大の特徴になっているのは、正義概念論を深化発展させたこと。国際政治学会(International Political Science Association)が出した百科事典International Encyclopedia of Political Scienceの中のJusticeという大項目は私が書いた。
これまで正義論というと、ある行動や制度が正義に合致するかどうか判定するための具体的な判定基準を示す正義構想論が主だった。功利主義、リバタリアニズム、平等基底的権利論などのうち、どれが正義構想として最良かという議論ばかりされていた。だが私は、対立競合する正義の諸構想に通底する制約理念としての正義概念こそが基盤的重要性を持つと論じた。
――正義の諸構想に通底する正義概念とは
正義概念の根幹は「普遍化不可能な差別の排除」だ。これは、フリーライダー排除、二重基準排除、権利(rights)と区別された既得権益(vested interests)の排除、集団的エゴイズムの排除などを含意するが、さらに一般的な含意として、反転可能性(reversibility)を要請する。反転可能性要請とは、自己の他者に対する要求が、もし自己が他者ならばという反実仮想的な条件の下でも、その他者もまた同じ自他反転テストを自己に課す限り拒絶できない理由により正当化可能か否かを、自己批判的に吟味せよ、という要請だ。これは、自己と他者が置かれている環境的状況の反転を求める位置反転可能性(positional reversibility)要請だけでなく、自己と他者の視点の反転を求める視点反転可能性(perspectival reversibility)要請をも含意する。
この正義概念は法概念論の再構築の指針になる。何が正しい法か、法の「正当性(rightness)」をめぐっては先鋭な対立が存在する。これは法の正当性評価基準になる正義構想の対立に根差す。しかし、人々が、自分が正当とみなす法にだけ従えばいいという態度をとるなら、政治社会は自然状態に回帰する。法の正当性、正義構想をめぐって先鋭な対立が持続する社会において、法が公共的秩序として存立し得るためには、現行法規を不当、誤っているとみなす者も、自分たちの社会の公共的決定の産物として尊重することが可能でなければならない。公共的秩序としての法のこの規範的権威は、法の正当性とは次元が異なり、法の「正統性(legitimacy)」と呼ぶべきもの。悪法も法かという法概念論の根本問題は、法の認識と評価の区別などではなく、法の「正当性」と区別された法の「正統性」の根拠と条件を問うものとして再定位されなければならない。この法の「正統性」の指針となるのが、対立競合する正義の諸構想に対する共通制約原理としての正義概念だ。
法が正当性と区別された正統性を持つためには、法を産出する政治的決定に至るまでの政治的競争の敗者、つまり法の正当性を否認する者たちが、新たな政治的競争のラウンドで当該決定が変更されるまではそれを尊重できるような、フェアな政治的競争のルールに従って政治的決定がなされなければならない。そのようなルールこそが法の支配であり、法の支配を憲法に具体化したのが立憲主義だ。先に述べたような規範的含意を持つ正義概念が、法の「正統性」条件として法の支配と立憲主義を再定位するための指針となる。
私はこのような議論を旧著『法という企て』と新著『立憲主義と言う企て』で展開したが、正義概念論を深化発展させて、それに基づき、伝統的な自然法論と法実証主義の二項対立を超えて、法概念論、法の支配論、立憲主義論を再編したのは、世界広しと言えども私しかいない。このことが法哲学に対する私の最も独創的な貢献だと思っている。
――自身の研究にとって重要な価値は正義だけですか
私の最初の著書『共生の作法』で、正義は大切な何か(something)であるが、すべて(everything)ではない、正義が排除する普遍化不可能な差別をむしろ要請する重要な価値もあるとはっきり言っている。例えば、愛とかね。子どもが「ママはぼくを愛してる?」と聞いて、母親が「もちろんよ、他の子どもたちとまったく同等にあなたを愛しているわ」と答えたら、子どもは「ママはみんなに公平だけどぼくを愛していないね」と思うだろう。私の子だからあなたを愛するという、普遍化不可能な差別を基盤にした価値もあるわけで、正義だけが人間世界を取り仕切っている価値ではない。だが法の内在的理念は正義であり、少なくとも法が律する空間は正義を基盤にしなければならない。正義が優越する領域と、個体的同一性に立脚する価値の生息領域とをどのように仕分けして両立させるのか、という法の限界、正義の限界の問題も考察する必要がある。このような発想が私の研究のもう一つのユニークな点だと思う。
――自身の研究が学界だけでなく社会に影響を与えたと思うことはありますか
一番論争的なのは憲法9条削除論だね。立憲主義とは、立法の「正当性」をめぐる抗争(立法闘争)だけでなく、憲法の「正当性」をめぐる抗争(憲法闘争)をも、「正統性」をもって裁断するための公正な政治的競争のルールを保障する原理だという私の基本的な立場に、9条削除論も立脚している。その点についての詳細は拙著『立憲主義という企て』第4章を参照してほしい。
私の9条削除論の原型的議論を初めて活字にしたのは、実は、東大新聞だよ。今から30年近く前、1993年4月13日の東大新聞に出た「憲法の現実--誰が『貢献』するのか、責任負担を民主化せよ」という論評。これは私の最近著『生ける世界の法と哲学--ある反時代的精神の履歴書』に再録している。論壇で本格的にこの主張を展開し始めたのは2005年以降。最初は「何言ってるんだ、こいつ」と思われていたが、だんだんと真面目に受け止められてきた。少なくとも、9条が戦力を縛っているという護憲派の主張は嘘だということがだいぶ理解されてきた。メディア上でも、9条があるがために、日本は戦力を縛るどころか最低限必要な戦力統制規範すら持てないのだという考えが広まってきたように思う。
――9条削除論とは
9条を削除して、安全保障政策は民主的立法過程での不断の討議に委ねると同時に、戦力統制規範を憲法でしっかり規定せよという主張だ。安全保障政策とは、非武装中立か武装中立か、個別的自衛権か集団的自衛権か、敵味方をグループ分けする集団的自衛権に代えて敵味方を包摂する集団的安全保障体制か、というような問題に関する方針選択だ。これに対し、戦力統制規範というのは、どのような安全保障政策をとるにせよ、戦力が恣意的に濫用されないように、戦力の編成と行使の決定権の所在と決定手続を明確に限定する規定。戦力に対する文民統制(シビリアンコントロール)や戦力行使の国会事前承認手続などは、そのミニマムな例だ。
憲法9条は、いまや護憲派も守る気のない非武装中立政策を定めることにより、安全保障政策についての実質的討議が棚上げされて、詭弁的な憲法訓詁学による解釈改憲に右も左も耽る状況を跋扈させている。安倍政権は解釈改憲で集団的自衛権を解禁したが、個別的自衛権・専守防衛の枠内なら自衛隊・日米安保は合憲だとする「修正主義的護憲派」もあからさまな解釈改憲をやっているし、自衛隊・安保は違憲だけどこの枠内なら政治的にOKだから違憲のまま存続させろという「原理主義的護憲派」は、違憲状態の固定化を提唱している。これで「護憲」とは笑止千万。
護憲派の若手とみなされている木村草太に至っては、9条が自衛隊・安保を禁止していることを認めながら、そんなの関係ない、「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」を保障した憲法13条で専守防衛の戦力を保有行使できるから9条改正無用だ、などという暴言を吐いている。13条は戦力に一切触れていない人権規定。人権規定の勝手な拡大解釈で、9条が明示的に禁止している軍事力を解禁するのは、9条の死文化に最後の止めを刺すもの。しかも、この13条代用論は、従来の護憲派が曲がりなりにも拘ってきた自衛隊に対する9条の封印、つまり原理主義的護憲派の「違憲の烙印」も修正主義的護憲派の「戦力ではない」という封印もあっさり破っている。本来なら従来の護憲派が彼を叩かなければならないのに、9条改正無用という結論さえ出してくれればOKと、9条を完全に死文化した木村を自分たちの新しい仲間として歓迎している。
さらに、より根本的な問題だが、9条があるために、日本国憲法は戦力統制規範を定めることができない。9条により憲法上、戦力が存在し得ないのに、戦力を統制する規範を憲法が定めるのは自己矛盾になるからだ。憲法66条2項は「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない」と定め「文民条項」と呼ばれているが、これは文民統制規定ではない。文民統制規定になるためには、「軍隊の最高指揮命令権は文民である内閣総理大臣に属する」と定めなければならないが、9条で軍隊は存在しないことになっている以上、こんな規定は置けるはずがない。まして、戦力行使に対する国会の事前承認を要請する規定も憲法で定められない。9条があるために、ミニマムな戦力統制規範すら憲法は定められない。
9条が戦力を縛っているという護憲派の主張はまったくの嘘。9条があるために、戦力が憲法の外部で、憲法的統制が出来ない形で、肥大化している。この状況を温存することに護憲派も加担している。
護憲派も存在を受容している自衛隊は世界有数の武装組織だ。自衛隊は海外派遣されているだけでなく、いまや東アフリカのジブチに常駐基地まで持っている。ジブチに自衛隊常駐基地が設置されたのは、護憲派勢力も含む立憲民主党の前身の民主党が政権をとっていた時だよ。こうやって戦力の現実を肥大化させながら、9条を改廃して戦力統制規範を憲法に盛り込む憲法改正を行うことを彼ら護憲派は頑なに拒否し続けている。彼らが「護憲派」を名乗るのはもはや詐称で、彼らの実態は「憲法破壊勢力」だ。
9条削除論に対して、戦力に対する憲法の縛りをなくすものだと批判する者がいるが、これはまったく的外れ。戦力に対する憲法的統制を不可能にする9条を削除して、最大限の戦力統制規範を憲法に盛り込む憲法改正をするのが9条削除論の狙いだ。拙著『立憲主義という企て』の第4章で、私の憲法改正案を具体的な条文の形で提示している。これを見れば、いかなる戦力統制規範を憲法で明定することが必要か、それを全く欠いた今の憲法を保持したまま、自衛隊・日米安保という巨大な戦力の現実を容認している現状がいかに危険かが分かるはずだ。
戦力は国家暴力装置の最も危険な要素。それに対する憲法的統制を欠いた日本は立憲国家の名に値しない。この現状を固持する「護憲派」は立憲主義の擁護者どころか、その破壊者だ。
――自衛隊は軍隊だと考えてよいのでしょうか
自衛隊の予算規模は世界4位ないし5位で、軍事的実力についての国際ランキングでは韓国と7位の座を争っている。その上にいるのは常任理事国とインドという核保有国だけ。つまり自衛隊は非核保有国の中で世界最強の軍隊だ。これに加えて世界最強の軍隊である米国を国内に駐留させ、一緒に軍事演習をしている。これが軍隊でないなんて、国際社会では通用しない戯言だ。だからこそ、日本政府も採用している自衛隊の公式英訳は”self-defense force”になっている。憲法9条2項の公式英訳で、”land, sea, and air forces, as well as other war potential”は保有しないと言っているにもかかわらずだ。
こんな戯言を日本で通用させるための詭弁が、いわゆる「ポジティヴリスト」論だ。自衛隊はポジティヴリストに縛られているから軍隊でないと歴代政権や修正主義的護憲派は主張してきた。ポジティヴリストというのは、明示的に許可された場合しか武器行使できないというルール。警察はポジティヴリストで規制されている。これに対し、軍隊は、ネガティヴリスト、つまり、明示的に禁止された場合以外は武力行使してよいというルールで規制されている。戦時国際法、今で言う国際人道法の交戦法規、そしてそれを自国軍に適用するための国内法体系がこのネガティヴリスト規制になる。民間人に対する無差別攻撃の禁止、捕虜に対する虐待の禁止、中立国攻撃の禁止などがこの規制の中心。自衛隊は軍隊でないと言う連中は、自衛隊はポジティヴリストで縛られているから警察力であって、軍隊でないと主張している。しかし、それは大きな嘘だ。
自衛隊法を見ると、治安出動時の武器行使を規定する89条と90条、防衛出動時の武力行使を規定する88条というように分かれている。治安出動は、国内での暴動などに際して警察力を補完するために行われるから、まさに警察行動であり、ポジティヴリストで武器行使できる場合が限定されている。しかし、防衛出動の場合には、88条1項で、「わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる」と、一般的に武力行使が授権され、同条2項で、「前項の武力行使に際しては、国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする」と武力行使に対する制約条件を定めるネガティヴリスト規制になっている。「国際の法規及び慣例」が、交戦法規を指すわけだ。自衛隊法上、自衛隊は防衛出動する場合、通常の軍隊として行動することになる。
しかし、ここで憲法9条の問題があらわになる。9条は「国の交戦権はこれを認めない」と規定しているから、自衛隊は交戦行動をしない建前になっているので、防衛出動の際の自衛隊の武力行使を国際交戦法規に従って統制する国内法体系が日本には欠損しているのだ。
要するに、自衛隊が防衛出動した際、民間人を誤射して国際交戦法規に違反した自衛隊員を処罰する国内法体系がないのだ。普通の刑法で裁けると主張する者がいるが、それも間違っている。刑法35条には「法令又は正当な業務による行為は、罰しない」と書いてあり、防衛出動命令を受けた自衛隊の武力行使は「法令による行為」だ。刑法が不可罰化していても、交戦法規違反の武力行使は罰するというのであれば、まさに、交戦法規違反の武力行使を罰する特別の軍事刑法が必要だ。
そもそも、一般刑法は人間の殺傷の禁止を原則にして、それが免責または不可罰化される例外的条件を限定している。これに対し、政府の防衛出動命令に従って武力行使する自衛隊は、防衛のため人間に対する殺傷行為を一般的に許可され、さらに義務付けられてさえおり、この一般的授権を交戦法規によって例外的に制限されている。一般刑法的統制と交戦法規的統制は根本的建前が違っているから、防衛出動命令に従った自衛隊の武力行使について、自衛隊員個人を刑法で裁くのは、範疇錯誤と言ってよい。
だからこそ、軍事力を保有するどの国も、一般市民を裁く一般刑法とは別に、軍隊の武力行使を裁く軍事刑法と軍事司法システムを国内法で整備している。日本は、憲法9条があるために、このような軍事刑法・軍事司法システムが欠損しており、欠損せざるを得ない。自衛隊法の罰則規定は、任務懈怠や業者との癒着などを罰するもので、一般公務員の職務規律違反罰則規定と本質的に変わらない。交戦法規違反の自衛隊員の交戦行動を罰する軍事刑法的規定は含まないし、含み得ない。軍事司法システムの欠損については、特別裁判所を禁止した憲法76条2項の制約もあるが、根本的原因は9条だ。9条により、交戦行動が存在しない建前になっているため交戦法規違反の武力行使を裁く国内法体系が存在し得ない以上、そのような法体系を適用する特別の軍事裁判所も存在する余地がない。
自衛隊は「法的統制でがんじがらめに縛られているから、使えない軍隊だ」と思っている者がいまだに多いが、これは根本的に誤っている。事態はまったく逆だ。自衛隊法により、自衛隊は防衛出動命令が下されれば、防衛のために武力行使できる。しかし、憲法9条により、交戦法規違反の武力行使に対する国内法的統制が欠損しているため、危な過ぎて政府は防衛出動命令が出せないのだ。要するに、自衛隊は「使えるにもかかわらず、使った場合の法的統制がないため、危なくて使わないことにしている軍隊」である。
しかし「危ないから使わないことにしている軍隊」も、使わざるを得ない非常事態、すなわち防衛出動命令を下さざるを得ない事態は生じ得る。その場合、自衛隊は、交戦法規違反に対する国内法的統制を欠いたまま武力行使する軍隊、すなわち「無法の軍隊」になる。こんな事態を放置し続けることに、歴代政権のみならず護憲派も加担してきた。これは日本の立憲主義を掘り崩しているだけでなく、国際社会に対しても無責任極まるものだ。
――国際的にはどのような問題が考えられますか
日本人は、「憲法9条を持つ日本は平和国家だ」と妄想しているが、実際には、ベトナム戦争やイラク戦争など、米国の侵略戦争に、基地と兵站の提供で幇助犯として加担してきたことを恥じろと、私は言ってきた。さらに、交戦法規の問題について言えば、他国と戦闘状態になった場合、他国の民間人に無差別攻撃してもそれを裁く国内法体系を欠く日本という国家は、国際社会では、無法国家と見なされる。このことは国連の平和維持活動についても言える。
自衛隊が平和維持活動で多国籍軍の一部として派遣されると、多国籍軍は国連によって交戦団体と見なされているので、自衛隊も、兵站業務だけ担ったとしても、交戦団体として扱われ、常に攻撃の的となる。自衛隊は非戦闘地帯にしかいないというのは嘘で、自衛隊がいる所は全て戦闘地帯になり得るのだ。実際イラクのサマーワではすでに何回も攻撃されている。
多国籍軍は派遣先の国家と地位協定を結ぶので、治外法権を与えられる。現地住民を誤射した多国籍軍兵士は現地法では裁かれない。その代わり、日本以外の他の参加国の兵士は、自国の軍法で裁かれることになる。しかし、日本ではこれまで述べたように、自衛隊の交戦法規違反を裁く国内法体系がないため、自衛隊員は現地住民を誤射しても、現地法で裁かれないだけでなく、日本法によっても裁かれない。一般刑法で裁くのは筋違いだとさっき言ったが、海外での自衛隊の武力行使についてはこのことは特にはっきりしている。民間人誤射は過失致死傷になるが、日本の刑法は過失犯については国外適用を認めていない。
しかもジブチには自衛隊の常駐基地がある。ジブチ政府に対して日本が締結させた地位協定は、日本と米国との地位協定が日本にとって屈辱的である以上にジブチにとって屈辱的だ。日米地位協定は、米軍の「公務上」の行動に対しては日本の司法が管轄できないが、少なくとも「公務上」という縛りはある。だがジブチと日本の地位協定は、自衛隊の行為には公務内外を問わず治外法権が認められる。それにもかかわらず、日本には自衛隊の交戦法規違反行為を裁く国内法体系がない。これは無責任極まりない。国連平和維持活動に参与してきた経験に基づき自衛隊の無法状態を指摘してきた伊勢﨑賢治氏は、この日本の姿勢を「外交詐欺」と指弾している。
──立憲民主党の山尾志桜里議員が唱える立憲的改憲論も、先生の主張を基にしていると伺っています
山尾議員の立憲的改憲論は、私の9条削除論とは異なる。9条を削除するのではなく、9条を明文改正して、個別的自衛権・専守防衛の枠内で戦力の保有・行使を明示的に認めた上で、文民統制・戦力行使に対する国会承認などミニマムな戦力統制規範を盛り込むものだ。これは言論界では「護憲的改憲論」とか「新9条論」とか言われてきた立場につながる。私にとって「最善」である9条削除論とは多少異なるが、私はこれを「次善」の立場として評価している。
ただ、山尾案は条文の書き方に問題がある。9条の条文はそのままにして、9条の2などの枝番号条文を追加して、個別的自衛権・専守防衛枠内で戦力を保有し、自衛のための交戦行動ができると明記する。9条は2項も含めて形の上では残しているが、枝番号条文で、戦力の保有と行使をはっきり認めている点で、自衛隊を明記するだけで戦力として認知せず9条と自衛隊の矛盾を温存する安倍改憲案とは異なり、実質は9条2項の明文改正と同じだ。ただ、形式的には9条を残しているため、安倍改憲案との違いが明白になっていない。9条を形式的に残したのは、護憲派の反発を和らげるという戦略的考慮に基づくのだろうが、結果的には、安倍改憲案と変わらないのではないかという誤解を受け、護憲派の支持を得られないだけでなく、9条明文改正論者からも批判されている。
条文の書き方の問題はあるが、実質論としては、山尾議員の立憲的改憲論は、護憲派も政治的に受容している個別的自衛権・専守防衛の枠内での戦力の保有・行使を憲法上も明確にした上で、ミニマムな憲法統制規範を憲法に盛り込む正規の憲法改正を遂行して立憲主義の筋を通そうとするもので、いま政界で提唱されている憲法改正論の中では、最もまともなものだ。残念ながら立憲民主党の方針としては採択されていない。立憲民主党には未だに昔の欺瞞的なリベラル派議員がたくさんいるからだ。(インタビュー後の事実の補記:新型コロナウイルス対策に関する新特措法問題を直接の契機にして、山尾議員は立憲民主党に離党表明した。)
――先生は徴兵制の導入も主張しています
徴兵制というと、軍国主義を連想する者が多いが、それは間違いだ。私はこれを最大限の戦力統制規範として提唱している。徴兵制は、いざ戦闘状態になったら、血を流すのは自分たちだと国民に自覚させ、無責任な交戦感情に駆られるのを防ぐ。専制国家における徴兵制は最悪だが、民主国家における志願兵制も最悪だ。貧しい層だけ戦場に送って、中流階級のマジョリティーは安全地帯に置いておくのだから。兵役を恵まれない層だけに押し付けるのではなく、徴兵制にして、国民多数者のみならず、政治家や軍事産業経営者とその子たちにも、戦場に送られる負担を共有させる必要がある。
もちろん、良心的兵役拒否権は憲法で保障すべきだ。しかし、良心的拒否権を、自らを安全地帯に置きながら兵役につく同胞に守ってもらおうとする非良心的・利己的動機で濫用するのを防ぐために、兵役拒否者には、非武装看護兵・消防隊員など、自らも生命リスクを負う厳しい代替役務を課す必要がある。
──退職後はどのような研究を予定していますか
長年棚上げしてきた学術書の刊行が当面の課題。『国家学会雑誌』に連載した私の助手論文「規範と法命題」を補論を付して単著化することが一つ。これはメタ倫理学的・メタ規範理論的研究で極めて専門的・純理論的な仕事。もう一つは、もっと実践的・政治的な含意を持つ研究で、より広い読者を想定した仕事だが、これまでいろいろな著作で私の民主主義論として触れてきた「批判的民主主義」を主題にした単著を出そうと思う。民主主義は衆愚政治を生むと言われるけど、そういう愚民観を振り回して民主主義をばかにしているエリートの連中こそが愚劣で、危機管理能力を持たないことが嫌というほど何回も示されてきた。
国民も愚かだが、エリートも愚か。国民が愚かだから民主主義はだめと言うのは全く逆で、そう言ってるエリート、エリート気取りの連中も含めて、みんな愚かだからこそ、自分たちがやった手痛い失敗から学んで試行錯誤的に成長するプロセスとして民主主義が必要不可欠だというのが、批判的民主主義の思想だ。
これまで国民は、軍事力を含め、自分たちの権力を自分たちの手で主体的に統制する責任を引き受けようとしてこなかった。国民に統治の主体としての自覚を持たせるためには、権力を振るだけでなく責任も負わせなければいけない。失敗から学習し、失政を修正していく責任が自分たちにあるのだと。
――危機管理能力を持たないとはどういうことですか
安全保障問題については、日本は攻められるはずがないとか、攻められても米国が守ってくれるはずだとか。原発事故問題については、想定を超えた事故は福島で起こるはずがないとか。そして今回の新型コロナウイルス騒動では、感染爆発が起こるはずがないとか。このように自分たちが起きてほしくないと思うことは起こらないはずだとする根拠の全くない願望思考に日本の政府、国民、メディアは浸ってしまっている。だから事前に抜本的対策を立てる必要はないと、呑気に構え、いざ事が起こってから慌てふためく。
リスク管理(risk management)と危機管理(crisis management)は同じではない。前者は、想定されるさまざまなリスクをいかに分散させるかを考える。後者は、福島原発事故のような「想定値」を超える津波による過酷事故や、新型ウイルスによるパンデミックなど、想定以上のリスクが現実化した場合に、いかに損害を最小限に抑える(damage controlする)かを考え、対処方法を事前に準備することだ。想定以上の事態の発生は想定しなくていいのではなく、むしろそのような例外事態を想定してdamage controlするのが危機管理なのに、福島原発事故が示したように、日本では、専門家や政治家・官僚も含め、エリートたちも、想定以上のことは「想定外」として想定しなくていいという態度にふけっている。
この国に、危機管理という発想がないのは、ある意味当然のことだ。自衛隊という危なっかしい戦力を法的に統制するメカニズムがないまま、日本は戦闘状態に巻き込まれるはずがないから、このままで大丈夫だと思っている国に危機管理ができるはずがない。
――日本が戦闘状態に巻き込まれる危険性が本当にあるのですか
既に巻き込まれてきたんだよ。それを一般国民だけでなく、政治家・知識人・メディアも見て見ぬふりをしている。拙著『立憲主義という企て』や『憲法の涙』、また伊勢﨑賢治氏・田原総一朗氏との共著『脱属国論』など、あちこちで、私はこの問題を指摘してきた。
既に触れたように、自衛隊は海外派兵先で何度も攻撃を受けている。イラクのサマーワでは自衛隊キャンプが攻撃されただけでなく、自衛隊の輸送車列が路上に仕掛けられた遠隔操作のロケット弾で攻撃されたが奇跡的に助かった。南スーダンでは自衛隊キャンプを挟んで政府軍と反政府軍が銃撃戦をやり、派遣されていた自衛隊員の中には家族に遺書を書いた者もいた。ところが当時の稲田防相はこれを「法的意味における戦闘ではない」などと、とぼけて済ました。
護憲派もこの点で同罪。「憲法9条のおかげで、イラクでは敵兵たちが自衛隊には攻撃しないと自制してくれた、これは9条の貯金だ」などという嘘を、恥ずかしげもなくついてきたんだから。昨年12月、アフガニスタンで医療支援をしていた医師、中村哲氏がテロリストに襲撃されて殺された。彼は立派な人で私も尊敬しているが、憲法9条があるから自分たちがアフガニスタンでも守られていると彼が主張してきたのが間違いであることを、自らの悲劇で証明した。彼より前、2016年にも、バングラデシュの首都ダッカで、国際協力機構(JICA)の関係者で現地支援していた日本人7人がテロで殺されている。
最大の問題は、これも既に触れたが、いまの日米安保条約・日米地位協定の下では、日本はベトナム戦争やイラク戦争など、米国が勝手に始めた侵略戦争に自動的に幇助犯として巻き込まれていることだ。国際人道法(戦時国際法)は中立国に対する攻撃を禁止しているが、米軍に基地と兵站を提供している日本は米軍支援国であり、中立国としての保護を剥奪されている。日本人の自己欺瞞を正すために私がよく指摘することだが、ベトナム戦争の時、もし米軍に空爆されていた北ベトナムの指導者ホーチミンが、今の北朝鮮の金正恩のように日本を射程に置くミサイルを持っていたとしたら、在日米軍基地を含む日本にミサイル攻撃したとしても、これは国際法上、正当な自衛権行使と見なされただろう。
今は日本を意図的に侵略する国があるはずがない、と思っている人たちに言っておきたいのだが、軍事衝突は、国家の意図的決断としての侵略によらなくても、偶発的事故や誤解・誤認、またはテロリストや好戦的軍人など一握りの「跳ね上がり分子(splinter)」の妄動などで起こることが少なくない。これは現在の日本にとっても「今そこにある危険」だ。
ごく最近も、日本を巻き込む危険な事件があった。もう忘れている人がいるが、2018年の12月、日本の排他的経済水域内で韓国の軍艦を確認した自衛隊の哨戒機が写真撮影したところ、韓国軍艦から火器管制レーダーを照射された。火器管制レーダー照射は攻撃対象に照準を合わせるためのもので、軍事的には、ロックオンと呼ばれ、攻撃の着手と見なされるので、米国やロシアの哨戒機が他国の軍艦にこんなことをやられたら即刻これを撃沈していただろうと軍事専門家は言っている。あの時、自衛隊哨戒機は韓国艦に攻撃しなかったけど、もし自衛隊哨戒機が攻撃用弾薬を装備されており、パイロットが条件反射的に行動していたとするなら、韓国軍艦との戦闘状態が発生することもあり得たわけだ。
韓国側はレーダー照射を否定しているが、説明が二転三転しており、信憑性が低い。しかし、仮に韓国側の言う通りだとしても、自衛隊哨戒機パイロットはレーダー照射を受けたと信じたわけで、これが「誤認」だとしても「誤認」に基づく戦闘が発生していた危険性があったということが深刻な問題だ。
おそらく、韓国軍艦側は「どうせ自衛隊哨戒機は反撃できないだろうから、ちょっと脅かしてやれ」と思って威嚇したというのが真相だろう。もしそうだとするなら、この事件は、単に偶発的な軍事衝突のリスクがあるというだけでなく、自衛隊を「法的統制がなくて危ないから使わないことにしている軍隊」の状態に置いている日本の現状が、かえって自衛隊に対する危険な挑発行動を誘発し、日本を戦闘状態に巻き込むリスクを高めていることを示している。
日本と韓国は政治的には対立しているが、自衛隊と韓国軍は軍事的には友軍関係にある。友軍である韓国軍との間でもこのような軍事衝突が起こるリスクがあるのだから、軍事上の「仮想敵国」と言ってよいロシアや北朝鮮、中国との間なら、このような偶発的事情による軍事衝突の蓋然性はより高くなる。
実際、昨年、2019年7月には、日本が領有権を主張している竹島の領空を、演習中と見られるロシア空軍機が侵犯し、竹島を実効支配している韓国の空軍機が360発もの警告射撃を行う事件があった。日本はロシアと韓国に抗議するだけで済ましたが、竹島領有権を本気で主張するなら、自衛隊機に警告射撃させなければならなかったはずだ。日本が実効支配している尖閣諸島の領空・領海の中国による侵犯は頻繁に起こっており、民主党政権時代は中国船の拿捕をめぐって緊張関係が高まったこともある。
要するに、偶発的トラブルが引き金になって日本が軍事衝突に巻き込まれる危険は常在している。衝突が起こったら、自衛隊は交戦行動を取らざるを得なくなる。だが前にも言ったように、それを国際交戦法規に合致した形で裁く国内法体系は存在しない。
今後も自衛隊を使わずに済むはずだというのは何の根拠もない願望思考で、こんな願望思考に浸っているこの国の在り方を変えなければいけない。そのためには9条及び安全保障に関わる諸規定の憲法改正が不可欠だ。拙著『立憲主義という企て』第4章で、私の9条削除論だけでなく、立憲的改憲論を含む代替的憲法改正論を、現状の問題点の解決・改善と言う観点から比較評価しているので、ぜひ参照していただきたい。
後編はこちら