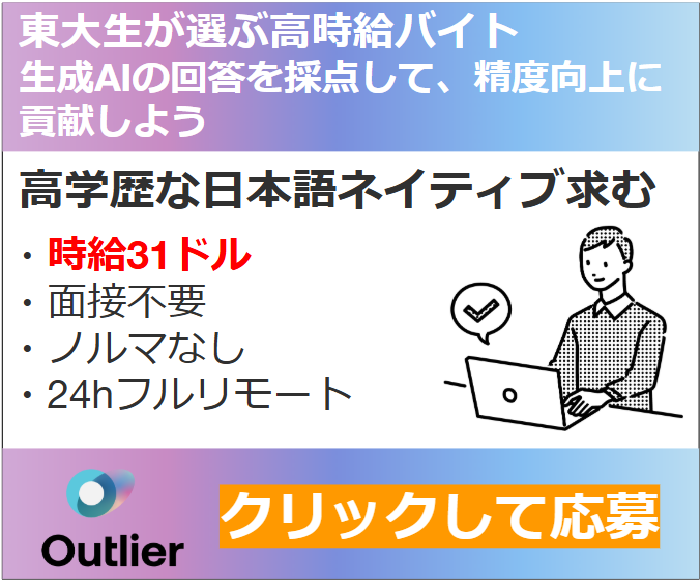本郷キャンパスの門といえば、徳川11代将軍家斉の21女溶姫が、加賀藩藩主である前田家13代斉泰の正室としてお輿入れの際に建てられた、赤門こと溶姫御殿の御守殿門が有名ですが、今回は正門を紹介します。

明治19年、大学令を受け帝国大学が本郷の地に開校しますが、当初は赤門が正門の役割を果たしていました。明治28年頃には現在の正門の位置に、木造の柵と柱、扉からなる「仮正門」が置かれます。その後キャンパス内の整備が進む一方、腐朽の進んだ仮正門があまりにみすぼらしいことから、正門の建設が計画されます。
現在の正門は明治45年、当時の東京帝国大学第8代総長濱尾新の考案のもと、建築学科教授伊東忠太の基本設計、営繕課長山口孝吉の施工管理により建設されました。
門の形式は、親柱を貫く横材(冠木)で柱を支える冠木門(かぶきもん)形式で、中央の冠木、門扉、脇門扉ともに鉄製、一方の親柱、脇柱、両脇門の楣(まぐさ・親柱と脇柱を繋ぐ横材)と笠石(親柱と脇柱の上に乗る横材)は稲田石(花崗岩)、両側の門衛所は煉瓦壁と白丁場石でできています。

冠木部分には雲文様、門扉部分は周囲に唐草文様、腰には青海波文様が施され、雲と水は天地を意味するといいます。これらの文様は、鋳鉄に比べ粘りが強い古典的な製鉄法である錬鉄で製造され、繊細な文様表現を得意としていました。エッフェル塔でも用いられている錬鉄ですが、鋼鉄の大量生産が可能となり、現在では姿を消した製鉄法です。
腐食が進んだ当初の中央門扉、冠木は昭和63年夏に取り外され、修復後、平成4年より構内で保管されています。現在の門扉、冠木はその際に、新たに設置されたアルミニウム合金製のレプリカです。当初の冠木中央には、中心に電灯を灯す赤色ガラスがはめ込まれた16葉の旭日鋳造紋章が配されていましたが、現在のものは電灯が配されていません。

門のデザインは当時赤坂にあった閑院宮邸の門を参考とし、日本における伝統的な木造建築特有の門形式を採用しましたが、材料は石、煉瓦、鉄という全く異なる半永久的な材料に置き換えています。
明治40年、議院建築(国会議事堂)の建設に際し、設計競技を行うべきか否かという議論に端を発した、「我国将来の建築様式は如何にすべきか」という建築様式に関する一大論争が、建築界で起こります。日露戦争を経て国家意識を強めていた当時、日本の建築様式はどうあるべきか、活発な議論がなされました。
そのような背景のなか、濱尾総長の「日本趣味をあらわし、武士道の精神を発揮せんとする」という意見をもとに、この正門は設計されました。
建設当初より世間から注目を集めていましたが、明治45年7月10日に図書館で行われた卒業証書授与式の天皇陛下行幸をもって開門しました。正門の高さは、正門の行幸の際の騎馬儀杖兵の槍先を考慮したためともいわれています。

建設当初は様式や材料の使い方に関して、手厳しい意見も交わされていたようですが、
「可笑しい可笑しいというのは目に慣れないというだけで、これが、何十年か過ぎた後には明治の煩悶時代に、この門が一つの刺激剤となったのだというようなことになるかも知ない。」(『建築雑誌』307)
と見越しており、事実、現在の私たちの目には違和感を感じることはなく、大学の「顔」として皆に認識されています。
文・角田真弓(つのだ・まゆみ) 工学系研究科技術専門職員
(寄稿)
【本郷キャンパス建築めぐり】