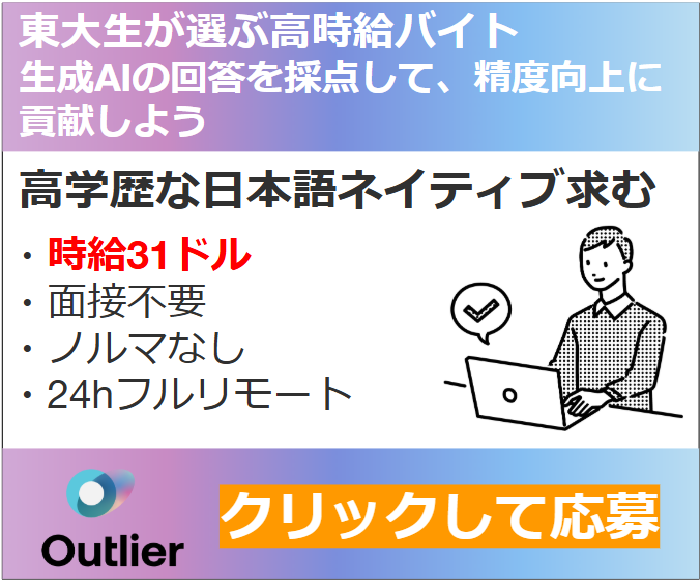「東大の女子学生の割合はわずか2割」という事実が相変わらず注目を浴び続けている。一方、残りの8割という数字は家父長制社会の象徴として批判対象になっても、そこにいる彼らが置かれている実際の境遇についての議論はあまり耳にしない。しかし、周りのほとんどを男性が占める特殊な環境は、女性のみならず男性自身にも影響を与えているに違いない。過度ないじり、恋愛をめぐるあれこれ、終わりの見えない競争─男性社会が抱える困難を語るものとしてこれまでさまざまな視点が提唱されてきた。
この記事で手掛かりとする「ホモソーシャル」とは、男性社会の基盤にある、男性同士の関係について分析する概念として今から半世紀前に登場した社会用語だ。身近な家族や大事な友達に時には特権的な地位を与え、時には生きづらさを背負わせることにもなるホモソーシャルな関係とは何か。そしてそれによる抑圧を少しでもなくすために何ができるのかを探っていきたい。なお、本記事は「男性同士の絆」についてであるが、何かしらの形でホモソーシャルな関係に足を踏み入れている男性を想定したものであり、男性全員ではないことに留意していただきたい。男性同士の絆の形としてホモソーシャルな関係が「普通」とされる社会の中でも、ホモソーシャルな関係とは距離を置いて過ごしている男性もいることを忘れてはいけない。
この記事は、女性の声、フェミニストの声を届ける出版社「エトセトラブックス」の雑誌『エトセトラ』の第10号「特集:男性学」に収録されている五月あかり氏の文章「誰も好きになってはならない」を参考にした。同誌は小説や論考、座談会などさまざまな形式で男性学(男性であるが故に男性が抱える諸問題について研究する学問)を取り上げている。「男らしさ」が形成された歴史、それがどのように日常の中に潜み人を抑圧・排除してきたのか、そしてその有害性からどう脱却し、多様な男性のあり方を実現できるのか─。本記事で全ての話題に触れられないことが残念だが、ぜひ機会があれば手に取ってみてほしい。((執筆・加藤美凪(仮名))

父兄関係、東大入学 「男らしさ」との出会い
幼少期から私は、肉体的にも精神的にも強い男性を「男らしい」と見るようになった。父は小さい頃からスポーツに打ち込み、大学もスポーツ推薦で入学した。画質の荒い画面越しに映る若かりし父の姿──主将として雄たけびを挙げながらチームを鼓舞し、試合で活躍する背中には「漢(おとこ)」らしさが漂う。物心付く前から父は兄にスポーツを始めさせた。人見知りでボールよりも本を好む兄が、泣きわめきあらがいながらも父に連れ出されていく様子を私は見ていた。「男は強くなければいけない」が口癖の父──実直に練習に励んだ兄は試合で金メダルを取るようにもなったが、後から兄に聞くとその経験はトラウマとして長い間付きまとっていたと話す。母はそんな父をたしなめ、小学校低学年で兄は習い事を辞めた。今では父も丸くなり、時々あの頃の後悔を口にする。
幸いにも、男女で仲良い友達グループで中高時代を過ごしてきた私は、それから「男/女らしさ」を強く意識することはあまりなかったが、東大に入学してこれまで見えていなかった「男らしさ」と出会った。今の時代「男というのはな…」「それでも男かよ」なんてことを言う同級生はほぼいない。しかし、男性の友達から聞く男子同士の会話には「男らしさ」が充満していた。「クラスの奴らが下ネタしか話さなくて苦痛」「カフェに行きたいって言ったら『女かよ』って笑われた」「スポーツも見ないしゲームもしないから話についていけない」─。彼らの日々の愚痴や悩みにはジェンダーをめぐる社会のあり方が反映されている、と今ではよく分かる。この理解の輪郭を描く手助けになったのは「ホモソーシャル」という概念だった。
「男性同士の絆」を支える、「女性的」なものの排除
1976年にジーン・リップマン=ブルーメンは、社会的な意味での「同性の仲間への選好」をホモソーシャリティ(homosociality)と定義した。1985年には、英文学研究者のイヴ・セジウィックが『男同士の絆』でその特徴を「ホモソーシャル」として浮かび上がらせ、男性同士の緊密な結び付きを意味する社会学用語として広く知られるようになった。今のジェンダー研究では、ホモソーシャルな関係は女性に対する蔑視・排除(ミソジニー)と同性愛の蔑視・排除(ホモフォビア)で構成されているという理解が一般的になっている。もちろん、全ての男性がこうした関係の中にあるわけではないだろう が、友人の話に表れるようにホモソーシャルな関係に足を踏み入れたことのある男性にとってこうしたことは経験的に分かるのではないだろうか。
『エトセトラ』の「特集:男性学」には、そんな男性同士の関係について描いた「誰も好きになってはいけない」と題した文章が収録されている。まず五月氏は、思春期以降の男性同士の絆の構築においては、自らを「男として」アピールし続けなければならないことを指摘する。その手段が「女性に対する欲望の表明」であり、女性を客体化し消費するようなわい談もその一例だ。また女性に「モテる」ことがステータスになるという話も耳にするが、これには女性がある種利用されているようにも感じる。これらはミソジニーの表れであるとジェンダー研究は指摘してきた。
女性に対する欲望の表明が男性性に直結する限り、「男らしさ」の有無とは無関係であるはずの同性愛者がホモソーシャルな関係性から排除されることも当然だろうと作者は述べる(もちろん、性的指向に関わらず恋愛や性に関わる話を好まない男性も排除される)。私も、兄が男性同士で「ゲイ」とからかい合うのを不思議に思いながら見てきた記憶がある。からかいに「面白い」返答ができるかが試されると友達は言う。同性愛もホモソーシャルな関係の中では話のネタとして消費されるのだろう。ホモフォビアは、女性への欲望とは関係なく、男性同士の強い絆が性的なものではないと証明したい反動から起こる現象であるなど、他にも解釈はあるが、ホモソーシャルな関係の中にミソジニーとホモフォビアがあるという主張には、自ら体験したり身近な男性の体験を見聞きしたりしてうなずける人が多いのではないだろうか。
ただ、トランスジェンダー女性でもある五月氏は、かつて男性としてホモソーシャルな関係に自ら入った経験をもとに、男性同士の関係の実態をもう一歩踏み込んで描いている。ホモソーシャルな関係は女性「と」同性愛の排除ではなく、「女性に対する欲望」として表象される「男性性」が欠如する「女性的」なもの全て(女性も同性愛も含まれる)の排除の上に成り立っているというのだ。たとえ異性愛者の男性であっても排除され得る危険は常に潜んでいる。「ピンク色が好き」といった「分かりやすい」ものでなくても、お笑い要素のない真面目な相談をする、ゲームやスポーツに関心がない─そんなささいなことが、ホモソーシャルなの関係の中では「居心地の悪さ」を生み出し結果的な排除にもつながり得る。男性同士では感情的な側面を見せづらいことや弱音を吐きづらい雰囲気もこれに起因していると考えられる(これらの要素が「女性的」とされている実態がこれまた女性差別に直結していることは言うまでもないだろう)。
こうして、ホモソーシャルな関係においては、男性という属性が異様に強調され、本来の自分らしさを削って同型の男性像の中に自分自身を彫り出さないといけなくなる。もちろん、この型がマッチし優位な立場になれる男性もいるだろう。それは直ちに否定されることではないが、その型に誰かをはめこもうとせず、いえ、最後はその型から誰もが自由になってほしい。そうなれば誰もが肩をすぼめず、のびのびできる社会になっているはずだ。
ホモソーシャル以外の関係を探る 連帯を妨げるものは?
このように、ホモソーシャルな関係はさまざまな排除の上に成り立っている。と、社会にある抑圧や排除の分析にとどまる論考はよく目にする。それこそがホモソーシャルな関係を一般的とする社会の落とし穴の一つなのではないだろうか。大多数のホモソーシャルな関係は浮かび上がってきても、そこから「外れた」男性の姿は一向に見えてこない。現代社会によって抑圧されている人々の生の声、実態については、考えようという発想がそもそも上がりづらいのである。私もその穴に落ちそうになったことを反省しつつ、社会が作り上げてきた型が合わなかった男性たちに焦点を当ててみたい。
私の兄の話に戻ろう。中学時代の転校など人間関係で不安定な時期もあり、早い段階からホモソーシャルな関係を苦痛に感じた兄は、気付けばいつも部屋に閉じこもっていた。今思えばマイクロ・アグレッション(無意識の偏見や思い込みが言葉や態度に表れ、意図せず誰かを傷つけてしまうこと)だが、中学生だった私は無邪気に「友達と遊ばないの?」「なんで外出ないの?」と質問攻めだった。返事はいつも「本を読んでいる方が/ゲームしている方が/1人でいる方が楽しい」だった。ただ単に自分とは「楽しい」のベクトルが違うだけでお兄ちゃんも楽しんでいるのだ、と未熟にも納得してしまった。年齢が上がるにつれて「多様性」についての理解も深まってきた私は、兄の過ごし方を「変」「心配」などと価値判断を付せずに単なる一つの在り方として捉え直すようになった。友達は数えられるほどしかいないかもしれないけど、本を読んで得てきた膨大な経験値、知識量を持っているし、男子の「カッコイイ」感じじゃないかもしれないけど、いくら自分にとって不都合でも困っている人には必ず手を差し伸べる優しい人だ、と。社会が要求する男性像に当てはまらなくとも、そこに優劣なんてないのだと。
しかし、この私の捉え方には大きな欠陥が二つあると今では思う。一つ目は兄の「孤立」の背景にある「ホモソーシャルな関係からの排除」を無視していることだ。「みんなそれぞれでみんな良い」を文字通りに捉え、全ての在り方が対等に認められるような多様性を考えるならば、属性ごとの規範は解体されその個性間の関係はフラットなものでなければならない。しかしそれとは程遠い現実がある。むしろ安易に「多様性」という言葉で人を捉えることで、規範から解放されたフラットな主体として相手を想定してしまった結果、相手が直面している排除や抑圧を見えなくする危険性もあるのだと気付いた。二つ目の欠陥は、ホモソーシャルな関係に加わっている(ように見える)男性が受けているかもしれない抑圧に無頓着である点にある。父と一緒にスポーツ観戦していた時のことだった。「スポーツだけ考えれば良くてそれでチヤホヤされて人生楽しそう」と脳天気に言った私に対して、父は「あの(スポーツの)男社会は息苦しいぞ」と一言だけ放った。ホモソーシャルな関係の中で「勝っている」ように見える男性たちでもその抑圧を受け得るというのは今ではよく分かる。
実際、ホモソーシャルな関係の恩恵を受けている人とその抑圧を受けている人をはっきり区別することはできないはずだ。生活の大部分はホモソーシャルな関係の中で過ごしつつ、適度な息抜き方法を身に付ける男性も多いだろう。他方、孤立を選んで個人主義を貫いたり、交友関係の大部分を女性の友達で占めたり「分かりやすく」ホモソーシャルな関係から脱している男性もいる。男性のほとんどは何かしらの形でその関係に息苦しさを感じているのではないか。それなのに「女々しい」と男性からいじめを受けた友達は、同時に別の男性を指さしては「あいついつもぼっちだよな」と言う。男社会の愚痴を言っていた運動部の友達は体育の授業になると「(女の子の名前)の方が上手いじゃないか」と別の学生をからかう。飲みの場で「男社会しんどい」とこぼした友達は私の友人を「女子とばっかいるよね」とあざける。ホモソーシャルな関係から脱却し孤立したように見える兄は今日も友達同士で「ゲイ」と呼んでふざけ合っている。ホモソーシャルな関係か自分に合った生き方か─ホモソーシャルな関係を内面化した結果として、その間にある他の生き方を排除し二者択一になっているように思える。同じ生きづらさを抱えているにも関わらずそれを共有しようとは決して思わず、深い分断が起きてしまうこと、これがホモソーシャルな関係に隠れた構造的なゆがみなのではないのか。