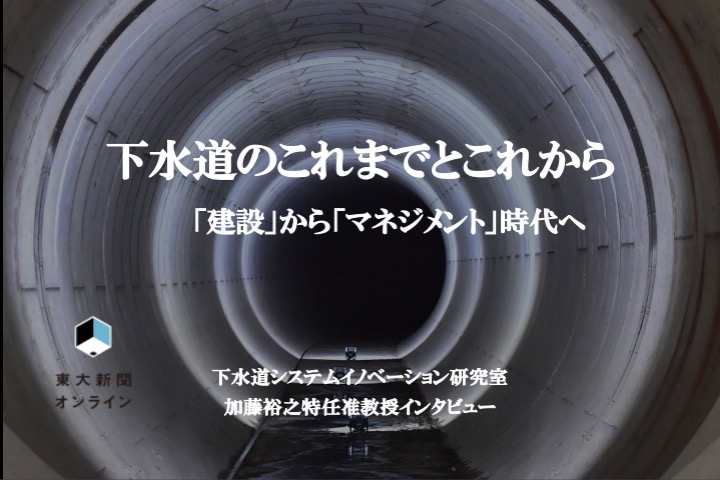日本の下水道は今、岐路に立たされている。1970年、高度経済成長期の最中にあった日本の下水道普及は他の先進国に比べて遅れていた。その後、半世紀の間とにかく普及率の向上を目指した下水道が抱えていた課題は「建設」に関することばかりだった。しかし下水道がある程度普及した現在、下水道は老朽化や経営難、環境問題などの新たな「マネジメント」の課題に直面している。それぞれの課題に下水道業界と東大はどのように対応してきたのか。それを探るため、東京大学下水道システムイノベーション研究室の加藤裕之特任准教授に取材した。(取材・葉いずみ)
下水道建設の時代
なぜ日本の下水道建設は遅れたのか
世界の下水道の整備は都市の発展と共に進んだ。欧州では産業革命以降都市に人口が集中すると川に直接流されたし尿により衛生状態が悪化し、伝染病が流行した。それを防ぐために下水道が整備された。日本でも明治維新以降、都市に人口が集中し始め、1884年に東京の神田で日本初とされる下水道が整備されたが、その後すぐには全国に普及しなかったという。その背景について加藤特任准教授は、戦後まで人のし尿を肥料として使用していたという日本の文化を指摘した。「戦後GHQが日本に来て一番衝撃を受けたのは、汚くて臭いものであるし尿を、農業に使っていたことだという資料も残っています」
日本で本格的に下水道が整備されたのは第二次世界大戦後だ。加藤特任准教授は「公害の社会問題化」が下水道普及の一番の要因だと説明する。1970年の「公害国会」では下水道法が改正され、下水道の目的に汚水を適切に処理して河川や海の水質を保全する「公共用水域の水質保全」が追加された。これにより、元々上水道の整備に優先されて後回しになっていた下水道への注目が増し急激に整備が進展した。「イノベーションのきっかけは社会問題であることが多いです」。他にも、化学肥料の普及により肥料として利用されていたし尿が余り、都市の衛生状況が悪化したことや、80年代の日米貿易摩擦時に日本の貿易黒字削減を目的とした内需拡大政策が採られ、欧米に比べて普及が遅れていた下水道への投資額が一気に増大したことが下水道普及の要因となった。
下水道建設のための人材と資本が整うと、次に必要なのは技術革新だった。都市の場合、上水道管やガス管、地下鉄よりも下水道管の方が遅れて建設されたため浅い土地が余っておらず、地下深くに建設する必要があった。また交通量も多いため道路を通行止めにする工事はできず、建物が密集していることから広い用地も確保できない。そこで、地面を掘り起こさずに下水道管を設置する非開削工法が発達した。非開削工法は、埋設する下水道管の始点と終点に立坑を掘り、非開削で立坑間に横穴を掘って下水道管を埋設する日本の得意技術。渋滞・騒音被害を最小限に抑え、開削工法よりも狭い用地での工事が可能だ。政府が推進する水ビジネスとしてベトナム等に輸出されている。
下水道建設は終わらない
今日まで下水道の整備は着実に進んできた。公害国会前(1970年頃)は8%だった下水処理人口普及率は、20年度末には80.1%まで向上した。しかし下水道施設の新設が終わったわけではない。
特に都市では、地球温暖化などにより近年増加しているゲリラ豪雨への対策のために下水道施設が増設されている。浸水には雨が河川などに排水できずに発生する「内水氾濫」と、河川から溢れて発生する「外水氾濫」がある。ゲリラ豪雨では局地的・短時間で豪雨が降るため、短時間で下水道管に雨が集まってしまう。すると、たとえ下水道管の先の河川や水再生センターに余裕があったとしても、下水道管が溢れて内水氾濫を起こしやすい。その対策として下水道管や雨水調節池、雨水ポンプを地下に増設し下水道を貯留・流出する能力を増やしている。

下水道マネジメント時代
2周目は「省エネ」で「創エネ」な下水道システムへ
今後日本の下水道施設は老朽化の問題に直面する。国土交通省のデータによると、標準耐用年数50年を経過した下水道管渠は19年度末で総延長の約5%だが、10年後には16%、20年後には35%と今後急速に増加する見通しだ。下水処理場も、主な設備の標準耐用年数15年を経過した施設が19年度末で全体の86%と老朽化が進行している。
「これからは2周目の施設の作り方を考えていく必要があります。そのためのキーワードは『省エネ』と『創エネ』です」と加藤特任准教授は説明する。「省エネ」とは、下水処理の過程で消費する大量のエネルギーをできるだけ削減すること。例えば、細かい空気の泡を作る技術で下水に空気が溶けやすくして、空気を溶かすために従来使用していた大量の電力の削減を目指す。
「創エネ」とは下水処理の過程で発生した副産物を、新たなエネルギーの創造に利用することだ。特に、下水処理の過程で発生する汚泥の活用が注目されている。汚泥は従来、焼却され灰として埋め立て処分されてきた。しかし燃焼の過程で温室効果ガスである一酸化二窒素を排出するため環境負荷が大きい。そこで汚泥を発酵させてメタンガスを発生させ発電する、バイオマスエネルギーとしての活用法が生まれている。

窒素とリンが含まれている汚泥を肥料として農業利用する方法もある。他にも下水処理で出る熱・CO2をビニールハウス内での栽培に活用し、栄養を含んだ下水処理水を水稲や海苔の養殖に活用するなど、下水道資源を農作物栽培に活用する取り組みは「ビストロ下水道」と呼ばれ全国に広がっている。しかしこのように再利用されている汚泥中の有機物は全体の約35%に留まっており、地球環境のために推進しなければならない。

「市民科学」の実践が下水道運営の鍵
今日、人口減少に伴う下水道使用料の減少、職員数減少、老朽化に伴う施設の大量更新期到来などにより下水道経営は厳しさを増している。そこで、特に過疎化の進む地方では下水道システムの「広域化」が採られている。「広域化」とは、隣接する市町村と下水道管や処理施設を合併することである。施設当たりの利用者を増やして下水道収入を増やし、設備の改築や点検箇所を最小化することで経営を効率化できる。またICT(情報通信技術)を用いて処理場の操作を遠隔で行い、少ない職員で処理場を運用して人件費を抑える方法もある。
また、経営を民間企業に任せるPPP(パブリック・プライベート・パートナーシップ、官民連携)も始まっている。従来、水に関することは公共団体がやらなければならないという伝統があったが、近年規制緩和の動きが見られるという。一方市民の間には、民間に経営を任せることで市場原理に基づいて使用料が値上げされることへの懸念や、企業倒産のリスクを心配する声もある。加藤特任准教授はこうした認識は間違っていると主張。勝手な使用料の値上げを防ぎ企業の倒産時にはリスクを回避できる仕組みが整っているものの、丁寧に説明しないと市民からの理解を得るのは難しいという。
市民の理解を得るためにはどうしたらいいか。加藤特任准教授は「市民科学」の実践が有効だと指摘する。市民科学とは、市民に観察者になってもらい、科学研究機関と市民が対等に科学研究を進めることである。市民と下水道職員がともに農業をする「ビストロ下水道」も市民科学の一種だ。市民科学を実践し、下水道に関する調査研究活動に市民と下水道職員や民間企業が共同して取り組むことで主に三つの効果が得られるという。一つ目は、普段地下に埋まっており注目されづらい下水道の存在意義や役割を、市民が主体的に発見する機会となる効果。二つ目は、下水道職員が市民から直接感謝される機会が増えることで職員のモチベーションが上がる効果である。「職員数が減少し、一人がたくさん働く必要がある今日、職員のモチベーションの維持は重要な課題です」。そして三つ目は、市民が下水道職員と協働することで、普段使用料金を払うだけの関係であった下水道職員に対して親近感が湧き、信頼関係が生まれる効果だ。こうして生まれた信頼があると、適切に下水道料金を払ってもらえて経営の安定につながり、災害時には市民の協力を得やすくなるという。PPPにおいても、市民科学を通して市民と企業が信頼関係を築くことで、市民がPPPを適切に理解するようになる。今後の下水道運営を支え得る市民科学だが問題点もある。市民科学の実践によって得られる成果が数値化できないため政策として国や自治体で予算が付きづらいという。「市民から得た信頼度の数値化をどのようにすればいいのか、東大生に解決策を問いたいです」

東大と下水道
加藤特任准教授が所属する下水道システムイノベーション研究室は新たな下水道システムの構築に向けた研究に取り組んでいる。下水処理水を利用したアユの陸上養殖が今年から始まった。「養殖池の水温やアンモニア濃度、pH値等を管理する技術は、下水処理のために水質を管理する技術と驚くほど似ています」と加藤特任准教授。下水処理水を利用することで養殖池に川の水を引く必要がなくなり、また水中でコケが育つための微生物が豊富で冬でも水温が高く、養殖に適しているといった利点がある。特に地方では容量に余裕のある池が多いため、こうした池での下水処理水を用いた養殖が、地域振興も兼ねた下水道業界の新たなソーシャル・ビジネスになることが期待されている。

AI技術の下水処理への活用にも取り組んでいる。下水処理場では、汚水の汚れ具合に応じて空気の注入量を調節しており、もし汚れの量が多ければ、微生物を活性化させるために空気の量を増やす。調整は手作業で行われるが、汚れの量の変化を感知できず空気を過剰に注入することもある。これは無駄な電力を消費するため、AI技術を活用し水中の汚れの量や水温に反応して空気量を調整するセンサーの開発を進めている。
建設からマネジメントの時代への転換点にある日本の下水道は、下水道普及率の向上をひたすら目指していたかつての時代よりも問題が複雑化している。同時に、下水道が扱う分野も工学だけでなく経営学や、市民科学の有効性の根拠である社会心理学、農学、水産学など多様化している。「これからの下水道の魅力は宝探し。多様な学問分野から下水道にアプローチし、下水道を通して循環型社会の形成、地域環境の改善に直接関与して地球環境に貢献できます」と加藤特任准教授は語る。
加藤裕之(かとう・ひろゆき)特任准教授(東京大学大学院工学系研究科)
86年早稲田大学大学院修士課程修了。博士(環境科学)。建設省(当時)入省後、国土交通省下水道部下水道事業調整官、同流域管理官、同下水道事業課長などを歴任。(公財)日本下水道新技術機構、(株)日水コンなどでの勤務を経て、20年より現職。