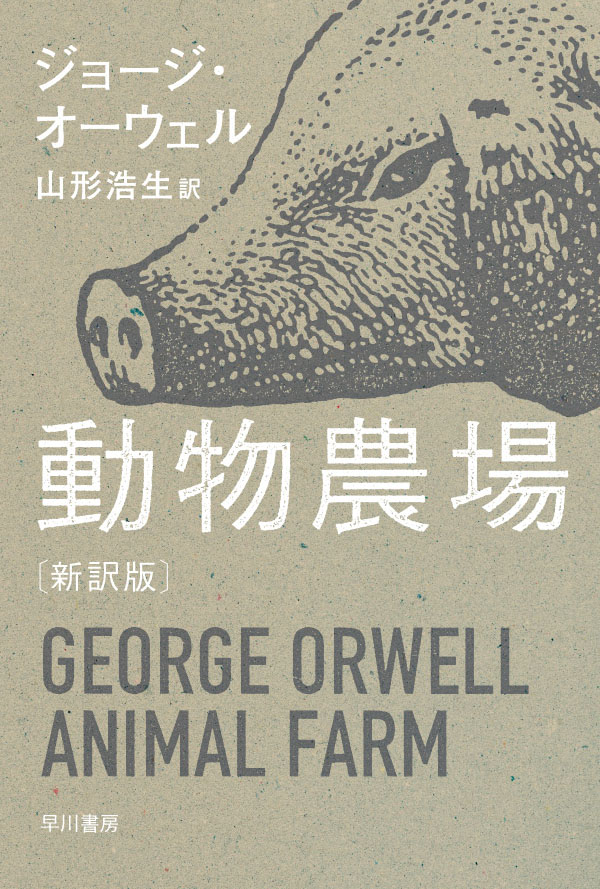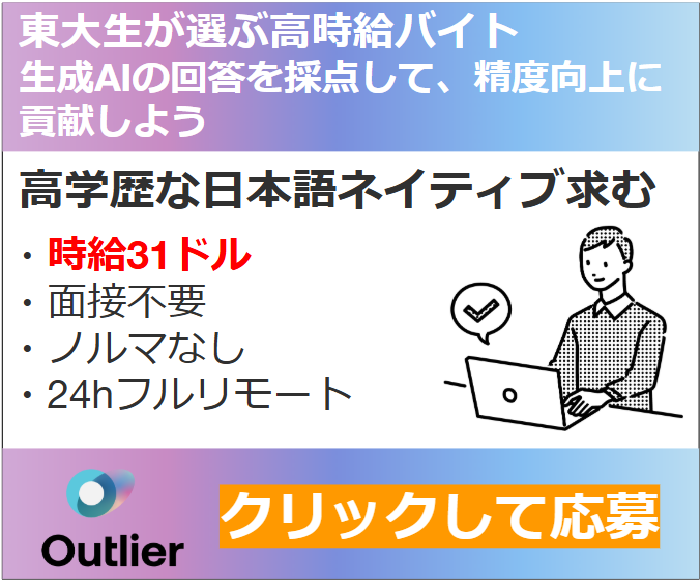もし、農場で人間に隷属し強制労働させられている動物たちが人間を追い出し、自ら農場を運営するようになったとしたら何が起こるだろうか。ジョージ・オーウェルによる小説『動物農場』(早川書房)はそんな動物たちの革命と、その後の顛末(てんまつ)を描いた物語だ。
ある英国の農場で、動物たちは過酷な労働を強いられていた。ある晩、動物たちの中で最も賢く尊敬されている老ブタのメージャーが動物たちを集め、人間による理不尽な支配を糾弾し、反逆を呼びかける。動物たちはそれに熱狂で応え、人間への報復を誓った。メージャーは老衰で死ぬが、動物たちを指導する役割は知能が高いブタが引き続き担うことになり、人間は敵、動物は皆平等な同志といったメージャーの教えを「動物主義(アニマリズム)」としてまとめることに成功する。教えの最後の一カ条は「すべての動物は平等である。」だった。後日動物たちはついに農場主を追放し、会合での話し合いに基づき農場を運営するようになる。今ここに人間の経営する「マナー農場」は「動物農場」となった。人間がいない農場で動物たちが協力して作業する牧歌的なシーンが描かれるが、雲行きは次第に怪しくなってくる。
指導者として頭角を現したのはナポレオンとスノーボールという2頭のブタだったが、2頭は掲げる政策の違いなどから事あるごとに対立し、最終的に凶暴なイヌを飼いならしたナポレオンがスノーボールを実力行使で追放してしまう。ブタたちは頭脳労働を口実にミルクを独占したりベッドで寝たりするといった特権を手に入れ、ナポレオンはスノーボールが革命の初期から裏切り者であったかのように歴史を改ざんするようになる。
本書は英国で1945年に発行されたが、動物たちの寓話(ぐうわ)は明らかにソ連をモデルにしており、作者もその政治的意図を隠していない。動物主義の原則を示したメージャーはレーニン、暴力的で陰謀に長けたナポレオンはスターリン、理論家で演説がうまいスノーボールはトロツキーといったように、いずれもソ連の指導者たちをモデルにしている。
その後、人間による支配から脱却したはずの動物たちはナポレオンによる支配に再びむしばまれていく。あくまでおとぎ話のような文体で書かれているものの、労働と飢えに苦しむ動物たちの様子や、大粛清、計画経済の破綻、外敵を持ち出したプロパカンダといったスターリン時代のソ連を思わせる描写は生々しく、それでもより良い未来を信じて愚直に労働に従事する動物たちの姿は涙ぐましい。
敵であったはずの人間と農産物を取引したり、豪華な居室や食事を独占したりするナポレオンが、動物の平等や人間を敵とすることを定めた最初期の戒律に違反しているのではないかと問う動物もいたが、戒律は都合の良いように書き換えられてしまっていた。たった一条残った戒律は「すべての動物は平等である。だが一部の動物は他よりもっと平等である。」平等な社会という理念はどこかへ行ってしまった動物農場の様子を描いたこの作品は、秘密警察が監視する独裁国家と化したスターリン下の体制に対する警告と見ることができる。
ソ連で起こっていたことは本書の物語とそう変わりはない。にもかかわらず、作者は複数の出版社に出版を断られたという。背景には、ナチス・ドイツに対する防衛戦争に貢献したソ連を礼賛する社会全体の雰囲気があった。作者は出版時の手稿で、イギリスの言論の自由はソ連の威信にかかわらない限りそこそこ保持されているといい、大半の知識人がソ連に対する無批判な忠誠心を発達させ、出版社やマスコミがソ連に対する批判だけは沈黙させようとする現状を深刻な症状と指摘している。
本書はブタ以外の動物たちの視点に寄り添った語り手によって語られ、ブタの話術によって煙に巻かれてしまう感覚や、社会に蔓延(まんえん)した閉塞感を味わうことができる。動物農場の闘争と勝利を祝う演説や行進に参加し、空腹の感覚も忘れて酔いしれる動物たちを描いたディストピア的な場面を読んだときの絶望感は強く印象に残る。重々しいテーマがあえて動物たちの寓話に落とし込まれているからこそ、かえってそのような印象が強くなるのかもしれない。
とはいえ、動物たちが権力を監視しようという考えを持たず、簡単にブタの言葉に丸め込まれてしまったことがブタによる独裁を招いたとも読める。この動物たちのようにならないためにはどうすればよいのか。ぜひ本書を読んで作者の警告に耳を傾けてほしい。
また、当時作者が置かれた状況についても考えたい。ソ連批判が黙殺される一方で、親ロシアプロパガンダについて「自分の聞きたいことが書かれている限り、事実の検討も、ろくでもない文章も、知識人たちは喜んで見過ごす」と作者は書いている。一般人であっても発信者になれる現代だからこそ、この言葉を頭の片隅に置いておき、時流に流されすぎず、歪められた情報に鋭い目を向け続けなければいけないだろう。【日】