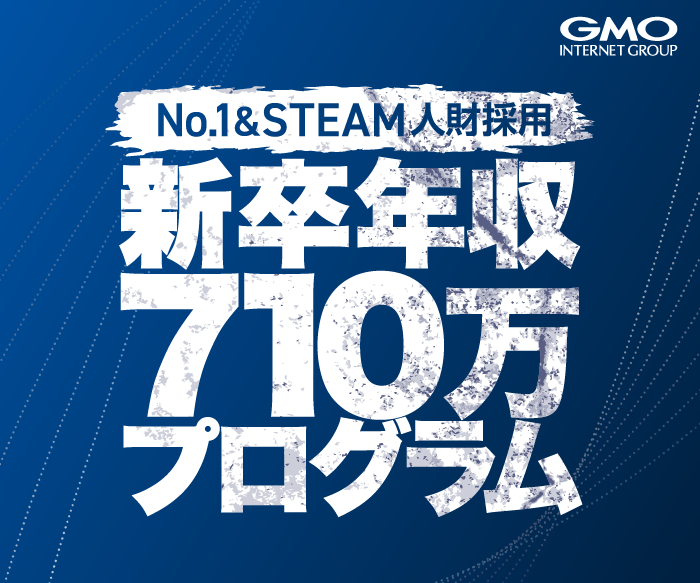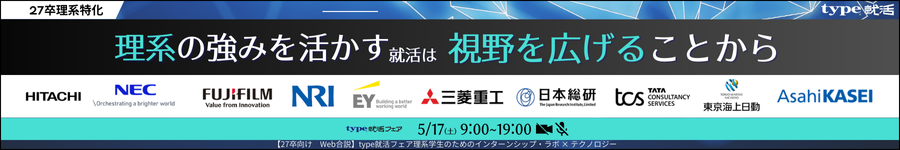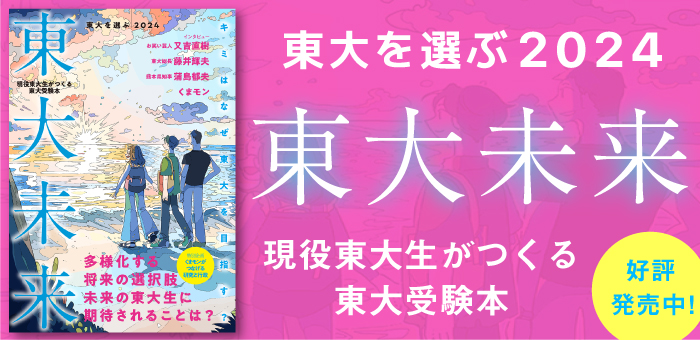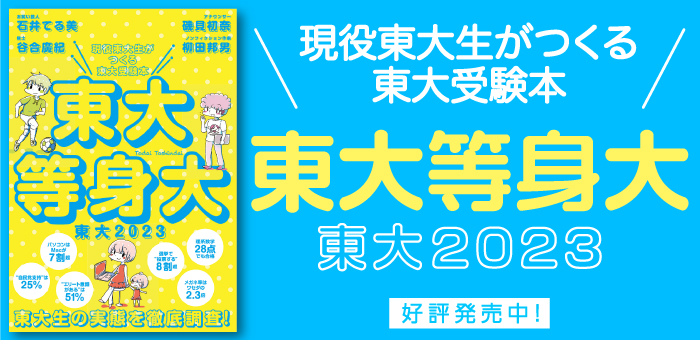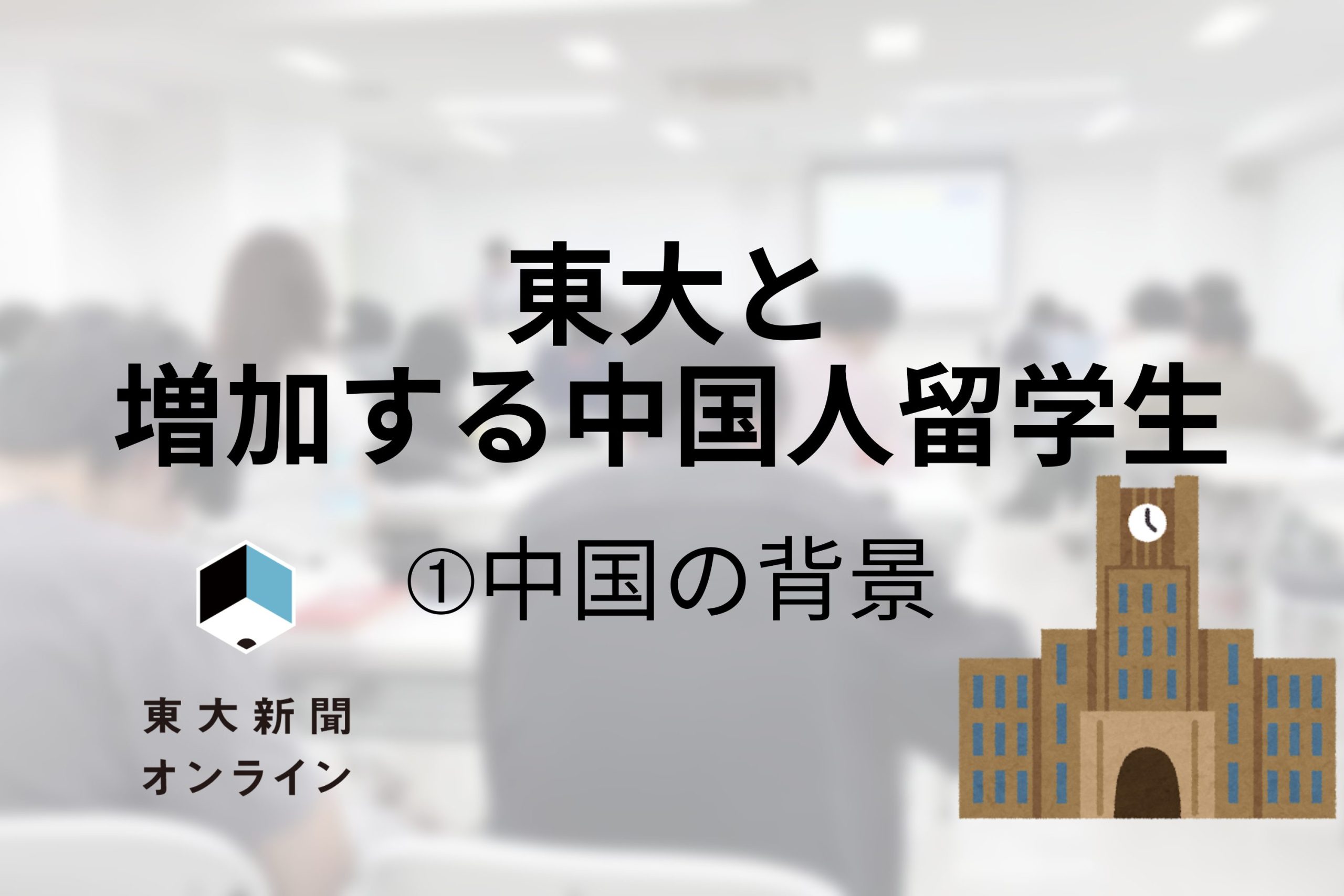
東大への中国人留学生の流入が増加している。東大の集計によると、昨年 11 月1日時点では 3545 人が中国から東大に留学しており、これは 2014 年(1270人)の3倍近くに当たる。また、現在の東大の外国人留学生全体(5231人)の約 67.8%を占めている。では、中国人留学生はなぜ日本を進学先として選び、その中でも東大を志望するのか。学部時代から日本に留学しており、現在は東大法科大学院2年の頼さんと、中国の大学を卒業した後、東大公共政策大学院に入学したAさん(仮名)に、進路選択の背景について聞いた。また、増加する中国人留学生などを対象とした予備校事業を2008 年から展開する行知(こうち)学園の代表・楊舸(よう・が)さんと、学部入試向け「東大クラス」を担当する江波戸亙さんにも話を聞いた。見えてきたのは、中国国内の厳しい受験競争や、日本が欧米よりも低コストの留学先になっているという社会経済的背景だ。(取材、構成・劉佳祺)
留学先が欧米から日本へ 為替やビザの影響も
──頼さんやAさんは、どうして日本に留学しようと思ったのでしょうか
頼さん 日本留学を決意したのは、高1の時です。日本語のアニメを見ているうちに、日本の文化や日本語に関心を持つようになりました。語学スクールに通って日本語を学び始め、次第に日本の大学進学を目指すようになりました。
Aさん 大学3年次に日本留学を志すようになりました。学内での成績は良い方でしたが、中国の大学院入試は定員が非常に少なく、倍率が高すぎて、優秀な学生でもなかなか合格できないと感じていました。
そうした中で海外進学を視野に入れるようになり、最初は日本にするか欧米にするかで迷いました。私の同級生には裕福な家庭の子が多くて、私より小さい頃から英語教育を受けてきた人もいました。欧米圏への留学は競争が激しいですが、英語力において自分は不利だと考えました。
──日本は欧米より費用も安く、現実的な選択肢として考えるようになりました。以前旅行で訪れた際に日本の環境が気に入っており、日本なら生活面でも自分に合っていると感じたことが日本を選ぶ決断につながりました。Aさんの話にもあるように、中国人の留学先は欧米から日本へとシフトしていると言われています。楊さんは、この背景をどう分析していますか
楊さん 以前は「富裕層」とまではいかないものの、数軒の不動産を所有しているような家庭が、米国やヨーロッパへの留学を選ぶ余裕がありました。しかし、最近は米ドルやユーロの為替レートが上昇し続けており、欧米への留学の経済的な負担が増大しました。その上、高価なものを買おうとしない消費降級(消費ダウングレード)の風潮も相まって、費用が多く掛かる留学への心理的ハードルも高くなりました。
他方、円安の影響もあり、日本への留学費用は相対的に少なくなりました。本来、米国やヨーロッパを目指していた層にとって、当初は留学先の選択肢に入っていなかった日本が「ちょうどいい選択肢」として浮上し、日本留学にシフトしたということです。
また、日本の観光ビザが解禁(団体は 2000 年、個人は 09 年)された後、中国人が実際に日本を訪れる機会が増えました。その結果、日本の社会や文化に直接触れ、現地の社会秩序や生活環境を自分の目で確認できるようになりました。これにより、日本に対する偏見や先入観が和らぎ「実際に住んでみたい」「日本の大学に進学したい」と考える人が増えてきています。対照的な要因として、米中関係の変化も挙げられます。
一方で、全ての社会階層でこのような変化が起こっているわけではないことも付言しておきます。もともと日本を留学先として考えていた家庭に関しては、大きな変化はありません。彼らは以前から「日本に行く」と決めており、欧米を選択肢として考えていなかったため、留学の動向はほぼ変わっていません。また、中下層の家庭に関しては、留学そのものをあまり考えなくなりました。以前は韓国や日本を選択肢に入れていた家庭も、現在では経済的な理由から留学を見送るケースが増えています。

東大合格者は「中国でも優秀」 学部と院で違いも
──頼さんとAさんは、日本の大学の中でも東大を選びました
頼さん 私は4年間、東大以外の日本の学部で学んだ経験があり、せっかくなら一度は東大に挑戦したいと思いました。また、キャリア面でも大きな強みになると思いました。中国の経済状況や就職環境は今かなり不安定で、リストラが多いと友人から聞きました。東大は日本最高峰の大学であり、国際的にも知名度が高いです。これまで学んできた法律が日本の制度に基づいているということもあり、まずは日本で実務経験を積み、5〜10 年後に帰国を検討したいと思っています。
Aさん 真面目な学びの雰囲気や学術レベルの高さに加えて、実務的な学びや国際交流が重視されている点に強く引かれました。進学した公共政策大学院の経済政策コースでは、日本銀行の元副総裁など、実際に政策形成に携わった専門家による講義が数多く開かれていたほか、現場での政策調査を通じた実践的な授業も充実していました。また、他国の政府職員や金融関係者も短期留学で参加しており、さまざまなバックグラウンドを持つ人々とのディスカッションができる環境は、非常に刺激的でした。
──中国人留学生の中でも、特にどのような学生が東大を目指しているのでしょうか
江波戸さん 行知学園には学部進学向けの東大クラスがあります。人数は毎年増加しており、直近の 2025 年度入試では東大クラスは最高で 60 人以上いました。全体的な傾向として理系の人気が高く、文系の中では文Ⅱの志願が増えています。大学での学びが自分の将来の仕事の収入に直結しやすいかで選ぶ傾向があると思います。
楊さん 文系・理系を問わず、東大に合格する学生は非常に優秀であり、中国国内ですでに高い学力を持ち、厳しい選抜や準備を経ている方がほとんどです。
──東大に在籍する中国人留学生 3545 人のうち、3361人(24 年 11 月1日時点の東大の発表)が大学院生です。学部を目指す学生と大学院を目指す学生との間に違いはありますか
楊さん 特に言語能力に大きな違いがあります。学部生は一般的に日本語能力が非常に高く、日本人学生とほぼ変わらないレベルでコミュニケーションができます。一方、大学院生は日本語能力が十分ではない場合が多く、特に SGU(スーパーグローバル大学創成支援)などの英語のみで授業を受けるプログラムを利用する学生の中には、日本語をほとんど話せないまま卒業する方もいらっしゃいます。
また、学部生に関しては家庭の経済力も大きな要素となります。東大の学部入試(第1種外国学校卒業学生特別選考)に合格するためには、EJU(日本留学試験)でほぼ満点に近いスコアを取得し、さらに TOEFL iBTでは 100 点以上(120 点満点)を取る必要があると言われています。また、高い日本語能力に加え、英語と中国語を自在に使いこなせる学生も多く、トリリンガルとしての強みを持つ方が多いです。このような学力を短期間で身に付けることは難しく、多くの学生は来日前から質の高い教育を受けています。そのため、家庭の経済的余裕や教育への投資意識が高いご家庭の出身者が多い傾向にあります。
一方、大学院生の場合、学部生ほど家庭の経済状況に左右されることは少なく、個人の学力や研究能力が合否に大きく影響します。東大の大学院を目指す学生の多くは、中国国内の「985・211」(トップレベルの大学群)出身であり、すでに学部時代から高い学力を持っている方が多いです。大学院進学では、研究テーマの明確さや研究計画の質、教員との適切なマッチングが重要となるため、研究への意欲や能力が評価される傾向にあります。
異なる入試制度 中国の院試は過酷
──日本の学部に留学するために、どのような勉強をしますか
江波戸さん 日本語学校や塾探しは、ほとんどの学生が 来日前から準備し、EJU(日本留学試験)を受ける年度 の4月ごろに来日します。少なくとも6月ごろまでは、 東大の1次選考に通過できるようにEJU の対策に集中します。その後、小論文や面接の対策を始めていきますが、小論文対策も早い人は1年前から取り組んでいます。
頼さん 私は、最初に留学したのが東大ではないものの、高1の頃から週末には日本語とEJU の勉強に励んでいました。
──中国と日本では、入学試験に関してどのような違いがありますか
頼さん 学部段階で日本を選んだ理由について「高考(中国の大学入試)を受けたくなかった」という現実的な事情もありました。高考は一発勝負の全国統一試験で、その激しい競争から逃れる手段として、比較的留学しやすい日本が魅力的に映りました。日本の大学入試は2段階で評価されるうえ、特に留学生に対する入試の倍率は、 中国の高考に比べて遥かに低いのが現状です。
大学院入試に関して、中国では、中国政治関連の科目や数学といった専攻とは無関係な科目まで試験に含まれ ることがあり、準備の負担が非常に大きいです。それに、 受験倍率が極めて高く、2〜3回受験しても合格できず、 最終的に海外進学を選ぶ人も少なくありません。
Aさん 正直に言って、中国の大学院入試の方がはるかに厳しいです。受験者数があまりにも多く、定員がごくわずかなので、本当に「千軍万馬過独木橋(千軍万馬が丸木橋を渡る)」のような状況です。
人口の多さという構造的な要因に加えて、試験の形式 そのものにも問題があると感じました。実務や専攻に生かせるような内容は少なく、暗記や型にはまった回答ばかりが求められます。特に政治関連の科目では、将来の専門性とは全く関係がないにもかかわらず、それを延々と暗記しなければならない。そういった状況は、非合理的だと強く感じました。
その一方で、日本の大学院入試は、まず受験者数自体が少なく、競争も比較的穏やかです。さらに、試験内容も実践的かつ柔軟で、将来の研究や仕事に直結するようなものが多いです。たとえば、公共政策大学院の入試で自分が関心を持つ社会経済問題についてエッセイを書くことが求められます。日本の大学院入試は形式にとらわれず、学生の総合力を評価する仕組みになっていると感じました。
楊さん 中国の入学試験と日本の入学試験の違いについ て、私は「卓球とバドミントンの違い」のようなものだと考えています。どちらもラケットを使って球を打つスポーツではありますが、ルールやプレースタイル、求められる技術が全く異なります。そのため、本質的に比較することは難しいと思います。もちろん、「受験生=アスリート」と捉えた場合、学力の基盤や思考スピードといった点では共通点があるかもしれません。しかし、試験対策のプロセスそのものが 全く異なるため、単純にどちらが難しい、どちらが楽だという比較はできません。
ただし、卓球でもバドミントンでも、上達するためには厳しいトレーニングが必要です。それと同じように、日本の大学入試も中国の高考・考研(大学院入試)も、それぞれの試験に適した勉強法でしっかりと準備しなければなりません。どちらの試験が自分に向いているのかというのは、その人がどのような学習スタイルに適応できるかによると思います。
例えば、中国の高考の場合、ひたすら過去問や問題集を解き、大量の問題演習をこなすことに適応できる人、 特に試験の最後に出題されるいくつかの難問を解ける人が有利になります。難問に正解できるかどうかが得点を大きく左右し、高得点を取るためには問題の解法を完璧にマスターしなければなりません。
一方、日本のEJU の場合、極端な難問は少なく、基礎から標準レベルの問題をミスなく正確に解ける人、幅広い知識を網羅し、安定した得点を取れる人が有利になります。つまり、日本の大学入試は「少数の難問を解けるかどうか」よりも、「基礎をどれだけ確実に押さえて いるか」が重視される傾向にあります。そのため、難問を解くのが苦手でも、基礎知識をしっかり身に付け、ミスを少なくできる学生には日本の試験が向いていると言 えます。
大学院入試に関しては、日本と中国の大きな違いとして、日本の大学院入試は中国の博士課程の入試と似ているという点が挙げられます。中国の考研は、基本的に統一試験の形式で実施されるため、多くの受験生が一律の試験を受け、その結果で合否が決まります。しかし、日本の大学院入試は教員の裁量が大きく、この点は中国の博士課程入試に似ています。そのため、日本の大学院を目指す場合、事前に志望する教員とコンタクトを取ること、研究計画書をしっかり作成すること、研究内容が教員の研究分野と合っていることが非常に重要になります。

よう・が/YANG Ge/06 年に中国で高校を卒業。12 年名古屋大学卒。15 年東大新領域創成科学研究科中退。自身の留学・受験経験と、多くの留学生から寄せられた相談をきっかけに受験指導を始め、08 年に中国人留学生向けの進学予備校「行知学園」を創立。現在に至るまで、同社の代表取締役社長を務める。
──特に大学院試験について、日本と中国の違いが目立ちますね
楊さん 日本人の大学院進学に対する考え方は、中国とは大きく異なります。日本では「大学院に進学する必要があるのか」「修士号を取得することで就職に有利になるのか」といった実利的な視点が重視されます。日本の就職市場では、修士号を取得することで必ずしも就職が有利になるわけではなく、むしろ年齢が上がることで不利になることもあります。
特に、以前の「就職氷河期」を経験した世代では「早く学部を卒業し、若いうちに企業に就職した方が良い」 という考え方が根強く、企業側も「新卒のうちに入社し、 企業文化に染まる方が望ましい」と考える傾向がありま す。そのため、日本人学生の多くが大学院進学を敬遠し、学部卒業後すぐに就職します。
しかし、研究室には一定の労働力、すなわち研究人材が必要です。理系・文系を問わず、実験や研究を進めるためには大学院生の存在が不可欠です。そのため、教員 たちは優秀な学生を確保するために、日本人学生だけで なく、留学生の受け入れを増やす方向にシフトしていま す。
一方、中国の学生から見ると、東大のようなトップ大学の大学院は、国内の競争に比べて「入りやすい」と感 じられることが多いです。中国国内では、大学院入試の競争が非常に激しく、一つの枠に数百人が応募すること も珍しくありません。しかし、日本では大学院入試の競争率がそれほど高くないため「日本の大学院の方が合格しやすい」と認識される傾向があります。
これは、日本の文系大学院が日本国内の就職市場では あまり評価されにくいこと、対して中国の学生は「学歴を重視する文化」を持っていることが影響していると考えられます。