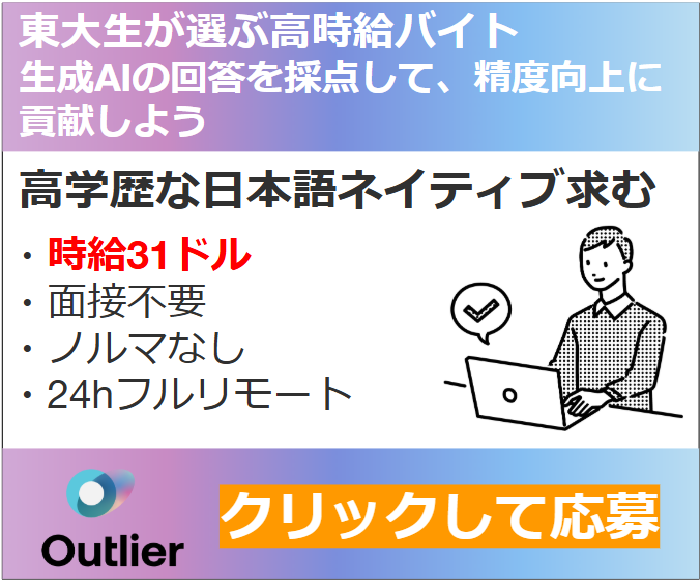習近平国家主席の就任以来、一帯一路政策の下東南アジアやアフリカの国々との連帯を強める中国。コロナ禍という非常事態でも「ワクチン外交」で積極的に世界に影響を与えてきた。存在感を増す中国に西側諸国は危機感を抱き、日本でも中国を警戒する報道がなされている。謎に包まれた中国外交の実態を丸川知雄教授(東大社会科学研究所)に聞いた。
高所得国まであと一歩に迫る中国
「コロナ禍は中国と西側諸国との関係を大きく変えました」。そう丸川教授は述べる。コロナ禍は2019年末に中国の武漢から広がったが、翌年4月にはおおむね収束した。その後、他国の経済のまひが続く中、中国は景気を急速に回復させた。今後の中国経済について、丸川教授は前向きな見通しを持つ。「これから中国は4%台の経済成長率をしばらく続ける潜在力を持っていると思いますし、2030年ごろには米国を抜いて世界最大の経済大国になるでしょう」。21年の中国の一人当たりの国民総所得(GNI)は1万1890ドル(世界銀行発表)に達しまであと一歩に迫った。世界経済において、14億という莫大(ばくだい)な人口を抱える中国の存在感はますます増していく。
実際、コロナ禍以降の世界貿易において中国の存在は大きい。例えば米国はコロナ禍で不足する呼吸器を中国から輸入。世界に大量のマスクを供給しているのも中国だった。「経済をいち早く回復させたのだから、これまで通りの貿易を確実に続けるだけで中国は世界に貢献できるはずです」
中国の対外援助・投資は「不透明」
対外援助、対外投資も中国の経済成長の要だ。コロナ禍の以前の対外援助・投資の特徴を、丸川教授は「不透明」という言葉で表す。経済協力開発機構(OECD)の中に開発援助委員会(DAC)という機構がある。OECD加盟国が発展途上国への援助について報告しあう枠組みで、途上国への援助において先進国が競合しないよう調整する役割を持つ。しかし、中国はOECDに加盟していないため、中国の対外援助についてのデータは中国が自発的に公開するものしか見ることができない。実際、中国政府は21年に7年ぶりの対外援助白書となる「新時代の中国国際発展協力」を公表したが、13年から18年の累計の、業種ごと合計した数字などしか公表されていない。
早稲田大学の北野尚宏教授の推計によると、中国の対外援助額は15、16年は年間66億ドルほど。 当時の日本の対外援助額が支出純額ベースで約150億ドルであることと比較すると、少なくともこの時点で中国は決して援助大国ではない。しかし、これらの援助に含まれるのは政府開発援助(ODA)や無利子借款などに限られる。中国の場合、厳密には対外援助に含まれないものの、対外援助と似た性格を持つ「優遇バイヤーズ・クレジット」と呼ばれる低金利の融資が盛んだ。優遇バイヤーズ・クレジットは、中国輸出入銀行がドル建てで資金を融通するというもので、被援助国によってはカンボジアのように援助とみなしている国もある。中国が16年に優遇バイヤーズ・クレジットで投資した金額は約93億ドル。この金額も考慮すると中国も援助大国と言える。
優遇バイヤーズ・クレジットは中国の一帯一路政策の要となっている。というのも、有償の援助は一帯一路政策で重視される途上国でのインフラ建設と親和性が高いからだ。無償で援助を行うと、資金がどのように使われるかが分からない。一方有償での援助の場合、資金は本来の目的であるインフラ建設に確実に用いられる。
中国の10年〜12年の対外援助額が最も多い地域はアフリカ(52%)だ。アジアが31%、ラテンアメリカが8%と続く。日本がアジアを中心に援助を行っているのに対し、中国はアフリカへの援助が多いのが特徴だ。
対外経済合作という取り組みも見逃せない。元は中国が貧困国だった1960、70年代に行われていた対外援助で、資金を援助する代わりに人的資源を提供するというもの。80年代、改革開放の時代になると外貨稼ぎの手段となった。人的資源を提供するという本質は残したまま、海外でダムなどの建設を積極的に請け負うことで外貨を得ようとしたのだ。これは現在中国の対外援助の一つの特徴となっている。資金は中国輸出入銀行が貸し出し、中国の大手建設会社が工事を請け負うというものだ。労働者も中国から派遣される。中国は、このように自国も外貨を得ながら他国へも協力する援助のことを南南協力と呼んでいる。
対外直接投資では新たな動きも
対外直接投資についても、中国側から発表される統計があまり参考にならないという問題がある。中国の20年度の最大の投資先は香港となっており、ヴァージン諸島やケイマン諸島といったタックスヘイブンへの投資額も多い。業種別では、リース・ビジネスサービス業で最も投資額が大きく、全体の25%を占めた。
中国の資金がどの地域のどの業種に流れているのかは不明確だが、自社よりも力のある企業を買収するというはっきりとした特徴がある。多くの先進国の場合、企業はライバル企業がいないなど、利益を上げる見込みのある地域を選んで進出し、工場を建て、投資をする。しかし中国には他地域で現地企業よりも優位性を持てる企業が少ないため、先進国の有力な企業を買収し、その力を取り込もうとする。顕著な例としては、05年、中国のパソコンメーカー・レノボによる米国のIBMのパソコン部門の買収が挙げられる。レノボはIBMのブランド名も活用しつつ世界最大級のパソコンメーカーへと上り詰めた。一方、最近ではファーウェイ、シャオミのように国際的に競争力を持つ中国企業も増えたため、自分が優位性を持てる地域に進出することもある。
その中でも特に目立つ動きがある。中国の自動車メーカーのタイへの進出だ。中国の電気自動車シェアは世界市場全体の過半を占めるともいわれる。中国は東南アジアへの電気自動車の輸出を強化してきたが、20年以降は現地での製造にも力を入れてきた。タイの自動車市場はこれまで日本企業がシェアのほとんどを占めていた。しかし、電気自動車部門では日本の自動車メーカーは決して強いとは言えない。中国にとってはチャンスなのだ。(②中国外交の窮状 中国側の理由、米国側の理由 へ続く)
丸川知雄(まるかわ・ともお)教授(東京大学社会科学研究所)
87年東大経済学部卒。アジア経済研究所、東大社会科学研究所助教授(当時)などを経て、07年より現職。著書に『現代中国経済』(有斐閣)など。