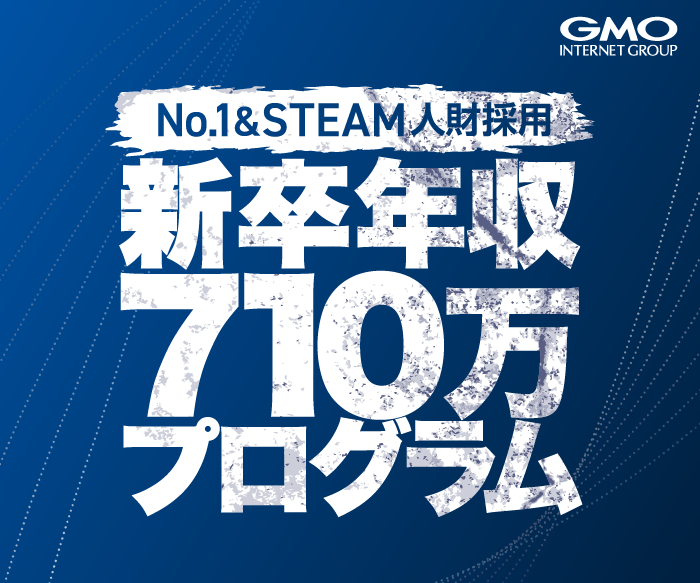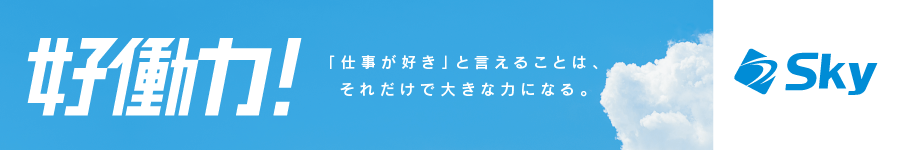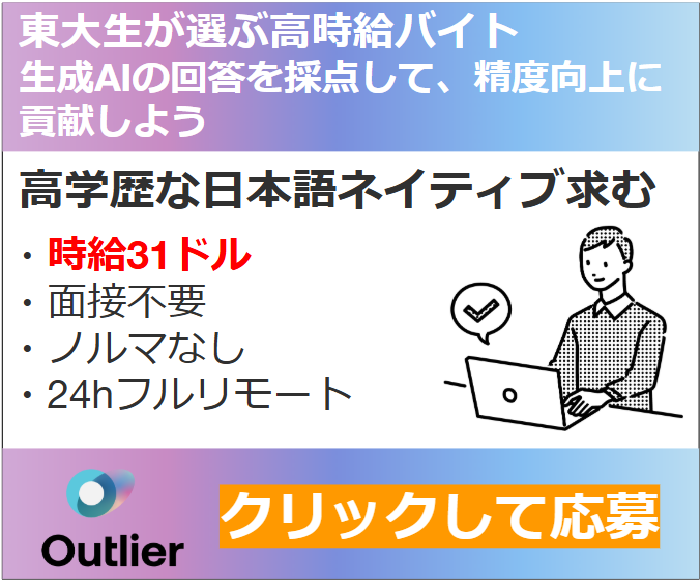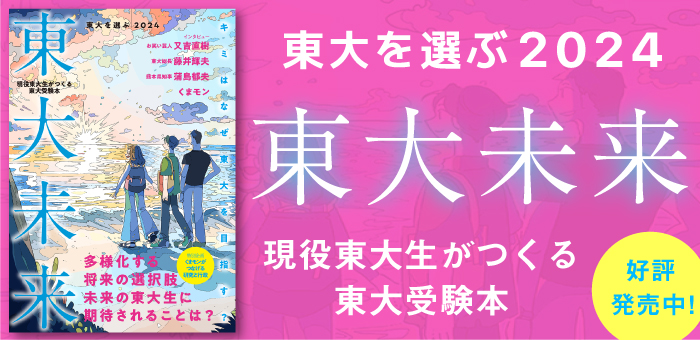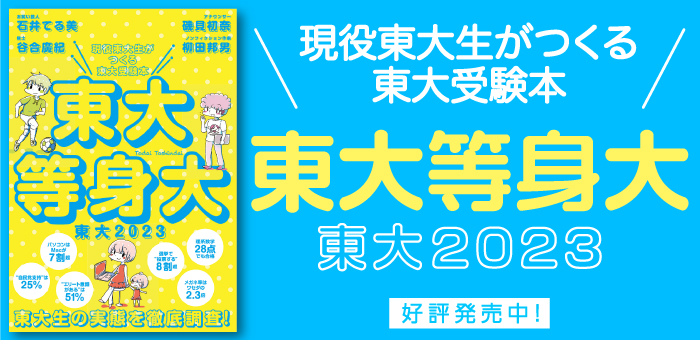ALESS/ALESA、FLOW、初年次ゼミナール(いずれも前期教養課程の必修科目)に関する支援を提供している駒場アカデミック・ライティング・センター(CAWK)。学生たちはこのサポートをどのように活用すべきか。同センターで学生支援を担当するダイアナ・カルティカ准教授(東大大学院総合文化研究科)に話を聞いた。(取材・渡邊詩恵奈)
──ALESS/SAに関してCAWKには何人ほどの学生がどういったサポートを求めて来ますか
CAWKには毎年約2,000人の学生がALESS/SAに関する相談で訪れ、そのうち半数近くがリピーターです。サポート内容はMicrosoftWordの使い方から、学術的な文章を書くための引用の方法まで多岐にわたります。大学院生のチューターとの一対一のセッションもありますし、学期中にはワークショップも開催されるので、興味のある学生は参加してみてください。定期的にアンケートも実施しているので、ワークショップの内容などについて要望があれば、遠慮せずに教えてください。
セメスター開始後、初めの4週間は利用者も少ないため、飛び込みでの利用でも十分にご相談可能です。セメスター半ば以降は混雑する時間帯もあるので、事前予約をおすすめします。予約は、予約サイトからUTokyoアカウントでログインする必要があります。公式Xでは、キャンセルをふくむ空き情報(予約不要な枠)、イベントの最新情報なども発信しているので、ぜひフォローしてみてください。
──毎年どんな相談が寄せられますか
時期によって寄せられる相談もさまざまです。CAWKでは執筆前の段階でも相談ができるため、学期の初め(4週目まで)は主に研究テーマの相談が寄せられます。テーマを適切に絞り込んでいく過程はその後の執筆においてとても重要なプロセスにもなりますし、CAWKもこうした執筆前の利用も特におすすめしています。学期中盤(8週目まで)になると、学生が本格的に執筆を始めるため、論の展開やアイデアのまとめ方、段落構成についての質問が増えます。学期終盤では進捗にもよりますが論文の仕上げや引用の確認に加え、ALESS/SAの発表準備や練習へのフィードバックなどの相談内容も増えます。特に発表準備では、デザインやレイアウトをふくむスライド作成のサポートや、チューターを相手にCAWKのスタンド・モニターを使った本番に近い形でのプレゼン練習が可能です。どの段階でも、学生のニーズに合わせた個別サポートを行っているので、少しでも助けが必要な場合は気軽に相談してください。
──特に混雑する時期は
各セメスター授業開始後の4週間は、予約不要で気軽に利用できます。この時期に研究テーマの相談や英語のアカデミックライティングに関する不安を解消するために訪れるのがおすすめです。5〜8週目は利用者が増え、予約が取りにくくなることもあります。CAWKのセッションは午後のみとなるため、授業や部活動で利用しづらくなる学生も多いかもしれませんが、補講日や試験日などの授業のない日も平日であれば開室するようにしているので、ぜひこうした日も活用してみてください。
AセメスターにALESS/SAの授業を受ける学生も、大学生活に慣れた分、授業や課外活動で忙しくなることが多いと思うので、早い時期から計画的にCAWKを活用するのがおすすめです。もちろん1回限りの利用やセメスターの後半から利用を開始することも可能です。
──ALESSLabとの違いは
ALESSLabとCAWKはそれぞれ異なる支援内容を提供していますが、協力しあいながらALESSの学生を支援しています。ALESSLabでは、必要な実験器具などの貸し出しや、理系の大学院生チューターが実験の計画から実験後のデータ分析、表・グラフの作成などをサポートするのに対し、CAWKでは主に英語でのアカデミックライティングに関する支援を行っています。また、学期末にはCAWKのチューター・ALESSLabのチューター・学生の3者で、実験データをどのように英語の学術的な文章としてまとめるかを相談できるセッションも行っています。ALESSを受講する皆さんはぜひ積極的に活用してみてください。

──例年、学生が特に苦戦する点はありますか
ALESAの学生が最初に苦労するのは論文のテーマ選びです。大切なのは、関心のあるテーマを選ぶことです。関心があれば、研究も自然と進みます。また、責任感をもって研究を進めていくことが重要です。アカデミックライティングでは、明確なメッセージを伝えるための基本的な論文全体の論理構成を理解し、それに則って、執筆していく必要があります。初めてのことなので難しさもあると思いますが、教員やCAWKがサポートしますので、できるところまで自分の力で書き進めてみてください。ALESAは単なる必修の科目ではなく、自分の学びや可能性を広げる機会として活用してほしいです。
ALESSの学生は必ず教員の指導のもとで実験を進めるため、研究テーマを明確にするのが比較的簡単です。一方で実験に重点を置きすぎて、ライティングが後回しになってしまい、研究結果を論文にする際に苦戦する学生も多いです。ALESSの学生には自分で実験を行い、結果をもとに論文を書く力を身に付けることが求められます。しかし今後、AIの活用が進む中で、執筆作業を全てAIに任せたいと考える学生も増えてくるでしょう。AIの活用自体は否定しませんが、まずは基本的な批判的思考や論文の書き方を学ぶべきです。特に、説得力を持って研究結果を伝える力を育むのが重要です。これはALESAの学生にも意識してほしい点です。
──学生はこういった課題をどう乗り越えていますか
CAWKのセッションは1回40分のみです。基本的な引用方法のような内容は1回で解決できるのに対し、文章構造や論理性などの問題は初回のセッションでチューターと一緒に課題を見つけ、2回目以降のセッションで自身で修正したものを確認してもらったり、よりよい論理展開などを深掘りしたり、改善したりする方法が効果的です。CAWKは無料で大学院生のチューターのサポートを受けられる貴重な機会ですので、ぜひ活用してみてください。
──サポートを上手に活用するために、学生が意識すべきことはありますか
CAWKを利用する学生には、遠慮せずにどんどんチューターに質問してほしいです。特にALESS/SAの学生にとって、CAWKの大学院生チューターは先輩的な存在で、ピアのように気軽に質問できる場でもあります。不明点は細かい部分まで積極的に聞き、自分の悩みを解決する場所として活用してください。
──リピートして利用した場合にもチューターは毎回変わりますか
予約サイトでは、チューターの名前を選ぶことができます。基本的に、初めて利用する学生は“Any Tutor”という、ランダムにチューターが割り当てられる選択肢を選ぶと思うので、それで実際に相談をしてみて、次回も同じチューターに相談したいと思えば、次回の予約時に同じ名前のチューターを選んでください。チューターはセッション開始時に自己紹介してくれますし、名札も下げているのでそこで名前を覚えてもらってもいいですし、予約完了メールに記載されているチューターの名前を確認することもできます。一方で、色々なチューターの意見がききたいからと、毎回別のチューターに予約をいれる学生もいます。チューターの指名は、相談事項や都合にあわせて活用してください。
──AIの活用に関して学生に伝えたいことは
AIは今後の社会でますます活用されると思いますが、ライティングにおいてAIに全てを任せるのはおすすめしません。教員は、AIを使って書いた文章をすぐに見抜けます。なぜなら、学生一人一人には独自の書き方やスタイルがあり、それが急に変わると不自然に感じられるからです。また、AIによる情報が間違っていることも多くあります。そのため、自分自身の考えと表現を大切にして書くことが重要です。
もちろんAIの使用自体は否定しません。例えば、スペルチェックや文法確認の際にAIを活用するのは良いかもしれません。ですが、ライティングのプロセス自体をAIに全て任せると、貴重な学びの機会を逃してしまいます。特に東大に入学しているからには、その機会を大事にし、自分の学びに向き合ってほしいと思います。もしAIの使い方に不安があれば、自己判断で利用せず、AIの適切な使い方を学び、自分の学びを深めるためにCAWKに質問しに来てください。
──学生はALESS/SAの授業を通じて、どういったスキルを身に付けることが求められていますか
ALESS/SAの授業では、英語で論文を書くことで自分の考えを英語で表現する力を身に付けるとともに、考え方のスキルも養われます。学生が卒業後に修士課程に進むにしても、社会に出るにしても、論理的な考え方や自分の意見を周囲の人々に納得させる力は非常に重要です。そのため、ALESS/SAプログラムは、単なる英語の授業ではなく、社会で活躍するために重要なクリティカルシンキング・論理的思考のトレーニングを含んでいます。この授業での学びを通じて学生は自分の可能性を発見し、成長していきます。
──ALESS/SAの授業を通じて学生が身に付けたスキルは今後の大学生活や人生でどのように役立ちますか
社会は常に変化しています。AIの発展も数年前には予測できなかったように、未来がどうなるかは誰にも分かりません。だからこそ、大学は単なる知識の提供にとどまらず、学生が未知の社会について自分で考え、問題解決のスキルを身に付ける場であることが大切です。この機会を通じて、予想できない未来に備えましょう。
──ALESS/SAを乗り越えるためのメッセージ
大学に入学するまで、英語でのアカデミックライティングの経験がない学生は少なくないからこそ、コミュニティーがすごく大事だと思います。同じALESS/SAクラスの人や担当教員とのコミュニティー。CAWKも一つのコミュニティーです。
1人で悩み続けるのではなく、良いアイデアや研究を共有し合える場が東大にはあります。情報共有や話し合いができる場が整っているので、東大の学生らしく、いろいろなコミュニティーを使って、ALESS/SAプログラムに限らず、さまざまな場面をみんなで乗り越えてほしいと思います。
駒場アカデミック・ライティング・センター(CAWK)ホームページはこちらから

17年早稲田大学大学院博士課程修了。博士(国際協力/教育開発)。東大教養学部特任講師などを経て、21年より現職。