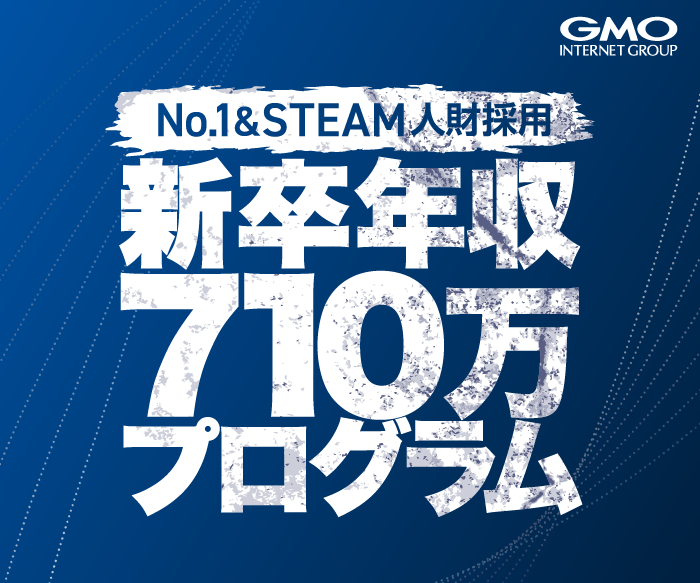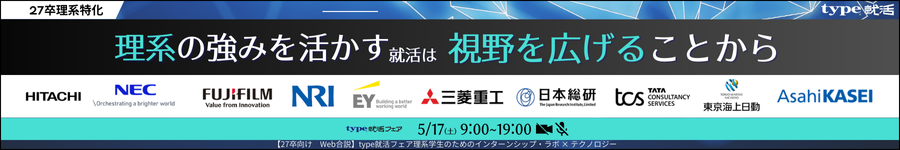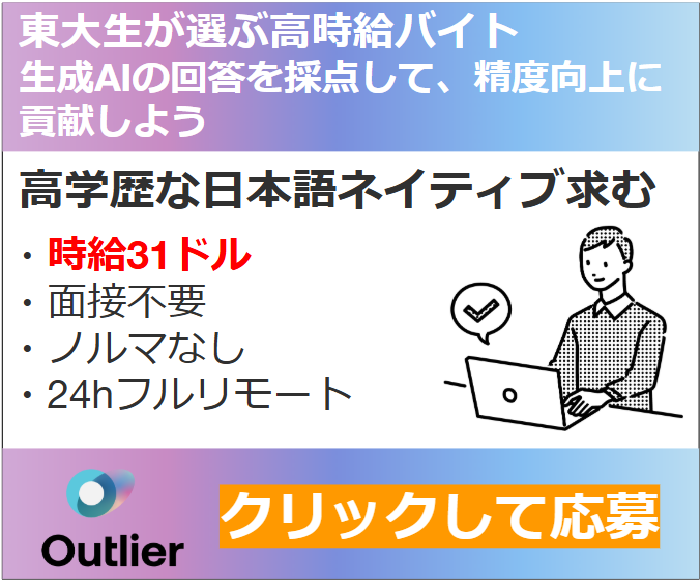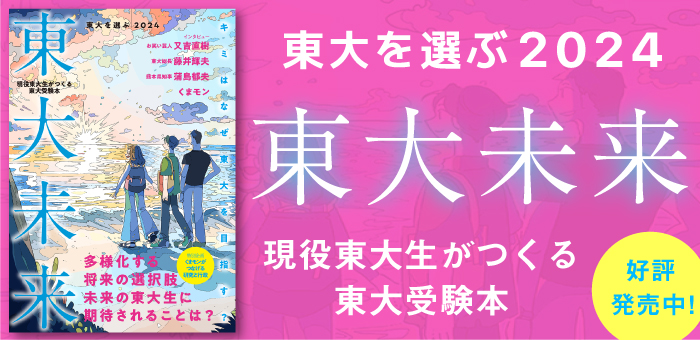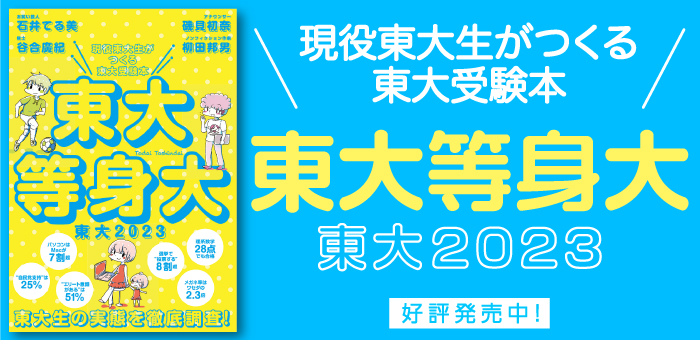2024年1月の留学準備特集号「キャンパスのひと」にて取材した周文佳さん(工・3年/当時文III・1年)。その後の活動はどのようなものだろうか。そして、新入生へのアドバイスとは。(取材・戸畑祐貴)
以前の記事は東大新聞オンラインにてご覧いただけます。
強みを生かして 真っすぐに
文IIIから理転を果たし、現在は工学部化学システム工学科でエネルギーや素材について学ぶ。この学科を選んだ理由は「環境問題の解決に貢献するため」。
環境問題のために学び始めたきっかけは、高3の時に参加した気候変動に関する模擬国連。理系参加者の少なさや、参加者の技術開発をひとごとと捉える立場に対し、当時覚えた違和感は強烈だった。当時は文系だったが、環境問題を解決するという人生の目標を見据え、専門性を身に付けようと理転を決意した。
一方で「自然科学を学ぶだけでは世界を救えない」とも。工学部で学ぶにつれ、現状を改善できる技術やシステムを生むだけでは限界があり、技術を普及させる戦略や社会心理学的な視点も必要だと感じた。入学前や前期教養課程で学んだ数学や経済学も力になっている。
常に目的を意識し「マクロの視点」を持てるのが、文系を経て理系の世界に入った自分の強み。学問としての興味だけでなく「何の役に立つのか」を問い続ける。近年は気候変動対策に「後ろ向き」な国際社会にも「一喜一憂しない」。環境問題が深刻化し猶予が無いからこそ、芯を曲げずに真っすぐ進んでいくことが一番の近道。今年も変わらず、目標に向けて動き続ける。
悩むより「目の当たりにしていく」
新入生に向けて学生生活のこつを尋ねると、まず勧められたのは「社会科見学」だった。
仮面浪人の1年間では、自分で計画し、いろいろな工場見学に行ったという。消費者の視点では見えなかった商品の背景や、都会では見る機会の少ない農地など、サプライチェーン全体を巡った。「世の中こうやって動いているんだと分かると、自分がどこで活躍できるのか、何をモチベーションに大学で学ぶのか、考えやすかったです」
東大入学直後の1年次は、社会に貢献したいという思いだけが強かったが、今では別の思いも加わった。2025年2月に「国土緑化推進機構」のプログラム、「緑の国際ボランティア研修」でカンボジアを約1週間訪れ、現地では友人もできた。そこで目にした景色はどれも心を揺さぶった。例えば、東南アジア最大の湖であるトンレサップ湖でマングローブをかき分け出た瞬間は「骨の髄にまで来る」ものがあったと言う。「この景色は絶対に守らないと」と強く思った。それまでは使命感やヒーローに憧れていたことが行動の動機となっていたが、環境問題がぐっと身近になり「友達が困っているから頑張ろう」と思えるようになった。
理転の準備を始めたのは1年次の夏ごろ。70ほどあった興味のある研究室全てを訪問や授業を聴きに行くなどして表計算ソフトにまとめていった。特に1年生向けの全学体験ゼミナールや学部が開講するオムニバス形式の授業などを通して、教養学部を含め、工学部や理学部、農学部などの研究室の解像度を高めたという。1年次の冬ごろにまとめる作業が完了し、2年生になる際には3学科に絞られていた。
1年次での研究室訪問は「レアケース」としつつも、珍しいからこそ喜ばれるそう。実際に訪れることで研究に関する熱のこもった話も聞けた。学びたいことがあるのであれば研究室へ、まだ曖昧なのであれば「社会科見学」に行く。実際に「目の当たり」にすることが重要だ。