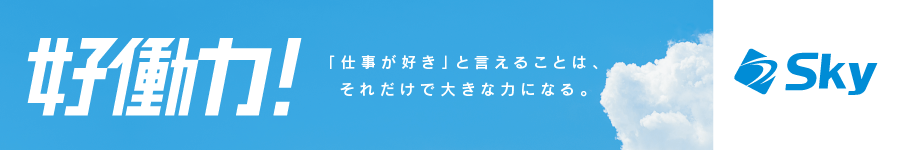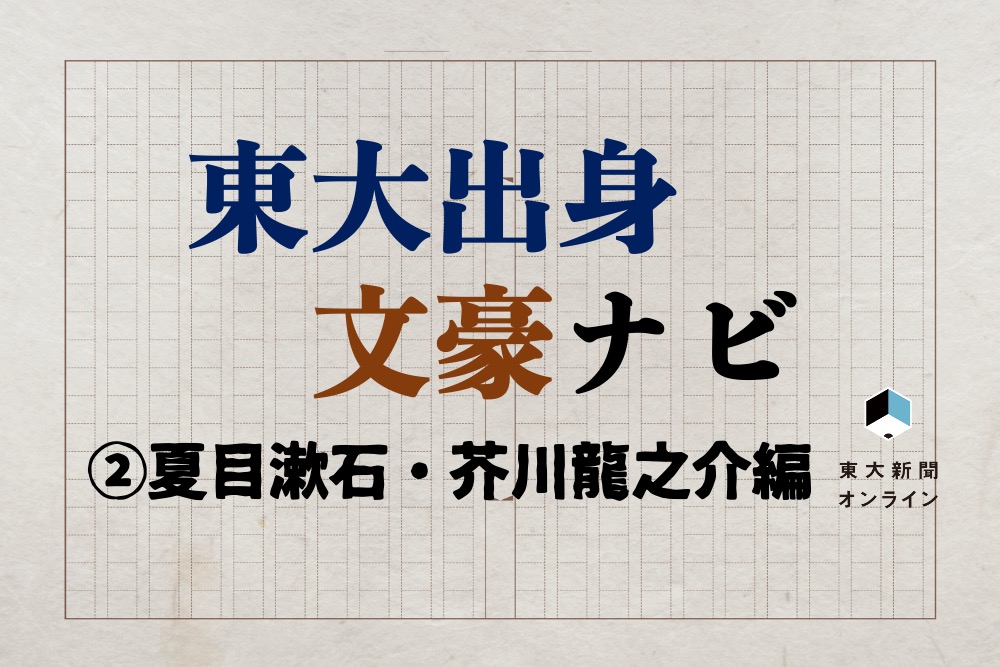「東大」と「文学」の関係は? と聞かれて、多くの人がすぐに思い起こすのは、いわゆる「文豪」たちの存在ではないだろうか。それほど、近代文学史に名を残した文学者たちには東大の出身者が多い。では、その文学者たちの東大での経験はそれぞれの作品にどのような影響を与えたのだろうか? 作品の東大生ならではの楽しみ方は? そんな疑問を解決するのが本企画。今回は夏目漱石・芥川龍之介の東大生時代や作品の魅力についてお届けする。記事を片手に、この秋は読書で「東大」を感じてみてはいかが。(構成・鈴木茉衣、取材・鈴木茉衣、佐竹真由子)
夏目漱石:『吾輩は猫である』をフェミニズムで読む
一言で言うならば「西欧の近代小説の技法とテーマの300年間の歴史を明治日本で再現し、わずか10年の作家人生の中で確立した」点が夏目漱石の文学の魅力であり特徴です。漱石は文学のさまざまな潮流やジャンルについて、特定の作品が特定の潮流と一対一で結び付くのではなく、一つの作品の中にさまざまな潮流の文学の特徴が現れ得るものであり、その差はあくまで文体の差であると考えていました。そして実際に『吾輩は猫である』から『明暗』まで、漱石の作品群にはロマン主義的な作品から自然主義に近いもの、さらには『虞美人草』の美文体など、実にさまざまな技法が駆使されています。このようなことが可能だったのは、漱石が帝大時代に英文学の知識を体系的に学んでおり、キリスト教文化への理解なども大変深いものだったからでしょう。
東大生に薦めたい漱石作品は『倫敦(ロンドン)塔』です。漱石の最初の作品として有名なのは『吾輩は猫である』ですが、この『倫敦塔』は『吾輩は猫である』の、後に第1章になる部分が発表された数日後に『帝国文学』(現在の東大文学部に当たる東京帝大文科大学の関係者による文芸機関雑誌)に発表されました。完成した作品として世に出たのは実はこちらが先ということになります。内容は「余」の倫敦塔見物の回想と「余」の空想で、現実の中に虚構が内包されている凝った構造の作品です。さらに登場する人名や文学作品、絵画作品などの数も膨大で、教養のある読者でないと十分に楽しめないようなものになっています。掲載媒体が読者に十分な教養のある『帝国文学』だったからこそ書けた作品だと思います。

漱石作品は女性作家からの人気が高いのですが、この理由は女性を「ブラックボックス」にせず描けているからだと思います。女性を「謎」として書く作家は同時代にも多かったですが、漱石は理想化してあがめることも、逆におとしめることもできるような存在としての女性ではなく「悩む女」を作品に登場させました。理解を超えた存在として人間や女性を描くことが、恣意(しい)的な意味を投影するエゴイスティックな行為であると気付いていたからでしょう。
特に「女性の現実」として描かれることが多かったテーマが結婚です。当時は近代的な自由恋愛・結婚を重視する価値観が形成され始めた頃でしたが、女性があくまで父親や夫などの男性に扶養される存在であることは変わってはいませんでした。
結婚に着目するというフェミニズム的視点から漱石文学を読むとまた違った面白さがあります。例えば『吾輩は猫である』がフェミニズム文学として素晴らしいのは、猫の飼い主・苦沙弥先生の細君について描けている点です。2人は互いに思ったことをはっきり言うためよくけんかになります。友人から「同じ女房を持つ位なら、たまには喧嘩(けんか)の一つ二つしなくつちや退屈で仕様がないからな。僕の母抔(など)と来たら、おやじの前へ出てはいとへいで持ち切つて居たものだ。さうして二十年も一所になつて居るうちに寺参りより外に外へ出た事がないだと云ふから情けないぢやないか」と評されるほどです。
この2人が正直にぶつかり合えていることは2人の関係性の対等さをよく表しています。『吾輩は猫である』は結婚生活を笑いに変えていますが、例えば『坊ちゃん』のマドンナが赤シャツを選んだことや『こころ』のお嬢さんが先生を選んだことなどからは、女性の人生と結婚に関するよりリアルな現実が垣間見えます。漱石は結婚と女性の人生や幸福について書き続けていたのです。

芥川龍之介:細部までこだわり、 文芸の限界を追求し続けた短編作家
芥川龍之介は、非常に文体へのこだわりが強い作家でした。それは、一字一句の美しさを追い求めるあまりに命を削ってしまったのではないかと思われるほどで、それが芥川作品の魅力につながっています。原稿提出後に、芥川自身の手元にはないその原稿のたった一文を直すためだけに編集者にはがきを書いたというエピソードもあります。細部にまで心を配り、何度も書き直すことによって作品の普遍的な魅力が生み出されたのです。芥川作品のこのような美しさを味わうには大正9年に発表された『舞踏会』という作品が特に完成度が高くおすすめです。
芥川は小説による表現の限界にも挑戦しました。文学者として、文章によって読者の頭の中にあらゆるものを描くことができると考え、挑戦したのです。小説という形態を取りながらも、例えば『秋山図』では幻の中国画を描いてみせ、また『影』では映画を表現しようと試みています。絵画など小説以外の芸術にも親しみながらも、芥川はあくまで文章によって表現しようとした作家でした。
また、芥川は古代から近世まで幅広い時代に題材をとった歴史小説を残しています。芥川は、人間の心理を描くという目的のため、現実にはありえない異常な事件を求めて歴史に題材を取りました。これらの作品の魅力は、登場人物の近代的な心理描写の巧みさと、舞台となった時代の雰囲気を壊さないための緻密なこだわりの両立にあります。元禄時代が舞台の物語には井原西鶴の作品から小道具を登場させるなど、描きたかった心理の背景にある時代性を、非常に細かくこだわって作り上げています。古い時代に題材を取っていても、描かれている心理は普遍的なものなので、現代の私たちにも共感しやすく、魅力的なのでしょう。
芥川が小説を書き始め、発表するようになったのは東京帝大在学中です。在学中に発表された作品には『羅生門』『鼻』などのちに代表作として数えられるようになったものもあります。芥川自身が『小説を書き始めたのは友人の扇動に負う所が多い』という雑誌記事で、久米正雄をはじめとする帝大時代の学友の勧めを受けて小説を書き始めたと述べています。また、在学中の失恋も小説執筆の動機の一つです。芥川は帝大在学中に作家としての第一歩を踏み出したのです。
芥川は学生時代から古今東西のあらゆる本を読み、全てを本から学ぼうとしました。私小説が盛り上がった大正時代にはこのような芥川の姿勢は批判の対象でもありましたが、それこそが芥川作品の魅力につながっていると考える人もいます。私は、国際芥川龍之介学会の国際大会で、ドイツの研究者が「ヨーロッパを訪れることなくヨーロッパの文学を吸収したことこそが芥川らしさだ」と言っていたのが印象に残っています。芥川は多くの本を読みながらも、日本、東洋、西洋の文学のどれかに収斂(しゅうれん)していくことはありませんでした。作家として活動した期間が13年ほどと短く、もしもっと長く活動していたら、谷崎潤一郎の古典回帰のような作風の変化があったかもしれません。
東大生におすすめの芥川作品は『あの頃の自分の事』と『路上』。どちらも東京帝大在学中の経験に基づく作品です。『あの頃の自分の事』は、大学在学中に小説を書き始めた頃を回想した随筆のような作品。『路上』は短編作家である芥川が長編小説を書こうとして中絶してしまった作品です。東大文科の学生を主人公とする作品で、師である夏目漱石の『三四郎』に着想を得たのではないかと思われます。