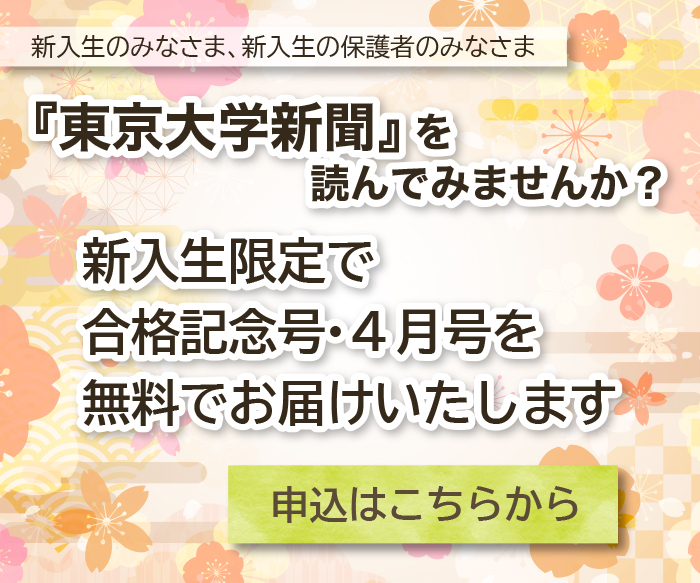森章教授(東大先端科学技術研究開発センター)らの研究グループは、自然保護区の生物多様性は炭素吸収に役立つことから、気候変動の課題解決に有効なことを明らかにした。
これまで気候変動が生物多様性に与える影響についての議論は進んできた一方、生物多様性が気候に与える影響や両者の相互依存性については議論が十分になされてこなかった。生物多様性が保たれていると多様な植物が二酸化炭素を吸収し、地球温暖化の抑制が期待される。研究にあたり、将来的な生物種の地理的分布を予測する「種分布モデル」と、植物種数、無機物から有機物を合成する一次生産性の関係性に関わるモデルを組み合わせた。そのモデルを用いてさまざまな気候変動の状況を想定し、将来の森林の炭素吸収機能の変化を予測した。予測の結果、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出削減、炭素貯留の促進、持続可能な土地管理のような気候変動緩和の努力がなされないまま植物の多様性が失われると、自然保護区が持つ炭素吸収機能が損なわれてしまう可能性を示唆した。
また、国連生物多様性条約のもとで、2030年までに30%の陸地を保護する、通称「30by30目標」に着目し、将来的な保護区の増加を、気候変動緩和がなされた状況となされていない状況で比較を行った。その結果、30%の陸地が保護されていても気候変動緩和に失敗していれば、自然保護区が意味をなさないことも明らかとなった。
こうした研究により、自然保護区の増加と気候変動緩和は独立した目標ではなく、相互に関わり合う目標であると分かった。国際環境政策の立案・実施が期待される。