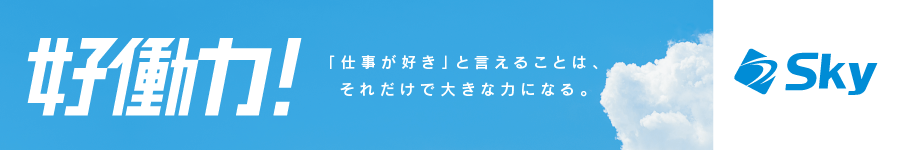2018年1~3月に放送されたTVアニメ「宇宙よりも遠い場所」は、女子高生4人が南極を目指す物語である。深夜の放送ではあったものの、高い完成度のストーリーなどから大いに話題を呼んだ。弊社が10月1日に発行した『はじめての東大―東京大学新聞年鑑2017ー18』では、極地研究を特集した過去の紙面とともに、アニメ制作に当たっての取材内容などを聞いたいしづか監督のインタビューを収録している。今回は書籍に収録しきれなかった、アニメ本編の内容について話を聞いた取材の模様をお伝えする。
(取材・伊得友翔)
──物語は、主人公・キマリが、報瀬、日向、結月とともに、南極へ向かう計画を立てるところから始まります。第5話ではいよいよ南極に向け出発しますが、キマリは親友・めぐっちゃんから絶交を告げられてしまいます。それまでの話からは想像できないような衝撃的なシーンですが、この話はどのように構想されましたか。
この作品が「女子高生もの」と決まった時点で、どこまで泥臭くするかというリアリティーラインが最初のポイントになりました。女の子たちが集まって何かをするというとき、放送時間帯を考えるといわゆる「萌え系」のノリにするのが安全なんですよね。それを好むお客さんが多いので、我々も本来そういった売り方をすべきだと思います。
でも今回私が女子高生ものを描きたいと思ったのは、そもそも自分が高校生のとき友達とどういう付き合いをしていたかを考え、その頃の友達が見て面白いと思ってくれるものを作りたいと思ったからでした。それで、アニメだからと開き直らずに、もっとちゃんとした生っぽい人間ドラマをやりたいという話を脚本の花田十輝さんにしました。もちろん花田さんも萌え系の作品は非常に得意な方なんですが、その中で花田さん自身が持っている奥深いドラマがあるなら引き出してほしいと思っていたんです。そうしたら、当然花田さんも似たような欲求があったんですね。そこで、女の子の嫉妬心を描いた第5話のような少し重めの話もきちんとやる作品にしようと覚悟を決めました。
その上でキマリのドラマを描いていったときに、彼女が南極を目指すに当たって成長するポイントはどこか考えると、「めぐっちゃん離れ」だったんです。特にこの年齢の自立できていない子どもにとって、友達とのつながりはどうしても依存関係になりがちだと思います。そんなキマリがいざ自立するというのが、地球の端っこを目指す上で非常に大事なドラマだろうと思い、思い切ってこのエピソードを入れてみました。そうしたら案の定、30代以上の私たちの世代からは共感を得られたんですが、逆に10代、20代の人たちにとってはつらいものだったと思います。多くの人が、まだ自分の親友は良い人だって信じているじゃないですか(笑)。単純に、裏切られた経験がほとんどないと思うんです。そういった人たちにとっては、きっと受け入れ難いドラマだろうなと思って作っていました。
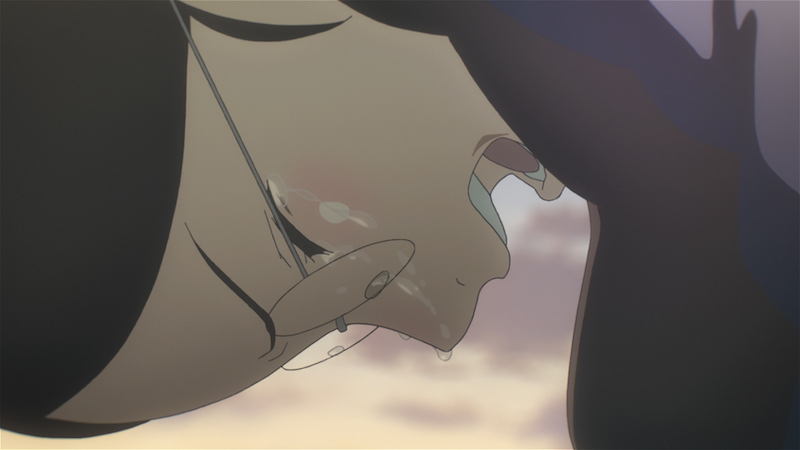
©YORIMOI PARTNERS
──若者に対するメッセージでもあるのでしょうか。
10代、20代前半の頃なんて、自分のことで精いっぱいだと思うんです。だから自分自身の性格や内面を、客観的に見ているようで見れていない。そうした完全に自立する前の状態において、心の中に占める友達のシェアってすごく高いと思います。その友達に対して直接向き合うことは、怖くてなかなかできないですよね。でもそこで怖くてもきちんと向き合ったのが、めぐっちゃんなんです。だからこのエピソードを見て、みんなもう少し素直になってくれたらいいかなとは思います。私は友達を失いたくないのでできませんけど(笑)。
そういった意味では、大人にとっては共感できるというより、「よく頑張った」という感じなのではないでしょうか。めぐっちゃんはよくそれを言えたし、キマリもよくそれを受け入れた。自分にはできなかったことを彼女たちは成し遂げたという、2人に対するエールの方がもしかしたら大人は大きいかもしれません。
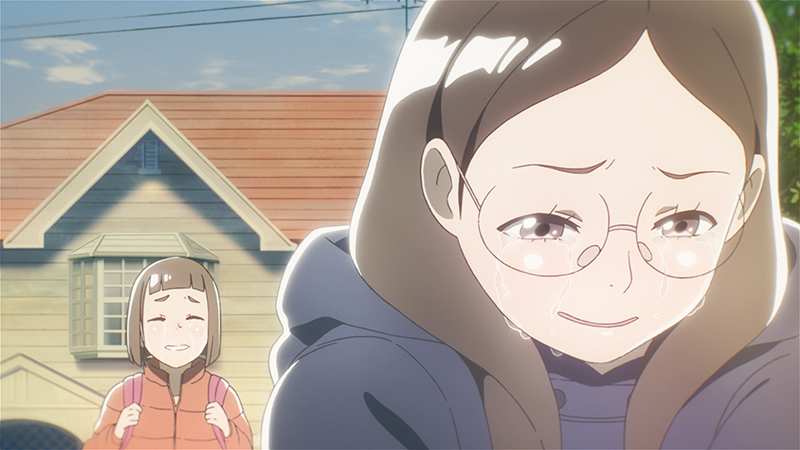
©YORIMOI PARTNERS
──4人は南極観測船「しらせ」で南極に向かい、南極での生活を始めることになります。第12話では、報瀬の母・貴子が消息を絶った内地で、遺品のノートパソコンを前に涙する報瀬の姿が印象的ですが、この場面はどのように構想されましたか。
これは、花田さんが自らの実体験から着想を得たものです。物語の最後、報瀬にどう「とどめを刺すか」悩んでいた際、ふとメーラーを立ち上げたときに思い付いたそうです。
ただ、本来アニメとしてはやらない表現なんですね。普通キャラクターを泣かせる場面というのは、そこに感情のぶつかり合いがあったりとか、もしくは1人孤独な中独白が流れたり、思い出のフラッシュバックがあったりして、分かりやすい記号が用いられます。第12話のように画面だけで泣かせるというのは、記号として非常に難しいんです。だから私としても「これはまずい」と内心思っていたんですが(笑)、ただアイデアそのものが面白かったので、その内心を隠して挑戦してみることにしました。
この作品はキマリの物語ではありますが、南極と関連したドラマは報瀬が握っているんです。最初に決まった縦軸も、実はキマリとめぐっちゃんではなく、報瀬とお母さんの話でした。

©YORIMOI PARTNERS
──登場人物はどのように決まったのでしょうか。
キマリは前進力のある、ポジティブな子にしたいと最初から思っていました。テーマが南極に決定する前から、主人公は前向きにステップアップしていく子にしようと決めていたんです。報瀬は縦軸を決めた段階で自然と生まれてきたんですが、それだけではつまらないということでいろんな要素を足していきました。人にすぐ突っかかる面倒くさいタイプであったりとか、「残念美人」であったりとか。そうすると、この報瀬とバランスを取るような子が必要で、それはキマリではないんですよ。キマリは報瀬に対してそこまでフォローできるような子じゃないんです。背中を押すことや前を走ることはできると思いますが。
報瀬に寄り添ってくれる子を考えたときに、日向というキャラクターが非常に重要になってきます。彼女は大人びていて、心の闇を抱えているけれどもそれを一切表に出さない。さらに日向は高校に行っていないんですが、これは女子高生ものにおいては新しい挑戦かなと思っています。というのも、もし実際に高校を中退した人が見たらとてもつらい設定なんですよね。でもそこにあえて向き合っていくのが、このドラマの持ち味だと考えているんです。そういう意味で、日向はただの良い子ではない深みのあるキャラクターになっているんじゃないでしょうか。
結月に関しては、深夜アニメにおいてアイドルやタレントという存在の需要が高いため、やや商業的な目線で最後に加えられたキャラクターです。ただ、普通のアイドルではなく、仕事も学校も上手くいってないような「足かせ」のある子なんです。言葉遣いやポーズ1つとっても、決してアイドルになれない、地方のしがないタレントというポジションに収まりました。
でも実はこうした女の子同士の掛け合いを描く上で必要な要素って、教科書的に決まったものがあるんです。ポジティブな女の子、癖の強い女の子、面倒見の良い女の子、萌えキャラ、みたいな。そこに、この作品ならではの足かせをはめたという形ですね。
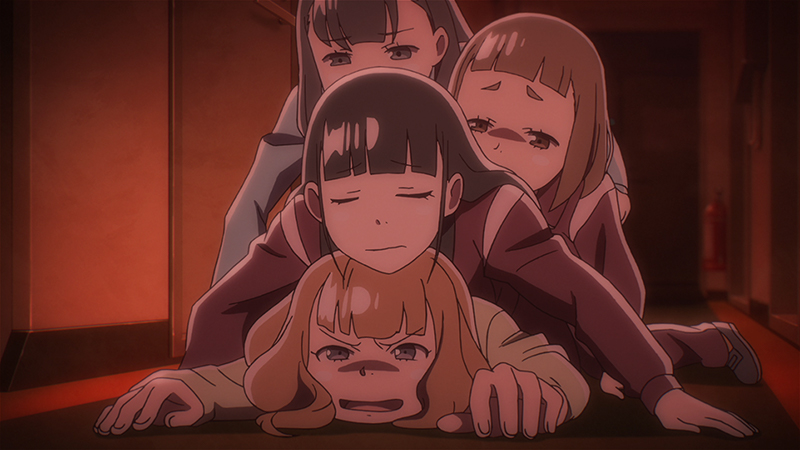
©YORIMOI PARTNERS
──テンポの良い会話劇もこの作品の特徴だと思いますが、どのように描くことを意識されましたか。
会話劇は花田さんの得意技なんですよね。それをいかに出してもらえるか、という感じでした。専門的な分野について描く必要があるときに、設定の説明につい引っ張られてしまう部分も多いんです。そこで花田さんの手が少しでも止まるようであれば、花田さんの筆が乗るように書き直してくださいというお願いをしました。とにかく会話で進めてくれれば、必要な情報は全部絵で埋める、というすみ分けをしていましたね。登場人物の生活感や生っぽさをいかに脚本に落とし込むかというのが、脚本段階で掲げていたテーマでした。
日常会話だと、ある話をしていたら突然違う話が入ってきて、また元の話に戻ることってよくあるじゃないですか。アニメは時間が短いので無駄な部分は省かれやすいんですが、そういった適度な脱線はキャラクターの人間関係を的確に表すことができると考えています。何を考えているかも、ちょっとした行間に表れてくるんです。こうした会話そのものが、キャラクターを生かすポイントになっているかなと思いますね。

©YORIMOI PARTNERS
──この作品は1話ごとにきちんと完結し、区切られる印象が強いですが、どのような意図があるのでしょうか。
個人的な好みもありますが、20分くらいお客さんにテレビの前で見てもらうからには、そこで何か1つ感動はしてほしくて、その話を見てよかったと思ってほしいですよね。それで、1話ごとにきちんと起承転結を作るようにしました。花田さんもこの点に関しては同意見だったので、最初からそれありきで進んでいたような気がします。
読書で言うところの読後感みたいなものはかなり前から意識していたことではあって、6年ほど前の「さくら荘のペットな彼女」を作っていた頃から、エンディングを大事にしたいと考えていました。エンディングに入る瞬間からエンディングが終わるまでは、読後感に非常に影響する部分ですよね。そのときに前向きな気持ちになれるかどうか、見てよかったと思えるかどうかって、すごく重要なポイントだと思っています。だからいつもエンディングに力を入れがちですね。エンディングの映像そのものというよりは、エンディングの前後をこだわることが多いです。
──作品を通して、どのようなメッセージを伝えたいですか。
旅に出てみると、もちろん旅の間に得られるものもあるんですが、帰ってきてからも続くものってすごく大きいと思っています。これは、制作にあたって南極観測隊の方々に取材している中で感じたことです。彼らは南極から帰ってきて何年たっても家族なんですよね。南極料理人の方が経営している「じんから」というお店に伺ったときも、たまたまその場に居合わせたOBやOGが当時さながら、家族が食卓を囲むように盛り上がるという空気感を感じました。
きっとキマリたちも、旅を終えて帰ってきてからの絆は非常に強いだろうなという余韻を残したいし、そう想像してほしいと思っていました。だからこれを見た人たちも何か行動を起こして、そこで得られた友情や絆、新しい人間関係を大切にしてほしいですね。

©YORIMOI PARTNERS
──放送から時間がたった今、振り返ってみてご自身の中でどのような作品であると位置づけられていますか。
自分のビジネス的に、大成功を狙って作った作品ではないんですね。売れなかったらそれはそれで仕方ないという感じでした。ただ自分たちが作りたいものをきちんと作れたので、作ってよかったと思っていました。そうしたら意外と大きな反響があって、「作ってよかったな」が「作ってよかった!」になりました(笑)。その意味では、すごく意外な成長を遂げた作品ですね。
先ほども少し触れましたが、売れるタイプの作品ではないはずなんですよ。結月というキャラクターが象徴的で、アイドルであるはずの彼女をちゃんとした萌えキャラにしなかったんですが、かわいいと言ってもらえました。他にも人間の黒い部分を掘り下げているとか、本来の放送枠としてはやってはいけないことをたくさんやっているんです。それでも「良い作品だった」と言ってもらえるのが、とてもうれしかったですね。
なおかつこの作品は、スタッフにとても愛されました。「やっていて楽しい」や「続きが見たい」といった声を多く聞くことができましたし、確認の段階では作っている自分たちが泣きながら見ることもありました。そういう現場って実はなかなかなくて、それだけでも作ってよかったと思える作品です。
──今後の目標を教えてください。
この作品では、オリジナルのタイトルできちんとお客さんに喜んでもらうことができました。今後もオリジナルで、人にぜひ見てほしいと思えるような作品を、今よりも広い人に見てほしいと思っています。今は放送枠の事情もあって、ターゲットがある程度絞られた状態でアニメを作っています。例えば劇場版であれば、また違った客層も得ることができますよね。そういった新しい映像の発信の仕方を、今後試していきたいと考えています。目指せ、オリジナル劇場アニメ!
◇
いしづかあつこさん(アニメーション監督)
04年、愛知県立芸術大学美術学部卒。マッドハウスに入社し、「月のワルツ」のアニメーションで監督デビューを果たす。主な監督作品に、「さくら荘のペットな彼女」、「ノーゲーム・ノーライフ」、「ハナヤマタ」などがある。
※現在発売中の『はじめての東大―東京大学新聞年鑑2017ー18』では、昨年日本の南極観測60周年を記念して紙面で展開した南極特集を収録しています。南極をどのように描こうと意識したかをいしづか監督に聞いたインタビューの他、国立極地研究所元所長へのインタビューなども掲載。ぜひご一読ください。
スマートフォン専用特設サイトはこちら→http://kutouten.co.jp/creca-